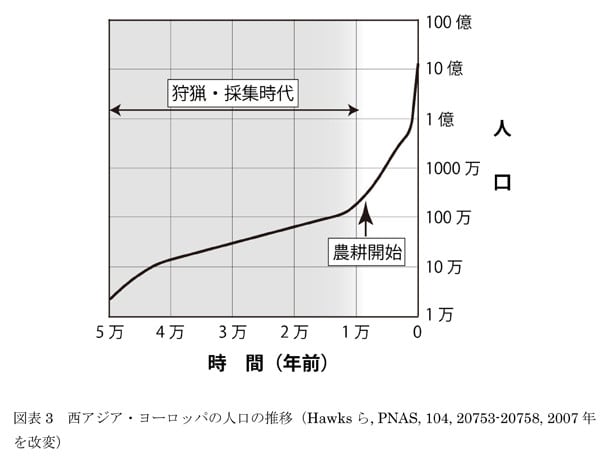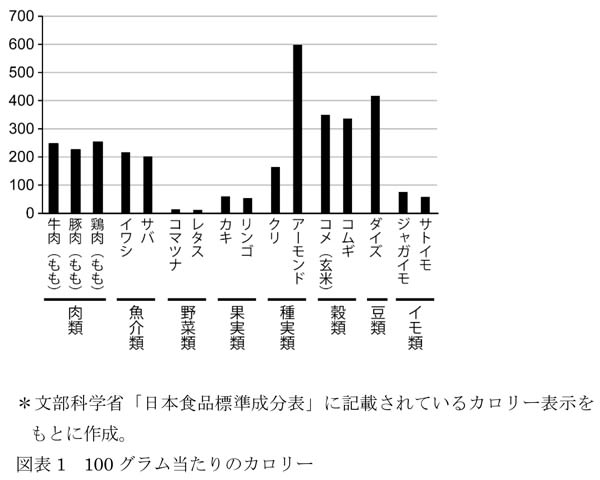雑草のすごい能力
小学校の理科の実験で定番なのが植物の栽培だ。低学年ではアサガオなどを育てて、植物が成長する様子を観察する。夏休みには育てたアサガオを家に持って帰って観察を続けるのが宿題だった。面倒くさがりの息子たちをなだめすかして観察日記を書かせたのは、良い思い出だ。
小学校の高学年になると少し高度なことを教わる。インゲン豆などを使って種子が発芽する条件を調べるのだ。インゲン豆を水につけたり冷蔵庫に入れたりして発芽するかを調べる。そして、植物の種子の発芽に必要な要件として、「水」「酸素(空気)」「適度な温度」の3つを学ぶのだ。
しかし植物の種子の中には、これらの3つの条件がそろっても発芽しないものがある。種子がこのような状態にあることを「休眠」していると言う。休眠していた種子は、発芽する季節がやって来ると休眠から覚めて発芽する。
この休眠の仕組みはとても重要だ。例えば、春に芽を出す種子が冬の初めに暖かいからといって芽を出してしまうと、後にやってくる冬の寒さで全滅してしまう。一方、秋に芽を出す種子が春に芽を出すと夏の暑さで死んでしまう。このような間違った出芽をしないために、適切な季節になるまで休眠する仕組みがあるのだ。出芽すべき季節になって休眠から覚めた種子は、水・酸素・適度な温度の3つの条件がそろうと発芽する。
雑草の多くはさらに、光の刺激が加わって初めて発芽する「光発芽」という仕組みを備えている。これは、光合成をしないと生きることができない植物が、光がある場合にのみに発芽する仕組みだ。例えば、ほかの植物が生い茂っているところで発芽すると、先に生えている葉で光が遮られてしまう。また、種子が土の中深くにある場合も、出芽しても光があるところに到達できずに枯れてしまう。雑草はこれらの危険性を避けるために、生育に必要な光を感じた場合のみ発芽する光発芽の仕組みを備えているのだ。土を耕すとすぐに雑草が生えてくるのは、土深くに埋まっていた雑草の種子が地表近くまで掘り起こされて、光発芽したことが理由の一つとして考えられる。
さらに雑草の種子には、同じ条件でも発芽するタイミングがずれるという特徴がある。もし一斉に発芽すると、草刈りなどによって全滅してしまうかも知れない。そこで、雑草の種子は同じ条件で一斉に発芽するのではなく、お互いの発芽の時期を微妙にずらすという特徴を備えている。こうして、雑草の種子は長期にわたって断続的に発芽する。人が草取りをしても雑草がすぐ生えてくるように見える理由はこれだ。
雑草はどんな時でも種子を残す
雑草の極めつけの能力は、「自家受精(自家受粉)」で子孫を残すことだ。
動物がオスとメスに分かれていて生殖により子孫を残すように、花を咲かせる植物の多くは、おしべで作られた花粉がめしべに受粉することによって子孫(種子)を作る。この時、多くの植物で、花粉が同じ個体のめしべに受粉する自家受精を避ける仕組みが備わっている。
例えば、多くの植物で、おしべよりもめしべが長くなっており、花粉が同じ個体のめしべにつきにくい構造になっている。また、オオバコやミズバショウ、キキョウなどは、花の中のおしべとめしべが成熟するタイミングをずらすことで、自家受精を防いでいる。キュウリやスイカ、メロンなどでは、おしべだけの花とめしべだけの花を別々に作る。
さらに、花粉が同じ個体のめしべに間違ってついてしまった場合には、化学物質を出して受精を阻止する「自家不和合性」という仕組みもある。
こうして自家受精を防止することで遺伝子の多様性が保たれる。同じ遺伝子ばかりを持っていると、環境変化に対して同じ応答しかできなくなってしまい、全滅する恐れがあるのだ。これを避けるために、ほとんどの動物や植物で生殖活動が行われていると考えられている。
しかし、これだと、近くに別の仲間がいないと子孫を増やすことができない。そこで雑草は、独りぼっちでも子孫を残せるように自家受精する道を選んだと考えられている。これは、子孫を残すことを最優先にした究極の戦略と言える。
さらにイネ科の植物は、受粉に虫や鳥を使わず、風や重力で花粉をめしべまで運んで受精する。これも、変動する環境下で、他の生物がいなくても確実に子孫を残すための戦略と考えられる。
このように雑草は受精に独特の仕組みを開発することで、悪い環境でも生き抜くことができるように進化してきたのだ。