以前、テレビのドキュメンタリー番組でアクターズスクールが運営するフリースクールのことを紹介していたことがある。
“アクターズスクールのフリースクール”というとなんだか脚韻踏んだラップの歌詞みたいでややこしいんだけど、「アクターズスクール」というのは安室奈美恵とかスピードを輩出した芸能学校で、「フリースクール」というのは、おちこぼれ、登校拒否児童、もしくは親の方針で普通の学校に入らなかったというような子供達を受け入れる私設の学校のことだ。(取材対象だったのは確か小学校クラス)
その中で子供に将来の夢を書かせるというのがあった。それは単に「宇宙飛行士になりたーい」とか、お気楽なものではなく、いってみれば将来のビジョンみたいなものを考えさせるというものだった。将来の夢を実現させるために、どういう努力をしていかなければいけないかということを具体的に書かせるのだ。
うわぁ、きびしぃなぁと思って見ていたら案の定、何人かの子供は何を書いていいかわからず泣き出してしまった。
そりゃそうだよ。自分の子供時代のレベルを思い出してその場面に当てはめたら、間違いなく私も「泣き組」のほうに属していると断言できる(苦笑)。
それを見ていて、なんで、この子らはおちこぼれたあとに、さらに厳しいところに放り込まれてしまったんだろう…なんて同情したりもした。
別にそのフリースクールの方針を否定するわけではないけれど、子供なんてそんなもんだと思うのだ。
“自由”といえば聞こえはいいけど、凡人にとっては、最初のうちはあちこちに線引いて区切ってもらって、その中で訓練していくほうがよっぽどラクで効率的なのだ。
最近の「ゆとり教育」っていうのは、そのどっちでもないような得体の知れないものに見える。
早くからビジョンを決めさせるというわけではない上に、引いてあげる線の数を減らしただけだ。
“区切り”や“囲み”をなくすと、一見、選択肢は無限になるように錯覚しているんだろうが、選ぶ側に「選択能力」が備わってなければ、選択肢は少ないどころかないも同じだ。
詰め込みと揶揄された、従来型の教育だけど、一方通行のよさというのもあるのだ。例えば本を5冊与えられて読めといわれたら読む子供も、なんでもいいから自分で図書館にいって何冊か読めといわれたら、めんどくさくって図書館にすらいかないものも出てくるだろう。
そんなことを考えていたらホリエモンのことがアタマに浮かんできた。
きのうのスーパーニュースで鳥越俊太郎氏がジャーナリストの重要性について説いていた。
それは↓
「日本は政治はダメですよ。経済が一番売れる。政治にはあまり興味がないみたい。それはそれで、いいんじゃないですか」
「人気がなければ消えていく、人気が上がれば大きく扱われる。完全に市場原理。我々は、操作をせずに、読み手と書き手をマッチングさせるだけ」
江川紹子ジャーナルより
というようなホリエモンの報道というものに対する考え方を受けてのことだろう。
ホリエモンの描く未来図は私が昨日「●ハードゲイの…」の記事の中で懸念した、検索エンジンの上位にある情報だけで人々のアタマの中が塗りつぶされていくような社会の究極の姿だ。
結局のところゆとり教育のように、選択肢を広げているようで実はせばめてしまっているということなのだ。
ニュースだけじゃない。例えばホリエモンとか高城剛なんて方々は本屋なんていうのもなくなると思っているだろう。
「ネットで自宅から注文できるし、検索したら本屋で探すよりずっと効率がいい。」
なんてね
でも、それは最初から買う物がきまっていればいいけど、そうでなかったら書店サイトのシステムの言うがままの本としか出会えない。
たとえば本屋の店先で偶然見つけた本なんてことはあり得なくなる。理論の上ではどんなマイナーな本にでもたどりつけるはずなのだろうが、検索結果が100件も出てきたらそれらをちゃんと全部見る人はまれだろうし、検索システムがこちらの意向をすべてくみ取ってくれるとは限らない。だってホリエモンにいわせりゃ私たちの多くは「ろくにネットを使いこなしてない」そうだから。まさにデスクトップ(机上)の空論だ。
100冊の本の背(もしくは表紙)を見回すのは本屋の店内でならほんの短い時間ですむ。
本屋でぶらっと、手にとってパラパラという「インターフェイス」が完全にフォローできるシステムができないかぎりは本屋がなくなってはいけないのだ。
それにホリエモンがニュースに対して言ったように“人気がなければ消えていく”という方針だとマイナーなものはすべて淘汰される危険性がある。
ホリエモンはきっと「再販制度」なんてさっさとなくしたいんだろうな。
とにかく技術というのは“使えるようになったときに”使えばいいのだ。技術にあわせた環境作りなんて本末転倒。見通しのない人体実験だ。
そう、技術といえばスーパーニュースではビデオニュースネットワーク神保哲生代表が
「堀江氏の主張はハード面主眼にしたメディア論なんですよ、回線が太くなって双方向になるからこんなことができるあんなことができるってことをたくさん言ってる」
と言っていた。
別にインタラクティブ(双方向)ができるようになったからといって、なにがなんでもそれを使わなければいけないというわけじゃないはずだ。
その考え方って、まるでかつてヘアーが解禁になったときに、出さなきゃ損みたいに不自然なくらいヘアを強調したようなポーズを多用した三流グラビアのような気持ち悪さがある。
むかしアップルのスティーブ・ジョブズが来日して日本の某会社の工場視察に訪れたとき
「おまえら日本人はハードを作れ、ソフトはここにある」と自分のアタマを指さして言ったという、屈辱的なハナシがあるけど、実際、日本にはソフトがないと言われ続けてきた。
日本では時代の最先端を行くとされている?ホリエモンさまがあのザマってことは、今もきっと日本にソフトはないのだろう。
ここでいうソフトっていうのはインフラ整備ならその方針であったり、システム全体の設計思想やらを言うのであって、単に計算式を立てたり、機械を動かすためのプログラムを組んだりということではない。それらはカタチの上ではたしかにソフトウエアだが実質的な役割という意味ではハードウエアの一部にすぎないのだ。
また同番組で明治学院大学法学部の川上和久教授は
「テレビ局にしたって企業ですし収益をあげなければいけない部分はありますけど放送というのは、たとえば所得の低い人にも情報を届けるという使命を持っていると私は思うんですね」と言っている
私の部屋にあるテレビはコジマに並んで5000円で買ったものだがホリエモンのメディアミックスを享受するには金がかかりそうだ。
金がかかるという文句はIT全体に言いたい。たとえばパソコンなんて、ほんとは一般ユーザーにとっては既にオーバースペックのはずなんだけど、ソフト(OSを含む)がバージョンアップするごとに、“ちゃん”と重くなってくれるので、それに合わせてハードも新しくしなきゃいけない制度になっている。ソフトのほうはビックリするような便利な機能はふえてないにもかかわらず…だ。
まぁ、貧乏人に厳しいというのは地上波がそのうちデジタル化するということにもいえるけどね。あれも一体、誰のための進歩なんだか…。
昨日の報道ステーションで古館氏が
「ライブドア派か、フジテレビ派かすぐ言える人は実は何も考えてない人なじゃないですかね」
…っていってたけど、そう思う。
「新しいことをやろうとかるときはみんな批判はうけるものだからねぇ」
といってる、おばちゃん、“新しいこと”の中身を知ってるのかい?
「お金で強引にっていうのはねぇ」
といってるおっちゃん
いや、極論をいっちゃえば、将来やろうとしていることがみんなの幸せのためならちょっとくらい強引でもいいよ…
みんなマネーゲームに気をとられて、世の中が、大切な未来がどう転ぶかっていう想像をちっともしていないんだ。
世の中のバカ親は、自分の子供にブランドものとか着せてやったりするのに、子供達の未来にある環境ってことはあまり考えないのかね。
そんな親たちは公務員や官僚の腐敗が話題になっても、自分の子供がなってくれる分には嬉しかったりするのだろう。
我が子が将来、ホリエモンみたいになって欲しいなんて思ってる親、いっぱいいるんだろうなぁ。
【まとめ】
結局、ホリエモンの夢見る未来はアホを量産するどころか、人類から多様性を奪って種として脆弱化させ、しまいには機械に支配されるという「マトリックス」な社会だ…と。
で、他のITのひとたちも大差はないんだろうな…と。
フジテレビかんけーのことはもう書かないと心に誓ってからすでに3つか4つくらい書いしまった(笑)↓けど、今度こそ最後…ぽい(笑)
●ハードゲイの向こうに見える情報流通の未来 2005-03-22 01:20
●アメリカ式の毒でアメリカ式の終末を… 2005-03-19 04:33
●ザル法もまた法なり? 2005-03-19 02:08
●ビルズに恋して by Vincent Gallo なんちって 2005-03-16 00:55
●きっかけは~謎だらけ!もういっかーい 2005-03-11 03:52
●きっかけは~謎だらけ 2005-03-09 05:11
●蛇足、フィリピンバナナ100円 2005-03-08 07:15
●エデンの東のずっと東~Beast of Eden 2005-03-07 01:01
●Livedoor and let die 2005-03-05 07:32
“アクターズスクールのフリースクール”というとなんだか脚韻踏んだラップの歌詞みたいでややこしいんだけど、「アクターズスクール」というのは安室奈美恵とかスピードを輩出した芸能学校で、「フリースクール」というのは、おちこぼれ、登校拒否児童、もしくは親の方針で普通の学校に入らなかったというような子供達を受け入れる私設の学校のことだ。(取材対象だったのは確か小学校クラス)
その中で子供に将来の夢を書かせるというのがあった。それは単に「宇宙飛行士になりたーい」とか、お気楽なものではなく、いってみれば将来のビジョンみたいなものを考えさせるというものだった。将来の夢を実現させるために、どういう努力をしていかなければいけないかということを具体的に書かせるのだ。
うわぁ、きびしぃなぁと思って見ていたら案の定、何人かの子供は何を書いていいかわからず泣き出してしまった。
そりゃそうだよ。自分の子供時代のレベルを思い出してその場面に当てはめたら、間違いなく私も「泣き組」のほうに属していると断言できる(苦笑)。
それを見ていて、なんで、この子らはおちこぼれたあとに、さらに厳しいところに放り込まれてしまったんだろう…なんて同情したりもした。
別にそのフリースクールの方針を否定するわけではないけれど、子供なんてそんなもんだと思うのだ。
“自由”といえば聞こえはいいけど、凡人にとっては、最初のうちはあちこちに線引いて区切ってもらって、その中で訓練していくほうがよっぽどラクで効率的なのだ。
最近の「ゆとり教育」っていうのは、そのどっちでもないような得体の知れないものに見える。
早くからビジョンを決めさせるというわけではない上に、引いてあげる線の数を減らしただけだ。
“区切り”や“囲み”をなくすと、一見、選択肢は無限になるように錯覚しているんだろうが、選ぶ側に「選択能力」が備わってなければ、選択肢は少ないどころかないも同じだ。
詰め込みと揶揄された、従来型の教育だけど、一方通行のよさというのもあるのだ。例えば本を5冊与えられて読めといわれたら読む子供も、なんでもいいから自分で図書館にいって何冊か読めといわれたら、めんどくさくって図書館にすらいかないものも出てくるだろう。
そんなことを考えていたらホリエモンのことがアタマに浮かんできた。
きのうのスーパーニュースで鳥越俊太郎氏がジャーナリストの重要性について説いていた。
それは↓
「日本は政治はダメですよ。経済が一番売れる。政治にはあまり興味がないみたい。それはそれで、いいんじゃないですか」
「人気がなければ消えていく、人気が上がれば大きく扱われる。完全に市場原理。我々は、操作をせずに、読み手と書き手をマッチングさせるだけ」
江川紹子ジャーナルより
というようなホリエモンの報道というものに対する考え方を受けてのことだろう。
ホリエモンの描く未来図は私が昨日「●ハードゲイの…」の記事の中で懸念した、検索エンジンの上位にある情報だけで人々のアタマの中が塗りつぶされていくような社会の究極の姿だ。
結局のところゆとり教育のように、選択肢を広げているようで実はせばめてしまっているということなのだ。
ニュースだけじゃない。例えばホリエモンとか高城剛なんて方々は本屋なんていうのもなくなると思っているだろう。
「ネットで自宅から注文できるし、検索したら本屋で探すよりずっと効率がいい。」
なんてね
でも、それは最初から買う物がきまっていればいいけど、そうでなかったら書店サイトのシステムの言うがままの本としか出会えない。
たとえば本屋の店先で偶然見つけた本なんてことはあり得なくなる。理論の上ではどんなマイナーな本にでもたどりつけるはずなのだろうが、検索結果が100件も出てきたらそれらをちゃんと全部見る人はまれだろうし、検索システムがこちらの意向をすべてくみ取ってくれるとは限らない。だってホリエモンにいわせりゃ私たちの多くは「ろくにネットを使いこなしてない」そうだから。まさにデスクトップ(机上)の空論だ。
100冊の本の背(もしくは表紙)を見回すのは本屋の店内でならほんの短い時間ですむ。
本屋でぶらっと、手にとってパラパラという「インターフェイス」が完全にフォローできるシステムができないかぎりは本屋がなくなってはいけないのだ。
それにホリエモンがニュースに対して言ったように“人気がなければ消えていく”という方針だとマイナーなものはすべて淘汰される危険性がある。
ホリエモンはきっと「再販制度」なんてさっさとなくしたいんだろうな。
とにかく技術というのは“使えるようになったときに”使えばいいのだ。技術にあわせた環境作りなんて本末転倒。見通しのない人体実験だ。
そう、技術といえばスーパーニュースではビデオニュースネットワーク神保哲生代表が
「堀江氏の主張はハード面主眼にしたメディア論なんですよ、回線が太くなって双方向になるからこんなことができるあんなことができるってことをたくさん言ってる」
と言っていた。
別にインタラクティブ(双方向)ができるようになったからといって、なにがなんでもそれを使わなければいけないというわけじゃないはずだ。
その考え方って、まるでかつてヘアーが解禁になったときに、出さなきゃ損みたいに不自然なくらいヘアを強調したようなポーズを多用した三流グラビアのような気持ち悪さがある。
むかしアップルのスティーブ・ジョブズが来日して日本の某会社の工場視察に訪れたとき
「おまえら日本人はハードを作れ、ソフトはここにある」と自分のアタマを指さして言ったという、屈辱的なハナシがあるけど、実際、日本にはソフトがないと言われ続けてきた。
日本では時代の最先端を行くとされている?ホリエモンさまがあのザマってことは、今もきっと日本にソフトはないのだろう。
ここでいうソフトっていうのはインフラ整備ならその方針であったり、システム全体の設計思想やらを言うのであって、単に計算式を立てたり、機械を動かすためのプログラムを組んだりということではない。それらはカタチの上ではたしかにソフトウエアだが実質的な役割という意味ではハードウエアの一部にすぎないのだ。
また同番組で明治学院大学法学部の川上和久教授は
「テレビ局にしたって企業ですし収益をあげなければいけない部分はありますけど放送というのは、たとえば所得の低い人にも情報を届けるという使命を持っていると私は思うんですね」と言っている
私の部屋にあるテレビはコジマに並んで5000円で買ったものだがホリエモンのメディアミックスを享受するには金がかかりそうだ。
金がかかるという文句はIT全体に言いたい。たとえばパソコンなんて、ほんとは一般ユーザーにとっては既にオーバースペックのはずなんだけど、ソフト(OSを含む)がバージョンアップするごとに、“ちゃん”と重くなってくれるので、それに合わせてハードも新しくしなきゃいけない制度になっている。ソフトのほうはビックリするような便利な機能はふえてないにもかかわらず…だ。
まぁ、貧乏人に厳しいというのは地上波がそのうちデジタル化するということにもいえるけどね。あれも一体、誰のための進歩なんだか…。
昨日の報道ステーションで古館氏が
「ライブドア派か、フジテレビ派かすぐ言える人は実は何も考えてない人なじゃないですかね」
…っていってたけど、そう思う。
「新しいことをやろうとかるときはみんな批判はうけるものだからねぇ」
といってる、おばちゃん、“新しいこと”の中身を知ってるのかい?
「お金で強引にっていうのはねぇ」
といってるおっちゃん
いや、極論をいっちゃえば、将来やろうとしていることがみんなの幸せのためならちょっとくらい強引でもいいよ…
みんなマネーゲームに気をとられて、世の中が、大切な未来がどう転ぶかっていう想像をちっともしていないんだ。
世の中のバカ親は、自分の子供にブランドものとか着せてやったりするのに、子供達の未来にある環境ってことはあまり考えないのかね。
そんな親たちは公務員や官僚の腐敗が話題になっても、自分の子供がなってくれる分には嬉しかったりするのだろう。
我が子が将来、ホリエモンみたいになって欲しいなんて思ってる親、いっぱいいるんだろうなぁ。
【まとめ】
結局、ホリエモンの夢見る未来はアホを量産するどころか、人類から多様性を奪って種として脆弱化させ、しまいには機械に支配されるという「マトリックス」な社会だ…と。
で、他のITのひとたちも大差はないんだろうな…と。
フジテレビかんけーのことはもう書かないと心に誓ってからすでに3つか4つくらい書いしまった(笑)↓けど、今度こそ最後…ぽい(笑)
●ハードゲイの向こうに見える情報流通の未来 2005-03-22 01:20
●アメリカ式の毒でアメリカ式の終末を… 2005-03-19 04:33
●ザル法もまた法なり? 2005-03-19 02:08
●ビルズに恋して by Vincent Gallo なんちって 2005-03-16 00:55
●きっかけは~謎だらけ!もういっかーい 2005-03-11 03:52
●きっかけは~謎だらけ 2005-03-09 05:11
●蛇足、フィリピンバナナ100円 2005-03-08 07:15
●エデンの東のずっと東~Beast of Eden 2005-03-07 01:01
●Livedoor and let die 2005-03-05 07:32










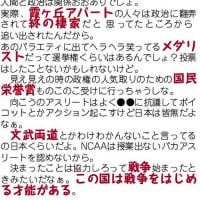
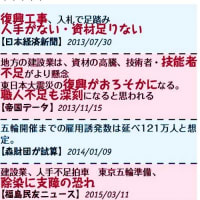












故に、そうした構えをしている人間達の堀江氏(およびIT関係者)に対する見方は、あたかも古いものを全て無に返す破壊主義者であるかのように定義して、おぼろげな脅威論を振りまいているかのようにも見え、それは対外脅威論を主張するタカ派政治家のそれにも重なって見えます。
ネット、それにパソコンに関わる人間でしたら、過去、大きな意味での「ログ」というものに価値を見出し、その価値あるものをどう扱うか一度は悩むものです。
再販制度というものは無くなるかもしれませんが、需要さえあれば別の形での旧作の提供方法・・・例えばデジタルデータでの提供や、受注生産といった「物理的な在庫を存在させない形の」提供方法が模索されるのではないのでしょうか。
進歩主義が辿った非現実的な思想を尊ぶ訳ではありませんが、悲観論に終始する社会は旧来の価値観への盲目的な賛美と回帰へと矮小化するのではないのかと、私は逆に危惧してしまいます。
フジ側はもちろん単純に保身という立場もあるので、堀江氏側の実態がどうあれ、なんらかの抵抗はしたと思いますし、今回はライブドア側から話を直接聞くことなく、「買収で経営価値が下がる」と主張しつづけていたことは裁判への心証を悪くしていたとも思います。
ただ実態がわかっていないかったかというと、そうは思いません。たしかに“経済体”としての、つまり資本的側面でのライブドアには得体の知れないジャングルに出没するゲリラのような脅威を感じていたかもしれませんが、彼らのメディアに対するポリシーについてはあちこちで堀江氏公言していたので大筋については誰の目にも明らかだった思います。
例えば、「メディアを殺す」発言では、言葉の選択がまずかったということを差し引いても「政治の記事は日本では人気がないからサンケイ新聞を経済新聞に作りかえたい」というのはジャーナリストの批判の的となるのには充分だったと思います。
しかしながら、今回の論争は
「株主を無視ししているフジテレビが悪い」
「いや、ライブドアのやり方は卑怯だ」
という経済的側面に終始し、このジャーナリストたちの怒りに対する反論はきこえてきませんでした。もちろん今回、反論がなかったからといってその主張の“勝ち”が確定したわけではありませんが、こちらの(メディア論の)ステージでも論議もう少しなされるべきだったかなと私は思っています。
さらに世論調査の意見にいたっては結局は賛成派も反対派も「人情論」の域を出ていなかったと思います。昨日の報道ステーションで紹介していた堀江氏の支持にまわっていた団塊の世代がこんどはフジテレビ側に傾いたという数字が示すように、最初は1ベンチャー企業が巨大企業に立ち向かう姿勢に共感を感じ、今度は強大な力にやられてるフジに同情を感じているという。なんかプロ野球の再編のイメージをそのままひきずっちゃってる気がします。放送局はかわらなきゃいけない…といってたおっちゃんが、フジテレビ側に傾くのはヘンですよね。
判官贔屓は日本人らしい考えではありますが、これからの世の中は、どちらが強者かという判断はわかりにくくなってくるので、いつまでもそういう価値観によりかかってはいられないでしょう。
たしかに、なんでもかんでも新しいものを否定するような人種というものは存在しますますし、それは時として未知のものへの脅威だけでなく、既得権益の固執であったりもするので、話はややこしいのですが、少なくとも(前の記事でも何回が書いていて重複になりますが)、元サンマイクロシステムズの創設メンバーでもあり科学者のビル・ジョイが警鐘を鳴らすように、技術の進歩にはそれが持つリスクへのケアは常に忘れてはいけないと思います。
もちろん石橋を叩いて渡らないのでは、進歩もクソもありませんし、何をもって見切り発車なのか?という線はひきずらいと思いますが、取り返しのつかないようなデメリットがはらんでいる場合にはよりいっそうの精査と準備が必要だと思います。
例えば原発なども放射能汚染という取り返しの付かない危険をはらんでいます。
「いや、事故については人的なミスであって技術的欠陥ではないぞ、あの事故をもって原発反対などというのは愚だ」
という意見も当然あろあかと思いますが、人を含んで初めてシステムといえるのではないかと思います。だって大汚染してから責任の所在追求したところで放射能は消えませんから。そこらへんがソフト面の整備ということになるのだと思います。
だから、携帯電話にしてもクローン電話を作られる可能性があるなら、携帯電話ほ発売しちゃいけなかった…のでは決してなく、そういうにリスクに対するマネージメント体制ができてなければいけなかったということです。あれってNTTはまだ認めてなかったんですっけ?「RL」には随分前に製作実験結果まで出してましたが(笑)
少なくとも私の目には、なんでもかんでも新しいもの反対派より、売らんかなのIT派のほうが、幅を利かせているように見えますが。まぁこれはあるいは少数派の意見なのかもしれませんが…。
それと
これも、前に書いた重複ですけど、ライブドア一社提供番組(正確にはライブドアグループ)である「指名手配」のサイトを見るとライブドアのサーバに飛ばされた上にID登録しなきゃならないということもさることながら、ページのデザインのセンスがねぇなぁ…と思ってしまいます。デザインのセンスというのは別に美しいとかアーティスティックということではなく見やすさ、使いやすさという点で。
ハッキリいってテレビ局のサイトのトップページってどこもゴチャゴチャしててISDNの私には重くて迷惑この上ないですけど、フジテレビのは配置や階層の作り方がかなりマシ。まぁ、トップページのオススメが深夜の番組の場合、次の日の日付になってしまうとか色々とツッコミどころはありますが…
とにかくユーザーインターフェイスへの配慮なしにITの進歩はないと思います。インターフェイスデザインって日本が遅れている分野だと思うんですがどうでしょうか?向こう(主に米国。主に衣料・雑貨系)のショッピングサイトとかだと、ひねくれ者の私にも「So Cool!!」といわせてしまうサイトがけっこうありますよ。
…と一見話がそれているように思われるでしょうが、要するに便利になってくれたらそれでいい、とは思っているのです。ホリエモンは「多くの人はろくにネットを使いこなしてない」と豪語していたので、どれだけ人に優しいインターフェイスを提供してくれるのか見物です。でも、フジテレビのサイト見るのに最初にID登録しなきゃならなくなったらちよっとイヤだなぁ…とも思っています。
うちは無断転載OKなので、パクリだとしても目くじら立てたりしませんよ(笑)。
偶然同じタイトルだったのも何かの縁、今後ともよろしくお願いします。
そういうことだろうとは思ってはいたんですが
実のところ私のほうが勝手にビックリしちゃったんですよ
こんな組み合わせが偶然会うなんて
ちょっと得したような不思議な気もしますけどね
こちらこそよろしくお願いいたします