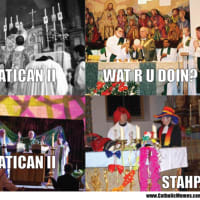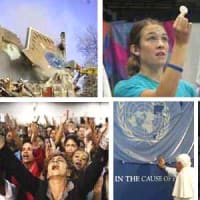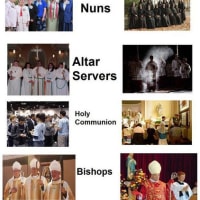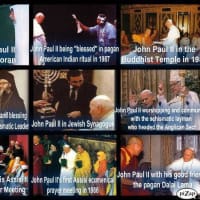5いけにえを実現させる4つの要素
いけにえがどのように実現するのかについてみてみよう。いけにえを実現させるものの中には次の4つの要素がある。
それは
1) キリスト
2) 司祭
3) 教会
4) 信者
であるが、それらについて見てみよう。
(1) 信者の占める位置
新しい司式に於いては信者の占める位置は自律的(切り離されている)78であり、全く偽りである。これは、最初の定義「ミサは、聖なる集会の儀、すなわち、民の集会である79」から司祭の会衆への挨拶に至るまで(総則28番)そうである。司祭の会衆への挨拶は一同に会した共同体に「主の現存」を示すためであり、この挨拶と会衆の返答とによって集った教会の神秘が表されるとされている。80
そこで暗示されていることは、確かにキリストは本当に現存されるが、しかし、それはただ単に霊的な現存に過ぎないこと、そして、教会の神秘は、ある一つの集会がそのような霊的現存を表し願っているに限りにおける教会の神秘に過ぎないということ、である。
この解釈は常に強調されている。
ミサの共同体的性格を取り憑かれているかのように言及することによって(74〜152番)。
「会衆の参加するミサ81」(77番〜126番)と「会衆の参加しないミサ82」という、依然にはなかった区別を付けることによって(209〜231番)。
「共同祈願、すなわち信徒の祈り」という定義によって(45番)。共同祈願の定義には、またしても、平信徒の「祭司職」83が強調され、この平信徒の祭司職が司祭の祭司職と切り離され、自律的であるかのように提示され、司祭の祭司職に従属することが全く述べられていない。しかし、司祭は聖別を受けた仲介者としてTe igiturの祈りと、2つのMementoの祈りの中で会衆の全ての意向を取り次ぐものである。
「第三奉献文84」(Vere sanctus, p.123)に於いては、次の言葉が主に対して発せられる。「御身はご自分のために民を集めることを絶えず続け給う。そは日の昇るところから沈むとことまで御身の御名に清き捧げものが捧げられん為なり。85」ここで、「そは、〜が為なり」(ut)という言葉のために、ミサを捧げるために必要かくべからざる要素として司祭よりも民が全面にでている。そして、ここでは誰が捧げるのかが明らかではない86ために、会衆は司祭を必要とせず、独立の司祭職を行使する権能を持っているかのように見える。この段階から、それほど長くない間に平信徒が司祭と共に聖変化の言葉を発するのが許されるようになったとしても(このことは既にあちらこちらで見受けられているが)、それは驚くに値しないだろう。
2)司祭の占める位置
司祭の立場は過小化され、変えられ、間違っている。
1. まず第一に、平信徒との関係に於いて、司祭は「キリストのペルソナにおいて87ミサを執行する聖別された司式者」ではなく、その代わりに、よくても平信徒たちの単なる座長、或いは兄弟として取り扱われている。
2. 第二に、教会との関係に於いては、司祭は「民のなかの或る一人88」である。エピクレーシスの定義に於いて(55番)天主への呼びかけは特定の個人がなすものではなく、教会がなすものとされている89。そのため司祭の役割は消されてしまっている。
3. 告白の祈り。告白の祈りは今ではもはや集団的になってしまった。司祭はもはや天主とともなる裁判官・証人・取り次ぎ者ではなくなった。そのため、司祭がかつてしていた許しを与えることが廃止されたのは論理的だといわねばならない。司祭は兄弟達の一部となった。「会衆の参加していないミサ」に於いて侍者でさえも告白の祈りの時に司祭を兄弟と呼ぶようになった。
4. 既に、この典礼改革の前から、司祭の聖体拝領と平信徒の聖体拝領という意味深い区別が廃止されていた。司祭の聖体拝領に於いて、永遠の大司祭(=イエズス・キリスト)とキリストのペルソナにおいて90行為している者(=司祭)が最も親密な一致に到達するのである。
5. 今では、司祭のいけにえを捧げる権能について、或いは司祭に固有な聖別するという行為について、つまり、司祭を通して御聖体における主の現実的な現存が生じることについて一言でさえも見いだすことが出来ない。今ではもはやカトリック司祭は、プロテスタントの牧師以外の何ものでもないようだ。
6. ある場合には、白衣とストラさえあればミサを捧げても良くなった(298番)など、祭服は目の前から消え失せ、任意的になった。祭服は、司祭が元来もっているキリストとの同一性を意味し、祭服が消えることによっては、この司祭とキリストとの同一性をゆがめてしまっている。つまり、司祭はキリストの全ての美徳を身につけているものではなく、平信徒と区別できるような点は1つか2つそこそこしか持たない単なる「非常任の役員」に成り下がっている91。ある現代の説教者92が与えたユーモラスな(しかし彼自身にとってはまじめな)定義によれば司祭は「その他の人よりもほんの少しだけましな人93」でしかない。
3)教会の占める位置
最後にキリストに関する教会の立場を見よう。「会衆の参加しないミサ」というただ唯一の例外を除けば、ミサが「キリストと教会の行為94」(総則4番・司祭職に関する教令14番参照)とは見なされていない。
「会衆の参加するミサ」においては、「キリストを思い起こし」、列席の会衆を聖化するためという目的を除いて、教会については、全く言及がなされていない。「司祭も、集会を司会し、その祈りを指導し、…キリストによって聖霊において神である父にいけにえを奉献するに当たって、会衆とともに一つになり95…。(60番)。」
ここでは、「聖霊を通して、父なる天主に96ご自分自身を捧げ給うキリストに、会衆を結びつける」と言うべきではなかったのではないか。
この文脈に於いて、次の諸点に注意すべきである。
まず第一に、「我らの主キリストによりて」という、いつの時代にあっても祈りが聞き入れられるための教会に与えられた保証の言葉が省略されているという重大な事態。(ヨハネ14:13-14、15:16、16:23-24)
第二に、どこにでも顕著な「復活主義97」。それはあたかも「聖寵の交わり」ということに、これほど重要な観点がもはや別に存在しないかのようである。
第三に、恒常的で永遠の現実である超自然の聖寵の分与ということが、時間の次元へと引きずり降ろされてしまっているほどの奇妙で疑わしい「終末主義」。われわれはもはや「暗闇の権力」に対する戦闘の教会ではなく、「永遠との結びつきを失ってしまったただ純粋に現世的なことでしか考えられていない未来」へと向かって旅する教会、歩む人々のことを聞くようになった。
教会は、一・聖・公・使徒継承とはもはや言われなくなった。第4奉献文98では、ローマ・カノンの祈りの「全ての正統カトリック使徒継承の信仰を保持する人々のために99」の代わりに、今ではただ単に「真摯なこころで御身を求めるすべての人の100」になってしまった。
更にまた、死者の記念では「信仰の印を持って平安の眠りに眠る101」が無くなってしまった。そこではただ単に「御身のキリストの平安に於いて逝った102」だけであり、しかも以前の目に見える一致という観念を明確によりひどく破壊するさらなる言葉が付け加えられた。「御身のみがその信仰を知り給う103」全ての死者のいけにえ、と。
さらに、既に述べたように、新しく作られた3つの「奉献文」のうちどれも死んだ人々の苦しんでいる状態を言及するものがない。特定の死者の記念の可能性さえない。これら全てはまたしてもミサのいけにえの罪を償い贖う性質についての信仰を破壊してしまうことだろう104。
どこにもかしこにもある省略は、教会の神秘の土台を壊し非神聖化させるものである。特に教会は聖なる位階制度として表されてはいない。天使達や諸聖人は共同の告白の祈りの第2部で名前を列挙されずに全てひっくるめられている。第1部において、聖ミカエルの名を省略することにより、聖ミカエルのペルソナに於いて、証人かつ裁判者としての諸天使・諸聖人は全て消え失せてしまった105。様々な位階の天使達も「第二奉献文」の新しい序唱から消え失せてしまった。(これは以前にはなかったことである。)コムニカンテスにおいて、ローマの教会がその上に建てられた、また彼らによって疑いもなく使徒の聖伝が伝えられた、聖なる教皇と殉教者達の記念をしていた。聖グレゴリオは、彼らの名を列挙してこれを完成させ、それを持ってローマ・ミサとなったのであるが、新しいものはそのコムニカンテス106からこれらの聖なる教皇や殉教者達の記念が廃止されてしまった。リベラ・ノス107の祈りにおいては聖母マリア、使徒と全ての聖人がもはや言及されなくなってしまった。こうして、聖母や諸聖人の取り次ぎはもはや危険の時に於いてでさえ求めなくなってしまった。
式次第の全てから、新しい3つの「奉献文」を含めて、ローマの教会の創立者である使徒聖ペトロと聖パウロ、そして唯一の普遍の教会の基礎かつ印であるその他の使徒達の名前を全く省略されてしまったのは耐えることが出来ない。唯一それが残っているのはローマ・カノンのコムニカンテスの中でだけである。これによって教会の一致は非常にゆゆしく弱められるだろう。
司祭が侍者なしに司式しているときに全ての挨拶、最後の祝福が省略されることにより、また「イテ・ミサ・エスト」は侍者がいるときでも、会衆が参加していなければ、もはや言わなくなってしまった。108諸聖人の通功というドグマが明らかに攻撃を受けている。
ミサの最初の告白の祈りが2つあったことは、司祭がキリストの役者の能力を身にまといながらも深々と上体を下げ、自分がこの崇高な使命にふさわしくないこと・彼が今なそうとしている恐るべき神秘109にふさわしくないことをどれほど良く認めているかを示していた。更には「主よ、願わくは我らより罪を遠ざけ、清き心を持って至聖なるところに入らせ給え」の祈り110で至聖所に侵入することさえもふさわしくないことをいかに良く認めていた。そのために祭壇に封印された聖遺物の殉教者達の功徳の取り次ぎを「主よ、ここに聖遺物を置く主の聖人らの功徳、また全ての聖人らの功徳によって、私の罪を赦し給えと我らは祈る。」の祈りをもって願っていた111を示していた。しかし、「主よ、願わくは我らより罪を遠ざけ・・・112 」の祈りも、「主よ、ここに聖遺物を置く・・・113」の祈りも両方とも省略されてしまった。告白の祈りが2つあったということ、また司祭と平信徒との2回の聖体拝領があることに関して既に述べたことはここでもまた意味深長である。
いけにえを捧げているという外的要素、つまり、ミサの聖なる性格を明らかにさせるものは非神聖化された。例えば、至聖所以外での司式のために叙述されていることを見ると、祭壇の代わりに、聖別された祭壇石や聖遺物のない単なる「食卓114」を用いて良いことになっている。しかも、祭壇布は1枚だけで良くなっている。(260、265番)ここでもまた、既に述べた主の現存にかかわることを全て適応することが出来る。「食卓に連なること115」と食事のいけにえを主の現存から切り離してしまっている。
非神聖化への過程は新しい供え物の行列によって完成された。すなわち種なしパンであるよりもむしろ普通のパンについて語られている。侍者の子供でさえ(しかも、両形態での聖体拝領の時には平信徒まで)もが、聖器具に触れることが許されていること(244番の「ニ」116)。司祭、助祭、教会奉仕者117、宣教奉仕者118、詩編を唱える係119、解説者120 (司祭は自分のしようとしていることを絶えず「説明」するように要請されているので司祭自身さえも注解者となってしまっている。)、男女の朗読者、会衆を門で出迎えて席まで付き添う奉仕者121、献金を集める人122、またその他、供え物を運ぶ人123、供え物を受け取る人、などなど、多くの侍者や平信徒が絶え間なく教会内をあちこちに行き来し非常に気を散らせる雰囲気。これら全ての規定された活動のほかに非聖書的であり非パウロ的な規定がある。それは、「ふさわしい女性124」が教会の聖伝に於いて初めて朗読し、さらに司祭がすること以外のことを執行する125のが許される(70番)。最後に、偏狂的な共同司式の強調。これによってついには司祭の御聖体への信心を破壊し、唯一の司祭かつ犠牲であるキリストの中心的姿をぼかし、このキリストという中心を共同司式者の集団的存在が影を覆って解き崩してしまうだろう126。
78 Autonoma (absoluta)
79 Missa est sacra synaxis seu congregatio populi.
80 "Qua salutatione et populi resonsione, manifestatur ecclesiae congregatae mysterium."(この挨拶と会衆の応答は、ともに集まった教会の神秘を表す。)
81 cum populo
82 sine populo
83 "populus sui sacerdotii munus exercens"(総則45番「共同祈願、すなわち信徒の祈りにおいて、会衆は、自分の祭司職の務めを実行して、全ての人のために祈る。」)
84 Prex eucharistica III
85 "populum tibi congregare non desinis ut a solis ortu usque occasum oblatio munda offeratur nomini tuo"
86 原注17: ルター派とカルヴィン派は全てのキリスト者が司祭であり、全てのキリスト者が晩餐を捧げると主張している。しかし、トリエント公会議に従えば(第22総会Canon 2 DS1752)、「全ての司祭は、そして司祭だけが、ミサのいけにえの二次的な司式者である。キリストがミサの第1の司式者である。信者も捧げるが、それは厳密な意味におけるのではなく、司祭を通して、間接的に捧げるのである。」(A. Tanquerey, Synopsis thologiae dogmaticae Descl?e 1930, t. III)
87 in persona Christi
88 "quidam de populo"
89 エピクレーシスについて、総則の55番「ハ」は、こう言っている。「この特別な祈りによって、教会は神の力を願い求め、…祈る。」
90 in persona Christi
91 原注18: キリスト教を信ずる民にとって信じられないほどの、且つ、悲惨な改革は、聖金曜日の祭服の色が黒ではなく、赤になったことである(総則308番のロ)。赤は、特に殉教者を記念する色であり、教会がその花婿であるイエズス・キリストの死を喪に服す色ではない。
92 原注19: これは、フランスのドミニコ会司祭Pere Roguet O.P.のことである。
93 "un homme un peu plus homme que les autres"
94 actio Christi et Ecclesiae
95 "Presbyter celebrans... populum... sibi sociat in offerendo sacrificio per Christum in Spiritu Sancto Deo Patri"
96 per Spiritum Sanctum Deo Patri
97 paschalismo
98 "prex eucharistica IV"
99 "pro omnibus orthodoxis atque catholicae fidei cultoribus"
100 "omnium qui te quaerunt corde sincero"
101 "cum signo fidei, et dormiunt in somno pacis"
102 "obieunt in pace Christi tui"
103"Quorum fidem tu solus cognovisti"
104 原注20: ローマ・カノンの翻訳のうちいくつかは、"locus refrigerii,lucis et pacis"(すずしみと光と平和の場所)が、「至福、光、平和」という状態として訳されている。「苦しむ教会」に関して明確な言及が消え失せてしまったことについては何と言ったらよいだろうか!
105 原注21: この省略omissionの病熱の最中に、ただ一つ付け加えられた言葉がある。それは、告白の祈りのなかで罪を告白し、「思い」と「言葉」と「行い」に続けて「怠りomissio」の罪が付け加えられたことである。
106 Communicantes, et momoriam venerantes, in primis gloriosae semper Virginis Mariae, Genitricis Dei et Domini nostri Jesu Christi, sed et beatorum Apostolorum ac Martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andeae, Jacobi, Joannis, Thomae, Jacobi, Philipi, Bartholomaei, Matthaei, Simonis et Thaddaei: Lini, Cleti, Clementis, Xysti, Cornelii, Cypriani, Laurentii, Chrysogoni, Joannis et Pauli, Cosmae et Daminai: omnium Sanctorum tuorum; quorum meritis, precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tuae muniamur auxilio. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.(聖なる一致をしつつ、我らは、まず、我らの天主なる主、イエズス・キリストの御母、終生童貞なる光栄あるマリアの記念を謹んで行い奉る。また更に、主の聖なる使徒かつ殉教者、ペトロとパウロ、アンドレア、ヤコボ、ヨハネ、トマ、ヤコボ、フィリッポ、バルトロメオ、マテオ、シモンとタデオ、また、リノ、クレト、クレメンテ、シクスト、コルネリオ、チプリアノ、ラウレンチオ、クリソゴノ、ヨハネとパウロ、コスマとダミアノ、および主の全ての聖人らの記念を恭しく行い奉る。願わくは、彼らの功徳と祈りとによって、我らが全てにおいて御身の保護の助力を与え給わんことを。同じ我らの主キリストによりて、アーメン。)
107 Libera nos, quaesumus, Domine, ab onmibus malis, praeteritis, praesentibus, et futuris: et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Dei Genitrice Maria, cum beatis Apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea, et omnibus Sanctis, da propitius pacem in diebus nostris: ut ope misericordiae tuae adjuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi.(主よ、願わくは、過去、現在、未来の全ての悪より我らを救い給え。終生童貞なる永福の光栄ある天主の御母マリアと御身の至福なる使徒ペトロとパウロ、また、アンドレアとともに、全ての諸聖人のおん取り次ぎにより、おん慈悲をもって今日平安を与え給え。そは、おん憐れみの御業に助けられ、常に我らが罪から救われ、全ての惑わしから安全に守られんがためなり。)
108 原注22: 新しい司式が提示されたとき記者会見の席で、レキュイェ神父P?re L?cuyerは理性だけを信じているという「信仰宣言」をはっきりとし、会衆の参加していないミサでの挨拶は、「Dominus tecum主はあなたと共に」「Ora, frater兄弟よ祈れ。」という言い方を考えているとさえいった。これは、「作り事がなくなり、真理に適わないことがなくなるためである」(ソノママ)とのことである。
109 "tremendum mysterium"
110 "Aufer a nobis"の祈り
111 "Oramus te, Domineの祈り
112 "Aufer a nobis"
113 "Omramus te, Domine"
114 "mensa" 総則の260番には、「感謝の祭儀は、…聖堂以外の場所においては、…適当な机の上でも行うことが出来る。但し必ず食卓布とコルポラーレを備えなければならない」とある。総則の265番には「可動祭壇、もしくは聖堂外の祭儀が行われる机(260参照)には、聖別された石をおく必要はない」とある。
115 "convivium"
116 総則244番の「ニ」によると、「助祭または教会奉仕者[これは、いわゆる侍者のことである。]は、カリスとプリフィカトリウムを拝領者に差し出し、拝領者は、適宜に、自分の手で、カリスを口に持って行く。拝領者は、左手でプリフィカトリウムを口の下に保ち、こぼさないように注意しながら、少量の御血をカリスから拝領する」とある。
117 総則65:「教会奉仕者は、祭壇での奉仕と、司祭及び助祭を助けるために選任される。教会奉仕者には、特に祭具の準備をすること、及び特別奉仕者として聖体を信者に授けることが委ねられる。」
118 総則66:「聖教奉仕者は、福音を除き、聖書を朗読するために選任される。また共同祈願の意向を述べ、詩編朗読者がいないときには、朗読の合間に詩編を唱えることが出来る。宣教奉仕者は、感謝の祭儀において、固有の役割を持っている。この役割は、より上級の位階の奉仕者がいる場合にも、宣教奉仕者自らが果たさなければならない。」
119 総則67:「朗読の間にある詩編または聖書参加を朗唱することは詩編朗唱者の務めである。」
120 総則68の「イ」:「解説者=信者を祭儀に導き、よりよく理解させるために、信者に指示や説明を与える。」
121 総則68の「ロ」:「案内係=地方によっては、教会の入り口で信者を迎え、適当な席に案内し、また行列を整理する。」
122 総則68の「ハ」
123 総則68「また、ミサ典礼書、十字架、ろうそく、パン、ぶどう酒、水、香炉を運ぶ者がある。」
124 mulier idonea 総則70:「助祭に固有な役務以外の役務は、選任を受けていなくとも、男子信徒が行うことが出来る。司祭席の外で行われる役務は、…女子にも委ねることが出来る。」
125 "ministeria quae extra presbyterium peraguntur"
126 原注23: このことに関して、今ではたとえ司祭が共同司式の前或いは後に一人でミサを捧げなければならない時でさえも、司祭はもう一度共同司式の時に両形色で聖体拝領することが合法的になってしまったようである。
いけにえがどのように実現するのかについてみてみよう。いけにえを実現させるものの中には次の4つの要素がある。
それは
1) キリスト
2) 司祭
3) 教会
4) 信者
であるが、それらについて見てみよう。
(1) 信者の占める位置
新しい司式に於いては信者の占める位置は自律的(切り離されている)78であり、全く偽りである。これは、最初の定義「ミサは、聖なる集会の儀、すなわち、民の集会である79」から司祭の会衆への挨拶に至るまで(総則28番)そうである。司祭の会衆への挨拶は一同に会した共同体に「主の現存」を示すためであり、この挨拶と会衆の返答とによって集った教会の神秘が表されるとされている。80
そこで暗示されていることは、確かにキリストは本当に現存されるが、しかし、それはただ単に霊的な現存に過ぎないこと、そして、教会の神秘は、ある一つの集会がそのような霊的現存を表し願っているに限りにおける教会の神秘に過ぎないということ、である。
この解釈は常に強調されている。
ミサの共同体的性格を取り憑かれているかのように言及することによって(74〜152番)。
「会衆の参加するミサ81」(77番〜126番)と「会衆の参加しないミサ82」という、依然にはなかった区別を付けることによって(209〜231番)。
「共同祈願、すなわち信徒の祈り」という定義によって(45番)。共同祈願の定義には、またしても、平信徒の「祭司職」83が強調され、この平信徒の祭司職が司祭の祭司職と切り離され、自律的であるかのように提示され、司祭の祭司職に従属することが全く述べられていない。しかし、司祭は聖別を受けた仲介者としてTe igiturの祈りと、2つのMementoの祈りの中で会衆の全ての意向を取り次ぐものである。
「第三奉献文84」(Vere sanctus, p.123)に於いては、次の言葉が主に対して発せられる。「御身はご自分のために民を集めることを絶えず続け給う。そは日の昇るところから沈むとことまで御身の御名に清き捧げものが捧げられん為なり。85」ここで、「そは、〜が為なり」(ut)という言葉のために、ミサを捧げるために必要かくべからざる要素として司祭よりも民が全面にでている。そして、ここでは誰が捧げるのかが明らかではない86ために、会衆は司祭を必要とせず、独立の司祭職を行使する権能を持っているかのように見える。この段階から、それほど長くない間に平信徒が司祭と共に聖変化の言葉を発するのが許されるようになったとしても(このことは既にあちらこちらで見受けられているが)、それは驚くに値しないだろう。
2)司祭の占める位置
司祭の立場は過小化され、変えられ、間違っている。
1. まず第一に、平信徒との関係に於いて、司祭は「キリストのペルソナにおいて87ミサを執行する聖別された司式者」ではなく、その代わりに、よくても平信徒たちの単なる座長、或いは兄弟として取り扱われている。
2. 第二に、教会との関係に於いては、司祭は「民のなかの或る一人88」である。エピクレーシスの定義に於いて(55番)天主への呼びかけは特定の個人がなすものではなく、教会がなすものとされている89。そのため司祭の役割は消されてしまっている。
3. 告白の祈り。告白の祈りは今ではもはや集団的になってしまった。司祭はもはや天主とともなる裁判官・証人・取り次ぎ者ではなくなった。そのため、司祭がかつてしていた許しを与えることが廃止されたのは論理的だといわねばならない。司祭は兄弟達の一部となった。「会衆の参加していないミサ」に於いて侍者でさえも告白の祈りの時に司祭を兄弟と呼ぶようになった。
4. 既に、この典礼改革の前から、司祭の聖体拝領と平信徒の聖体拝領という意味深い区別が廃止されていた。司祭の聖体拝領に於いて、永遠の大司祭(=イエズス・キリスト)とキリストのペルソナにおいて90行為している者(=司祭)が最も親密な一致に到達するのである。
5. 今では、司祭のいけにえを捧げる権能について、或いは司祭に固有な聖別するという行為について、つまり、司祭を通して御聖体における主の現実的な現存が生じることについて一言でさえも見いだすことが出来ない。今ではもはやカトリック司祭は、プロテスタントの牧師以外の何ものでもないようだ。
6. ある場合には、白衣とストラさえあればミサを捧げても良くなった(298番)など、祭服は目の前から消え失せ、任意的になった。祭服は、司祭が元来もっているキリストとの同一性を意味し、祭服が消えることによっては、この司祭とキリストとの同一性をゆがめてしまっている。つまり、司祭はキリストの全ての美徳を身につけているものではなく、平信徒と区別できるような点は1つか2つそこそこしか持たない単なる「非常任の役員」に成り下がっている91。ある現代の説教者92が与えたユーモラスな(しかし彼自身にとってはまじめな)定義によれば司祭は「その他の人よりもほんの少しだけましな人93」でしかない。
3)教会の占める位置
最後にキリストに関する教会の立場を見よう。「会衆の参加しないミサ」というただ唯一の例外を除けば、ミサが「キリストと教会の行為94」(総則4番・司祭職に関する教令14番参照)とは見なされていない。
「会衆の参加するミサ」においては、「キリストを思い起こし」、列席の会衆を聖化するためという目的を除いて、教会については、全く言及がなされていない。「司祭も、集会を司会し、その祈りを指導し、…キリストによって聖霊において神である父にいけにえを奉献するに当たって、会衆とともに一つになり95…。(60番)。」
ここでは、「聖霊を通して、父なる天主に96ご自分自身を捧げ給うキリストに、会衆を結びつける」と言うべきではなかったのではないか。
この文脈に於いて、次の諸点に注意すべきである。
まず第一に、「我らの主キリストによりて」という、いつの時代にあっても祈りが聞き入れられるための教会に与えられた保証の言葉が省略されているという重大な事態。(ヨハネ14:13-14、15:16、16:23-24)
第二に、どこにでも顕著な「復活主義97」。それはあたかも「聖寵の交わり」ということに、これほど重要な観点がもはや別に存在しないかのようである。
第三に、恒常的で永遠の現実である超自然の聖寵の分与ということが、時間の次元へと引きずり降ろされてしまっているほどの奇妙で疑わしい「終末主義」。われわれはもはや「暗闇の権力」に対する戦闘の教会ではなく、「永遠との結びつきを失ってしまったただ純粋に現世的なことでしか考えられていない未来」へと向かって旅する教会、歩む人々のことを聞くようになった。
教会は、一・聖・公・使徒継承とはもはや言われなくなった。第4奉献文98では、ローマ・カノンの祈りの「全ての正統カトリック使徒継承の信仰を保持する人々のために99」の代わりに、今ではただ単に「真摯なこころで御身を求めるすべての人の100」になってしまった。
更にまた、死者の記念では「信仰の印を持って平安の眠りに眠る101」が無くなってしまった。そこではただ単に「御身のキリストの平安に於いて逝った102」だけであり、しかも以前の目に見える一致という観念を明確によりひどく破壊するさらなる言葉が付け加えられた。「御身のみがその信仰を知り給う103」全ての死者のいけにえ、と。
さらに、既に述べたように、新しく作られた3つの「奉献文」のうちどれも死んだ人々の苦しんでいる状態を言及するものがない。特定の死者の記念の可能性さえない。これら全てはまたしてもミサのいけにえの罪を償い贖う性質についての信仰を破壊してしまうことだろう104。
どこにもかしこにもある省略は、教会の神秘の土台を壊し非神聖化させるものである。特に教会は聖なる位階制度として表されてはいない。天使達や諸聖人は共同の告白の祈りの第2部で名前を列挙されずに全てひっくるめられている。第1部において、聖ミカエルの名を省略することにより、聖ミカエルのペルソナに於いて、証人かつ裁判者としての諸天使・諸聖人は全て消え失せてしまった105。様々な位階の天使達も「第二奉献文」の新しい序唱から消え失せてしまった。(これは以前にはなかったことである。)コムニカンテスにおいて、ローマの教会がその上に建てられた、また彼らによって疑いもなく使徒の聖伝が伝えられた、聖なる教皇と殉教者達の記念をしていた。聖グレゴリオは、彼らの名を列挙してこれを完成させ、それを持ってローマ・ミサとなったのであるが、新しいものはそのコムニカンテス106からこれらの聖なる教皇や殉教者達の記念が廃止されてしまった。リベラ・ノス107の祈りにおいては聖母マリア、使徒と全ての聖人がもはや言及されなくなってしまった。こうして、聖母や諸聖人の取り次ぎはもはや危険の時に於いてでさえ求めなくなってしまった。
式次第の全てから、新しい3つの「奉献文」を含めて、ローマの教会の創立者である使徒聖ペトロと聖パウロ、そして唯一の普遍の教会の基礎かつ印であるその他の使徒達の名前を全く省略されてしまったのは耐えることが出来ない。唯一それが残っているのはローマ・カノンのコムニカンテスの中でだけである。これによって教会の一致は非常にゆゆしく弱められるだろう。
司祭が侍者なしに司式しているときに全ての挨拶、最後の祝福が省略されることにより、また「イテ・ミサ・エスト」は侍者がいるときでも、会衆が参加していなければ、もはや言わなくなってしまった。108諸聖人の通功というドグマが明らかに攻撃を受けている。
ミサの最初の告白の祈りが2つあったことは、司祭がキリストの役者の能力を身にまといながらも深々と上体を下げ、自分がこの崇高な使命にふさわしくないこと・彼が今なそうとしている恐るべき神秘109にふさわしくないことをどれほど良く認めているかを示していた。更には「主よ、願わくは我らより罪を遠ざけ、清き心を持って至聖なるところに入らせ給え」の祈り110で至聖所に侵入することさえもふさわしくないことをいかに良く認めていた。そのために祭壇に封印された聖遺物の殉教者達の功徳の取り次ぎを「主よ、ここに聖遺物を置く主の聖人らの功徳、また全ての聖人らの功徳によって、私の罪を赦し給えと我らは祈る。」の祈りをもって願っていた111を示していた。しかし、「主よ、願わくは我らより罪を遠ざけ・・・112 」の祈りも、「主よ、ここに聖遺物を置く・・・113」の祈りも両方とも省略されてしまった。告白の祈りが2つあったということ、また司祭と平信徒との2回の聖体拝領があることに関して既に述べたことはここでもまた意味深長である。
いけにえを捧げているという外的要素、つまり、ミサの聖なる性格を明らかにさせるものは非神聖化された。例えば、至聖所以外での司式のために叙述されていることを見ると、祭壇の代わりに、聖別された祭壇石や聖遺物のない単なる「食卓114」を用いて良いことになっている。しかも、祭壇布は1枚だけで良くなっている。(260、265番)ここでもまた、既に述べた主の現存にかかわることを全て適応することが出来る。「食卓に連なること115」と食事のいけにえを主の現存から切り離してしまっている。
非神聖化への過程は新しい供え物の行列によって完成された。すなわち種なしパンであるよりもむしろ普通のパンについて語られている。侍者の子供でさえ(しかも、両形態での聖体拝領の時には平信徒まで)もが、聖器具に触れることが許されていること(244番の「ニ」116)。司祭、助祭、教会奉仕者117、宣教奉仕者118、詩編を唱える係119、解説者120 (司祭は自分のしようとしていることを絶えず「説明」するように要請されているので司祭自身さえも注解者となってしまっている。)、男女の朗読者、会衆を門で出迎えて席まで付き添う奉仕者121、献金を集める人122、またその他、供え物を運ぶ人123、供え物を受け取る人、などなど、多くの侍者や平信徒が絶え間なく教会内をあちこちに行き来し非常に気を散らせる雰囲気。これら全ての規定された活動のほかに非聖書的であり非パウロ的な規定がある。それは、「ふさわしい女性124」が教会の聖伝に於いて初めて朗読し、さらに司祭がすること以外のことを執行する125のが許される(70番)。最後に、偏狂的な共同司式の強調。これによってついには司祭の御聖体への信心を破壊し、唯一の司祭かつ犠牲であるキリストの中心的姿をぼかし、このキリストという中心を共同司式者の集団的存在が影を覆って解き崩してしまうだろう126。
78 Autonoma (absoluta)
79 Missa est sacra synaxis seu congregatio populi.
80 "Qua salutatione et populi resonsione, manifestatur ecclesiae congregatae mysterium."(この挨拶と会衆の応答は、ともに集まった教会の神秘を表す。)
81 cum populo
82 sine populo
83 "populus sui sacerdotii munus exercens"(総則45番「共同祈願、すなわち信徒の祈りにおいて、会衆は、自分の祭司職の務めを実行して、全ての人のために祈る。」)
84 Prex eucharistica III
85 "populum tibi congregare non desinis ut a solis ortu usque occasum oblatio munda offeratur nomini tuo"
86 原注17: ルター派とカルヴィン派は全てのキリスト者が司祭であり、全てのキリスト者が晩餐を捧げると主張している。しかし、トリエント公会議に従えば(第22総会Canon 2 DS1752)、「全ての司祭は、そして司祭だけが、ミサのいけにえの二次的な司式者である。キリストがミサの第1の司式者である。信者も捧げるが、それは厳密な意味におけるのではなく、司祭を通して、間接的に捧げるのである。」(A. Tanquerey, Synopsis thologiae dogmaticae Descl?e 1930, t. III)
87 in persona Christi
88 "quidam de populo"
89 エピクレーシスについて、総則の55番「ハ」は、こう言っている。「この特別な祈りによって、教会は神の力を願い求め、…祈る。」
90 in persona Christi
91 原注18: キリスト教を信ずる民にとって信じられないほどの、且つ、悲惨な改革は、聖金曜日の祭服の色が黒ではなく、赤になったことである(総則308番のロ)。赤は、特に殉教者を記念する色であり、教会がその花婿であるイエズス・キリストの死を喪に服す色ではない。
92 原注19: これは、フランスのドミニコ会司祭Pere Roguet O.P.のことである。
93 "un homme un peu plus homme que les autres"
94 actio Christi et Ecclesiae
95 "Presbyter celebrans... populum... sibi sociat in offerendo sacrificio per Christum in Spiritu Sancto Deo Patri"
96 per Spiritum Sanctum Deo Patri
97 paschalismo
98 "prex eucharistica IV"
99 "pro omnibus orthodoxis atque catholicae fidei cultoribus"
100 "omnium qui te quaerunt corde sincero"
101 "cum signo fidei, et dormiunt in somno pacis"
102 "obieunt in pace Christi tui"
103"Quorum fidem tu solus cognovisti"
104 原注20: ローマ・カノンの翻訳のうちいくつかは、"locus refrigerii,lucis et pacis"(すずしみと光と平和の場所)が、「至福、光、平和」という状態として訳されている。「苦しむ教会」に関して明確な言及が消え失せてしまったことについては何と言ったらよいだろうか!
105 原注21: この省略omissionの病熱の最中に、ただ一つ付け加えられた言葉がある。それは、告白の祈りのなかで罪を告白し、「思い」と「言葉」と「行い」に続けて「怠りomissio」の罪が付け加えられたことである。
106 Communicantes, et momoriam venerantes, in primis gloriosae semper Virginis Mariae, Genitricis Dei et Domini nostri Jesu Christi, sed et beatorum Apostolorum ac Martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andeae, Jacobi, Joannis, Thomae, Jacobi, Philipi, Bartholomaei, Matthaei, Simonis et Thaddaei: Lini, Cleti, Clementis, Xysti, Cornelii, Cypriani, Laurentii, Chrysogoni, Joannis et Pauli, Cosmae et Daminai: omnium Sanctorum tuorum; quorum meritis, precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tuae muniamur auxilio. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.(聖なる一致をしつつ、我らは、まず、我らの天主なる主、イエズス・キリストの御母、終生童貞なる光栄あるマリアの記念を謹んで行い奉る。また更に、主の聖なる使徒かつ殉教者、ペトロとパウロ、アンドレア、ヤコボ、ヨハネ、トマ、ヤコボ、フィリッポ、バルトロメオ、マテオ、シモンとタデオ、また、リノ、クレト、クレメンテ、シクスト、コルネリオ、チプリアノ、ラウレンチオ、クリソゴノ、ヨハネとパウロ、コスマとダミアノ、および主の全ての聖人らの記念を恭しく行い奉る。願わくは、彼らの功徳と祈りとによって、我らが全てにおいて御身の保護の助力を与え給わんことを。同じ我らの主キリストによりて、アーメン。)
107 Libera nos, quaesumus, Domine, ab onmibus malis, praeteritis, praesentibus, et futuris: et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Dei Genitrice Maria, cum beatis Apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea, et omnibus Sanctis, da propitius pacem in diebus nostris: ut ope misericordiae tuae adjuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi.(主よ、願わくは、過去、現在、未来の全ての悪より我らを救い給え。終生童貞なる永福の光栄ある天主の御母マリアと御身の至福なる使徒ペトロとパウロ、また、アンドレアとともに、全ての諸聖人のおん取り次ぎにより、おん慈悲をもって今日平安を与え給え。そは、おん憐れみの御業に助けられ、常に我らが罪から救われ、全ての惑わしから安全に守られんがためなり。)
108 原注22: 新しい司式が提示されたとき記者会見の席で、レキュイェ神父P?re L?cuyerは理性だけを信じているという「信仰宣言」をはっきりとし、会衆の参加していないミサでの挨拶は、「Dominus tecum主はあなたと共に」「Ora, frater兄弟よ祈れ。」という言い方を考えているとさえいった。これは、「作り事がなくなり、真理に適わないことがなくなるためである」(ソノママ)とのことである。
109 "tremendum mysterium"
110 "Aufer a nobis"の祈り
111 "Oramus te, Domineの祈り
112 "Aufer a nobis"
113 "Omramus te, Domine"
114 "mensa" 総則の260番には、「感謝の祭儀は、…聖堂以外の場所においては、…適当な机の上でも行うことが出来る。但し必ず食卓布とコルポラーレを備えなければならない」とある。総則の265番には「可動祭壇、もしくは聖堂外の祭儀が行われる机(260参照)には、聖別された石をおく必要はない」とある。
115 "convivium"
116 総則244番の「ニ」によると、「助祭または教会奉仕者[これは、いわゆる侍者のことである。]は、カリスとプリフィカトリウムを拝領者に差し出し、拝領者は、適宜に、自分の手で、カリスを口に持って行く。拝領者は、左手でプリフィカトリウムを口の下に保ち、こぼさないように注意しながら、少量の御血をカリスから拝領する」とある。
117 総則65:「教会奉仕者は、祭壇での奉仕と、司祭及び助祭を助けるために選任される。教会奉仕者には、特に祭具の準備をすること、及び特別奉仕者として聖体を信者に授けることが委ねられる。」
118 総則66:「聖教奉仕者は、福音を除き、聖書を朗読するために選任される。また共同祈願の意向を述べ、詩編朗読者がいないときには、朗読の合間に詩編を唱えることが出来る。宣教奉仕者は、感謝の祭儀において、固有の役割を持っている。この役割は、より上級の位階の奉仕者がいる場合にも、宣教奉仕者自らが果たさなければならない。」
119 総則67:「朗読の間にある詩編または聖書参加を朗唱することは詩編朗唱者の務めである。」
120 総則68の「イ」:「解説者=信者を祭儀に導き、よりよく理解させるために、信者に指示や説明を与える。」
121 総則68の「ロ」:「案内係=地方によっては、教会の入り口で信者を迎え、適当な席に案内し、また行列を整理する。」
122 総則68の「ハ」
123 総則68「また、ミサ典礼書、十字架、ろうそく、パン、ぶどう酒、水、香炉を運ぶ者がある。」
124 mulier idonea 総則70:「助祭に固有な役務以外の役務は、選任を受けていなくとも、男子信徒が行うことが出来る。司祭席の外で行われる役務は、…女子にも委ねることが出来る。」
125 "ministeria quae extra presbyterium peraguntur"
126 原注23: このことに関して、今ではたとえ司祭が共同司式の前或いは後に一人でミサを捧げなければならない時でさえも、司祭はもう一度共同司式の時に両形色で聖体拝領することが合法的になってしまったようである。