--
以下の文章は、ゲーム「THE iDOLM@STER」を題材とした二次創作小説です。原作のゲームとは一切関係ありません。キャラクターの描写などにおいては、原作のゲームを参考にしておりますが、物語の都合により意図的に改変している箇所もありますので、読み進めるにあたりましては、ご注意とご理解をよろしくお願い致します。
--
・春霞蒼月記 ~序
春香にとって半年ぶりとなる水瀬の町は、変わることなく活気に満ち溢れていた。
市街を南北に貫く大通りに沿って多数の商店が軒を連ね、客を呼び込む威勢のいい声が飛び交う。店先を覗いて品定めする人々の横顔も、心なしか生き生きしているように見える。
忍びの隠れ里とは百八十度異なる空気。だが、それを春香は不快とは感じなかった。それどころか、むしろ好ましいとさえ思っていた。もしかしたら、こんな賑やかな町で暮らす人生もあったのかもしれない――そんな夢想を抱かなかったと言えば嘘になる。喧しく、騒がしく、静けさをどこかに置き忘れてきたような町の雰囲気に、とうの昔に失くしてしまった何かを感じ、不思議な安らぎを覚えたのもまた事実ではあったのだ。
しかし、そんな感傷を抱いたのはほんの一瞬のことに過ぎない。
通りを行き交う人々の間を縫うように、春香は再び歩み出す。如月家の使用人として雇ってもらう前にやっておかなければいけないことが、まだ幾つか残っていた。ただ如月家の門を叩けばよいという、単純な話ではないのだ。
「萩原屋は……確か、こっちだったよね……」
と、春香は独りごちる。
大通りの中程にある角を西に曲がったところにある商店。それが、萩原屋であった。
様々な雑貨、道具や日用品を扱い、店の入口に白字で『萩原屋』と書かれた藍染めの暖簾が掛かっている以外には主張らしい主張はない。賑やかな呼び込みもなく、派手な宣伝も、謳い文句もない、ごくひっそりとした構え。しかし、品揃えの良さでは定評があった。店頭に並ぶ品物の質の高さは、水瀬に住む職人達からも大いに頼りにされており、いまや萩原屋と言えば知る人ぞ知る良店である。
が、それは表向きの顔――萩原屋の持つ一面に過ぎなかった。
「ごめんください」
と声を掛けつつ、春香は萩原屋の暖簾をくぐる。
はーい、と店の奥から澄んだ声がして、一人の少女が姿を見せた。
「何をお求めですか?」
気さくに応対する少女の髪は肩の少し上で綺麗に切り揃えられており、その肌は雪のように白かった。
「雪歩!」
春香が呼び掛けると、雪歩と呼ばれた少女は柔らかい笑みを浮かべた。
「お久しぶりだね、春香ちゃん」
「雪歩こそ、元気にしていた?」
訊ねる春香に、雪歩は小さく頷き返す。
「うん。……話は聞いているよ。奥に行こうか」
「そうだね」
春香と雪歩は連れ立って店の奥に姿を消し、二人と入れ替わるように若い男が店番に立つ。何事もなかったかのような静けさが戻ってくる。
たまたま店内に客はなく、一連のやり取りを見ていた者はいなかった。けれど、仮に誰か見ている者がいたとしても、離れて暮らしていた友人もしくは親戚の再会、というようにしか見えなかったに違いない。
だが、それもまた見せかけに過ぎない。忍びである春香と顔なじみである雪歩という少女が、その雪歩が店番をしている萩原屋という店が、見た目通りの存在であるはずがなかった。
忍びは、世の裏を歩く稼業である。しかし、ただ闇に紛れての暗殺を生業とするだけの存在ではない。世の中に影響を及ぼそうとするのであれば、裏からだけでなく、表からも力を行使しなくてはならない。
そのために作られたのが『萩原屋』という存在だった。表通りに堂々と存在し、その信頼感を担保に各方面から情報を収集する。自らが工作活動を行うことはないが、忍びの行動を支援することで間接的に任務達成に貢献する。それが、萩原屋の真の存在理由であった。
「――今度は長いんだって?」
奥座敷に通された春香がぼんやりと壁のシミを眺めていると、不意に雪歩が訊ねてきた。
「……少なくとも半年はかかるって言われてる」
「そっか。大変だね……」
と、お茶を淹れながら雪歩が応える。
大変だよーと言いつつ、春香が畳の上に寝転がる。
「そもそも、見ず知らずのお姫様に近付いて、しかも親密な仲になるなんて、そんな簡単にできるものなのかな」
「うーん……」
頤に手を当てて、雪歩が小首を傾げる。
「でも、春香ちゃんに命令が下されたってことは、それができるって判断されたってことなんじゃないのかなぁ」
「だといいんだけどね」
苦笑しながら身を起こした春香の前に、湯呑み茶碗が置かれる。
「はい、お茶。気弱なんて、春香ちゃんらしくないよ?」
「ありがと、雪歩」
湯気を立てるお茶に息を吹きながら、春香は訊ねた。
「どうなの? 雪歩は上手く行ってるの?」
「おかげさまで」
と、雪歩は微笑んだ。
元はと言えば、雪歩も春香と同じ隠れ里で過ごしてきた忍びの一人である。春香達と共に忍びとしての特殊訓練を受け、実地での任務経験もある雪歩だったが、今は萩原屋の責任者として忍び達を後方支援する立場にあった。
彼女の能力自体は高く評価されていたものの、長期に渡って忍びとして前線で戦い続けることは性格的に向いていない。そう判断した里長により、雪歩は萩原屋での後方支援任務へ回されることになった。それに異を唱える者はいなかった。忍びとして生きていくには、雪歩は優しすぎる。里の誰もが、そう思っていたから。
「もう一年になるんだね」
そう言って、春香は湯呑みに口をつけた。
「そうだね。ほんの一年前まで、私も命懸けの任務に就いていたのかと思うと、なんだか不思議な気持ちがする……かな」
「ま、それはそれとして――」
「仕事の話、だね」
「うん」
二人の間に流れていた空気が、ピンと張りつめたものに変わる。
雪歩は立ち上がり、壁に作り付けられた棚から大きな封筒を取り出すと、その中身を卓袱台の上に並べた。
「これが、春香ちゃんの身元を保証する書類一式。打ち合わせの通り、天海村の出ということにしてあるけど、一応ちゃんと確認しておいてね」
「わかった」
春香は首肯して、それらの書類を手に取った。
いまだ全国統一の戸籍は整備されていないが、水瀬は自らの支配地域において住民登録とでも呼ぶべき制度を施行していた。氏名、性別、生年月日、出生地、現住所といった情報を政庁に登録することで、いわば水瀬家が領民の身元保証をおこなうというものであった。
租税徴収のための領民管理が制度の目的であったことから導入当初は抵抗もあったが、住民登録と引き換えに各種のサービスを提供することで急速に浸透していき、今では水瀬城下では政庁発行の身元保証書なしには働くこともままならない状態となっていた。
忍びの里に身を置く春香達も、架空の住民登録を済ませており、必要に応じてこれを使用していた。
「それから、これが紹介状。これがないと門前払いされちゃうから、失くしちゃダメだよ」
「気をつけます」
春香が神妙な顔で頷くと、雪歩は懐から小さな巾着袋を取りだして春香の前に置いた。
「あとは、当座の資金。どうせ、路銀だって大して持たされていないんでしょう?」
「……ご明察」
「住み込みの使用人だから必要なものは支給されると思うけど、だからといって一文無しというわけにはいかないものね」
「ありがとう。助かる」
応えて、春香は立ち上がる。
積もる話は幾らでもあるが、今はゆっくりしていてよい時ではない。
「じゃあ、行ってくるね」
「気を付けて。落ち着いたら、遊びに来てね」
「そっか、そうだね。同じ町にいるんだもんね。ありがと、雪歩」
そう言い置いて、春香は萩原屋をあとにした。
背後は振り返らなかった。
水瀬の大通りを北上すると、やがて立派な屋敷が建ち並ぶ区画に辿り着く。この町を中心とした一帯を支配する水瀬家の家臣達の居宅が集められているのだ。春香が目指す如月家も、この区画の中にあった。
どこまでも長く続く土塀。風格ある門構え。どこを取っても他の屋敷とは規模が違う。細工の精巧さも比にならない。さすが譜代の重臣と言うだけのことはある、と春香は感心した。
しかし、感心してばかりもいられない。見物に来たわけではないのだからと気を引き締め、まずは屋敷の正門に立つ門番に声を掛けてみることにする。
「あの、こちらで使用人を募集していると聞いて来たんですけれど」
「確かに募集はしているけど、飛び込みでの応募は受け付けてなくて――」
と門番が言い終える前に、紹介状を取り出す。
「紹介状なら、ありますっ!」
春香の勢いに面食らったのか、門番の青年は目を瞬かせた。
だが、すぐに我に返ると慇懃な口調で春香にしばらく待つように告げて、奥へ引っ込む。と、間もなく人を連れて戻ってきた。
どこか凜とした雰囲気を漂わせる妙齢の女性だった。着ている服装から判断する限り、門番よりも家中における位は上であると思われた。
「こちらの方が、使用人の応募に来られた……えーっと、お名前は何でしたっけ?」
「春香、と申します」
「春香さんですね。その紹介状を見せていただけますか?」
「はい」
と、春香は紹介状を差し出す。
「では、失礼して――」
女性が紹介状を検める。
使用人を雇う際に紹介状の提出を義務づけるのは、間者が紛れ込むことを避けるためでもあった。防諜対策――つまり、今まさに春香がやろうとしていることを防ぐのが目的なのだが、そのことを忍びの側も熟知しているから紹介状を偽造する。それも単純に偽造したのでは裏を取られてしまうし、そもそも相応の名前と立場と力のある人間の紹介でなければ意味がない。ゆえに、各地の有力者とパイプを作り、偽造でありながら本物の紹介状を用意する。それもまた萩原屋の仕事のひとつであった。
「……問題ないようですね」
念入りに紹介状を確かめていた女性は顔を上げ、納得げに頷いてみせると、春香を屋敷の中に招き入れた。
「では、こちらへ」
「はい」
女性の後を歩きながら、春香はさり気なく周囲に視線を走らせて、屋敷の様子を観察する。初めて訪れる場所では、侵入経路や逃走経路を考慮しつつ、建物や部屋の配置を把握することに努める――というのは、忍びとしての職業意識というか習い性のようなものであった。
(広い敷地だな……)
というのが、まず率直な感想だった。これならば、事を起こしても屋敷全体に情報が伝わるには時間が掛かるだろう、とも思った。それは、如月家の危機管理という観点からは由々しき問題だろうが、春香にとっては好都合である。逃げる時間が稼げるということなのだから。
もっとも、暗殺実行の時期は如月家の姫が神官の座に就く直前と決められているから、今すぐどうこうという話ではないのだが。
そんなことを考えている間に、春香は母屋から少し離れた建物に辿り着いていた。
「こちらです、春香さん」
誘われるままに、春香は敷居をまたぐ。
「私は、ここで。あとは、女中頭がご案内しますので」
「あ、ありがとうございました! その、お名前を伺ってもよろしいですか?」
「あら、光栄ですわね。私は、梓と申します。春香さんが如月家にお仕えすることになったら、私の後輩ということになるのかしら~」
「はい。その、もし、そうなったときは、よろしくお願いします」
「こちらこそ。……しっかりね、春香さん」
「はい!」
梓が出て行くのと入れ替わりに、一人の老女が奥から姿を現した。
老女の名前は、八重といった。女中頭を務め、先々代から如月家に仕えているということだったが、それ以上のことは語ろうとしなかった。
広間に春香を通し、座る位置を指示した後で、八重は躊躇いがちに切り出した。
「……春香さん」
「はい、何でしょうか」
「もうすぐ姫様が参られます。決して粗相のないように」
「と申されますと?」
「あなたに言うべきことではないのかもしれませんが、姫様は少々気難しいお方なのです。機嫌を損ねれば、使用人としての採用は見送らねばなりません。よいですか?」
「わ、わかりましたっ」
「よろしい。くれぐれも気をつけるように」
とはいえ、そんなことを言われても、春香にはどうしようもなかった。
ここで不採用を言い渡されれば、即任務失敗である。それは避けたかったが、さりとて何が人の気分を害するかなど、そう簡単にわかるものではない。会ったこともない相手なら、なおのことだ。しかも、春香は如月家の姫についての予備知識らしいものを殆ど与えられていない。一抹の不安が胸をよぎるが、じたばたしても仕方ない。こうなれば、なるようになれ、である。
春香は静かに頭を垂れて、姫が現れるのを待つことにした。
程なくして、部屋の戸が開かれる音がした。
上座へ向かう人物の着物の裾を視界の端で捉える。鮮やかな青色の衣だった。
足音は春香の正面で止まり、腰を下ろす気配が伝わる。
「あなたが、新しく当家に仕えることを志望される方ですか?」
何とも涼やかな声だった。
「はい、春香と申します!」
顔を伏せたまま、春香は応えた。
「……面を上げなさい」
「はい」
言われるままに顔を上げると、姫と視線がぶつかった。
瞬間、姫が息を呑むのがわかった。
何かを躊躇うような、戸惑うような表情が浮かんだのを、春香は見逃さなかった。
「千早様、如何なさいましたか?」
八重が横から声を掛けるが、それには応えず、姫は春香をひたと見据えていた。
その澄んだ眼差しに、春香も少なからず動揺していた。
「……春香さん、と言いましたね」
「は、はい」
問い掛ける姫に、ぎこちない頷きを返しながら、春香は『千早』という名前を頭の中で何度も繰り返していた。如月家の姫の名前が千早であるというのは、聞いていた。知っていた。けれど、そんな筈はないと思っていた。千早など、ありふれた名前だと。どこにでもある名前だと。そう思っていたのに、これではまるで――
「少し庭を歩きませんか? 花が綺麗ですよ」
姫の誘いを拒否する理由など、春香にあるわけがない。
「お供します」
と頷いて、姫の、千早の眼差しを受け止める。
「八重」
「はい」
「人払いを」
「かしこまりました」
そう応えて、八重が静かに退室する。
「行きましょう」
千早に誘われるままに、春香は腰を上げた。
屋敷の庭はよく手入れされていて、様々な草木が色とりどりの花を咲かせていた。
人払いがされていて、他には誰もいない。
二人きりの庭は、静寂に満ちていた。
その静けさを破るように、千早が口を開いた。
「……私は、今から十年前に故郷を失い、如月家の養子となりました。もう、ずいぶんと昔のことです。実の両親の顔さえ、確とは思い出せません。ただ、いつも一緒に遊んでいた幼馴染みがいました。彼女のことは、今でもよく覚えています。名前を春香といいました。あの時の混乱の中で離ればなれになってしまい、それから一度も会っていません。生きていれば、きっとあなたと同じくらいの年のはずです。あなたの名前で、そのことを思い出して、少し取り乱してしまいました。気を悪くしたなら、ごめんなさい」
千早は一度も振り返らなかった。春香を見ようともしなかった。
その意味が理解できたわけではない。
だが、春香も言わなければいけないと思った。
「奇遇ですね。実は、私も十年前に故郷を失くしました」
と、努めて冷静に告げる。
前を歩く千早が立ち止まり、息を呑む気配がした。
「何が原因なのか、今となってはわかりません。それを理解するには、私は幼すぎました。覚えているのは、燃えさかる炎の光と熱だけです。どこをどう歩いたのか、気づけば私は知らない家で寝ていました。たまたま通り掛かった人が助けてくれたんですね。その里で、私はずっと過ごしてきました。今でも、時々思い出します。仲が良かった幼馴染みのことを。千早ちゃんっていうんです。姫様と同じ名前ですね。歌が上手で、いつも歌を聴かせてくれました。その歌が忘れられなくて、だからきっと千早ちゃんのことも忘れられなかった……。千早ちゃんがよく歌っていた『蒼い鳥』を……」
それは、ずっと昔に旅芸人から教わった歌。哀しい歌。
子供の時は上手く歌えなかった歌を、もう一度口ずさんでみる。
もし、目の前で背を向けている姫が春香の思った通りの人なら、何かしらの反応があるはずだと思った。
「……音が外れているわよ、春香」
と、千早は言った。
それだけで、春香には十分だった。
「……本当に、千早ちゃんなんだね?」
「それは、こちらの台詞よ。……本当に、春香なのね? 陽月荘の春香なのよね?」
ようやく振り返った千早の目には光るものがあった。
「うん――」
そうだよ、と言いたかった。一緒に山野を駆けた春香だよ、と言いたかった。
だが、声にならなかった。声にできなかった。
顔を伏せる。
生き別れていた幼馴染みに再会できたことは嬉しい。けれど、その幼馴染みを暗殺するために、春香は今この場に立っている。その現実の重みに、春香は込み上げる感情を押し殺すことで耐えようとした。声を出せば、自分を支える土台が崩れ去ってしまいそうだった。
と、不意に温もりに包まれる。
それが千早の体温であることに気づいて、春香はついに涙を堪えることができなかった。
千早に抱きしめられて、その温もりに安らぎを感じる。しかし、いずれは自らの手でこの温もりを断たねばならない。
生き残れたから、千早に再び出会えた。
生き残れたから、千早を殺さねばならぬ。
もし運命の神がいるのだとしたら、それはきっととびきり残酷で非情な存在に違いない。
春香に与えられた密命など知らない千早は、ただ幼馴染みとしての優しさで包んでくれている。それがわかるから、春香の心は千々に乱れる。
不幸中の幸いなのは、今すぐ決着をつける必要がないということ。少なくとも、半年の猶予は与えられている。
その間に気持ちの整理をしなければならないという冷徹な忍びとしての思考と、どんな理由であれ千早の傍にいられることを喜ぶ一人の娘としての感情とが、春香の中で混濁していた。
まだしばらくは、千早の腕に身を任せているしかなかった。
(つづく)
以下の文章は、ゲーム「THE iDOLM@STER」を題材とした二次創作小説です。原作のゲームとは一切関係ありません。キャラクターの描写などにおいては、原作のゲームを参考にしておりますが、物語の都合により意図的に改変している箇所もありますので、読み進めるにあたりましては、ご注意とご理解をよろしくお願い致します。
--
・春霞蒼月記 ~序
春香にとって半年ぶりとなる水瀬の町は、変わることなく活気に満ち溢れていた。
市街を南北に貫く大通りに沿って多数の商店が軒を連ね、客を呼び込む威勢のいい声が飛び交う。店先を覗いて品定めする人々の横顔も、心なしか生き生きしているように見える。
忍びの隠れ里とは百八十度異なる空気。だが、それを春香は不快とは感じなかった。それどころか、むしろ好ましいとさえ思っていた。もしかしたら、こんな賑やかな町で暮らす人生もあったのかもしれない――そんな夢想を抱かなかったと言えば嘘になる。喧しく、騒がしく、静けさをどこかに置き忘れてきたような町の雰囲気に、とうの昔に失くしてしまった何かを感じ、不思議な安らぎを覚えたのもまた事実ではあったのだ。
しかし、そんな感傷を抱いたのはほんの一瞬のことに過ぎない。
通りを行き交う人々の間を縫うように、春香は再び歩み出す。如月家の使用人として雇ってもらう前にやっておかなければいけないことが、まだ幾つか残っていた。ただ如月家の門を叩けばよいという、単純な話ではないのだ。
「萩原屋は……確か、こっちだったよね……」
と、春香は独りごちる。
大通りの中程にある角を西に曲がったところにある商店。それが、萩原屋であった。
様々な雑貨、道具や日用品を扱い、店の入口に白字で『萩原屋』と書かれた藍染めの暖簾が掛かっている以外には主張らしい主張はない。賑やかな呼び込みもなく、派手な宣伝も、謳い文句もない、ごくひっそりとした構え。しかし、品揃えの良さでは定評があった。店頭に並ぶ品物の質の高さは、水瀬に住む職人達からも大いに頼りにされており、いまや萩原屋と言えば知る人ぞ知る良店である。
が、それは表向きの顔――萩原屋の持つ一面に過ぎなかった。
「ごめんください」
と声を掛けつつ、春香は萩原屋の暖簾をくぐる。
はーい、と店の奥から澄んだ声がして、一人の少女が姿を見せた。
「何をお求めですか?」
気さくに応対する少女の髪は肩の少し上で綺麗に切り揃えられており、その肌は雪のように白かった。
「雪歩!」
春香が呼び掛けると、雪歩と呼ばれた少女は柔らかい笑みを浮かべた。
「お久しぶりだね、春香ちゃん」
「雪歩こそ、元気にしていた?」
訊ねる春香に、雪歩は小さく頷き返す。
「うん。……話は聞いているよ。奥に行こうか」
「そうだね」
春香と雪歩は連れ立って店の奥に姿を消し、二人と入れ替わるように若い男が店番に立つ。何事もなかったかのような静けさが戻ってくる。
たまたま店内に客はなく、一連のやり取りを見ていた者はいなかった。けれど、仮に誰か見ている者がいたとしても、離れて暮らしていた友人もしくは親戚の再会、というようにしか見えなかったに違いない。
だが、それもまた見せかけに過ぎない。忍びである春香と顔なじみである雪歩という少女が、その雪歩が店番をしている萩原屋という店が、見た目通りの存在であるはずがなかった。
忍びは、世の裏を歩く稼業である。しかし、ただ闇に紛れての暗殺を生業とするだけの存在ではない。世の中に影響を及ぼそうとするのであれば、裏からだけでなく、表からも力を行使しなくてはならない。
そのために作られたのが『萩原屋』という存在だった。表通りに堂々と存在し、その信頼感を担保に各方面から情報を収集する。自らが工作活動を行うことはないが、忍びの行動を支援することで間接的に任務達成に貢献する。それが、萩原屋の真の存在理由であった。
「――今度は長いんだって?」
奥座敷に通された春香がぼんやりと壁のシミを眺めていると、不意に雪歩が訊ねてきた。
「……少なくとも半年はかかるって言われてる」
「そっか。大変だね……」
と、お茶を淹れながら雪歩が応える。
大変だよーと言いつつ、春香が畳の上に寝転がる。
「そもそも、見ず知らずのお姫様に近付いて、しかも親密な仲になるなんて、そんな簡単にできるものなのかな」
「うーん……」
頤に手を当てて、雪歩が小首を傾げる。
「でも、春香ちゃんに命令が下されたってことは、それができるって判断されたってことなんじゃないのかなぁ」
「だといいんだけどね」
苦笑しながら身を起こした春香の前に、湯呑み茶碗が置かれる。
「はい、お茶。気弱なんて、春香ちゃんらしくないよ?」
「ありがと、雪歩」
湯気を立てるお茶に息を吹きながら、春香は訊ねた。
「どうなの? 雪歩は上手く行ってるの?」
「おかげさまで」
と、雪歩は微笑んだ。
元はと言えば、雪歩も春香と同じ隠れ里で過ごしてきた忍びの一人である。春香達と共に忍びとしての特殊訓練を受け、実地での任務経験もある雪歩だったが、今は萩原屋の責任者として忍び達を後方支援する立場にあった。
彼女の能力自体は高く評価されていたものの、長期に渡って忍びとして前線で戦い続けることは性格的に向いていない。そう判断した里長により、雪歩は萩原屋での後方支援任務へ回されることになった。それに異を唱える者はいなかった。忍びとして生きていくには、雪歩は優しすぎる。里の誰もが、そう思っていたから。
「もう一年になるんだね」
そう言って、春香は湯呑みに口をつけた。
「そうだね。ほんの一年前まで、私も命懸けの任務に就いていたのかと思うと、なんだか不思議な気持ちがする……かな」
「ま、それはそれとして――」
「仕事の話、だね」
「うん」
二人の間に流れていた空気が、ピンと張りつめたものに変わる。
雪歩は立ち上がり、壁に作り付けられた棚から大きな封筒を取り出すと、その中身を卓袱台の上に並べた。
「これが、春香ちゃんの身元を保証する書類一式。打ち合わせの通り、天海村の出ということにしてあるけど、一応ちゃんと確認しておいてね」
「わかった」
春香は首肯して、それらの書類を手に取った。
いまだ全国統一の戸籍は整備されていないが、水瀬は自らの支配地域において住民登録とでも呼ぶべき制度を施行していた。氏名、性別、生年月日、出生地、現住所といった情報を政庁に登録することで、いわば水瀬家が領民の身元保証をおこなうというものであった。
租税徴収のための領民管理が制度の目的であったことから導入当初は抵抗もあったが、住民登録と引き換えに各種のサービスを提供することで急速に浸透していき、今では水瀬城下では政庁発行の身元保証書なしには働くこともままならない状態となっていた。
忍びの里に身を置く春香達も、架空の住民登録を済ませており、必要に応じてこれを使用していた。
「それから、これが紹介状。これがないと門前払いされちゃうから、失くしちゃダメだよ」
「気をつけます」
春香が神妙な顔で頷くと、雪歩は懐から小さな巾着袋を取りだして春香の前に置いた。
「あとは、当座の資金。どうせ、路銀だって大して持たされていないんでしょう?」
「……ご明察」
「住み込みの使用人だから必要なものは支給されると思うけど、だからといって一文無しというわけにはいかないものね」
「ありがとう。助かる」
応えて、春香は立ち上がる。
積もる話は幾らでもあるが、今はゆっくりしていてよい時ではない。
「じゃあ、行ってくるね」
「気を付けて。落ち着いたら、遊びに来てね」
「そっか、そうだね。同じ町にいるんだもんね。ありがと、雪歩」
そう言い置いて、春香は萩原屋をあとにした。
背後は振り返らなかった。
水瀬の大通りを北上すると、やがて立派な屋敷が建ち並ぶ区画に辿り着く。この町を中心とした一帯を支配する水瀬家の家臣達の居宅が集められているのだ。春香が目指す如月家も、この区画の中にあった。
どこまでも長く続く土塀。風格ある門構え。どこを取っても他の屋敷とは規模が違う。細工の精巧さも比にならない。さすが譜代の重臣と言うだけのことはある、と春香は感心した。
しかし、感心してばかりもいられない。見物に来たわけではないのだからと気を引き締め、まずは屋敷の正門に立つ門番に声を掛けてみることにする。
「あの、こちらで使用人を募集していると聞いて来たんですけれど」
「確かに募集はしているけど、飛び込みでの応募は受け付けてなくて――」
と門番が言い終える前に、紹介状を取り出す。
「紹介状なら、ありますっ!」
春香の勢いに面食らったのか、門番の青年は目を瞬かせた。
だが、すぐに我に返ると慇懃な口調で春香にしばらく待つように告げて、奥へ引っ込む。と、間もなく人を連れて戻ってきた。
どこか凜とした雰囲気を漂わせる妙齢の女性だった。着ている服装から判断する限り、門番よりも家中における位は上であると思われた。
「こちらの方が、使用人の応募に来られた……えーっと、お名前は何でしたっけ?」
「春香、と申します」
「春香さんですね。その紹介状を見せていただけますか?」
「はい」
と、春香は紹介状を差し出す。
「では、失礼して――」
女性が紹介状を検める。
使用人を雇う際に紹介状の提出を義務づけるのは、間者が紛れ込むことを避けるためでもあった。防諜対策――つまり、今まさに春香がやろうとしていることを防ぐのが目的なのだが、そのことを忍びの側も熟知しているから紹介状を偽造する。それも単純に偽造したのでは裏を取られてしまうし、そもそも相応の名前と立場と力のある人間の紹介でなければ意味がない。ゆえに、各地の有力者とパイプを作り、偽造でありながら本物の紹介状を用意する。それもまた萩原屋の仕事のひとつであった。
「……問題ないようですね」
念入りに紹介状を確かめていた女性は顔を上げ、納得げに頷いてみせると、春香を屋敷の中に招き入れた。
「では、こちらへ」
「はい」
女性の後を歩きながら、春香はさり気なく周囲に視線を走らせて、屋敷の様子を観察する。初めて訪れる場所では、侵入経路や逃走経路を考慮しつつ、建物や部屋の配置を把握することに努める――というのは、忍びとしての職業意識というか習い性のようなものであった。
(広い敷地だな……)
というのが、まず率直な感想だった。これならば、事を起こしても屋敷全体に情報が伝わるには時間が掛かるだろう、とも思った。それは、如月家の危機管理という観点からは由々しき問題だろうが、春香にとっては好都合である。逃げる時間が稼げるということなのだから。
もっとも、暗殺実行の時期は如月家の姫が神官の座に就く直前と決められているから、今すぐどうこうという話ではないのだが。
そんなことを考えている間に、春香は母屋から少し離れた建物に辿り着いていた。
「こちらです、春香さん」
誘われるままに、春香は敷居をまたぐ。
「私は、ここで。あとは、女中頭がご案内しますので」
「あ、ありがとうございました! その、お名前を伺ってもよろしいですか?」
「あら、光栄ですわね。私は、梓と申します。春香さんが如月家にお仕えすることになったら、私の後輩ということになるのかしら~」
「はい。その、もし、そうなったときは、よろしくお願いします」
「こちらこそ。……しっかりね、春香さん」
「はい!」
梓が出て行くのと入れ替わりに、一人の老女が奥から姿を現した。
老女の名前は、八重といった。女中頭を務め、先々代から如月家に仕えているということだったが、それ以上のことは語ろうとしなかった。
広間に春香を通し、座る位置を指示した後で、八重は躊躇いがちに切り出した。
「……春香さん」
「はい、何でしょうか」
「もうすぐ姫様が参られます。決して粗相のないように」
「と申されますと?」
「あなたに言うべきことではないのかもしれませんが、姫様は少々気難しいお方なのです。機嫌を損ねれば、使用人としての採用は見送らねばなりません。よいですか?」
「わ、わかりましたっ」
「よろしい。くれぐれも気をつけるように」
とはいえ、そんなことを言われても、春香にはどうしようもなかった。
ここで不採用を言い渡されれば、即任務失敗である。それは避けたかったが、さりとて何が人の気分を害するかなど、そう簡単にわかるものではない。会ったこともない相手なら、なおのことだ。しかも、春香は如月家の姫についての予備知識らしいものを殆ど与えられていない。一抹の不安が胸をよぎるが、じたばたしても仕方ない。こうなれば、なるようになれ、である。
春香は静かに頭を垂れて、姫が現れるのを待つことにした。
程なくして、部屋の戸が開かれる音がした。
上座へ向かう人物の着物の裾を視界の端で捉える。鮮やかな青色の衣だった。
足音は春香の正面で止まり、腰を下ろす気配が伝わる。
「あなたが、新しく当家に仕えることを志望される方ですか?」
何とも涼やかな声だった。
「はい、春香と申します!」
顔を伏せたまま、春香は応えた。
「……面を上げなさい」
「はい」
言われるままに顔を上げると、姫と視線がぶつかった。
瞬間、姫が息を呑むのがわかった。
何かを躊躇うような、戸惑うような表情が浮かんだのを、春香は見逃さなかった。
「千早様、如何なさいましたか?」
八重が横から声を掛けるが、それには応えず、姫は春香をひたと見据えていた。
その澄んだ眼差しに、春香も少なからず動揺していた。
「……春香さん、と言いましたね」
「は、はい」
問い掛ける姫に、ぎこちない頷きを返しながら、春香は『千早』という名前を頭の中で何度も繰り返していた。如月家の姫の名前が千早であるというのは、聞いていた。知っていた。けれど、そんな筈はないと思っていた。千早など、ありふれた名前だと。どこにでもある名前だと。そう思っていたのに、これではまるで――
「少し庭を歩きませんか? 花が綺麗ですよ」
姫の誘いを拒否する理由など、春香にあるわけがない。
「お供します」
と頷いて、姫の、千早の眼差しを受け止める。
「八重」
「はい」
「人払いを」
「かしこまりました」
そう応えて、八重が静かに退室する。
「行きましょう」
千早に誘われるままに、春香は腰を上げた。
屋敷の庭はよく手入れされていて、様々な草木が色とりどりの花を咲かせていた。
人払いがされていて、他には誰もいない。
二人きりの庭は、静寂に満ちていた。
その静けさを破るように、千早が口を開いた。
「……私は、今から十年前に故郷を失い、如月家の養子となりました。もう、ずいぶんと昔のことです。実の両親の顔さえ、確とは思い出せません。ただ、いつも一緒に遊んでいた幼馴染みがいました。彼女のことは、今でもよく覚えています。名前を春香といいました。あの時の混乱の中で離ればなれになってしまい、それから一度も会っていません。生きていれば、きっとあなたと同じくらいの年のはずです。あなたの名前で、そのことを思い出して、少し取り乱してしまいました。気を悪くしたなら、ごめんなさい」
千早は一度も振り返らなかった。春香を見ようともしなかった。
その意味が理解できたわけではない。
だが、春香も言わなければいけないと思った。
「奇遇ですね。実は、私も十年前に故郷を失くしました」
と、努めて冷静に告げる。
前を歩く千早が立ち止まり、息を呑む気配がした。
「何が原因なのか、今となってはわかりません。それを理解するには、私は幼すぎました。覚えているのは、燃えさかる炎の光と熱だけです。どこをどう歩いたのか、気づけば私は知らない家で寝ていました。たまたま通り掛かった人が助けてくれたんですね。その里で、私はずっと過ごしてきました。今でも、時々思い出します。仲が良かった幼馴染みのことを。千早ちゃんっていうんです。姫様と同じ名前ですね。歌が上手で、いつも歌を聴かせてくれました。その歌が忘れられなくて、だからきっと千早ちゃんのことも忘れられなかった……。千早ちゃんがよく歌っていた『蒼い鳥』を……」
それは、ずっと昔に旅芸人から教わった歌。哀しい歌。
子供の時は上手く歌えなかった歌を、もう一度口ずさんでみる。
もし、目の前で背を向けている姫が春香の思った通りの人なら、何かしらの反応があるはずだと思った。
「……音が外れているわよ、春香」
と、千早は言った。
それだけで、春香には十分だった。
「……本当に、千早ちゃんなんだね?」
「それは、こちらの台詞よ。……本当に、春香なのね? 陽月荘の春香なのよね?」
ようやく振り返った千早の目には光るものがあった。
「うん――」
そうだよ、と言いたかった。一緒に山野を駆けた春香だよ、と言いたかった。
だが、声にならなかった。声にできなかった。
顔を伏せる。
生き別れていた幼馴染みに再会できたことは嬉しい。けれど、その幼馴染みを暗殺するために、春香は今この場に立っている。その現実の重みに、春香は込み上げる感情を押し殺すことで耐えようとした。声を出せば、自分を支える土台が崩れ去ってしまいそうだった。
と、不意に温もりに包まれる。
それが千早の体温であることに気づいて、春香はついに涙を堪えることができなかった。
千早に抱きしめられて、その温もりに安らぎを感じる。しかし、いずれは自らの手でこの温もりを断たねばならない。
生き残れたから、千早に再び出会えた。
生き残れたから、千早を殺さねばならぬ。
もし運命の神がいるのだとしたら、それはきっととびきり残酷で非情な存在に違いない。
春香に与えられた密命など知らない千早は、ただ幼馴染みとしての優しさで包んでくれている。それがわかるから、春香の心は千々に乱れる。
不幸中の幸いなのは、今すぐ決着をつける必要がないということ。少なくとも、半年の猶予は与えられている。
その間に気持ちの整理をしなければならないという冷徹な忍びとしての思考と、どんな理由であれ千早の傍にいられることを喜ぶ一人の娘としての感情とが、春香の中で混濁していた。
まだしばらくは、千早の腕に身を任せているしかなかった。
(つづく)



















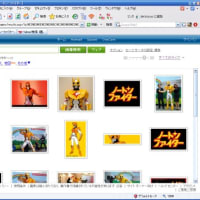
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます