昼頃か、僕はまあ昼下がりの柔らかい光が穏やかに差し込む中、これはまた摂田屋の近所である南図書館へ行き、本を借りて来ようと自転車で、出発する。いつもよりも体調的には絶好調とはいかず、多少スローな面持ちで図書館へと向かうのである。着くと、僕は直ぐに一冊の本を借り、図書館を後にする。タイトルは、
:お江戸風流散歩道(杉浦日向子)
である。
そこには、こう書かれていて例えば江戸におけるファッション、これに関してである。
江戸と言うのは、ここで言うファッションもそうだが対方にある上方の真似ここから始まるようである。その上方を真似る江戸っ子の気質は、上方で言う豪華絢爛のいで立ち、振る舞いからは逆の江戸では黒が極上とされたモノトーンが主流と言ういで立ちであったそうだ。
どちらが上か下か?と言えば、当然普段の日本と言うお国柄あるいは人間的な常識から考えても、色使いが派手な上方が上、地味な黒色に押さえる江戸が下、と言うランクに部類されるのは言うまでもない。こう、この本には例えがあって、
例え:上方が道行く人のファッションをあれこれ品定めしたと言うのに対し、江戸は近くに寄って触れるくらいの親しい間柄のものに「すごい羽二重だね!手が吸い付くようだ!」と褒められるのを良いとした!
とある。どうやら、この著者が言うこの言い草は、上方と江戸っ子の気質をもろに表していて、僕から言うと(またまた取り出し、言い放つが!)上方のおんながピチピチなのに対し、江戸のおんながいしいし!となっている様を、ここでももろに受けるようだ!(分かるか?)当然、日本と言う国は国の出来上がりと言う事に関しては、弥生時代に邪馬台国があって始まり(地域は不明とされるが、僕は見当が付く)、その後大和朝廷が覇権を握るように奈良の台地や、平安時代の到来を指す京都の地に都が作られていくわけだが、その最終着地点として江戸(東京)がある。開国後はこの際おいて置き、日本と言う国家は、始め邪馬台国と言うどこぞやの桃源郷の地に始まりを持って、最終江戸の地へ辿り着く。(まあ詳しくはここでは書かない)
ファッションは、江戸好みとし、「四十八茶百鼠」と言う言葉に代表される色使いで、つまりこれは四十八と言う数字に対する’茶’と言う色使い、これと百色に渡る鼠色の色使い!と言う事で言っているわけだ!江戸の二大流行色と言う事で、これを真に受けると、
1、四十八茶(渋色が四十八色)
と、
2、百鼠(地味色が百色)
と、こう言い表せる。まあこの2パターンの流行色の話しはここでは置いておくとし、私的に言えば当然江戸と言う国は、完全上方地方に比べれば、地味な印象に受けるファッションのあり方があるわけだ!
歴史がそのまま如実に言っているわけだが、邪馬台国と言う先陣を切るお国時代をここでは外して考えると、その先にあった奈良の地から始まっている日本の歴史と言うのは、大きく日本列島が左から右へ動いて行く常識があるわけであり、当然最初に西日本から歴史が始まる事実からすると、最終お江戸に辿り着くこの日本と言うのは、順番的に言えばお江戸が、一番足が遅いわけだ!
ここで、ファッションに因む色の話しをしたが、お江戸が一番地味なのは言う通り。他方(逆方)の上方は、豪華絢爛派手と来るわけだから、日本と言うのは、始めファッション的に言っているが色の傾向は派手な色使いから始まって、徐々に地味色にシフトして行く変遷を辿っている。何を言い表しているか?と言うと、日本と言うお国が、最も大事にする’色’と言う感覚について、その最上級が、
(天上級:邪馬台国)
最上級:上方
最低級:江戸
と、こうなっているわけだ!
色と言うのは大事なわけだ。本来日本人気質として派手な色使いが本当に日本人らしく、地味と言うのはそれに反している。
いやはやー、僕の言っていることは今の時代多少難しいことを言っているだろう!上に僕が言う、四十八茶と言う色使いが僕には現代に降り立つ時、その江戸(東京)の色(おんな)が、’おんなのレベルはそのキャリア(仕事系か?)’と言うアホらしい物ぐさに言うような代物に取って替わって、おんなのレベルが四十八茶と言う渋い色の一色もなくなった一手に代表されていると言うお笑い話しは、この際置いておくとして、実は、現代と言う時代は、この最終江戸期(当然鎖国)でも当然あり残る日本としての色これがあったわけだ!
さてさて、この「お江戸風流散歩道」を少し読んでの感想は、一先ずこれくらいに。
それでは~~!!
追記
先程、この図書を借りて来る帰り道宛ら、僕は一軒の摂田屋に佇む醤油蔵、越のむらさきさんを訪ね出ている。外にあるその醤油蔵の横にこの醤油蔵についての走り書き、路標があって眺めていると中から一人おんなのこが出て来て、’中に入って、昔の写真でもみませんか?’と、僕に言って来る。’いいですよー’と、僕は一つ返事をし、連れられるまま中に入ると、そのおんなのこはその醤油蔵についてある壁掛けの写真を前に、色々とこの醤油蔵に纏わる歴史を教えてくれる。僕も、教えてくれるお姉さんのこの摂田屋醤油蔵の歴史等の説明に、ふむと頷き、面白く聞き入るが、この摂田屋越のむらさき醤油蔵は、確か160年くらいの歴史を持った醤油蔵だそうだ!隣に佇んでいるここは、摂田屋の酒蔵吉乃川さんに比べると、その歴史は多少浅いわけだが、それでも江戸期くらいから歴史を持ったこの醤油蔵の歴史を聞くと、僕は寄り道掛けた先のおんなのこの蔵の説明に、ふむふむ面白く聞き入るわけだ!
さてさて、表に小さな神社竹駒神社があって、参りその神社の中を覗き見て提灯やら、太鼓が置いてあるのを見ると、この摂田屋のこの界隈の出来る歴史を知るわけだ!江戸に天領としてあって、長岡藩からも管理を受けていないと言うこの摂田屋は、昔からの竹駒神社に表される特別な地を思わせる。
それではまた!
:お江戸風流散歩道(杉浦日向子)
である。
そこには、こう書かれていて例えば江戸におけるファッション、これに関してである。
江戸と言うのは、ここで言うファッションもそうだが対方にある上方の真似ここから始まるようである。その上方を真似る江戸っ子の気質は、上方で言う豪華絢爛のいで立ち、振る舞いからは逆の江戸では黒が極上とされたモノトーンが主流と言ういで立ちであったそうだ。
どちらが上か下か?と言えば、当然普段の日本と言うお国柄あるいは人間的な常識から考えても、色使いが派手な上方が上、地味な黒色に押さえる江戸が下、と言うランクに部類されるのは言うまでもない。こう、この本には例えがあって、
例え:上方が道行く人のファッションをあれこれ品定めしたと言うのに対し、江戸は近くに寄って触れるくらいの親しい間柄のものに「すごい羽二重だね!手が吸い付くようだ!」と褒められるのを良いとした!
とある。どうやら、この著者が言うこの言い草は、上方と江戸っ子の気質をもろに表していて、僕から言うと(またまた取り出し、言い放つが!)上方のおんながピチピチなのに対し、江戸のおんながいしいし!となっている様を、ここでももろに受けるようだ!(分かるか?)当然、日本と言う国は国の出来上がりと言う事に関しては、弥生時代に邪馬台国があって始まり(地域は不明とされるが、僕は見当が付く)、その後大和朝廷が覇権を握るように奈良の台地や、平安時代の到来を指す京都の地に都が作られていくわけだが、その最終着地点として江戸(東京)がある。開国後はこの際おいて置き、日本と言う国家は、始め邪馬台国と言うどこぞやの桃源郷の地に始まりを持って、最終江戸の地へ辿り着く。(まあ詳しくはここでは書かない)
ファッションは、江戸好みとし、「四十八茶百鼠」と言う言葉に代表される色使いで、つまりこれは四十八と言う数字に対する’茶’と言う色使い、これと百色に渡る鼠色の色使い!と言う事で言っているわけだ!江戸の二大流行色と言う事で、これを真に受けると、
1、四十八茶(渋色が四十八色)
と、
2、百鼠(地味色が百色)
と、こう言い表せる。まあこの2パターンの流行色の話しはここでは置いておくとし、私的に言えば当然江戸と言う国は、完全上方地方に比べれば、地味な印象に受けるファッションのあり方があるわけだ!
歴史がそのまま如実に言っているわけだが、邪馬台国と言う先陣を切るお国時代をここでは外して考えると、その先にあった奈良の地から始まっている日本の歴史と言うのは、大きく日本列島が左から右へ動いて行く常識があるわけであり、当然最初に西日本から歴史が始まる事実からすると、最終お江戸に辿り着くこの日本と言うのは、順番的に言えばお江戸が、一番足が遅いわけだ!
ここで、ファッションに因む色の話しをしたが、お江戸が一番地味なのは言う通り。他方(逆方)の上方は、豪華絢爛派手と来るわけだから、日本と言うのは、始めファッション的に言っているが色の傾向は派手な色使いから始まって、徐々に地味色にシフトして行く変遷を辿っている。何を言い表しているか?と言うと、日本と言うお国が、最も大事にする’色’と言う感覚について、その最上級が、
(天上級:邪馬台国)
最上級:上方
最低級:江戸
と、こうなっているわけだ!
色と言うのは大事なわけだ。本来日本人気質として派手な色使いが本当に日本人らしく、地味と言うのはそれに反している。
いやはやー、僕の言っていることは今の時代多少難しいことを言っているだろう!上に僕が言う、四十八茶と言う色使いが僕には現代に降り立つ時、その江戸(東京)の色(おんな)が、’おんなのレベルはそのキャリア(仕事系か?)’と言うアホらしい物ぐさに言うような代物に取って替わって、おんなのレベルが四十八茶と言う渋い色の一色もなくなった一手に代表されていると言うお笑い話しは、この際置いておくとして、実は、現代と言う時代は、この最終江戸期(当然鎖国)でも当然あり残る日本としての色これがあったわけだ!
さてさて、この「お江戸風流散歩道」を少し読んでの感想は、一先ずこれくらいに。
それでは~~!!
追記
先程、この図書を借りて来る帰り道宛ら、僕は一軒の摂田屋に佇む醤油蔵、越のむらさきさんを訪ね出ている。外にあるその醤油蔵の横にこの醤油蔵についての走り書き、路標があって眺めていると中から一人おんなのこが出て来て、’中に入って、昔の写真でもみませんか?’と、僕に言って来る。’いいですよー’と、僕は一つ返事をし、連れられるまま中に入ると、そのおんなのこはその醤油蔵についてある壁掛けの写真を前に、色々とこの醤油蔵に纏わる歴史を教えてくれる。僕も、教えてくれるお姉さんのこの摂田屋醤油蔵の歴史等の説明に、ふむと頷き、面白く聞き入るが、この摂田屋越のむらさき醤油蔵は、確か160年くらいの歴史を持った醤油蔵だそうだ!隣に佇んでいるここは、摂田屋の酒蔵吉乃川さんに比べると、その歴史は多少浅いわけだが、それでも江戸期くらいから歴史を持ったこの醤油蔵の歴史を聞くと、僕は寄り道掛けた先のおんなのこの蔵の説明に、ふむふむ面白く聞き入るわけだ!
さてさて、表に小さな神社竹駒神社があって、参りその神社の中を覗き見て提灯やら、太鼓が置いてあるのを見ると、この摂田屋のこの界隈の出来る歴史を知るわけだ!江戸に天領としてあって、長岡藩からも管理を受けていないと言うこの摂田屋は、昔からの竹駒神社に表される特別な地を思わせる。
それではまた!













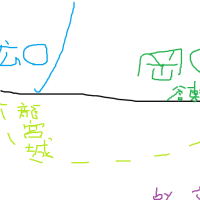

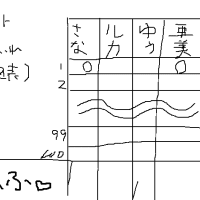




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます