今回は、EAGLEのPCDエディタの使い方をまとめておきます
 PCBエディタの起動
PCBエディタの起動
前回までは回路図エディタのほうを開いていたので、そこからの続きになりますが
エディタ画面上部の、横並びのツールバーの アイコンを押してPCBエディタを起動します
アイコンを押してPCBエディタを起動します
(回路図エディタとPCBエディタの切り替えスイッチです)
はじめてPCBエディタを起動する際、以下の警告が表示されますが [OK]を押して進めます

PCBエディタが起動します

エディタ内に枠(オレンジ線で囲まれた黒い四角)が表示されていると思いますが、これが基板の外形になります
枠の外側(左下)に、回路図で使用したパーツがごちゃごちゃと表示されてます(これが正常です)
 デザインルールの設定
デザインルールの設定
最初に、FusionPCBの基板設計ルールに合わせたデザインルールをセットします
メニューの「Tools」→「DRC」を選択し、デザインルール設定ウインドを開きます

[Load]ボタンを押して、インストールの際に準備しておいたFusionPCBのルールファイルを読み込みます
これは、FusionPCBが製作できるPCBの最低限の設計ルールとなっていて
PCBを作成する際に、1箇所でもこのルールに逸脱していると、FusionPCB側で受け付けてくれません。
正しく読み込むと、DRCウインドウのタイトルバーに、読み込んだルールファイル名が表示されます

 エディット画面の基準寸法の変更
エディット画面の基準寸法の変更
基板上のパーツや配線、外枠を移動する際に、グリッドを設定してある程度の寸法単位で動かす基準となります
画面左上の を押すと、編集画面が出ます
を押すと、編集画面が出ます

デフォルトの基準は「mil」単位になっているので、使いやすい単位にセットします
基板外形や、LED・スイッチ等の位置を調整する場合は「mm」にすると合わせやすいと思います
(1mil=0.0254mm、ICのピン 2.54mm=100mil)
・「Display」をONにすると、画面上にグリッドが表示されます
・「Style」 グリッドの表示が Dot=線、Line=線
・「Size」 通常の移動単位
・「Alt」 [Alt]キーを押しながら移動したときの移動単位
とりあえず今回は「Size」を10mmでセットします
 基板のサイズ調整
基板のサイズ調整
まずは基板の外形を、作成したい寸法に調整します
ツールアイコンの を押して移動モードにします
を押して移動モードにします
移動したい外枠の角にマウスカーソルを合わせ、左クリックしながら移動すると、外枠の頂点が移動します

グリッドのサイズを 10mm にしているので、1ラインが 10mm で、10mm単位で移動できます

これで基板の外形は、50mm x 50mm になりました
 編集モードの解除
編集モードの解除
[Esc]キーを押すか、別のツールアイコンを選択すると、その編集モードは解除されます
 画面の拡大、縮小
画面の拡大、縮小
マウスホイールの上下で出来ます
常にマウスカーソルのある場所を基準にして拡大縮小するので、先にマウスを合わせてから
マウスホイールで拡大すると、丁度よく拡大できます

 パーツの移動
パーツの移動
パーツの移動も移動モードを使います
各パーツの中心あたりに「+」のマークが出ていると思いますが、そのあたりにマウスを合わせて
左クリックしながら移動すると、パーツが任意の場所に移動できます
この際、パーツが最初に配置されていた場所から、移動の単位で設定した単位で動くので
必ずしもグリッドラインにピッタリ合いません
その際は [Alt]キーを押して、細かくパーツを移動しますが、それでも位置がずれるようなら
移動の単位を細かく設定して微調整するといいと思います
数値で調整する方法
微調整したい部品を選択して、キーボードの[i]キーもしくは、マウスの右クリックメニューで「プロパティ」を選択すると
部品の詳細が表示されます

Positionの項目が、基板の左端の+部分を基準点とした X,Y座標になっているので
この値を直接変更して位置の調整が行えます
(Backyさんありがとうございます!)
だいたいこんな感じで配置が出来ました

 パーツの回転
パーツの回転
ツールアイコンの を押して回転モードにしておき
を押して回転モードにしておき
回転させたいパーツの上で左クリックすると回転できます

 パーツの背面移動
パーツの背面移動
実装するパーツを、基板の反対側に設置したい場合、ツールアイコンの で
で
反転モードになるので
反対側に移したいパーツの上で左クリックすると移動します

背面に移動したパーツは、左右が反転して表示されます(ピンの位置も逆になるります)
 パーツシルクの移動
パーツシルクの移動
パーツを移動していると、部品名のシルクが重なってしまったり、変な位置に来る場合があります
シルクだけを移動させたい場合、先にパーツとシルクを分離させます
ツールアイコンの ボタンを押し、分離モードにしておき、シルクを分離させたいパーツの+マークあたりで左クリックすると
ボタンを押し、分離モードにしておき、シルクを分離させたいパーツの+マークあたりで左クリックすると
部品とシルクがそれぞれ分離します
シルクにもそれぞれ+マークが付くので、移動モードでシルク単体で移動できるようになります
 ドリルホールの設置
ドリルホールの設置
ネジ用の穴等、基板に穴をあけたい時に使います
ツールメニューの を押してホールモードにして、あとはマウスで位置を決めて左クリックすると位置が決まります
を押してホールモードにして、あとはマウスで位置を決めて左クリックすると位置が決まります
ホールモードを解除して、設置した穴の位置でマウスの右クリックメニューから「Propaties」を選ぶと
「Drill」の項目で、穴の半径サイズが変更できます

FusionPCBのドリル穴は 0.3mm — 6.35mm と決まっているので、その範囲内で開けることができます
基板の4か所にネジ用の穴を開けてみました

 PCBエディタの起動
PCBエディタの起動前回までは回路図エディタのほうを開いていたので、そこからの続きになりますが
エディタ画面上部の、横並びのツールバーの
 アイコンを押してPCBエディタを起動します
アイコンを押してPCBエディタを起動します(回路図エディタとPCBエディタの切り替えスイッチです)
はじめてPCBエディタを起動する際、以下の警告が表示されますが [OK]を押して進めます

PCBエディタが起動します

エディタ内に枠(オレンジ線で囲まれた黒い四角)が表示されていると思いますが、これが基板の外形になります
枠の外側(左下)に、回路図で使用したパーツがごちゃごちゃと表示されてます(これが正常です)
 デザインルールの設定
デザインルールの設定最初に、FusionPCBの基板設計ルールに合わせたデザインルールをセットします
メニューの「Tools」→「DRC」を選択し、デザインルール設定ウインドを開きます

[Load]ボタンを押して、インストールの際に準備しておいたFusionPCBのルールファイルを読み込みます
これは、FusionPCBが製作できるPCBの最低限の設計ルールとなっていて
PCBを作成する際に、1箇所でもこのルールに逸脱していると、FusionPCB側で受け付けてくれません。
正しく読み込むと、DRCウインドウのタイトルバーに、読み込んだルールファイル名が表示されます

 エディット画面の基準寸法の変更
エディット画面の基準寸法の変更基板上のパーツや配線、外枠を移動する際に、グリッドを設定してある程度の寸法単位で動かす基準となります
画面左上の
 を押すと、編集画面が出ます
を押すと、編集画面が出ます
デフォルトの基準は「mil」単位になっているので、使いやすい単位にセットします
基板外形や、LED・スイッチ等の位置を調整する場合は「mm」にすると合わせやすいと思います
(1mil=0.0254mm、ICのピン 2.54mm=100mil)
・「Display」をONにすると、画面上にグリッドが表示されます
・「Style」 グリッドの表示が Dot=線、Line=線
・「Size」 通常の移動単位
・「Alt」 [Alt]キーを押しながら移動したときの移動単位
とりあえず今回は「Size」を10mmでセットします
 基板のサイズ調整
基板のサイズ調整まずは基板の外形を、作成したい寸法に調整します
ツールアイコンの
 を押して移動モードにします
を押して移動モードにします移動したい外枠の角にマウスカーソルを合わせ、左クリックしながら移動すると、外枠の頂点が移動します

グリッドのサイズを 10mm にしているので、1ラインが 10mm で、10mm単位で移動できます

これで基板の外形は、50mm x 50mm になりました
 編集モードの解除
編集モードの解除[Esc]キーを押すか、別のツールアイコンを選択すると、その編集モードは解除されます
 画面の拡大、縮小
画面の拡大、縮小マウスホイールの上下で出来ます
常にマウスカーソルのある場所を基準にして拡大縮小するので、先にマウスを合わせてから
マウスホイールで拡大すると、丁度よく拡大できます

 パーツの移動
パーツの移動パーツの移動も移動モードを使います
各パーツの中心あたりに「+」のマークが出ていると思いますが、そのあたりにマウスを合わせて
左クリックしながら移動すると、パーツが任意の場所に移動できます
この際、パーツが最初に配置されていた場所から、移動の単位で設定した単位で動くので
必ずしもグリッドラインにピッタリ合いません
その際は [Alt]キーを押して、細かくパーツを移動しますが、それでも位置がずれるようなら
移動の単位を細かく設定して微調整するといいと思います
数値で調整する方法
微調整したい部品を選択して、キーボードの[i]キーもしくは、マウスの右クリックメニューで「プロパティ」を選択すると
部品の詳細が表示されます

Positionの項目が、基板の左端の+部分を基準点とした X,Y座標になっているので
この値を直接変更して位置の調整が行えます
(Backyさんありがとうございます!)
だいたいこんな感じで配置が出来ました

 パーツの回転
パーツの回転ツールアイコンの
 を押して回転モードにしておき
を押して回転モードにしておき回転させたいパーツの上で左クリックすると回転できます

 パーツの背面移動
パーツの背面移動実装するパーツを、基板の反対側に設置したい場合、ツールアイコンの
 で
で反転モードになるので
反対側に移したいパーツの上で左クリックすると移動します

背面に移動したパーツは、左右が反転して表示されます(ピンの位置も逆になるります)
 パーツシルクの移動
パーツシルクの移動パーツを移動していると、部品名のシルクが重なってしまったり、変な位置に来る場合があります
シルクだけを移動させたい場合、先にパーツとシルクを分離させます
ツールアイコンの
 ボタンを押し、分離モードにしておき、シルクを分離させたいパーツの+マークあたりで左クリックすると
ボタンを押し、分離モードにしておき、シルクを分離させたいパーツの+マークあたりで左クリックすると部品とシルクがそれぞれ分離します
シルクにもそれぞれ+マークが付くので、移動モードでシルク単体で移動できるようになります
 ドリルホールの設置
ドリルホールの設置ネジ用の穴等、基板に穴をあけたい時に使います
ツールメニューの
 を押してホールモードにして、あとはマウスで位置を決めて左クリックすると位置が決まります
を押してホールモードにして、あとはマウスで位置を決めて左クリックすると位置が決まりますホールモードを解除して、設置した穴の位置でマウスの右クリックメニューから「Propaties」を選ぶと
「Drill」の項目で、穴の半径サイズが変更できます

FusionPCBのドリル穴は 0.3mm — 6.35mm と決まっているので、その範囲内で開けることができます
基板の4か所にネジ用の穴を開けてみました











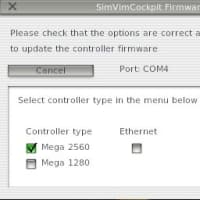
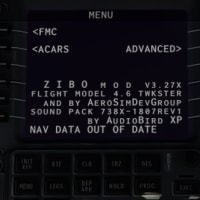
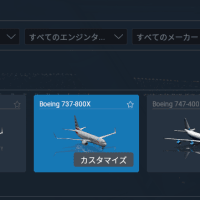
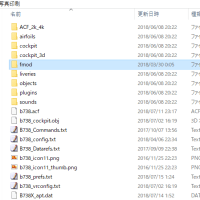
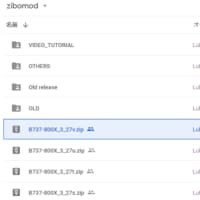





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます