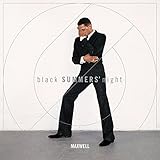 |
black SUMMERS' night |
| Maxwell | |
| SMJ |
アメリカでは発表した4作のオリジナル・アルバムがミリオン・セラーで、グラミー賞も受賞しているのに…なぜか?(日本人ウケするキラキラが少ない?)日本では認知度が低い感じのR&B~ソウル系ミュージシャン──それが今回オススメなマックスウェルです。
まあ私自身は、ミリオン・セラーとかグラミー賞なんてあまり興味ないのですが、歴史を省みると大抵の名盤と語り継がれているアルバムは、発表当時それなりに売れたものが多いようにも思います。
このマックスウェルというアーティスト、生演奏とテクノロジーも駆使したエレクトリックな音とのバランスを大切にし、最先端とか前衛性みたいなものにこだわり過ぎない程度にオリジナリティーを保っているというか…キャッチーなだけの方向にも走り過ぎず、難解にならない程度にアートとしての魅力を感じさせてくれるのです。
マックスウェルは母親がハイチ出身(大坂なおみさんと同じ!)であり、『VooDoo』という名盤を発表した同期のミュージシャンであるディアンジェロ(この人もオススメ!)よりも、血筋はVooDooなのに、それにはこだわらずニュートラルな感じです。
それよりも彼が3歳の頃、飛行機事故で亡くなったプエルトリコ系の父親への思いが強いのか、2枚目のアルバム『Embrya』ではスペイン語の歌詞を歌っています。
R&B~ソウル、ジャズなどブラック・ミュージック好きであると、人種問題──アメリカほど白黒はっきりしなくとも明らかに日本に存在する──について考えさせられることが多いんですよねぇ(アート全般に言えることかもしれませんが…)。
これもややこしい問題で、差別されている黒人同士であっても色が黒いとか白いとかでなんとなく言い合ったり、黒人の血が少しでも入っていると戸籍で「黒人」と表記されるとか音楽雑誌で読んだ記憶があります(なんと!あのマライア・キャリーも…)。
同じ黒人系(ネット検索のみですが、アメリカにおいて黒人系は12%程度のようです)でも奴隷として直接アメリカへつれてこられてしまったアフリカ系が多数派で、マックスウェルはマイノリティー(少数派)である黒人系の中でも、さらにマイノリティーと言えるのでしょう(フランスによって奴隷としてつれてこられたアフリカ系の人々が結束し、1804年に世界初の黒人共和国となったハイチは、歴史も人種も複雑そうです)。
異なった人種同士の結婚で生まれた子どもは、否応なく国や人種の狭間に立たされるので、アイデンティティー形成にかなり苦労するようです。
そのような国や人種をまたぐ混乱に覆い尽くされ犠牲となってしまう者も多いのかもしれません。でも、そのような厳しい混乱を経てこそマックスウェルのようなセンスが養われるのでしょうから──アートとは何とすばらしくも残酷……。
マックスウェルは以前読んだインタビューなどから察するにシャイで謙虚な人のようです。
自分が作詞や作曲した曲のクレジットもMusze(Muse/詩や音楽の女神みたいな感じ?)とし、自分だけの力ではなく、いろんな人々との交流の中で魂を導かれ曲が作られる…みたいに考えているのではないでしょうか。
今回のアルバムのラストを飾るNightという曲は、波打ち際の音であり、クレジットの最後にはWritten by Earthとあって、自然に対する敬意も感じます。
さて新作の『black SUMMERS' night』ですが、個人的にはグラミー受賞の前作『BLACK summers' night』より曲同士の流れが何だか心地よく、全体としての完成度が高く感じます。
このアルバム・タイトルがややこしく、同じスペルのタイトルだけど大文字表記になっている部分だけが異なっているのです。
おかげでコンピューターは同じものと認識してしまい…アマゾンのレビューもしばらく前作とごちゃ混ぜになっていたし、iPodでも同じ作品と認識されごちゃ混ぜ化してしまうのです――もう改善されたかな?
この同じタイトルのアルバム群、確か?最初は3枚組で出す、とか言ってたのに、今度は3連作を1年ごとに出すに変わったのです。そして1枚目がグラミー賞を穫っちゃったら、プレッシャーからか?7年を経てやっと2作目が出た!…ということなんです。
そんな経緯から、意図せずとも?コンピューターを混乱させてしまうなんて、まさにアートならでは!と言えるのか?
今回は全体的にギターの音が控えめな感じなのですが、ジャズの裾野を拡げようと奮闘中のピアニスト――ロバート・グラスパーも参加しており、それもあってかシンセ的な音が多いように感じます。
 |
Coverd |
| Robert Glasper | |
| ユニバーサル ミュージック |
2015年に発表されたこのグラスパー作品は、公開録音したライブ・アルバムです。もう十分実力を証明したグラスパーが難解なジャズ方向へ行き過ぎない(イントロで"I wanted to do a nice happy medium"と語っている)よう肩の力を抜きつつ、ライブ録音という緊張感に挑んだという感じがします。
ジョニ・ミッチェルやレディオヘッド、R&B系ではジョン・レジェンドなど、HipHop系ではケンドリック・ラマーまで幅広くカヴァーしており、In Case You Forgotのように曲の途中で忘れちゃった?…けどシンディー・ローパーやボニー・レイットの曲まで引用したりするユーモラスな曲も入っています。
ジャズとか聴いたことないけど、音楽的趣味の幅を広げたい!というような人にオススメです!
彼が係わった曲はやはりいい感じで、特に今までにない感じの曲であるLostで重くなった空気の後に続くOf All Kindは、シンセがレゲエのようなリズムで入る軽快な曲です――マックスウェルの魅力の一つであるファルセットも聞けるのでお気に入りです(なぜか?ウチの子も好き)。
そして、その後に続くListen Hearという曲なのですが…この曲っていわゆるラブソング的な所もありますが、マックスウェルの内面の告白のようで、混乱すれば?時に嘘をついてしまうかもしれないことや、「自分はこれでいいのだろうか?」というすべてを壊したくなるような欠落感などを歌っているように感じました。
そういった自分の弱さをさらけだし、ネガティブなものにも向き合いつつ、Nothing is wrong(悪いことなどない)、Everything is right(すべては正しい)とポジティブな言葉を重ねます。
あれ?これってこの前ディランの所で書いたこととつながっているぞ!?
…と思っていたら、マックスウェルがジミ・ヘンドリックスのカヴァーで有名なディランの名曲All Along The Watchtower(見張塔からずっと)の歌詞(ネガティブにしか考えられないほどひどい混乱に襲われているのか?)をそれぞれジミヘンとディランの写真入りでツイートしているではありませんか!(2016/8/3のツイート)
書いているうちにこんな風につながってくるとは予想外でしたが、こんがらがったもの(Confusion)をキーワードとしたディランの影響力はすごいのかもしれませんね。
もうすぐマックスウェル初の来日公演ですね。今回私は行けないのですが、いつかは絶対行きたいです。
もっと日本で人気が出れば行けるチャンスが増えるので、チケット入手困難にならない程度に人気が出ればいいな~!
最新作と合わせてオススメなのは、このファースト・アルバムです。ちょっとオシャレ過ぎる嫌いはあるかもしれませんが、リズム・ギターの名手ワー・ワー・ワトソンのおかげで芯のあるサウンドとなってこれまたカッコイイのです!
マックスウェルのファルセットも瑞々しくてすばらしいですよ!ぜひ聴いてみて下さい!!
新作では彼のファルセットに変化が感じられ、アマゾンのアメリカ版レビューを見るといろいろ物議を醸しているようです。
でも、このLive版Lake By The Ocean見てみて下さい!CD版よりややスローでデリック・ホッジのベースもねっちょり効いていて超カッコイイです!! http://abcnews.go.com/GMA/video/maxwell-performs-lake-ocean-gma-40394424
瑞々しさを代償にして円熟の深みが増すのが世の常…それこそNothing is wrongですね!




















