こんばんは、皆さん。
今回は、久々に電子工作関係の記事です。
と言っても、私はオーディオ機器を主に作るので、事実上のオーディオの記事にもなるわけですが。
別に、新しいヘッドフォンアンプを設計するという類の話ではありません。
過去に作ったヘッドフォンアンプの回路について、少しお話します。
結構な数を作ってきましたが、今でも使用しているのは、僅か一台。
確か、五台目ぐらいに作ったやつで、もう四年?ぐらい使ってます。
回路だけ見ると、特に凝った作りにはしていません。
唯一凝ったのは、電源から出力まで、完全LR独立(良く、ツインモノラルとか言ってる構成)だというぐらい。
電圧増幅は、OPA2604(LRで一つずつ使用)で、ここにディスクリートで組んだバッファを付けただけの構成です。
一つだけ妙があるとすれば、バッファでして、ダイヤモンドバッファを基礎としながらも、出力段に電流ブースタを付けています。
これだけだと、出力がコレクタ出力になってしまって、出力インピーダンスが高くなってしまいますが、オペアンプの高い裸利得を利用して、深くNFBを掛け、出力インピーダンスを低く抑えています。
また、そもそもヘッドフォンアンプとしてだけ使う場合には、仮に電流ブースタがなくても十分な出力が得られます。
(=ヘッドフォンアンプだから許される構成です。)
電源は、±18Vの両電源で、三端子レギュレータを使うというお手軽構成。
(まともに電源回路を設計する力がなかった頃だから。)
フロントパネルにはVUメーターを配し、メーターアンプはトランスから出力まで完全独立。
という感じです。
確か、製作費は2万5千円ぐらいだったと思います。
(失敗が多く、部品がた~くさん無駄になったから。最初からゴールまで無駄が無ければ、こんなには掛かりません。)
これ以降作ったヘッドフォンアンプが、これを超えられないのは、多分、電源の問題だと思います。
電圧を高めで作ったというのもありますが、それ以上に、ミニパワーアンプが作れるトランスをLR独立に使用しているというのが、効いているのかな、と。
箱もかなり大きめの箱で、中はゆったり作りました。ノイズ対策の腕がなかったので、そもそもノイズ源から離せば良い、という力技によるものです。
一応、6ohmのスピーカーを鳴らせないこともないですが、何分、自分の回路設計力がひく~い頃のものなので、音量を上げると何かが起こりそうで怖い。
(でも、AU-D607を修理して使うまでは、このアンプでDIATONEのスピーカーを鳴らしていました。)
今更、このアンプの話をするのは、LUXMAN DA-200を購入したから。
世間には、DA-200のヘッドフォンアンプを、なかなかの出来、などと評する声もあるようです。
まぁ、音質と回路の手間が掛かっているかどうかは、決してイコールではないので、別に構いませんが、多分、中身をそのままコピーした自作アンプを作っても、評価してくれる人は少ないのではないかと思います。
で、具体的にどんな回路かと言いますと、電圧増幅段と電力増幅段の2段構成で、どちらもオペアンプ1個でLRとも駆動しています。
電圧増幅段は、プリアンプと共通で、5532DDが一つ。電力増幅段は、多分、ボルテージフォロワになっていると思われる4580DDが一つ。
値段は、個人で購入すると、5532DDが100円、4580DDが40円です。
デカップリングコンデンサには、東信工業のオーディオ用ケミコン等が使われていますから、コンデンサの方が値段が高い。他に高い部品と言ったらミューティングリレーでしょうか。
(固定抵抗には、金属皮膜抵抗が使われているようなので、ケチった造りというわけではありません。)
音質云々は置いておいて、私が言いたいのは、
“決してオマケではない”ということは無く、間違いなくオマケだということです。
オペアンプなので、歪み率などの数値上のスペックは非常によろしいですが、いかんせん、電流供給力が低すぎる。
電源電圧は、据え置き型ということもあって高めに設定されていると思いますから、ハイインピーダンスのヘッドフォンを駆動する限りに於いては、特に問題はないと思います。むしろ、最近のローインピーダンスのものがまともに鳴らないのではないかと。
こればかりは、強力なバッファをディスクリートで組む以外には方法がありません。従って、ヘッドフォンアンプを自作する人達は、電圧増幅こそオペアンプで行っても、必ずバッファをディスクリートで組みます。
LUXMANを買うような人が、5000円のヘッドフォンやイヤホンで音楽を聴いているはずがないので、問題が起きないと言えば起きないのですけどね・・・。
ということで、自作してると、知らなきゃ良かったなぁ、ということがあるってことです。回路見ちゃうとねぇ。
それだけが言いたかった。
以上。
今回は、久々に電子工作関係の記事です。
と言っても、私はオーディオ機器を主に作るので、事実上のオーディオの記事にもなるわけですが。
別に、新しいヘッドフォンアンプを設計するという類の話ではありません。
過去に作ったヘッドフォンアンプの回路について、少しお話します。
結構な数を作ってきましたが、今でも使用しているのは、僅か一台。
確か、五台目ぐらいに作ったやつで、もう四年?ぐらい使ってます。
回路だけ見ると、特に凝った作りにはしていません。
唯一凝ったのは、電源から出力まで、完全LR独立(良く、ツインモノラルとか言ってる構成)だというぐらい。
電圧増幅は、OPA2604(LRで一つずつ使用)で、ここにディスクリートで組んだバッファを付けただけの構成です。
一つだけ妙があるとすれば、バッファでして、ダイヤモンドバッファを基礎としながらも、出力段に電流ブースタを付けています。
これだけだと、出力がコレクタ出力になってしまって、出力インピーダンスが高くなってしまいますが、オペアンプの高い裸利得を利用して、深くNFBを掛け、出力インピーダンスを低く抑えています。
また、そもそもヘッドフォンアンプとしてだけ使う場合には、仮に電流ブースタがなくても十分な出力が得られます。
(=ヘッドフォンアンプだから許される構成です。)
電源は、±18Vの両電源で、三端子レギュレータを使うというお手軽構成。
(まともに電源回路を設計する力がなかった頃だから。)
フロントパネルにはVUメーターを配し、メーターアンプはトランスから出力まで完全独立。
という感じです。
確か、製作費は2万5千円ぐらいだったと思います。
(失敗が多く、部品がた~くさん無駄になったから。最初からゴールまで無駄が無ければ、こんなには掛かりません。)
これ以降作ったヘッドフォンアンプが、これを超えられないのは、多分、電源の問題だと思います。
電圧を高めで作ったというのもありますが、それ以上に、ミニパワーアンプが作れるトランスをLR独立に使用しているというのが、効いているのかな、と。
箱もかなり大きめの箱で、中はゆったり作りました。ノイズ対策の腕がなかったので、そもそもノイズ源から離せば良い、という力技によるものです。
一応、6ohmのスピーカーを鳴らせないこともないですが、何分、自分の回路設計力がひく~い頃のものなので、音量を上げると何かが起こりそうで怖い。
(でも、AU-D607を修理して使うまでは、このアンプでDIATONEのスピーカーを鳴らしていました。)
今更、このアンプの話をするのは、LUXMAN DA-200を購入したから。
世間には、DA-200のヘッドフォンアンプを、なかなかの出来、などと評する声もあるようです。
まぁ、音質と回路の手間が掛かっているかどうかは、決してイコールではないので、別に構いませんが、多分、中身をそのままコピーした自作アンプを作っても、評価してくれる人は少ないのではないかと思います。
で、具体的にどんな回路かと言いますと、電圧増幅段と電力増幅段の2段構成で、どちらもオペアンプ1個でLRとも駆動しています。
電圧増幅段は、プリアンプと共通で、5532DDが一つ。電力増幅段は、多分、ボルテージフォロワになっていると思われる4580DDが一つ。
値段は、個人で購入すると、5532DDが100円、4580DDが40円です。
デカップリングコンデンサには、東信工業のオーディオ用ケミコン等が使われていますから、コンデンサの方が値段が高い。他に高い部品と言ったらミューティングリレーでしょうか。
(固定抵抗には、金属皮膜抵抗が使われているようなので、ケチった造りというわけではありません。)
音質云々は置いておいて、私が言いたいのは、
“決してオマケではない”ということは無く、間違いなくオマケだということです。
オペアンプなので、歪み率などの数値上のスペックは非常によろしいですが、いかんせん、電流供給力が低すぎる。
電源電圧は、据え置き型ということもあって高めに設定されていると思いますから、ハイインピーダンスのヘッドフォンを駆動する限りに於いては、特に問題はないと思います。むしろ、最近のローインピーダンスのものがまともに鳴らないのではないかと。
こればかりは、強力なバッファをディスクリートで組む以外には方法がありません。従って、ヘッドフォンアンプを自作する人達は、電圧増幅こそオペアンプで行っても、必ずバッファをディスクリートで組みます。
LUXMANを買うような人が、5000円のヘッドフォンやイヤホンで音楽を聴いているはずがないので、問題が起きないと言えば起きないのですけどね・・・。
ということで、自作してると、知らなきゃ良かったなぁ、ということがあるってことです。回路見ちゃうとねぇ。
それだけが言いたかった。
以上。











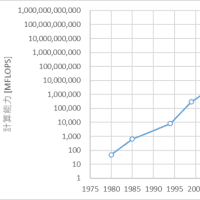













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます