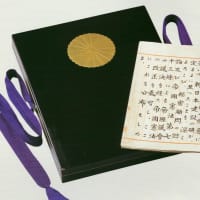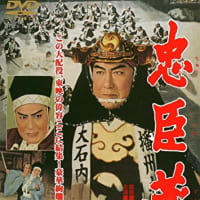●「背中の窪み」
風の盆を最初に見たのは20年以上前になります。当時私は着物ショ―の演出の仕事をやっていました。仕事で富山を訪れた時、仕事先の方が勉強になるからと連れて行ってくださったのがこの祭りでした。
その時、女性の着物姿は何処が美しいかという話題で宴が盛り上がりました。意見を求められた私は「背中の肩甲骨の間の窪みが美しい」と答えました。私の言葉が予想外であったのか、座にいた人々は皆訝しげな顔をしました。
着物は直線断ちで、洋服の立体裁断とは違って身体のラインが出にくいということになっていますが、実はそうではないのです。確かに脚のラインは隠せますが身体のラインは如実にでます。肩甲骨と二の腕は身体の中で皮下脂肪が付きにくいところですが、年をとるとやはり脂肪が付いて来ます。若い女性程ここに脂肪が付いていませんから背中の窪みがくっきりと出ます。この窪みの上に細い首筋がつながると実に美しいのです。30代になるとこの窪みが出る人は残念ながら少なくなってきます。
私の見方は少し変わっているということでその場は収まりました。後日、T画伯という著名な挿絵画家にお話を伺う事が出来ました。T画伯は妖艶な着物姿の女性を描く事で大変人気のある画家でした。T画伯に「女性の着物姿の何処に美しさを感じられますか」という質問をしてみました。するとT画伯は躊躇する事無くこう答えられました。
「私は後姿、特に背中の肩甲骨の間の窪みが一番美しいと思う。着物のラインはその人の身体の線を良く表しています。ですから私が着物姿の女性を描く時は、下絵にその女性のヌードを描き、その上から着物を描いてゆきます」してやったりです。私の審美眼の正しいことが証明されたのです。
●「現と幻」
「風の盆」の踊りは手の振りが実に細やかです。女性の踊り手は膝を少し曲げ後ろに反り返るような所作をします。各地の踊りにはあまり見られない、日本舞踊のような振り付けです。もともと花街の芸者衆が踊ったことに端を発していますから、成る程とうなずけます。
息の合った男の踊り手と女の踊り手が絡む所作は、歌舞伎の道行きを連想させるほどに華があります。端で見ている者がそう感じる位ですから、踊っている当人達の間には特別な感情が生まれ、恋が芽生える事も少なくなかろうと思われます。
こうして一緒になった二人に子が生まれ、その子が踊りを習い、またその子供が踊りを受け継いでいく。八尾の町の人々には「風の盆」が生活に深く息づいています。
最近は見られなくなりましたが、盆踊りの一隊が新盆の家を訪ねて踊るという風習が各地にありました。編み笠を被るのは顔を隠すことによって踊り手は死者の霊を宿す特別な存在になります。死者の霊が生者の身体を借りて、自分の家を訪れるという意味合いがあるのだそうです。編み笠を被った踊りの一団は、生を謳歌する生者の一団であると共に死者の霊の一団でもあるらしいのです。
今を生きる者は踊り手に亡き人の面影を見、あるいは過去の想い出をオーバーラップさせる。「風の盆」はまさに「現と幻」なのかもしれません。この幻想的な踊りを見ていると、その意味合いが良く分かるような気がしてきます。
●「祭りの後で」
今回の「風の盆」初日の人出は20万人以上と発表されました。以前の祭りでは考えられない人出です。多くの人々がこの祭りに触れることが出来るのは良いことなのですが、反面この祭りの良さが年々薄らいでいるのではないかという気もします。
翌日、祭りの喧騒を離れ、妻と娘を連れて八尾町周辺の里山と棚田を訪れました。五穀豊穣と人々の安寧を願う「風の盆」に相応しい景色を見せたくなったからです。
里山の林の中にはすでに色づき始めた木々もありました。雪深いこの里の短い秋がすぐそこまで来ているようです。棚田にはたくさんの実をつけた稲穂が、重たげにこうべを垂れていました。秋の気配を感じさせる涼やかな風が山間に吹き渡ると、稲色に輝きながら棚田の上を広がってゆきました。
Copyright:(C) 2005 Mr.photon
最近の「美しの国ニッポン」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
- 台湾(3)
- 今日のちょっと見、拾い読み(31)
- 安全保障(22)
- 米中戦争(1)
- ロシア(ソ連)の大犯罪!シベリア抑留(1)
- ディープステート(7)
- もうひとつの無法国家 北朝鮮(2)
- 韓国崩壊(1)
- 中国滅亡(21)
- 教科書検定不正問題(6)
- 大東亜戦争(2)
- アイヌ利権(1)
- アメリカ大統領選(0)
- アメリカ大統領選挙(26)
- 情報ソース(2)
- デジタル言論統制(1)
- トランプ大統領(2)
- ビックテック(1)
- チャイナ利権(1)
- お清め(2)
- スメラミコト(2)
- 日本の心(7)
- 美しの国ニッポン(32)
- 日本人に謝りたい(9)
- 日本の今を考える(71)
- 日本人必見!軍事講座(4)
- 情弱とお花畑が思考停止する「軍事と国防」(6)
- 「左翼に騙されるな」アンチ左巻き講座(2)
- WGIP覚醒講座(2)
- 知っ得、納得「政治・経済」(6)
- 反日種族主義 ビデオ講座(4)
- 売国奴・売国企業図鑑(15)
- 在日問題(16)
- 中共のウィグル人弾圧と人権侵害(4)
- 中共の蛮行・愚行(35)
- 中共の臓器移植・臓器狩り・大量虐殺 (3)
- 武漢ウィルス ・武漢肺炎(16)
- 中共の超限戦(3)
- 沖縄が危ない! 中国、北朝鮮、韓国(1)
- 体験的昭和戦後史(4)
- 国連・国際機関の深い闇 (3)
- ユダヤの陰謀(45)
- 今そこにある日本の危機(5)
- 神社と古神道の教え(25)
- スピリチュアル(59)
- 死後の世界(19)
- 世界宗教の真実(18)
- 昭和ノスタルジー(7)
- 意識のパワーレベル(9)
- 易と手相(14)
- 爬虫類人とプラズマ兵器(36)
- ケムトレイル(18)
- もったいない(3)
- 食の安全と健康(3)
- 医療の虚実(8)
- その他(24)
バックナンバー
人気記事