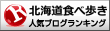ダイダラボウ
ダイダラボウ
千波湖(茨城県水戸市)の遊歩道をウォーキングしていたある日のこと。
こんな石柱を見つけました。

「ダイダラ坊の伝説」。
「ダイダラ坊」と聞いて、「ダイダラボッチ」が頭の中に浮かんだ私。
しかし、「ダイダラボッチ」が何だったかよく覚えておらず、ちょっと調べてみることにしました。
 ダイダラボッチについて
ダイダラボッチについて
日本の各地で伝承される巨人である。数多くの類似の名称が存在する。
山や湖沼を作ったという伝承が多く、元々は国づくりの神に対する巨人信仰がダイダラボッチ伝承を生んだと考えられている。
(鬼や大男等の妖怪伝承が巨人伝承になったという説もある。)
柳田國男は『ダイダラ坊の足跡』(1927年(昭和2年)4月中央公論社)で日本各地から集めたダイダラボッチ伝説を考察しており、
ダイダラボッチは「大人(おおひと)」を意味する「大太郎」に法師を付加した「大太郎法師」で、
一寸法師の反対の意味であるとしている。
呼び名としては、「でいだらぼっち」、「だいらんぼう」、「だいだらぼう」、「でいらんぼう」、「だいらぼう」、「デエダラボッチ」、
「デイラボッチ」、「デイラボッチャ」、「デーラボッチャ」、「デエラボッチ」、「デーラボッチ」、「タイタンボウ」、「デエデエボウ」、
「デンデンボメ」、「ダイトウボウシ」、「レイラボッチ」、「ダダ星」等がある。
大太法師(だいだらぼっち)、大太郎坊(だいだらぼう)とも表記し、九州では大人弥五郎(おおひとやごろう)と呼ばれる。
(ウィキペディアより)
ちなみに水戸では「ダイダラ坊」と呼んでおり、こちらの石柱によると、
千波湖をつくったのは、「ダイダラ坊」なのだそうです。
<石柱に記された文章>
千波湖をつくったのはダイダラ坊という巨人だ、と言い伝えられている。
ダイダラ坊は現在の内原町大足に住んでいた。
村が朝房山のために日陰になり、村人の困っているのを見たダイダラ坊は、山を村の北方に移してしまった。
ところが、その跡に水がたまって洪水になったため、指で小川をつくって水を流し、
その下流に掘った沼が千波湖だという。
思いもかけず、日本の文化伝承に触れることになりましたが、とても良い勉強になりました。
なお、水戸市には「ダイダラ坊」伝説の地、「大串貝塚」があり、
そちらにもぜひ、行ってみたいと思ったのでありました。