備忘録、という事で今まで少林寺拳法(以下SKと略す)について考えてきた事を、自分がボケる前に記しておこうと思うのですが、ブログの説明に書いてある通り、
※注:本ブログは(た)個人の見解に基づいており、如何なる他の個人・団体の見解を解説・代弁するものはありません。
SKの技について考察はするのですが、もし本部の公式見解と矛盾していたら、私の方が間違っていると考えて頂いて差し支えありません。個人の備忘録ですから。。
◆ ◆ ◆
突天二は、旧・科目表では1級科目として習得した天王拳(上段攻撃から始まる連攻防の拳系)の法形です。それ迄に天王拳として突天一(旧・3級)・混天一(旧・2級)を習いましたが、初の「天二之形」だった訳です。天王拳の天二之形は「段受の修練」が眼目であり、1級科目としては突天二と振天二を修練しました。
※注:本ブログは(た)個人の見解に基づいており、如何なる他の個人・団体の見解を解説・代弁するものはありません。
SKの技について考察はするのですが、もし本部の公式見解と矛盾していたら、私の方が間違っていると考えて頂いて差し支えありません。個人の備忘録ですから。。
◆ ◆ ◆
突天二は、旧・科目表では1級科目として習得した天王拳(上段攻撃から始まる連攻防の拳系)の法形です。それ迄に天王拳として突天一(旧・3級)・混天一(旧・2級)を習いましたが、初の「天二之形」だった訳です。天王拳の天二之形は「段受の修練」が眼目であり、1級科目としては突天二と振天二を修練しました。
攻撃法は「上上二連撃」、即ち順上段直突-逆上段直突を一呼吸、ワンツーで叩き込む訳です。ここで少し疑問に思うのは、突天一で「上中二連撃」に対して上受-同時受(二連防)で受けたのは「二撃目が上段に来るかも知れないから」だった訳ですよね? であるならば突天二でも上受-同時受(二連防)で受けても良いんでは無いでしょうか。
突天二では打上受-打落受の段受で受けて、同時蹴りの順蹴りで返します。反対の手は胸前に留めて、二撃目でも下受をしません。
これをどう研究・解釈するかはひとによって様々と思いますが、私は守者が「上上二連撃」と読み切った時は打上受-打落受を行なう、という事だと思いました。実際には突天一と突天二はグラデーションの様な関係なのではないか、というイメージでやっています。
二撃目が顔面に飛んでくるのは結構厳しい攻撃で、私は武専では遠慮の欠如した(…)学生拳士に何発も入れられました…(拳サポつけた当て止めルールですが)。やり返そうと頑張るのですが、向こうは素早く反り身をして間合いを切られてしまいました。…
突天二は旧・科目表の一つ前の科目表では、二段科目でした。振天二の方が初段科目でしたから、共に1級科目になる前は振天二の方が簡単だと考えられていた事になります。振突攻撃の方が伸びてこないので、その通りだと思います。
振天二の後に突天二を習うと、打落受の際に腰が入ってしまい(身体が入ってしまい)、直蹴の蹴上げが上手く出来なくて困りました。(振天二の二撃目の受けも打落受!)
また、順蹴りを意識しながら定型的な打落し受をやると、どうも突きを引き込んでしまう感じもしました(=受けに力が入らない)。
中々技のイメージが出来なくて困っていたのですが、上述したような突天一と突天二はグラデーションというイメージを持ってからは、蹴上げが楽になったと思います。
なので私の突天二は、打落し受も内受に近いものになっています。打上受で肘が上がってますから内受をしても打落し受になる(とみなす)、という感じです。反対の手は胸前で握ってますが気持ち下受をしています😅。一方突天一では、私(守者)は二撃目は中段に来ると読んでいますから、上受けした手は一旦肩まで戻ってきて(二撃目に備えるイメージ)、そこから同時受けをする訳です。
対・連撃は一瞬の判断になりますから、予めどこに手があるかが重要です。ボクシングで「ガードを下ろすな!」と言っているような事(修練)を、天王拳はやっているのだと思います。
上述の反り身を主体とした避け方の方が伸びてくる攻撃には安全かも知れないのですが、(振天二ではなく)突天二と突天一の連携・親和性、順蹴り蹴上げ指定である事を考えて、現在はこの考えでやっています。修練・修練・・。引き身をして(=攻者にやや正対するような体勢で受けて)蹴り返すので、しっかり打ち落とさないとまた悔しい思いをしかねません🤔。
頑張ります💪。
実戦では、打落し受で腰が入ってしまったら足刀蹴でも無問題だと思います👍。














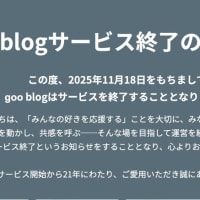










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます