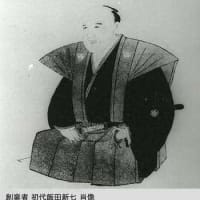東近江市の歴史文化研究家の中島伸男氏が近江の「八日市場」に纏わる巻物発見に関し、滋賀報知新聞に寄稿した第2回目を紹介する。
中島 伸男(東近江市・野々宮神社宮司、元八日市郷土文化研究会会長)

■原本から書写した瓦屋禅寺版
ところで、瓦屋禅寺に伝えられる「八日市場市神之略本記」は巻物になっている。鯛を抱えた恵比寿像の押印はない。
八日市場の起源を記した内容をはじめ、内容は変わらないが漢字には振り仮名があり、文章の末尾に「推古9年より安政5年まで1260年也」と記されている。推古9年から安政5年(1858年)までは、正確に数えれば1257年で少し誤差があるが、市神神社蔵「八日市場市神之略本記」を安政5年に転写したものであろうと推測できる。
瓦屋禅寺が「八日市場市神之略本記」を転写・巻物にして所蔵された理由は、勿論「市神之略本記」に聖徳太子が白鹿山に瓦屋寺を造営されたこと、及び「大悲の像」を刻み給うたことなど、瓦屋寺の重要な由緒が記されているからであろう。大悲の像とは、瓦屋禅寺御本尊(秘仏・国指定重要文化財)の木造千手観音菩薩立像のことである。
■蛭谷「御縁起」を入手した
それでは、惟喬親王(844~897年)の「御縁起」が瓦屋禅寺に伝えられている理由は何なのだろうか。瓦屋寺と木地師とは縁もゆかりもないはずである。
惟喬親王「御縁起」は蛭谷・筒井神社に1つ、君ケ畑・大君器地祖(おおきみきじそ)神社に3つ、あわせて4つが伝えられている。
この4つは少しずつ内容が異なっている。瓦屋禅寺に遺されてきた御縁起を拝見すると、文面すべてが蛭谷の御縁起とまったく同じであることが分かった。細かく指摘すれば、異なっているのは「御縁起」末尾の署名人3名のうち、民部卿頼貞の「頼貞」が瓦屋禅寺蔵には「頼定」になっていることのみである。
巻物には、正方形の印章が一角を上にして3箇所押印されている。印章の文字は、中央に「小椋太政大臣實秀印」、右に「近江國愛知郡」左に「筒井公文所」とある。この印章によって、巻物は瓦屋禅寺で書写されたものではなく、明らかに蛭谷・筒井神社(もしくは蛭谷・帰雲庵)で作成され、これを瓦屋寺が買い求められたものであると推定できる。
ところで、「御縁起」の文面には、瓦屋寺と関係する叙述はどこにもない。
住職の藤澤さんは、「御縁起」の前半に聖徳太子の事績が記されていることが重要であったのではないか、と指摘された。
「御縁起」には、貞観元年(859年)3月5日、惟喬親王が白馬に乗り従臣とともに都を出て東へ向かわれたとの叙述に続き、次のように記している。原文は難解な漢文体なので、その大意を紹介するとおよそ次のとおりになる。
「(惟喬親王が)近江国愛智郡岸本城橋に到着されたころ日没となった。その辺りに堂塔仏閣があり、親王はここで一夜を明かそうと立ち寄られた。すると一人の翁が現れこの地の由緒を語った。それは、遠い昔、この地に守屋大臣(物部守屋=飛鳥時代に排仏を唱えた有力豪族の長)の城郭があり、聖徳太子は物部守屋との戦いののち、この地に七堂伽藍を構えて春日大明神ならびに太子手造りの薬師如来を祀られた」という故事である。惟喬親王は、翁から以上のような聖徳太子のこの地におけるご事績をお聞きになり、「ここに三日三晩閉籠されたのち、3月8日朝、ふたたび愛智河上へと駒を進められた」旨が記されている。
「御縁起」は全文約1100字あるが、当然のことながら主文は惟喬親王隠棲のご様子を伝えることであり、聖徳太子にかかわる記述は冒頭部分のみである。
https://blog.goo.ne.jp/ntt000012/e/16e2800e618bf2dea52b7425b988bc3b
東近江市の君ケ畑を「木地師の聖地」に 資料展示や懇談の交流館開く
https://blog.goo.ne.jp/ntt000012/c/1e10c7afbb8184145fcbe1d1777c59cc/5
郷土歴史家が「惟喬親王伝説を旅する」出版
https://blog.goo.ne.jp/ntt000012/c/1e10c7afbb8184145fcbe1d1777c59cc/23