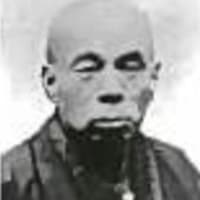羽田公こと、「羽田 矢国」(はた の やくに)(羽田公矢国)、生誕不明ー朱鳥元年(686年)没は、飛鳥時代の人物。名は八国とも書く。
天武天皇元年(672年)の壬申の乱で大友皇子(天智天皇の子)から大海人皇子(天智天皇の弟・天武天皇)側に寝返り、琵琶湖北回りの軍を率いて三尾城を攻略した。大弁官。冠位は直大参、贈直大壱。
羽田氏の姓(カバネ)は公、後に真人。近江の蒲生野一部であった羽田郷(東近江市)を地盤とする土豪。
***********************************
壬申の乱(じんしんのらん)
天武天皇元年6月24日 - 7月23日、(672年7月)に起こった古代日本最大の内乱である。
天智天皇の太子・大友皇子(1870年(明治3年)に弘文天皇の称号を追号)に対し、皇弟・大海人皇子(後の天武天皇)が兵を挙げて勃発した。
反乱者である大海人皇子が勝利するという、日本では例を見ない内乱であった。
名称の由来は、天武天皇元年が干支で壬申(じんしん、みずのえさる)にあたることによる。
天武天皇元年6月24日 - 7月23日、(672年7月)に起こった古代日本最大の内乱である。
天智天皇の太子・大友皇子(1870年(明治3年)に弘文天皇の称号を追号)に対し、皇弟・大海人皇子(後の天武天皇)が兵を挙げて勃発した。
反乱者である大海人皇子が勝利するという、日本では例を見ない内乱であった。
名称の由来は、天武天皇元年が干支で壬申(じんしん、みずのえさる)にあたることによる。
***********************************
「羽田公は応神天皇の血筋を引く稚野毛二俣王を祖とする湖北から出て、6世紀初頭の大和朝廷を制した継体天皇の同族である。羽田氏に「君」の性があるのは、湖北や越前を基盤とする継体天皇の皇親グループに属し、内乱で継体の陣に加わった功績によるものと思われる。
6世紀頃には旧八日市市、五個荘、蒲生(現東近江市)及び近江八幡市南部一帯の中小豪族を支配下に置いて、かなりの勢力を持っていたらしい。
雪野山山麓の八幡神社(東近江市中羽田町)境内に前方後円墳などの古墳群が存在するが、それは羽田氏一族のものであろうと推定されている。(湖国と文化第46号「羽田公矢国を追う」を一部引用)
壬申の乱での活躍
天武天皇元年(672年)6月に壬申の乱が勃発した際、矢国は近江の朝廷の軍(天智天皇の子、大友皇子)の将として、山部王、蘇我果安、巨勢比等(巨勢人)が率いた数万の軍の中にあった。この軍は琵琶湖東岸を進んで美濃国の不破にある大海人皇子の本拠を攻撃しようとしたが、7月2日頃に果安と比等が山部王を殺したため、混乱して止まった。
このとき、近江の将軍・羽田公矢国とその子大人らは己の族を率いて大海人皇子側に寝返った。斧鉞を授かり、将軍となり、ただちに北越に行くよう命じられた。
矢国は琵琶湖東岸を北進して越国への入り口を押さえてから、西岸を南下したらしい。7月22日、矢国は出雲狛と共に三尾城を攻め、これを降した。この三尾は、現在の滋賀県高島市にある三尾里にあたると推定されている。同じ日に味方の主力軍は瀬田で敵の最後の防衛線を破った。翌23日に大友皇子(弘文天皇)が自殺し、乱は終わった。
功臣のその後
戦後、天武天皇元年(672年)12月4日に、壬申の乱での勲功者の冠位が進められ、小山の位以上が与えられた。矢国もそれ以上の位を授けられたと考えられる。
天武天皇12年(683年)12月13日に、伊勢王、羽田矢国、多品治、中臣大島は、判官・録史・工匠といった部下を引き連れて全国を巡り、諸国の境界を定めた。この事業は年内には終わらなかった。矢国の位はこのとき大錦下であった。
天武天皇13年(684年)に羽田氏は真人の姓を与えられた。
羽田公矢国は、天武朝では文官として重用され、「諸国の境界」を定める大事業に3年余も取り組んでいる。
天武天皇15年/朱鳥元年(686年)の3月6日、大弁官・直大参、羽田真人矢国が病気になったため、僧3人を得度させた。矢国は26日に死んだ。「直大壱」(省の長官に相当する高い位)の位が贈られた。功なり名を遂げての死であった。
雪野山山麓にある古墳群に矢国又は一族が葬られたのか定かでない。また、その後の羽田氏の盛衰の記録は不思議とない。羽田公の羽田郷(東近江市)は中世佐々木氏の臣下「後藤氏」(後藤賢豊)の本拠に歴史が繋がっている。
<Wikipedia引用>