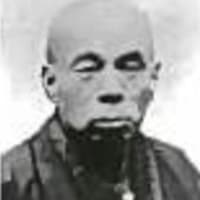川島右衛門俊蔵、(享和2年(1802年)-明治3年(1871年)、南五個荘村川並生まれ。
南五個荘村川並(川並村)(現東近江市五個荘町川並)にあった寺子屋の指導者。医学の知識、書道の技術にたけ、読み書きやそろばんを教えたという。
この寺子屋(川並村唯一の寺子屋)から2代目塚本定右衛門定次や妹の塚本さとなど多数の近江商人や人材を輩出した。
【過去ログ】
滋賀・近江の先人第11回】小町紅の行商から甲府を拠点に身を興す塚本家本家・塚本定右衛門(東近江市)
https://blog.goo.ne.jp/ntt000012/e/b7439863f15331229c778075c3d366d5
https://blog.goo.ne.jp/ntt000012/e/b7439863f15331229c778075c3d366d5
滋賀・近江の先人第29回】近江商人夫人としての女子教育の淡海高等女学校創設者・塚本さと(東近江市)
https://blog.goo.ne.jp/ntt000012/e/36538554f288b37143a62acbe6b05386
https://blog.goo.ne.jp/ntt000012/e/36538554f288b37143a62acbe6b05386
寺子屋があった江戸においても当時大半の村の子供達が実質的に村の学校としてこの寺子屋で学んだと言われる。また、五個荘の寺子屋は近江商人養成の一翼も担っていた。
川島俊蔵の寺子屋は明治政府の学制導入により寺子屋は閉じ、川並村の「川並学校」に変わってゆく。川島俊蔵の寺子屋は今も子孫により保存されている。
<「近江商人の魂を育てた寺子屋−川島俊蔵の教えに学ぶ−」中野 正堂【著】参照>
近江商人の心を育てる川並の寺子屋
近江商人を多く輩出した東近江市五個荘の地には、江戸時代に10校の寺子屋があり、1校あたり生徒数が平均110人で、全国平均の54人に比べて多く、算術を教える比率が高いという特徴があった。
五個荘川並の寺子屋の幕末期の五代目師匠川島俊蔵は、宝永年間出版のものをモデルにしながらも独自の記述 をふんだんに挿入した手書きの 「寺子教訓 」を編纂 している。
その中に「仏神 」とか 「仁義礼智信の五常 」という他の「教訓 」には全く見られない宗教や儒教の言葉が出てくる。
よく 知られているように、近江商人の家には 「家訓 」が定められているが、そこには「人間の力を超えた仏や神への信仰の大切さ」「自分を忘れ、 他人や世間を大切に考える儒教精神の重要性」が説かれている。
後の学者が「三方よし 」と名付けた近江商人の商業哲学がこの家訓の中にちりばめられているが、川島俊蔵の「寺子教訓」はこれにつながる教えを説いている。
近江商人を輩出する寺子屋では 「読み書き計算」といった商人必須の学力に加え 、「近江商人の心」をも育んでいる。
学び続ける師匠川島俊蔵は、若い時、青蓮院門跡(御家流書道の家元 )で書道 を指導していた勝見主殿の門を叩き御家流を学んでいる。
川並に戻り寺子屋師匠となってからも、勝見との交流 を続け、自分の書いた字を京都に送 り、勝見に朱を入れてもらったりしている。
五個荘川並の寺子屋の幕末期の五代目師匠川島俊蔵は、宝永年間出版のものをモデルにしながらも独自の記述 をふんだんに挿入した手書きの 「寺子教訓 」を編纂 している。
その中に「仏神 」とか 「仁義礼智信の五常 」という他の「教訓 」には全く見られない宗教や儒教の言葉が出てくる。
よく 知られているように、近江商人の家には 「家訓 」が定められているが、そこには「人間の力を超えた仏や神への信仰の大切さ」「自分を忘れ、 他人や世間を大切に考える儒教精神の重要性」が説かれている。
後の学者が「三方よし 」と名付けた近江商人の商業哲学がこの家訓の中にちりばめられているが、川島俊蔵の「寺子教訓」はこれにつながる教えを説いている。
近江商人を輩出する寺子屋では 「読み書き計算」といった商人必須の学力に加え 、「近江商人の心」をも育んでいる。
学び続ける師匠川島俊蔵は、若い時、青蓮院門跡(御家流書道の家元 )で書道 を指導していた勝見主殿の門を叩き御家流を学んでいる。
川並に戻り寺子屋師匠となってからも、勝見との交流 を続け、自分の書いた字を京都に送 り、勝見に朱を入れてもらったりしている。
<東近江市教育研究所便り引用>