ご存知の方も多いとは思うが勘違いしている方もいらっしゃるようなので
このブログでは何度か書いてはいるけれど・・・再び言う「相撲は国技にあらず」と
どの法律を見ても相撲が国技であると定めたものは存在しない
大相撲協会がそう言っているだけなのだ
ここで言っておくが私は相撲取りを心から尊敬しているし相撲という格闘技も尊敬している
ただ格闘技の興行のために国技という錦の御旗を利用するやり方に文句があるのだ
明治になって相撲場を建てた時「国技館」と名付けたのが国技詐称の始まりだった
江戸時代の浮世絵を見れば判る通り行司は侍の裃を着ていた
相撲興行は有力大名の遊びの道具だった
古代ローマのコロッセオで戦闘士同士であったり戦闘士と猛獣の戦いに興じる貴族たちと同じく
異様に背が高かったり低かったり太っているような特異な体型の青年を戦わせる見せ物で
戦いのない時代の大名たちはおのれの名誉欲を満たすために強い相撲取りを庇護していたのだ
寺社の境内を使って寄付寄進という形を借りた勧進相撲という興行は大いに栄えた
しかしその時代はいきなり終わる
明治以降になって行司の姿が今のような烏帽子装束になったのは
国中の寺が神社に変わり坊主が慌てて神主になったのと同じで
廃仏毀釈の社会風潮に合わせて神道風を装い生き残りを計ったためだったが
裸体の禁止という法律が定められ髷とまわしの姿が問題になった時には
明治帝が相撲好きであるという噂を流してうやむやにした
そして・・・明治42年両国に国技館が建つ
ついに「相撲は国技である」という印象づけに成功したのだ
娯楽が少ない時代に大相撲は いち早くラジオ放送を使って人気を博し
戦前の日本人を楽しませたが敗戦とともに消滅した
昭和24年に蔵前国技館が仮設され再び相撲が始まった
昭和27年に蔵前国技館は完成 テレビ放送の都合上 土俵回りの四本柱が取り除かれた
子供の頃に白黒テレビで観た相撲中継は貧弱な機材のせいか薄暗くて
土俵下にいた新聞記者のカメラのマグネシウムフラッシュが光っていたのを覚えている
薄暗闇の中でぶつかり合う男たちの肉体が白く輝いていた景色はどこか妖しげで
遠い世界で行われている夢の世界の出来事のように見えた
今は明るい照明と高精細に写るカメラで観客の髪の毛の一本一本が見えるほどで
取り組み前の関取たちの肌が紅潮する様子まで見えて素晴らしいのだが
その代わりに隠し事は出来なくなったし隠し事が出来ない時代にもなっているということを
きっと子供の頃から相撲の世界しか知らない世間知らずの親方衆は気付いていないのだろう
見えてはいけないモノまで見えてしまうのは相撲の世界に限らなくなっているけれど・・・
何度も言うが私は相撲が好きだし相撲という格闘技を尊敬しているが
けっして「国技」だとは思っていないし「神事」だとも思っていない
もう特別扱いをやめて公益財団法人を辞して普通の株式会社としてやっていってはどうか?
日本人の子供が集まらないうえに加速する国際化を止めることがもう出来ないとするならば
このさい総当たり制のリーグ戦やトーナメント制にして本物のスポーツにする手もあると思う
たった15日で幕内優勝を決めることの不自然さは世界には絶対に通用しない
世界的スポーツとなった柔道の良いところだけを取り入れれば成功するだろうし
興行としてやっていこうと思うのならばプロレスの WWE が参考になるに違いない
もう戻れないのならより良い方へ向かうべきだし
それが出来ないというのなら滅んでしまえば良い
それが自然の摂理だ










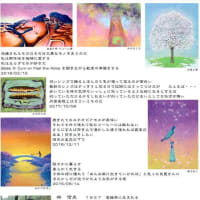
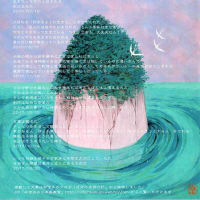
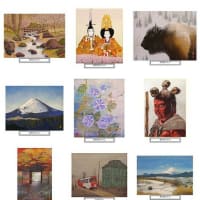












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます