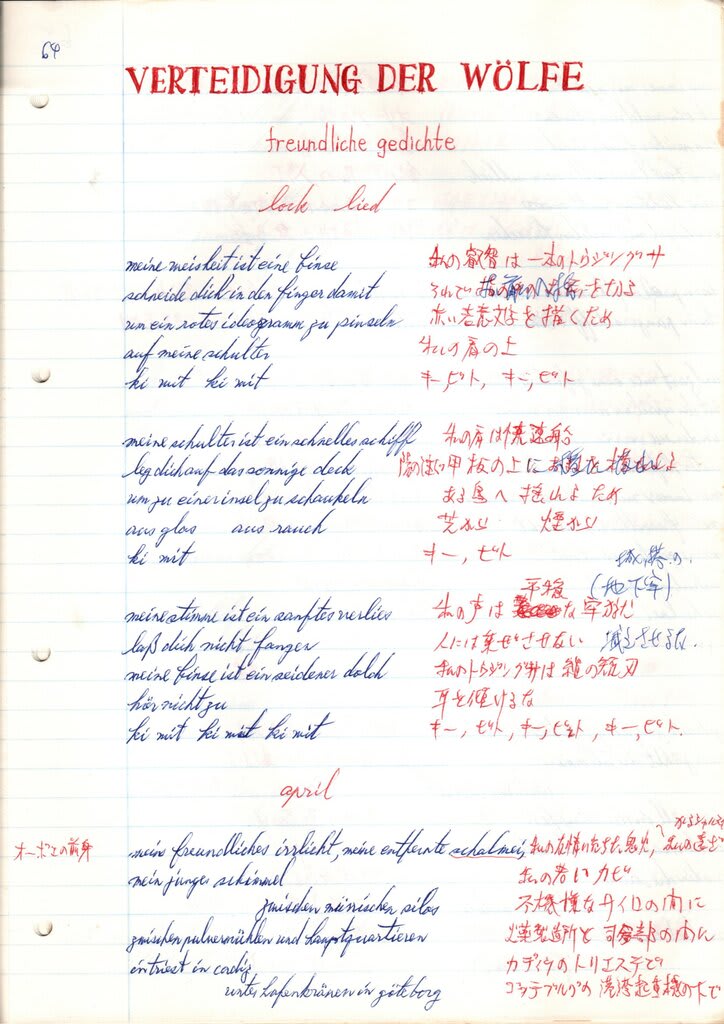Wahlsieg für die Union, ein großer Rechtsruck und eine neu erwachte Linke - so kommentieren internationale Medien die Entwicklungen zur Bundestagswahl.
キリスト教民主・社会同盟勝利(Union=同盟)、拡大一方の極右化と新たに目覚めた左翼党‐と、連邦総選挙に対する海外メディアがコメント
https://www.tagesspiegel.de/.../so-kommentiert-das...
P.S."風と光の北ドイツ通信/Wind und Licht Norddeutsch Info"(https://blog.goo.ne.jp/nichidokuinfoでもシェア
ドイツ総選挙で明らかになったのは社民党首相オラフ・ショルツの難民対策に対する無為無策とウクライナ軍事支援に対する有権者の懲罰投票だったということだろう。その結果、難民排除の極右AfD大躍進とウクライナ事情抜きで反戦の左翼党の復活につながったと言える。どちらの理由も短絡的だが、有権者の気持ちはそういうことだ。
深層ではハンブルク市長からUnionとのメアケル首相下での大連立で副首相を務めた経歴が全く生かされず、世界の危機的状況下でショルツには必要な指導力が欠けていることが露呈した事実がある。
私自身これほど言葉少なく、喫緊の課題について説明責任を果たそうとしない首相にそれが本人の戦略なのか能力不足なのか判断できなかったのだが、最後にこの方にはまったく政治的実行力がないのだと解り、少なからずショックだった。思いついたのは“ピーターの法則(『〈創造的〉無能のすすめ―(ローレンス・J・ピーター/レイモンド・ハル 田中融二訳)』ダイヤモンド社、 Peter-Prinzip “Die Hierarchie der Unfähigen” Rowohlt Verlag)“という言葉で、その意味は市長や副首相までは無難にこなしたが、国の頂点での責務では能力の限界に突き当たり、なす術がなく言葉を失ったのだ、と言うこと。彼には安部元首相やトランプのように口から出まかせのデタラメで人をケムにまくにはあまりにも上品で、その為の下司な度胸もなかった。オルタナイティヴ・ファクトのフェク時代、ポピュリズムに対応するにはそれ相応の言語が必要で、お上品にお高くとまっていたのでは対応できない。それをEstablishment(体制既得権者層)といい、今回の総選挙では罰せられるべくして罰せられた、という他ない。
Unionのフリードリヒ・メァツ党首が次期首相に就くが、喜んでばかりもいられない。投票率84%で得票率が28.5%と連立を必要とし、その相手は数からして社民党しかない。メアケル首相時代の連立再来だが、立場はメアケル元首相より弱く、国の内外の状況も比較にならない緊迫した危機的現実が待っている。そんな時に「得票総数で増えた」などと政治家の典型のような子供だましの言い訳などしている時ではなかろう。
第一に取り組むべきは難民問題の解決。AfDを躍進させた問題だが、ショルツは茫然自失するばかりで、最後までその実態を把握していなかったのではと思われる。我々のように電車やバスで移動すれば、その現実が解るのだが、公用車で移動するだけでは無理でしょう。車内の80,90%が外国系、私なども頻繁にアラブ系や東欧系の男が大声で罵っていたり(これが普通の口調だと聞いた)、女性も傍若無人の態度で携帯にむかって、異国の言葉で怒鳴っているのを目、或いは耳にし、「場を弁えろ」と言いたくなり、越権行為と自覚しながら、腹の痛みを抑えて、実際そう注意したことも一度ならずあった。しかし、一般の善良なドイツ市民にそんなことを言うのは絶対タブー、即外国人差別と非難される。
その解決は欧州共同体との連携でしかできないが、同じことはもっと大きな課題であるドイツ経済の立て直しにも言えよう。この危機下で“債務ブレーキ”という経済成長期の2009年に導入した政策に固執し、主要先進国で唯一ゼロ成長。責任は連立政権で財務金融大臣だったドイツ自民党首リントナーの借金ゼロ原理主義にあり、その為今回の総選挙で5%条項にかかり議席ゼロと罰せられたのだが、堪らないのは連立相手の社民党と緑の党でそのとばっちりで得票を大きく失った。
日本の国民総生産230%の借金を考えるまでもなく、国内の借金でインフラなどに投入する借金が、ギリシャ危機の当時のような外国の借金でその返済に首が回らなくなったのとは違う、という事情も考慮すべきだろう。誤解を避ける為に言っておくが、平時にアホ(ソ)タレ(ロ)の遊興費に国の借金を当て、平気というのとは違う世界経済の危機に借金でニューディール政策をとれ、と言っているのだ。
特にドイツ自動車界は中国市場一辺倒で習のE-自動車政策の落とし穴にはまり、ハイブリッドや火力発電で走る電気自動車よりは燃費の少ないガソリン車の方が環境車だという事実を無視したツケを今払わされ、危機的状況に陥った。家庭用電気さえ十分にないアジアやアフリカの国々を考えるまでもなく、少なくともここ十年はトヨタのように全方面政策をとるべきだろうが、ハイブリッド技術をトヨタにお願いするには沽券にかかわると、おそらくは電気自動車にこだわり続け、墓穴を大きく深くするばかりのような気がして、心配だ。ドイツ自動車界には謙虚な理性を期待したい。
当時米大統領ビル・クリントンが言った"It's the economy, stupid"は今こそ思い出されるべき原則だろう。ドイツもまずは”債務ブレーキ”を外し、ニューディール政策を早急に実施すべきだが、その端緒は現在次期国会が召集するまで政務を執る現政権と、これまで反対一辺倒だったUnionがここに来て自政権で資金不足は火を見るより明らかなので、今のうちに基本法から“債務ブレーキ”を外そうとの動きが出て来ている。
次期連立政権では極右AfDと左翼党が議席の30%近くを占め、少数派条項という基本法変更に歯止めをかける条項で、反対する恐れがあるので、次期首相のメァツUnion党首は掌を返すようにブレーキ解除を言い出した。勿論党内や連立相手の中にもそれは無理などというのがいるが、一応体裁を整えているだけ、ブレーキ解除は時間の問題だと思われる。
責任ある政治家なら時代が変わり、状況が変化すれば己の政治的態度を変えるべきだという、現実主義の勇気を持つべきだと思われるが、一昔前なら私もそんなことは言わなかったで笑!