≪6/4≫
「守備はピッチャーの成績も関わってくるので、助けられるようにと思っています」。
ロッテの友杉篤輝は今季、ここまで32試合でショートのポジションで出場しているが無失策。広い守備範囲で、何度も投手を救っている。
5月20日のオリックス戦、0-1の6回二死一、三塁で西野真弘の三遊間の打球を逆シングルでキャッチし、難しい体勢で二塁へ送球しアウトにすれば、5月28日のオリックス戦、1-0の5回先頭の西野が放ったピッチャーの股を抜けるあたりに、ひょこっと現れスライディングでキャッチしすぐに立ち上がり一塁へ送球しアウト。さらに同日のオリックス戦、1-1の8回二死満塁で西川龍馬のセンターへ抜けそうな鋭い当たりに、横っとびでキャッチし、素早く一塁へ送球しアウトにしたのは素晴らしかった。
好守備が多い要因に友杉は「送球が良くなっていると思うので、それと一緒に安定しているかなと思います」と分析する。
“送球が良くなっている”でいえば、昨年ZOZOマリンスタジアムで行われた秋季練習で、「根元さんと課題でゲッツーのスローイングの確実性、ランニングスローの確実性だったりというところをやっているので、うまく体の使い方を覚えながら正確性を上げていけたらと思います。守備はショートとして一番大事だと思うので、毎日しっかりやっていきたいと思います」と、全体練習後の特守でスローイングの練習に力を入れていた。
その守備練習で意識していたのが、“軸足”の使い方。「根元コーチから守備に関しては、軸足じゃないかと言われるので、今(昨年11月6日取材)は取り組んでやっています。スローイングは今年(2024年)から力を入れてやっているんですけど、今(昨年11月6日取材で)は結構バッティングも守備も右足の軸の足の使い方を言われるので、軸足の使い方を意識したらスローイングも良くなってきました」。
2月の石垣島春季キャンプでも守備に関して、「去年よりもいいスローイングになってきたと結構実感できているので、実戦が楽しみですし、実戦たいいボールが投げれるかっていうのを楽しみにしながらやっていますね。守備は特に軸足意識しながら継続してやれてるかな。それもだいぶ良くなってきたかなって思います」と好感触を掴んだ。
シーズンが開幕してから“軸足”を意識してやってきた成果が出せているか訊くと、「そうですね、それもあると思いますし、縦振りというか上から回転よくというのを意識してから送球がすごく良くなったかなと思います」と話した。
これまでも守備範囲は広かったが、今季はさらに守備範囲が広くなったように見える。友杉本人は「あんまり広くなったとは感じないですけど」としながらも、「送球が良くなったので、アウトにできている数が多くなっているのかなと思います」と話した。
ショートという過酷なポジションで、ここまで無失策。どんな守備を目指しているのだろうかーー。「ミスは誰にでもあるので、そこは気にしてはいないですけど、結果的にゼロというのはいいことだと思います。僕の売りはスピードなので、みんなが捕れない打球をアウトにしたいなという気持ちはずっともっています。そこはやっていきたいかなと思います」。
広い守備範囲で、投手を助けていく。
取材・文=岩下雄太
(ベースボールキング)
**************************************
≪6/5≫
「ここまでずっと不甲斐ないピッチングをしているので、そろそろちゃんと長いイニングを投げて、納得できるピッチングができるように。交流戦で掴んでいきたいと思います」。
ロッテの種市篤暉は、巻き返しを誓った。
種市は開幕前に行われた『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vsオランダ』の第2戦に先発し、「自分のやりたいことは全部できたかなと思います」と自己最速タイの155キロを計測するなど、2回・23球を投げ、0被安打、2奪三振、無失点と圧倒的なピッチングで日本の野球ファンを熱くさせた。
オランダ戦の投球を見れば、開幕から先発の軸として1年間投げた時に素晴らしい成績を残すのではないかと期待感を抱かせた。開幕してからの投球は、今季への期待値を考えれば物足りないものだった。
5月28日のオリックス戦で、らしさが戻ってきた。特に最大の武器であるフォークは素晴らしかった。「初回は全然だったんですけど、3回くらいから掴みましたね」と振り返る。その中でも、1-0の5回一死一、二塁で紅林弘太郎を1ボール1ストライクから空振りを奪った3球目の140キロフォーク、続く空振り三振を奪った141キロフォークはストライクゾーンからボールゾーンに良い落ち。本人も「ああ良かったですね!ちょっとシュートしながら、はい」と納得のいくフォークが投げられた。
フォークが良くなったところについて、「力感が良くなったのかなと思います。ずっと力んで投げていたので、その分いい指の抜け感というか、そういう感じですね」と明かした。
ストレートも力強かった。シーズン序盤は150キロを超えるストレートが1試合を通して10球届かなかったこともあったが、前回登板のオリックス戦では最速153キロ、150キロ超えは25球あった。
「それまでずっとブルペンもキャッチボールも良くなくて、投手コーチ、吉井監督とも技術の話をいろいろしました。今井に教えてもらったのが、感覚が良くなったので、試合の日のキャッチボール、ブルペンも、投球内容は良くなかったですけど、去年の感覚に近いものが出てきた。自信を持って次の登板に臨めるんじゃないかなと思います」。
種市はこれまでの取材で、ストレートの状態が落ちた時に見直す部分について、“左肩の開き”、“横の動きの時間”、“体を振りすぎないこと”を挙げてきたが、そこ以外の部分を見直してきたのだろうかーー。
「そうですね、結局投げる時は開かないといけないので、開くタイミングの問題というか、僕はちょっと左肩が我慢しすぎちゃったのかなと思います」。
スライダーも0-0の2回一死一、二塁で若月健矢をファウルにした初球の136キロ、2球目の135キロ真ん中低めの空振りが逆曲がりで良かった。
「逆曲がりしていて、(若月への)2球目は良かったですね。意図的に投げられたらいいですけど、という感じです」。
スライダーも良くなっているように見えるが、本人は「スライダーはもうちょっとかなと思います。フォークの方が逆にいい感覚になってきているという感じです」と教えてくれた。
前回登板のオリックス戦は5回を投げ、球数96球とやや多かったが、5被安打、5奪三振、3与四球、無失点にまとめた。前回登板、無失点に抑えられた理由のひとつに、0-0の2回無死一、二塁で中川圭太、若月を連続三振で2アウトにすれば、1-0の3回一死二、三塁で頓宮裕真を空振り三振、1-0の5回一死一、二塁で紅林、頓宮を連続三振と、得点圏に走者を置いた場面で三振を奪えたことが挙げられる。
種市本人も「ピンチになって三振を狙おうと思って入った試合だったので、そこをしっかり自分で取れたのが状態がちょっとずつ上がっている要因かなと思います」と話し、「犠牲フライも許せない状況もあったので、そこはやっぱり三振狙いながら配球できたのも良かったと思います」と続けた。
開幕から奪三振が少なく、追い込んでから狙って三振が取れなかったのも苦しんだ原因のひとつだったのだろうかーー。
「そうですね、そもそも三振数が僕のバロメーターでもあるので、そこはやっぱり上げていけたら支配的なピッチングができるんじゃないかなと思います」。
状態は上がってきている。シーズンをどう始めるかではなく、どう終わらせるかが重要になってくるーー。「去年、一昨年と終わり方が悪かったので、徐々に上げていけるように。チーム状況もあまり良くないので、自分のピッチングで流れを変えられればなと思います」。多くの野球ファンが注目する巨人戦で、圧倒的支配的な投球で、これが種市篤暉という姿を見せて欲しい。
取材・文=岩下雄太
(ベースボールキング)
**************************************
≪6/6≫
「呼ばれたからにはチームに貢献できるようにというのは思います。また違った形ですけど、貢献できたらなと思います」。
ロッテ・唐川侑己は予告先発となっていた5月6日の楽天戦が雨天中止のため、登板が叶わず、その後もファームで登板を続けていたが、6月4日に今季初昇格を果たした。
唐川は開幕から「実戦入ってきた中でそこの感覚だけは実戦の中でしかできないと思っているので、積極的に投げるようにしています」と左打者のインコースにカットボール、ストレートを多めに投げ、4月12日の西武二軍戦、0-0の初回先頭の蛭間拓哉に投じた初球143キロのカットボールでバットをへし折る投直に仕留めれば、5月14日のくふうハヤテ戦、0-0の初回二死走者なしで仲村来唯也を1ボール2ストライクから投じた5球目のインコース146キロ見逃し三振に仕留めたカットボールが良かった。
「真っ直ぐ、カット、腕がしっかり振れていれば、いい球を投げられているので、そこを目標にという感じですね」。
左打者のインコースだけでなく、6月1日の日本ハム二軍戦では、1-4の6回二死走者なしで平田大樹を2ボール2ストライクから外角145キロのストレートで見逃し三振に仕留めるなど、アウトコースでも打ち取った。
左打者の外角にストレートをどんどん投げ込んでいきたい考えがあるのか訊くと、「そうですね、真っ直ぐもしっかり投げていく必要があるなと今は感じているので、投げられる時は投げたいなと思います」とのことだ。
◆ 色々な捕手とバッテリーを組む
5月23日の楽天二軍戦、21個のアウトのうち9個がフライアウト、開幕してからの登板を見るとカットボールとストレートで空振り、ファウル、フライアウトが取れている時は良い時に見える。
「そうですね、バッターのアプローチにもよりますけど、どちらかというとそういうイメージです」。
また、ファームでは植田将太、松川虎生、田村龍弘といろんな捕手とバッテリーを組んだ。植田がマスクを被った4月12日の西武戦は序盤スライダーが少なめで、田村龍弘が先発マスクだった5月23の楽天二軍戦は立ち上がりからカーブが多かった。それは捕手の配球によるところが大きいのか、それとも打者との兼ね合いでそういった配球になっていたのだろうかーー。
「キャッチャーとミーティングしたり、投手コーチと話をしたりして、どういうふうな形で入っていこうかという話の中で変わっていると思いますね」。
緩急というところでカーブは「カウントをとったり、優位に進めるためにカーブが必要になってくると思うので、その辺は大事にはしていますね」と話した。
◆ スライダー
昨季は勉強中のボールと話し、4月4日の取材で「目先を変える意味でもスライダーが増えたかなという感じ」と話していたスライダーは、今季投球の割合が増えた。
その中で、4月12日の西武二軍戦、0-0の4回二死走者なしで栗山巧を1ボール2ストライクから空振り三振に仕留めた7球目のインコース低めの127キロスライダー、5月23日の楽天二軍戦、3-1の6回二死一塁で小森航大郎を2ストライクから空振り三振に打ち取った外角低めのスライダーは素晴らしかった。
スライダーに関して「徐々に良くなっているので、有効な球で使えるかなという意識ではいますね」と明かし、現在のスライダーの位置付けについて「幅広く使っていけたらなと思っています」と話した。
ファームでは9試合(7試合に先発)・41回1/3を投げ、3勝3敗、防御率3.05。自身の状態について「その時、その時で自分の状態が良い球というのがばらつきがあるんですけど、全体的にしっかり投げられているので、その中でどの球を選択して、どの球を投げるかは特に一軍に来たら必要になってくるので、そこを気をつけながら投げたいなと思います」と意気込んだ。
ファームでは先発調整してきた中で、一軍ではリリーフでの登板が予想されるが、若手にはない経験、味を一軍のマウンドで発揮して欲しいところだ。
取材・文=岩下雄太
(ベースボールキング)
**************************************
≪6/6≫
清水直行が分析するロッテの現状 前編
今季のロッテは49試合を消化した時点で18勝31敗、5位の楽天と5ゲーム差のリーグ最下位と低迷している。苦しいチーム状態が続いているが、OBはどう見ているのか。長らくロッテのエースとして活躍し、2018年、19年にはロッテの投手コーチも務めた清水直行氏に見解を聞いた。
【「VISION 2025」が目指していたものと現実】
――ロッテは苦しいチーム状態が続いていますが、ここまでの戦いぶりをどう見ていますか?
清水直行(以下:清水) 借金が2ケタありますし、チーム状態がよくないのは間違いありません。細かく分析をすればさまざまな課題が出てくると思いますが、大きな部分で言うと、昨年に機能していたネフタリ・ソトとグレゴリー・ポランコの不振が長く、点が取れない状況が続いていること。点が取れないのでピッチャーも我慢しきれず、流れをつかめないままズルズルきている印象です。
昨年のロッテは5つの貯金をしてシーズンを終えましたが(71勝66敗)、西武戦では17個もの貯金をしました。ただ、今年はいまのところ西武に負け越していますよね(4勝6敗/6月4日時点、以下同)。その部分だけを切り取ると、西武に負け越したらトータルで借金してしまうのも当然のこと。つまり、今年のロッテは数字だけで考えれば、実は昨年とあまり変わっていないという見方もできます。
昨年のロッテは5つの貯金をしてシーズンを終えましたが(71勝66敗)、西武戦では17個もの貯金をしました。ただ、今年はいまのところ西武に負け越していますよね(4勝6敗/6月4日時点、以下同)。その部分だけを切り取ると、西武に負け越したらトータルで借金してしまうのも当然のこと。つまり、今年のロッテは数字だけで考えれば、実は昨年とあまり変わっていないという見方もできます。
――昨年は16勝8敗と大きく勝ち越したオリックスに対しても、今年は2勝7敗と負け越していますね。ロッテは主力にケガ人が少ないにもかかわらず、ここまで状況が暗転しているのはなぜでしょうか。
清水 これも大きな問題で、シーズン終了後にしっかりと精査しなければいけません。ただ、これらのことは、単に選手の状態や実力といった問題というよりも、「もっと根深い部分の問題なのでは?」と感じます。
ロッテは2025年までに常勝軍団となることを掲げ、2021年に「VISION 2025」を発表しましたが、その頃からの球団の編成も含め、大きな視点で議論するようなことがあってもいいのではないか、と思います。球団としてビジョンを掲げたのであれば、それに対して何らかの成果が求められるのは必然だと思いますし、それが実現できないとなれば、何かしらのアクションがあっても不思議ではありません。
――大きな改革が必要になる可能性もある?
清水 日本ハムの新庄剛志監督が今年4年目。チームを根本から変えてきて着実に力をつけていますが、やはり過去の例を見てもチームを変えていくためには3年~5年くらいはかかります。2021年に掲げた「VISION 2025」を自分なりに解釈すると、「近年のドラフトで指名した選手たちを、日本代表クラスに育てていきながら優勝をつかむ」というビジョンだと思うんです。
今のロッテに、日本代表に選ばれるような選手がどれくらい、いるのか? チームを引っ張っていく選手がいるのか? そう考えると、スッと名前が出てきませんよね。取っ替え引っ替えの選手起用では、選手に「自分は中心選手なんだ」といった自覚が芽生えにくいと思いますし、チームの柱になるような選手はなかなか育っていかないんじゃないのかなと。
【改革が進まなかった理由】
――選手を育てるためには、ある程度我慢して使っていくべき?
清水 あくまで個人的な意見ですが、ある程度は固定したほうがいいと思います。すべてのポジションを固定したほうがいい、1番から9番まで固定したほうがいい、クリーンナップを固定するべきだとか、そういうことではなく、将来中心になっていくような選手、現在結果が出ている選手は辛抱強く使い続けたほうがいいんじゃないかと。
相手ピッチャーとの相性などもあると思いますが、バッティングもピッチングも"生き物"です。当然データ班が提示するデータも大事だと思いますが、その日の調子を見て臨機応変に対応していくことへの意識が少し薄くなっているような気がするんです。
例えば、山本由伸(ロサンゼルス・ドジャース)が、(5月21日のアリゾナ・)ダイヤモンドバックス戦で110球(投球回7回)を投げましたよね。状態を近くで見ている監督やコーチが、山本の投球のメカニックや表情、息づかいなども踏まえ、100球を超えても投げさせる判断をしたと思いますが、それが采配であり仕事だと思うんです。
――先ほど「VISION 2025」が実現できないのであれば、何かしらのアクションがあっても不思議ではない、という話がありました。現在のチーム状態は、常勝軍団を目指すといったビジョンとの乖離を感じざるをえません。
清水 企業は想定していたよりも業績が悪ければ下方修正しますよね。それと同じように「VISION 2025」が難しくなったのであれば、誰かが責任をとりつつ、例えば「VISION 2030」といったようにビジョンを変えてもいいと思うんです。やっぱりフロントと現場の監督・コーチ、選手が一体となって、遮二無二やならなければチームを強くしていくことは難しい。
それと、ここ数年ロッテはシーズン終盤に粘りを見せて2位になったり、3位に滑り込んだりしぶとさを見せています。そのしぶとさゆえの弊害と言ったら変ですが、そのことがチームを改革しにくくしているのかもしれません。
「Aクラスになれるかも」「優勝できるかも」というシーズンが続いていて、(54勝87敗2分けでリーグ最下位となった)2017年以来、ドカンとやられたシーズンがありません。そうなると、思いきったことがやりにくくなったりするんです。
――選手の世代交代なども、それに当たりますか?
清水 そうですね。例えばベテランや、経験値が高い選手を多く使えば、「3位にはなれる」「日本で実績のある外国人選手を獲れれば、優勝争いができるかも」となるかもしれませんが......それも、もちろん悪いことでないのですが、そうなると世代交代も遅れかねません。ベテランは起用を続ければ、それなりに結果を出します。でも、それを繰り返してしまったために、若手がなかなか育っていないんです。
それは"逃げ"の考えであって、どういう状況であろうと世代交代を図っていくこと、チームを強くしていくことが、フロントや監督・コーチの仕事なはずです。常に優勝争いできるチームを目指すということは、そういうことがありながらも、しっかりと"血"を入れ替えていかなければ実現できないと思うんです。
――極端に言うと、落ちるところまで落ちたほうが改革に着手しやすい?
清水 そうですね。ただ、監督は就任から1、2年が勝負になりますよね。選手を育てることも大事ですが、やはり勝つことが最優先。目先の勝ちだったり、「自分が監督になったからには、こうする」みたいなものはどの監督にでもあるでしょうし、負けを受け入れるのは難しいでしょう。
しかし、そこはフロントと現場が「この政権で〇年間」といったようなロードマップを共有して足並みをそろえて進めていかないと。そうしなければ、根っこから変えていくことは難しいような気がします。
**************************************
清水直行が分析するロッテの現状 後編
現在、パ・リーグ最下位に低迷しているロッテ。OBの清水直行氏に聞くチームの現状の後編では、バッテリーが抱える課題、苦しいチーム状況のなかで垣間見えるポジティブな要素について聞いた。
【盗塁されることが多い理由】
――ロッテ抱える課題のひとつとして、出塁を許したあとに盗塁を決められてしまうケースが多いことが挙げられると思います。
清水直行(以下:清水) 大前提として、盗塁を阻止するのはバッテリーの共同作業です。ピッチャーは投球フォームを盗まれないようにしなければいけませんし、クイックも必要です。キャッチャーは捕ってから投げるまでのスピード、送球の速さや正確性などが求められます。
ただ、ここまで走られてしまっているということは(被盗塁46)どういうことなんだろうかと......。ここ数年、ロッテのキャッチャーの盗塁阻止率が低迷していることを考えると、「もしかしたらトレーニングマニュアルが確立されていないのでは?」という疑問を抱かざるをえません。
――先ほど(前編で)、選手を育てるためには辛抱が必要という話がありましたが、キャッチャーも同様でしょうか。
清水 そうですね。キャッチャーはそう簡単には育たないんですが、そこも辛抱でしょう。誰を中心と考えて育てていくのか。それと、ここまで課題が明白であれば、ロッテのキャッチャー陣はバッティング練習よりも、「捕ってからいかに素早く投げるか」といったディフェンス面の練習に時間を割いたほうがいいんじゃないかと思います。
例えば、サト(ロッテOB・里崎智也氏の愛称)のようなスーパーキャッチャーを呼んで、短期キャンプを張るのもいいかもしれません。彼なら、キャッチャーとしての極意を伝授してくれると思うので(笑)。
――"打てるキャッチャー"もいいけれど、やはり守りが肝になる、ということですね。
清水 古田敦也さんや谷繁元信さん、城島健司、サト、阿部慎之助にしろ、歴代のスーパーキャッチャーと言われている人たちはバッティングもすごかったのですが、ウエイトを置いていたのは、やはり"守り"なんです。「キャッチャーとしての仕事がおろそかになったらダメだ」と考えていて、「ダメだったら打てばいいんでしょ」とは決して思っていなかった。少なくとも僕からは、そのように見えていました。打席に入ったら、スーパーバッターにもなるんですけどね。
すごいキャッチャーたちは、ピッチャーをしっかりリードして、"扇の要"としてチームを牽引していました。キャッチャーだけがほかの野手とは反対の方向を向いているわけで、全体を俯瞰する司令塔でなければいけません。まずは、その仕事が「100」なんです。打つことも大切ですが、まずはそれぞれがキャッチャーとしての成長を見せてもらいたいです。
――佐藤都志也選手は昨年、打撃が開花したように見えましたが、今季は低迷(打率は昨季.278、今季はここまで.092)。そこの改善も必要ですが、それでもまずは守備の向上が優先となりますか?
清水 そうですね。佐藤は、キャッチングやブロッキング、スローイングにしても、改善しなければいけない点が多々あるように感じます。捕ったり、盗塁を刺したりすることに自信が持てず、「打つほうで挽回しよう」と考えてしまう部分が、ひょっとしたらあるのかもしれません。
極端な言い方をすると、「打てなくてもいいから、守りをうまくなろう」という意識を持ってほしいのですが、やはり打つほうが好きで、「打つほうで結果を出したい」となってしまうのかもしれません。寺地隆成にしても同じことが言えます。ただ、寺地に関してはまだ2年目の19歳ですし、今は守るのも打つのも必死に経験を積んでいる段階だと思いますが。
【苦しい状況で経験を積む若手たちに期待】
―― 一方、ロッテが足で相手バッテリーにプレッシャーをかけていく場面は少ないです。
清水 昨秋のトレーニングや今春のキャンプで、チームとして走塁練習に注力するようなシーンはあまり見られませんでした。対照的に、日本ハムはベースランニングなども徹底して練習していた印象です。走塁もそうなのですが、ここ数年のロッテは「チームとして、これをやっていくぞ」というものが、ちょっと"薄い"ような感じがします。
例えばサッカーであれば、監督によって4-2-3-1や3-4-2-1などフォーメーションがありますよね。攻撃型なのか守備型なのか、バランスを重視する型なのか、自分のやりたいサッカーのカラーを打ち出すじゃないですか。新庄剛志監督が日本ハムの監督に就任した時も、「選手全員を一軍の舞台に立たせる」など、いくつかの方向性を明言していました。賛否両論はありましたが、選手もファンもわかりやすいですよね。
――現在のチーム状態において、ポジティブな要素を挙げるとすれば?
清水 打つほうでは寺地、山本大斗、池田来翔、投げるほうでは田中晴也、中森俊介、木村優人ら、「今のうちに、レギュラーを獲ってしまえ」と思えるような若い選手たちが一軍の試合を多く経験できているのは、すごくポジティブなことです。中継ぎだった横山陸人に先発を経験させたりもしていましたが、選手の活躍する領域を広げるうえでいい取り組みだと思います。
――ドラフト1位ルーキーの西川史礁選手はシーズンに入って苦しんでいます。
清水 現状見る限り、しばらくの間は苦労するんじゃないかなと。西川は仕掛けが早いバッター。相手もそれをわかっているので、ストライクとボールの見極めが難しい、くさいコースから入る配球をしています。西川もそれを見極めようとしていると思いますけど、一軍レベルのピッチャーは絶妙なコースにポンとくる。そこに飛びつくようなバッティングになってしまっているので、自分の形でバットを振れていません。
現在(6月4日時点)の打率が.145で本塁打が0。フォアボールは1個で出塁率は.165。この数字を受け入れて、課題を一つひとつ克服していかなければいけません。ただ、彼はどんなボールに対しても強く振れますし、自分のバッティングスタイルを持っていると思うんです。それを貫けるかどうかもポイントになるはずです。
コーチ陣も「1年目は自由にやらせてみよう」と考えていると思いますし、自分の課題にどう向き合っていくか。本人が「何かを変えなければいけない」と思い始めているのであれば、それはそれで前進じゃないですか。1、2年目がダメでも3、4年目くらいから覚醒する選手は多い。今は苦しいと思いますが、何とか乗り越えてほしいですね。
【OBとしても「勝っているロッテが見たい」】
――若い選手たちが経験を積み、何が足りないかを明確に認識できることはいいことですね。
清水 そうですね。それと、若い選手たちが結果を出した試合はやはり勝ちたいです。彼らが何かのきっかけをつかんでいる試合は、どんな手を使ってでも勝たないとダメです。活躍した試合は勝って笑いたいし、喜びたいじゃないですか。でもチームが負けてしまうと、それも控えなければいけない雰囲気になってしまう。
勝てればみんながハッピーですし、そのなかで活躍できた若手は自信もつきます。年俸も上がりますし、いいことだらけ。ボビー(・バレンタイン)が監督の時は、勝っている試合の終盤に選手をよく交代していたのですが、それは、ひとりでも多くの選手をグラウンドに出して、勝ち試合の喜びを共有するためでした。普通は大差がついた負け試合の展開の時に若手を途中出場させたりしますが、逆だったんです。
勝てればみんながハッピーですし、そのなかで活躍できた若手は自信もつきます。年俸も上がりますし、いいことだらけ。ボビー(・バレンタイン)が監督の時は、勝っている試合の終盤に選手をよく交代していたのですが、それは、ひとりでも多くの選手をグラウンドに出して、勝ち試合の喜びを共有するためでした。普通は大差がついた負け試合の展開の時に若手を途中出場させたりしますが、逆だったんです。
――ロッテはチーム体制の強化を目的に、サブロー二軍監督兼統括打撃コーチが一軍ヘッドコーチに就任するなど、配置転換に踏み切りました。
清水 借金は多いですが、まだ6月に入ったばかり。ここで舵を切るのも、チームの状況を変えるためのひとつの手ですよね。それと、僕が言いたいのは、決してフロントや監督・コーチに対しての批判というわけではなく、現状のチームに対しての"疑問"を抱いているということ。自分はOBなので、やはり勝っているロッテが見たいですし、上昇していってもらいたいという思いが強いんです。
そのためには、ストロングポイントを生かしつつ、ウイークポイントにもしっかりと向き合う姿勢が大事ですし、フロントと監督・コーチ、選手が三位一体で取り組んでいってほしいと願っています。
【プロフィール】
清水直行(しみず・なおゆき)
1975年11月24日に京都府京都市に生まれ、兵庫県西宮市で育つ。社会人・東芝(旧・東芝府中)から、1999年のドラフトで逆指名によりロッテに入団。長く先発ローテーションの中核として活躍した。日本代表としては2004年のアテネ五輪で銅メダルを獲得し、2006年の第1回WBC(ワールド・ベースボールクラシック)の優勝に貢献。2009年のシーズン後にトレードでDeNAに移籍し、2014年に現役を引退。通算成績は294試合登板105勝100敗。引退後はニュージーランドで野球連盟のGM補佐、ジュニア代表チームの監督を務めたほか、2019年には沖縄初のプロ球団「琉球ブルーオーシャンズ」の初代監督に就任した。
著者プロフィール
- 浜田哲男 (はまだ・てつお)千葉県出身。専修大学を卒業後、広告業界でのマーケティングプランナー・ライター業を経て独立。『ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)』の取材をはじめ、複数のスポーツ・エンタメ系メディアで企画・編集・執筆に携わる。『Sportiva(スポルティーバ)』で「野球人生を変えた名将の言動」を連載中。『カレーの世界史』(SBビジュアル新書)など幅広いジャンルでの編集協力も多数。
(以上 Sportiva)
















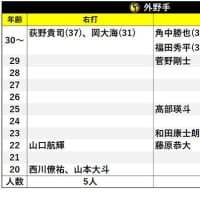
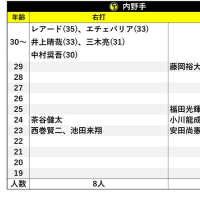
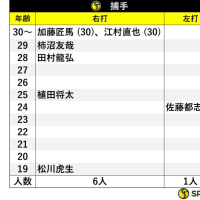
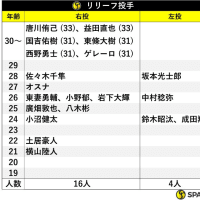





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます