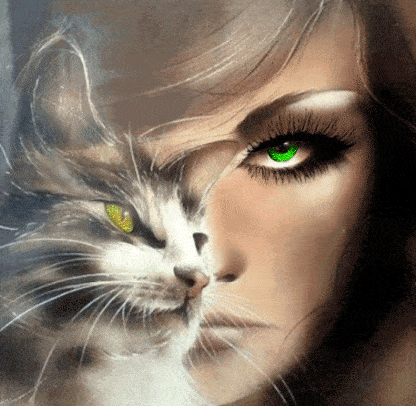~ 女性の身にて 盛長を騙し討たんとは 何者なるぞ ~
『大森彦七道に怪異に逢ふ図』
(おおもりひこしち みちに かいい にあう ず)

大蘇芳年筆
大森彦七(おおもりひこしち)は南北朝時代の北朝方の武士。名は盛長。
矢取川の鬼女
健武三年(1336)湊川の戦いに足利尊氏方に味方して
敵将の楠木正成を自刃に追いつめたその功により
足利尊氏から伊予に所領を与えられた。
その領地内の金蓮寺で猿楽を催すこととなり
大森彦七も舞を舞うため「金蓮寺」に赴くこととなった。
道中、館を出て魔住ケ窪をぬけて矢取川にさしかかり
もう日も暮れかかってきた川を渡ろうとしていると
なにやら河畔に佇む美しい姫がいたので声をかけると
「川向こうに行きたいけれど、流れが速く深い川に難渋している」と答える
そこで、背中を貸して矢取川を渡り始めたところ
背中の姫が急に重たくなり、川面に写る様子を見ると
口は耳まで裂け、振り乱した髪からは角が生え恐ろしい鬼女となり
大森彦七の頭髪をわしづかみにし天空へ舞い上がろうとしていた。
大森彦七は鬼女の手をシカと離さず岸へ取って返し
「おのれ 妖怪」と押し返すが、「正成参上」と鬼女は手向かってきた。
格闘の末撃退するが、それ以後も七度にわたって襲われ
大森彦七は正気を失いかけたが、大般若経の功徳で救われたという。