
少し前のことですが、毎年の如く正倉院展に家族で出かけました。今年は展示品が少し少ないのでは?と思いました。その前に、京都非公開文化財特別公開の時期だったので、奈良の北の木津川の海住山寺と現光寺に行きました。海住山寺には小振りの五重塔と十一面観音立像。そして現光寺にも十一面観音坐像。これは鎌倉の慶派の流れを汲むもので実に立派でした。この寺には、老朽化した本堂があるのみで、この仏さんは新たに建てられた収蔵庫にありました。こんなところに、こんな立派な仏さんがあるとは。あたりの歴史の奥深さを感じました。
ということで、今回はブラームス。弦楽五重奏曲第1番へ長調作品88であります。ブラームスの弦楽器による室内楽は、弦楽四重奏曲、五重奏曲、六重奏曲とあります。この中で弦楽五重奏曲は2曲あり、1882年と1890年ごろのともに晩年に近くなって書かれたものです。第1番は、ブラームス49才の1882年、ピアノ協奏曲第2番と交響曲第3番の間、イシュルで作曲されました。
ブラームスのこのジャンルの曲は、弦楽四重奏にヴィオラが加わるもので、シューベルトのチェロが加わるものではなく、モーツァルト型のものであります。ドイツ・ロマン派の室内楽では、やはりブラームスは他の追随を許さない存在ですね。
それで、この弦楽五重奏曲のCDは、それほどあるわけではありません。ブタペストSQやアマデウスSQ、ジュリアードSQによるもの、それにBPOメンバーによるものなどがありました。20代のころ、ブラペストSQとトランプラーの演奏をLPでよく聴いたものでした。残念ながら、この演奏のCDは持っていません。なかなかこの曲のCDでは見つけにくいのが現状かもしれません。そんなこんなで過日、仕事で外回りをしていたときに、太子町のBOOKOFFにちょこと寄ったときに、このCDを見つけました。ウィーン・フィルハーモニア弦楽五重奏団よる演奏です。ペーター・ヴェヒター、ハラルド・クルムベック(Vn)、ペーター・サカエシェック、エルマー・ランデラー(Va)、ローベルト・ノージュ(Vc)により編成されています。1996年にヴェヒターを中心にVPOの若手奏者を集めて結成されました。そしてこのこの演奏は、1997年5月12~14日にウィーンで録音されましたものです。
そして、この曲は特に第1楽章は、正に春を迎える心からの抒情的な歓びを伝えるようで、一度聴けば忘れられない曲で、ここにこの曲の強烈な印象がある。この演奏は、それほどこの歓びを歌い上げるというより、どこか控え目でありながらも、5つの楽器がそれぞれの美しい音色で存分に歌い上げています。そして、それぞれの表情は実に柔和で、優しいのでした。このあたりは、さすがにVPOでありますね。1st Vnのヴェヒターは、それほど傑出した存在ではなく、四人のバランスもしっかりしているのも、印象に残ります。そして、表情の彫りが深く、それぞれの深いところまで演奏であることも、聴いていてたいそう心に響くのでありました。
第1楽章は、明るさが存分に表現されていて、ブラームスの春でしょうか。そうは言っても、ブラームスらしい重厚な響きというより、清新さに5人がしっかり呼応しています。安心して耳を傾けられるのです。第2楽章、援徐楽章とスケルツオが接続したような楽章。援徐楽章は、心に染み込んでくる優しい様がいいです。弦楽合奏の援徐楽章は内容的に深さを感じさせてくれるので、私は好きです。そして、弦はたいそう美しい、と実感させてくれます。ゆったりとし他に媚びることのない響きが心に充満して、心地よいのでありました。そして終楽章。フーガとソナタ形式を融合したもので、ベートーヴェンのラズモフスキー3番の終楽章をモデルにしたと言われています。明快な響きで、透明感に満ちたところが爽快でもある。多少控え目と感じるところもあるが、各楽器は存分に歌い上げています。
そう言えば、20才代のころ、室内楽をよく聴いていた時期がありました。CDは出はじめで高くて買えなかったので、中古LPを漁っていたんですね。もう随分昔のことになりました。
(CANERATA 30CM-534 1998年)、
ということで、今回はブラームス。弦楽五重奏曲第1番へ長調作品88であります。ブラームスの弦楽器による室内楽は、弦楽四重奏曲、五重奏曲、六重奏曲とあります。この中で弦楽五重奏曲は2曲あり、1882年と1890年ごろのともに晩年に近くなって書かれたものです。第1番は、ブラームス49才の1882年、ピアノ協奏曲第2番と交響曲第3番の間、イシュルで作曲されました。
ブラームスのこのジャンルの曲は、弦楽四重奏にヴィオラが加わるもので、シューベルトのチェロが加わるものではなく、モーツァルト型のものであります。ドイツ・ロマン派の室内楽では、やはりブラームスは他の追随を許さない存在ですね。
それで、この弦楽五重奏曲のCDは、それほどあるわけではありません。ブタペストSQやアマデウスSQ、ジュリアードSQによるもの、それにBPOメンバーによるものなどがありました。20代のころ、ブラペストSQとトランプラーの演奏をLPでよく聴いたものでした。残念ながら、この演奏のCDは持っていません。なかなかこの曲のCDでは見つけにくいのが現状かもしれません。そんなこんなで過日、仕事で外回りをしていたときに、太子町のBOOKOFFにちょこと寄ったときに、このCDを見つけました。ウィーン・フィルハーモニア弦楽五重奏団よる演奏です。ペーター・ヴェヒター、ハラルド・クルムベック(Vn)、ペーター・サカエシェック、エルマー・ランデラー(Va)、ローベルト・ノージュ(Vc)により編成されています。1996年にヴェヒターを中心にVPOの若手奏者を集めて結成されました。そしてこのこの演奏は、1997年5月12~14日にウィーンで録音されましたものです。
そして、この曲は特に第1楽章は、正に春を迎える心からの抒情的な歓びを伝えるようで、一度聴けば忘れられない曲で、ここにこの曲の強烈な印象がある。この演奏は、それほどこの歓びを歌い上げるというより、どこか控え目でありながらも、5つの楽器がそれぞれの美しい音色で存分に歌い上げています。そして、それぞれの表情は実に柔和で、優しいのでした。このあたりは、さすがにVPOでありますね。1st Vnのヴェヒターは、それほど傑出した存在ではなく、四人のバランスもしっかりしているのも、印象に残ります。そして、表情の彫りが深く、それぞれの深いところまで演奏であることも、聴いていてたいそう心に響くのでありました。
第1楽章は、明るさが存分に表現されていて、ブラームスの春でしょうか。そうは言っても、ブラームスらしい重厚な響きというより、清新さに5人がしっかり呼応しています。安心して耳を傾けられるのです。第2楽章、援徐楽章とスケルツオが接続したような楽章。援徐楽章は、心に染み込んでくる優しい様がいいです。弦楽合奏の援徐楽章は内容的に深さを感じさせてくれるので、私は好きです。そして、弦はたいそう美しい、と実感させてくれます。ゆったりとし他に媚びることのない響きが心に充満して、心地よいのでありました。そして終楽章。フーガとソナタ形式を融合したもので、ベートーヴェンのラズモフスキー3番の終楽章をモデルにしたと言われています。明快な響きで、透明感に満ちたところが爽快でもある。多少控え目と感じるところもあるが、各楽器は存分に歌い上げています。
そう言えば、20才代のころ、室内楽をよく聴いていた時期がありました。CDは出はじめで高くて買えなかったので、中古LPを漁っていたんですね。もう随分昔のことになりました。
(CANERATA 30CM-534 1998年)、













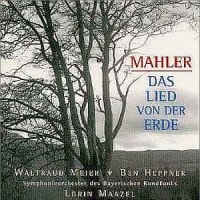
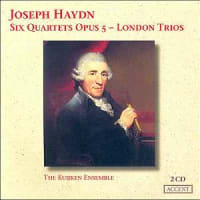
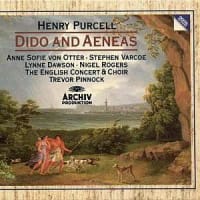









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます