
台風12号は日本海へ抜けた様だ。しかしこののろのろ台風、執拗に南からの湿気を吸い込む様に呼び寄せ続け、それが紀伊山地の峰々にぶつかり長時間の豪雨をもたらした。私が何回か訪れた大塔や黒滝といった名前が出てくるテレビ画面に映し出される濁流の川や山崩れの被害の様子は心痛まずに見られない。
ここ京北では、一昨日の夜から時々吹く強い風もありその影響を感じていた。昨日は昼間は雨は大したことはなかったし、風もそう強いものではなかったのだが、ただ夜になると雨は強くなってきた。天気予報の画面をみるとこれは明け方までしっかりと降るだろうと思いつつ、深夜の雨音を聞きながら寝入った。
朝が明けると温度計は23℃を示していた。台風一過の秋晴れではなく、空はどんよりと曇り、遠くの山は霞んでその姿を隠している。雨は小降りだが降り続いている。
私は今日は非番なので地域の、お歩きさん、の役目でご近所さんに市民新聞などを配達した。そのついでに大堰川の水や如何に、と長谷を越えて山国神社方面へと向かう。神社裏の大堰川に目をやると、お、かなりの水量で濁流の風景を見せている。上の写真が山国神社すぐ北にある潜没橋をまさに埋没させて流れる風景だ。流木が一本引っかかっているのも生々しい。この橋には苦い思い出がある。橋の完成を祝っての開通式のすぐ後に集中豪雨に襲われ、すぐ近くにあった同級生の家が、堤防が決壊して流されたのだ。濁流に流された家の屋根に上って難を逃れていた友人のお父さんを救い出す真夜中の救出劇や、一夜明けると新しい川が出来た様に一変した風景を思い出してしまう。その後堤防は改修されて高くなり、洪水の被害は無くなった。
田圃に目をやると、風は強くなかったとは言いながらしっかりと実り刈り取り間近の稲を倒していた。

そのまま小塩まで車を走らせたが、山国盆地は川が増水している姿以外はいつもと変わらない風景だった。帰る途中にブックマークに載せているブログを書いておられるsuikyoさんとばったり出合う。屋久島から帰られたばかりなので、屋久島の写真をもっと載せてよ、とおねだりしておいた。あちこち跳び回って活躍されていることよ。
次の写真は、山国の殿橋から上流を望んだ風景。昔だったらこの水量でも堤防ぎりぎりまで達していたのではないかなあ、なんて思ったり。

周山に引き返しウッディ京北に立ち寄ると、栗尾峠、深見峠や黒田への国道が通行止めになっている掲示があった。災害があっての措置ではなく、事前措置の様だ。
朝出掛けたのはお歩きさんと書いたが、その足で立ち寄ったのは八坂神社。実は8月下旬にある方と京北・美山の神社仏閣や里の史跡や文化財巡りをした時、我が膝元の八坂神社にある史跡を、そんなもの無いですよと答えていたのに、実際入ったらちゃんとあった、という恥ずかしい経験をしたので、それをもう一度撮影に行ったのだ。社殿を出てふと見上げると、神社の木が秋色になり始めていたのに気がついた。写真ではうまく捉えきれていないが、かすかに色づき始めている様だ。秋色の始まりか、季節の移り変わりを感じた。
秋色?

8月は職場の繁忙期だったが、今月は果たすべき課題がいっぱいで、私にとっての魔の9月が既に始まってしまっている。やるっきゃないか。










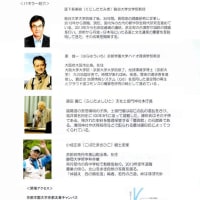
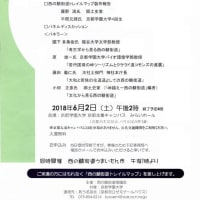
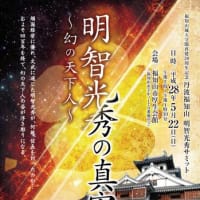


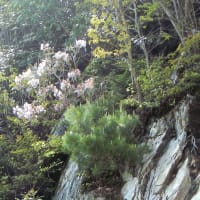


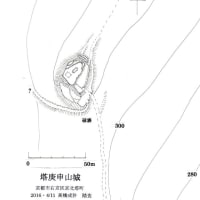


京北地区もかなり増水した様ですが、大きな被害が無くて何よりでした。予防の通行止めで終ったのは不幸中の幸いでした(私は勘違いしましたが)。
堤防決壊や田畑の冠水など、上桂川の水害は子供の頃から何度も体験しており、各地のそうした被害を見ますと他人事ではない悲壮感が拭えません。
昭和20年~30年代の京都は、特に台風の襲来が多かった記憶があります。小学校5~6年生と、続いてヘスター台風とジェーン台風に見舞われました。
かつての上桂川は実によく氾濫しました。山国や周山の製材所や貯木場の材木が大量に流失し、まるでマッチ箱をぶちまけた感じで、太い材木が折り重なって流れて行く怖ろしい光景は、今でも目に焼き付いています。
栃本の木橋は簡単に流失し、田畑は冠水して砂利で覆われるなど、民家よりも山野の被害が大きかったと思います。周山大橋に材木が詰まって町が水没したのは、もう少し後のことでしょうか。mfujinoさんの同級生の家が流されたのは、台風13号(昭和28年)だったのかも分かりません。
その頃には私は八木町へ引っ越しており、私の同級生の家も流失しています。その後も何度か床上・床下浸水に遭っており、家財はもちろん私の教科書や書物なども泥水に浸かって、情けない思いを頻繁に味わいました。
今は大堰川~上桂川は護岸工事も完成して、昔の様な直接的な水害は免れていますが、それでも作物や森林の被害は避けられないのでしょう。八木大橋の畔に、台風13号の救援で殉職した自衛隊員の石碑が建っています。今では振り返る人もいないのかも知れません。
ともあれ台風一過。かなり涼しくはなりました。また残暑がぶり返すかどうか分かりませんが、季節は少しずつ秋に向かっております。超多忙な日々、ご自愛(禁飲み過ぎも)を祈っております。
今回、台風は岡山から鳥取へと抜けましたが、今少し西のルートをとっていたら、京都も凄まじい豪雨に襲われたに違いありません。1時間に100ミリとかの豪雨に堪えうるのかは、降ってみなければ分からないところがあり心もとないですね。
確かに言えることは、都市はダメだろうということです。「彩都」のある山の斜面なんかは、途中に水を蓄えておくものが何もありませんし、他の町も市街化が進むにつれて、たくさんのため池が埋めたてられました。もうこうなったら、自分の一生の間にそれに直面するかしないかの運ですね。
周山街道は、一定の降雨量を超えると自動的に通行止めになるようですね。以前に弓槻峠で目前の土砂崩れに直面したことがありますから、納得できます。
山間に住んでいると道路が寸断されると孤立してしまって大変ですが、今日職場で黒田在住の同僚に、「昨日は井戸からルートも花脊峠も通行止めになって黒田は孤立してたね」なんて冗談を言ってました。その後、芹生のルートは通行止めじゃなかった見たいですがどうなんでしょう。
徘徊堂さまも淀川の治水を考えるとその上流の山の状態は気になることでしょう。今回の様な雨量が丹波山地に降ったら京阪神の都市部はどうなっていでしょうね。不謹慎な表現かもしれませんが、南からの湿った空気を紀伊山地の山々が壁になって塞いでくれたのでこちらの方は助かったのかもしれません。