
お盆の間、仕事で忙しかったので墓参りにも行けなかった。先日お盆も過ぎてから姉と墓参りに行った。午前10時半頃だったろうか、さすがに誰の姿も見えずに静まりかえっていた。こんなに遅い墓参りで親爺もお袋も呆れていることだろう。
墓参り

先日会議の為高浜へ行ったが、途中美山の田圃はかなり色づいていた。高浜に入るとコンバインが道端に。もうすぐ刈り入れが始まるのだろう。こう猛暑が続くと秋という言葉が頭に浮かばないが、自然は秋に向かって着実に歩を進めているのが分かる。黄金色になり始めている田の風景は22日の美山は大野で撮影したもの。
京北の稲田はまだ緑だ。田圃の向こうにはムクゲが咲き誇っている。我が家の庭にも咲いていて、蝶が傍で乱舞していたのが印象的だった。
京北の田圃

途中車を走らせていると、道端はサルスベリが綺麗に花を咲かせている。道路脇にも咲いているのだが電線が邪魔した作品しか撮れなかったので、ご近所の庭のサルスベリをアップご覧あれ。美山ではもっと大きい木が花を咲かせていた。
サルスベリ

墓場の傍を通ったら、遠目には、お、彼岸花?と見間違うキツネノカミソリが。もう盛りは過ぎている様だが。オオキツネノカミソリだともっと曼珠沙華に似ているそうな。淡いピンクのリコリスも庭先に咲いているが、そう目に入らない。
墓場に咲くキツネノカミソリ

美山の下吉田付近を通る。ナラ枯れの風景が飛び込んでくる。今年の新緑の頃は綺麗な緑の風景だったのに。また京北では杉檜の山が多く、この風景を目にすることは少ない。
ナラ枯れ

松の木はほぼ全滅に近い。今度はコナラなどがカシノナガキクイムシの標的になっているようである。京都の東山でも大変な様だ。
この自然現象については、独立行政法人森林総合研究所関西支部のサイトで「ナラ枯をの被害をどう減らすか 里山林を守るため」と題して説明されている。
http://www.fsm.affrc.go.jp/Nenpou/other/nara-fsm_201003.pdf
カシノナガキクイムシだけでこの現象は語れず、気候変化、人間の自然に対する変化、動物や菌類の変化、などなど諸要因がこの現象に現れているそうである。便利さを追求する人間の経済活動が与えている影響も大きいのだろう。人間の寿命という短いスタンスで考えなければ森は回復するだろうが、そんな悠長なことも言っておれない面もある。複雑な気持ちでこの山の様相を見つつ車を走らせていた。
山を歩き自然を見て語り、かたや車を走らせながら自然を語る。人の業は罪深いものなのだろうか?おじいさんは山へ柴刈りに、という生活に帰れるわけでもなし。










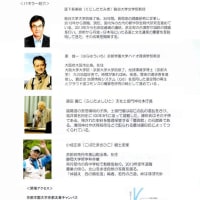
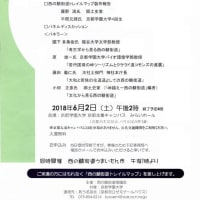
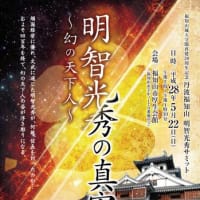


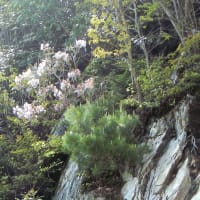


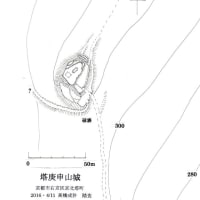


京北地区は常緑樹が多く、たまに古里を訪れますと、その中で松枯れがかなり目につきます。遠くから眺める景観も相当に異様なものがあります。こうして、大木になった落葉樹の代表的な樹木が枯れることなども、昔なら信じられない光景です。
病原菌が最大の原因とのことですが、異常気象もさりながら、里山の笹や低木が鹿などに食べられてしまい、生態系が大きく変動したことが遠因と説明されていました。昔のように、お祖父さんが山へ芝刈りに行って適当に低木を伐る暮らしなら、こんな事態は起こらなかったのでしょうけど、もうそんな生活は望めないことです。
宇津地区で橡(トチ)を増やす運動があるとのことですが、山にはやはり様々な種類の木々があってこそ本来の姿です。楢や樫や椎も大切な里山の木です。
今夏の猛暑は、日本が亜熱帯へと移行しつつある現象との説明があります。この季候の変動の原因が人間の所業なら、ある意味では修復の可能性はあるとも言えます。政策の重要な基本方針の一つとして掲げ、真剣に取り組むべき時期にあることは間違いありません。
美山ではもう稲が黄色く実り始めましたか。今年は庭の百日紅の開花が遅くて心配していたのですが、今が満開に咲き競っています。古里の里山が、昔の風景を取り戻すことを切に願います。
「ふるさと」 井上 靖
〝ふるさと〟という言葉は好きだ。古里、故里、故郷、どれもいい。
外国でも〝ふるさと〟という言葉は例外なく美しいと聞いている。
そう言えば、ドイツ語のハイマートなどは、何となくドイツ的なも
のをいっぱい着けている言葉のような気がする。漢字の辞典の
援(たす)けを借りると、故園、故丘、故山、故里、郷邑(きょうゆう)、
郷関(きょうかん)、郷園(きょうえん)、郷井(きょうせい)、郷陌(きょうは)、
郷閭(きょうりょ)、郷里、たくさん出てくる。故園は軽やかで、
颯々と風が渡り、郷関は重く、憂愁の薄暮が垂れこめているが、
どちらもいい。しかし、私の最も好きなのは、論語にある〝父母国〟と
いう呼び方で、わが日本に於ても、これに勝るものはなさそうだ。
〝ふるさと〟はまことに、〝ちちははのくに〟なのである。
ああ、ふるさとの山河よ、ちちははの国の雲よ、風よ、陽よ。
各地のナラ枯れ、残念ですね。その害虫には天敵はいないのでしょうか。
一番恐れているのは人が山に入らなくなっている事態だと思っています。山に入っても経済的に成り立たないのだと思います。山が荒れることは都市で生活される人達にも影響があるでしょう。地球規模で考えなければならないといけない問題なのでしょうが、そこまで大上段に考えなくても、また若者が山の仕事で生活できる様な仕組みを考えて行かなければならないと思います。これは難しい問題でしょうが色々な取組も為されているとは聞きます。目の前の現象に傍観者でしか居られないのがもどかしい気持ちもあります。
しかし世界と競争して行かねば、、、なんて考えていたら昼寝なんか出来まへん。その能力もないのに偉そうなことを考えずに、自分の足でこつこつと何か楽しみながらやることが人様の役に立てれば良いか、という気持ちになっています。
カシノナガキクイムシの天敵で解決するのは対症療法の一つに過ぎないかもしれないのではと素人なりに考えています。何かついつい堅い話になってしまいます。秋になったら頭巾山へ登り頭を柔らかくしましょう。
そちらはおおらかな明るいお墓でいいですね。以外に野花の少ないこの時期のキツネノカミソリやセンニンソウは嬉しいものです。以前は淡いピンクや白いサルスベリの花が多かったように思いますが、(家のは白色)最近は百日紅と字のごとく紅色やオレンジ色まで多彩にあるのですね。
次の権蔵坂と美山深訪に向け毎朝頑張って歩いています。お世話かけますがよろしくお願いいたします。
私が幼い頃の記憶はサルスベリは白ですが、最近は紅が圧倒していますね。百日紅とはよく言ったもので長~い間花を咲かせています。
ある山や植物・動物にも詳しい方から「秋の気配、宇宙の手配絶妙だと感じ入っています」というメールを頂きましたが、この宇宙の手配という言葉が頭から離れません。夜には虫の音も聞こえ始めています。
来週には権蔵坂へ三度目の訪問予定です。皆さんに楽しんで頂ける様頑張ってきます。
里山はどこも荒れているのでしょうか? 鎌倉は「緑を守る」と言う名目のもと木を切らせません。手が入らない山は雑木を伸ばし放題にしますので、山の下に住んでおりますと年々日陰が多くなります。人の手が入ってこそ良い状態で山は維持されるのにタダタダ木を切るなという行政に納得がいかないのですが。
庭木を切るのにも市の許可が必要な地域に住んでおりますと、うんざりすることがあります。庭を掘っていて骨が出てきたりしますと、「自分の庭だからといってそんなに深く掘ってもいいものではない。」と言ってお叱りを受けますし。
黄金色に色づき始めた田圃を撮影したのは美山の大野という地区ですが、そこにはまだ何軒かの茅葺きの家が残っています。そうかもっとアングルを考えるべきでしたね。
里山は荒れています。山には入らなくなっているからです。もっと人が山と交流しておれば違った様相になっているかもしれません。自然界は人間や動物、昆虫や鳥、植物そして菌類、天候まで含んだ、まさに有機的関係で成り立っているわけですし、どこかが変わればそれは他の生態に影響を及ぼす訳で、その集大成が表に現れている姿でしょう。でもまだ我々の目に見えない世界で大きな変化がおきているのかもしれません。人間の体と同じで、病気の症状が出始めたらもう既に手遅れなのかもしれません。
ただ我々人間にとっては不快な現象も、ある動物や植物、菌類にとっては愉快な現象なのかもしれません。松が枯れてしまい人間にとっては松材や松茸の恵みを奪われますが、マツクイムシにとっては良い環境なのかもしれません。でも彼らは全部松を食べてしまったらその後はどうするのかしら、なんて考えてしまいます。
ここには経済という要素も大きな、というか最大の影響を与えているのではないかと思っています。山には入るメリットがなければ人は山に入らなくなり環境が変わるでしょう。今の生活には山は恵みを与えてくれない訳です。柴刈りに行かなくてもガスや電気で風呂は沸かせますしね。昔はそれなりの恵みがあったから人が入ったわけですから。ただこうした目先の経済で自然を考えると大きなしっぺ返しを受けるということです。
こんな事を考えていたら益々深みにはまります。でも木を切るなという鎌倉の行政はちょっと信じがたいものがあります。里山って人と山が共生している場所だと理解しているのですが。
自然環境はみんなの問題ですから私権は制限されるべきというのが我が基本的考えですが、それがどの程度なのかというのはよう分かりません。がんじがらめの生活なんて逃げ出したいものですしね。永遠の悩みなのでしょう。よう分かりません。
こういった問題にお釈迦さん、イエスさん、マホメットさんはどう考えていたのでしょうかね?