
現在、カサゴくん達が、 白点虫の猛攻を受けています。
白点虫の猛攻を受けています。
約7ヶ月ぶりに、白点虫との闘いが始まりました。
しばらくの日記は、本記事の更新する形態を取ります。。。
【更新履歴】
7/7 経過報告:チンタ・シロギス2号、死亡
6/26 経過報告:メゴチ弟、死亡
6/24 経過報告:メゴチ兄&弟とマアジ3号&4号、石ゴカイ喰らった!!
6/23 経過報告追記
6/22 本記事発行
【海水性白点病・予備知識】
淡水魚の白点病では寄生虫の種類が違うらしい。
繊毛虫の一種であるクリプトカリオン・イリタンスの寄生によって発症。
寄生により成長すると宿主の個体を離れシスト化し、
水中あるいは底砂で分裂による増殖し、再び寄生するというサイクルを繰り返す。
25~30℃の高水温を好む。
白点病は他の魚に感染する感染症ではない。
1匹の魚が白点病にかかったからと言って、他の魚も白点病になるわけでは無い。
まず、子虫が魚の体表等に貼り付く。
魚に付いた子虫は体表から栄養分を吸い取り成長。
成長してきた白点虫は次第に肉眼でも見える様なる。
この状態で白点虫は一度寄生した魚の体を離れ、シスト[被嚢体]となって水底に沈む。
シストは1日程度で百個以上に分裂し、白点子虫[遊走子]となって水中を漂う。
水中を漂う白点子虫は再び宿主である魚の体に張り付き成長する。
(分裂して24時間以内に新しい宿主に寄生できない者は死ぬらしい)
【治療方法】
■マラカイトグリーンによる治療・・・実施中
即効性を有している反面、持続性はなく効果時間が短い。
従って魚に付いた白点病が進行している場合は有用ではあるが、
魚の表皮から剥離している病原虫や卵には効果はほとんどないと考えられる。
マラカイトグリーンの効果が切れると白点病は再発する。
従ってこの方法での治癒の可能性は低い。
■民間治療法として鷹の爪治療法・・・実施中
鷹の爪(唐辛子)に含まれているカプサイシンという物質に強い殺菌性質があり、
それを利用する使用方法。
参照URL:http://www.patentjp.com/12/D/D101978/DA10001.html
■硫酸銅による治療・・・未実施
硫酸銅を用い溶けた銅イオンにて病原虫を殺虫してしまう方法。
水族館やアクアリウム等の閉鎖的水槽環境においては最も有効かつ即効性がある。
【経過報告】
6/13(日)
第二水槽の蛸壺カサゴ、死亡。[参照記事①]
6/15(火)
第二水槽のセイゴ6号・7号、白点病に。
これにより、第二水槽は、白点虫が蔓延していることが判明。
治療用水槽に隔離、治療開始。[参照記事②]
6/17(木)
第二水槽のセイゴ7号、治療中死亡。[参照記事②]
6/18(金)
第二水槽のムラソイ1号・シロギス初号、死亡。[参照記事②]
6/20(日)
第二水槽のセイゴ6号、治療中死亡。
第二水槽、壊滅。
カサゴくん・隻腕カサゴ・イシガレイ1号・メゴチ兄&弟・マアジ3号&4号
・・・治療用水槽に隔離、治療開始。
全水槽水を破棄。
水槽丸洗い実施。
6/21(月)
第二水槽のセイゴ8号、重度の白点病により海へリリース。
第二水槽で唯一生き残った活き餌・手長エビ、治療用水槽で脱皮する。
6/22(火)
第二水槽のイシガレイ1号、治療中死亡。
第一水槽のカサゴ8号、死亡。
6/23(水)
第一水槽のタケノコメバル、重度の白点病により海へリリース。[参照記事④]
これにより、第一水槽まで、白点虫が蔓延していることが判明。
治療水槽の水槽水入れ替え時、アミエビ投下・・・マアジ2匹荒食い。
メゴチ兄&弟とマアジ3号&4号、第二水槽へ帰還。
6/24(木)
第一水槽のマハゼ・メバル・ヘダイ・チンタ、石ゴカイ食べる。
第二水槽のメゴチ兄&弟とマアジ3号&4号、石ゴカイ食べる。[参照記事③]
※餌食日報(2010年6月)参照
6/25(金)
寝不足のオイラ、なんとか今週を乗り切る。。。


6/26(土)
第二水槽のメゴチ弟、死亡。
7/7(水)
第一水槽のチンタ、死亡。
第二水槽のシロギス2号、死亡。
※但し、白点病との関連は不明。
チンタは、ヘダイの虐めが原因か? ストレス?
シロギスは、釣り捕獲投入後、8日目。。。 水槽に適応出来なかった?

水槽投入後、数日でこうなる。
投入したセイゴは、捕食された魚を除いて、皆酷い白点病に。
カサゴからのプレッシャーによるストレス?
いや、カサゴも、暑さと白点病で苦しんでいたから・・・。
汽水飼育のほうが良さそうだ。
他の魚と比べても、白点病の進行スピードが比較にならないほど高い。
セイゴを起点として、白点虫が蔓延したとも考えられる。

カサゴくんに貼りついた白点虫。
この程度だと、なかなか目視できない。
太陽の光が当たっただけでも、うまく判別できないのだ。
この写真は、夜中一方向から照らして撮影したもの。
遮蔽物もなく、ほぼ0距離撮影。

痒いのでしょうね。
エアレーションの泡を利用してました。
60cm幅水槽に居た時は、水中モーターフィルターの水流を利用してました。

ジャイアン・タケノコメバルまで。。。
隠れ家から全く出てこなくなった為、発見が遅れた。
体力ある溜め込んだタケノコだったからこそ、生き延びれたと思う。
[参照記事④]
今回、特にほとんど根魚は、白点病で苦しんだ。
やはり、根魚は冬・低温の魚なんだね。
唯一、白点メバルのみ、体調不良で拒食になった。
多分、暑さの為だろう。
この子は、昨年秋、白点病に患ったものの、生き残ったツワモノである。
免疫でも出来たのだろうか?
[参照記事⑤][参照記事⑥]

唯一生き残った手長エビ、脱皮した。
でも、最近見かけなくなった。。。
健康を取り戻したカサゴくんに食べられたようだ。
ランキング参加中です! ポチっと応援ください!!
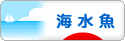
にほんブログ村 海水魚

blogramランキング
 白点虫の猛攻を受けています。
白点虫の猛攻を受けています。
約7ヶ月ぶりに、白点虫との闘いが始まりました。

しばらくの日記は、本記事の更新する形態を取ります。。。
【更新履歴】
7/7 経過報告:チンタ・シロギス2号、死亡
6/26 経過報告:メゴチ弟、死亡
6/24 経過報告:メゴチ兄&弟とマアジ3号&4号、石ゴカイ喰らった!!
6/23 経過報告追記
6/22 本記事発行
【海水性白点病・予備知識】
淡水魚の白点病では寄生虫の種類が違うらしい。
繊毛虫の一種であるクリプトカリオン・イリタンスの寄生によって発症。
寄生により成長すると宿主の個体を離れシスト化し、
水中あるいは底砂で分裂による増殖し、再び寄生するというサイクルを繰り返す。
25~30℃の高水温を好む。
白点病は他の魚に感染する感染症ではない。
1匹の魚が白点病にかかったからと言って、他の魚も白点病になるわけでは無い。
まず、子虫が魚の体表等に貼り付く。
魚に付いた子虫は体表から栄養分を吸い取り成長。
成長してきた白点虫は次第に肉眼でも見える様なる。
この状態で白点虫は一度寄生した魚の体を離れ、シスト[被嚢体]となって水底に沈む。
シストは1日程度で百個以上に分裂し、白点子虫[遊走子]となって水中を漂う。
水中を漂う白点子虫は再び宿主である魚の体に張り付き成長する。
(分裂して24時間以内に新しい宿主に寄生できない者は死ぬらしい)
【治療方法】
■マラカイトグリーンによる治療・・・実施中
即効性を有している反面、持続性はなく効果時間が短い。
従って魚に付いた白点病が進行している場合は有用ではあるが、
魚の表皮から剥離している病原虫や卵には効果はほとんどないと考えられる。
マラカイトグリーンの効果が切れると白点病は再発する。
従ってこの方法での治癒の可能性は低い。
■民間治療法として鷹の爪治療法・・・実施中
鷹の爪(唐辛子)に含まれているカプサイシンという物質に強い殺菌性質があり、
それを利用する使用方法。
参照URL:http://www.patentjp.com/12/D/D101978/DA10001.html
■硫酸銅による治療・・・未実施
硫酸銅を用い溶けた銅イオンにて病原虫を殺虫してしまう方法。
水族館やアクアリウム等の閉鎖的水槽環境においては最も有効かつ即効性がある。
【経過報告】
6/13(日)
第二水槽の蛸壺カサゴ、死亡。[参照記事①]
6/15(火)
第二水槽のセイゴ6号・7号、白点病に。
これにより、第二水槽は、白点虫が蔓延していることが判明。
治療用水槽に隔離、治療開始。[参照記事②]
6/17(木)
第二水槽のセイゴ7号、治療中死亡。[参照記事②]
6/18(金)
第二水槽のムラソイ1号・シロギス初号、死亡。[参照記事②]
6/20(日)
第二水槽のセイゴ6号、治療中死亡。
第二水槽、壊滅。
カサゴくん・隻腕カサゴ・イシガレイ1号・メゴチ兄&弟・マアジ3号&4号
・・・治療用水槽に隔離、治療開始。
全水槽水を破棄。
水槽丸洗い実施。
6/21(月)
第二水槽のセイゴ8号、重度の白点病により海へリリース。
第二水槽で唯一生き残った活き餌・手長エビ、治療用水槽で脱皮する。
6/22(火)
第二水槽のイシガレイ1号、治療中死亡。
第一水槽のカサゴ8号、死亡。
6/23(水)
第一水槽のタケノコメバル、重度の白点病により海へリリース。[参照記事④]
これにより、第一水槽まで、白点虫が蔓延していることが判明。
治療水槽の水槽水入れ替え時、アミエビ投下・・・マアジ2匹荒食い。
メゴチ兄&弟とマアジ3号&4号、第二水槽へ帰還。
6/24(木)
第一水槽のマハゼ・メバル・ヘダイ・チンタ、石ゴカイ食べる。
第二水槽のメゴチ兄&弟とマアジ3号&4号、石ゴカイ食べる。[参照記事③]
※餌食日報(2010年6月)参照
6/25(金)
寝不足のオイラ、なんとか今週を乗り切る。。。



6/26(土)
第二水槽のメゴチ弟、死亡。
7/7(水)
第一水槽のチンタ、死亡。
第二水槽のシロギス2号、死亡。
※但し、白点病との関連は不明。
チンタは、ヘダイの虐めが原因か? ストレス?
シロギスは、釣り捕獲投入後、8日目。。。 水槽に適応出来なかった?

水槽投入後、数日でこうなる。
投入したセイゴは、捕食された魚を除いて、皆酷い白点病に。
カサゴからのプレッシャーによるストレス?
いや、カサゴも、暑さと白点病で苦しんでいたから・・・。
汽水飼育のほうが良さそうだ。
他の魚と比べても、白点病の進行スピードが比較にならないほど高い。
セイゴを起点として、白点虫が蔓延したとも考えられる。

カサゴくんに貼りついた白点虫。
この程度だと、なかなか目視できない。
太陽の光が当たっただけでも、うまく判別できないのだ。
この写真は、夜中一方向から照らして撮影したもの。
遮蔽物もなく、ほぼ0距離撮影。

痒いのでしょうね。
エアレーションの泡を利用してました。
60cm幅水槽に居た時は、水中モーターフィルターの水流を利用してました。

ジャイアン・タケノコメバルまで。。。
隠れ家から全く出てこなくなった為、発見が遅れた。
体力ある溜め込んだタケノコだったからこそ、生き延びれたと思う。
[参照記事④]
今回、特にほとんど根魚は、白点病で苦しんだ。
やはり、根魚は冬・低温の魚なんだね。
唯一、白点メバルのみ、体調不良で拒食になった。
多分、暑さの為だろう。
この子は、昨年秋、白点病に患ったものの、生き残ったツワモノである。
免疫でも出来たのだろうか?
[参照記事⑤][参照記事⑥]

唯一生き残った手長エビ、脱皮した。

でも、最近見かけなくなった。。。

健康を取り戻したカサゴくんに食べられたようだ。

ランキング参加中です! ポチっと応援ください!!

にほんブログ村 海水魚
blogramランキング











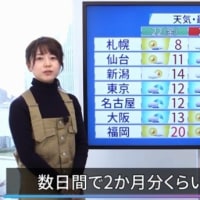


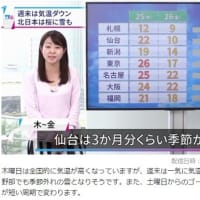











うちはメジナが以前なった時、水温を上げる方法で直しました
でも魚によって水温が上がるとダメなのもいるでしょうから、同じ水槽にいると大変ですね
白点病は、うちでは金魚になりやすいです
なので金魚の水槽は常にあったかく、餌もバリあげてるので みるみる大きくなってきてます(笑)
少しでも治って生き残ってくれる事を祈ってますね
もしよろしければ、メールにてのご連絡をお待ち申し上げます。
やはり、冬の釣れる魚・・・根魚などは、暑さに弱い傾向にありますね。
チンタやヘダイは、逆に元気ですから。
暑い⇒食欲激減⇒体力低下⇒白点虫に狙われる。
ほとんどが、このパターンですね。
寄生虫が最も活動し易い水温なんですね。
仮に治っても濾過層などに潜んでいないのですか?
濾過地や砂地に潜伏していそうで、根絶は無理そう。
餌食べて、体力付けて、白点虫に負けないように頑張ってもらうしかないなぁ、現状。。。
でも・・・クーラー付けろ!てか?!