データハウス
2005/07
①【私のここに注目】
東大が問いたいことは、基礎を完璧に理解しているか。うわべの知識にとどまらず、人に説明できるくらい、自分の中で知識が消化できているかなのだ。
たいていの勘違いの内容は、東大を受ける人は基礎より応用問題に重点をおいている、とか公式を山のように覚えている、などだと思う。
僕が参考書を選ぶときの基準は、「実況中継」(語学春秋社)など一から基礎をわかりやすく説明してくれる本を1冊、それに解答が詳しい問題集(解答が別冊になっているのがお勧め)を1冊。あとは赤本、この3冊だった。
ここではっきりいっておきたいことは、基礎となる最初の参考書を2冊も3冊も買わないことだ。信頼できる先生を1人見つけたら、最後までその先生についていくことだ。
特に東大の問題に関しては基礎は本当に大切で、出題者の意図は常にいつも基礎を問うている。ということは、点数配分や部分点も基礎的な内容がきちんと分かっているか、に割り当てているということだ。基礎力が7割を占め、あとの3割は問題集を使って実践形式で磨くというイメージでいい。こんなことをいうと当然次のような反論が出てくるだろう。教科書はちゃんとやっている。でも東大の問題は全然違うし、別次元だ、と。“ちゃんとやる”というのはきちんと理解するということだ。高校の小テストや中間や期末で満点近くとれる、というのはわけが違う。
たとえば理数系の公式の暗記より公式の導出方法を大切にし、歴史の知識の詰め込みより、その背景を大切にする。そんなことが要求される。断片的な知識は、それらを繋ぐ流れをおさえておかないと東大の試験では全く役に立たない。東大の出題者も正にそういったところを突いてくる。中間や期末試験のように横着な一夜漬けの丸暗記をしてきた生徒は大学側も欲しくないのだ。
数年前の数学の加法定理の証明などは正にその典型例だった。みんな結論は知っている。でも証明方法など、改めてあまり時間を割いて考えたことがない。さらに円周率3.14を何もない状態から導き出させたり、と型通りではない出題方法が目立つ。これらの問題に対処するには、普段から基礎をがっちりと、弟や妹や違う生徒に説明できるくらい、自分の中で消化していることが大切。
僕は満点を狙える能力よりも、常に8割を維持できる能力の方が重要であると思う。簡単な問題であろうと、である。
確かに満点を取るのは良い事である。その単元で学んだことを100%理解し、応用できている証拠だからだ。しかし、満点にこだわるせいで前に進めないのは甚だ問題である。一を身につけて二を身につけてから三を身につけようとする線形志向型の人はいつまでたっても一のままなのである。それよりも、一を8割がた身につけたらに二に進み、それも8割がた身につけたら三に進むというチェーンモデルな方法を採った方が結果的に全部を身につけるのが速いのだ。
皆さんの中には、そんな風に基礎がしっかり身についていない方法ではいずれ足元をすくわれるんじゃないか、と思われる方がいらっしゃるかもしれないが、そうなったらそうなった時にもう一度基礎に戻れば良いのである。これは一見すると行ったり戻ったりという非効率的なやり方だが、基礎となる事項がその先でどのように応用されているかを知っている分、基礎を身につけ直すのが速く効率が良い。また、先に進んで学んだ事を基礎的な事項にフィードバックさせる事もできる。
私も最後の30分は見直しに費やした。
私が言えることとしては、満点に近づくことができるような勉強をしてから、満点を狙うか捨てるかを選択すべきではないか、といったところである。
方針があっていてもポロポロと部分点を引かれて点数がなくなってしまう事も多々ある。
そもそも東大レベルの問題は3分で方針が立てられるはずがないからだ。現実には、手を動かして答案を書いている間に解法が見えてくる事の方が多い。数学の基本は「図を描き、目で見て、手を動かして、考える」である。
ではなぜ数学がスポーツなのか?東大の模試を受けたことがある人なら分かるだろうが、6問を150分で解くというのはかなりきつい。知らない人は、なぁんだ、1問に25分もかけられるのか、と思うかもしれないが、それは全く違う。たしかに、すぐ解法に気付く問題なら20分もいらないかもしれないが、大抵の問題はいわゆるハマってしまう問題である。40分、50分とかけても皆目見当もつかない。気付いたら時間がすごく経過していた、というのがありがちなパターンで一番やってはならないパターンである。大抵試験に失敗した人の話を聞くと、「ある問題に時間をかけすぎて、知らないうちにすごく時間が過ぎていた。しかも結局その問題は解けなかった」というのである。これを回避する鍵が正に、スポーツのように数学を解くことなのだ。試験中は手を休める時間を出来るだけ少なくする。常に何かを書いていること。手を動かすこと、手を動かすと脳が働き、すると最初ぼっーと問題とにらめっこしていても気付かなかった解法を思いついたりする。
始まるとばらばらと駆け足で全ページを一通り見て、どの問題から手をつけていくか大体決める。当然自分の得意分野から始める。幸先よく始めると、いい流れができるからだ。逆に得意分野のはずの最初の一問が解けないときも当然ある。そういうとき僕は開き直っていた。選んでしまった問題はたまたま難しく、自分が難しいと感じる問題は他人もまた難しいと感じているのだ、と。後で友達に聞いたりすると、みんなそういう問題には苦戦しているものだ。苦しいときはまわりも苦しんでいるのだ。
東大入試、特に数学において時間がネックであることは周知のとおりであり、従ってほとんどの人にとって下書きをしてから清書するといったことは不可能に近い。つまり、人によって程度の差はあれ、事実部分を一部削除したり、追加したりする必要性が出てくる。
2つ目として、かなりの分量が書けるようになってしまったために、答案が冗長になってしまいがちということがある。 東大数学のほとんどの問題は、それほど長い答案になってしまうことは少なく、長い答案になってしまうということはキーポイントを掴みきれていないということになる。
概して、少し飛躍気味の答案よりも冗長しすぎる答案のほうが読みづらく、採点者の印象が悪くなってしまうものであるのだ。
東大数学攻略三本柱を提示しておきましょう!
・計算力
単純な四則計算から様々な関数演算、さらには積分計算と三段階の計算能力を鍛えておく必要があります。数学を解く時には一番使う能力であり、これを鍛えていない受験生はきっと数学を攻略するのに苦労することでしょう。そもそも、計算能力は物理や化学の能力にもつながります。物理でも化学でも東大はややこしい式変形を何段もこなす必要があります。東大は、処理能力の高い柔軟な学生を求めているのですから。
・基本
実際のところ、すべての問題がわりと難しい問題ですが、最近の傾向としてきちんと基礎が出来ていて、なおかつ計算力があれば完答できる問題も一問はあるようです。さらに小問に分かれている問題があるときは、最初の小問は基礎的なことで解ける場合が多いようです。
とにかく物理はイメージが沸くかどうかなのだ。イメージがわけば、こむずかしい数式はいらない。微積分もいらない。数学に帰着させることもない。実際入試本番の問題というのは、微積分を使わなくても解けるような問題を出してくれている。使ったら回り道になりすぎて、時間以内に終わらないという悲惨なケースも多々ある。
「 問題は解けなくてもいいから僕の解答を読んで理解していって下さい。それで分からないところは僕の方が間違っているんじゃないかと批判的に見て下さい。そうやって考えて、それでも分からないところは何でも質問して下さい。それで、理解できたら今度解く時は解答を見ずに解く。それを繰り返して下さい。」
つまり、解答を読んで理解できることも1つの能力であるという事だ。考えてみれば、数学や物理ができない人の中には「解答を読んでもさっぱり分からない」と嘆く人が多い。解答を読んでも分からないのに自力で解く事ができるはずがない。東大レベルの難問を解くにあたっては、解答が読める能力が最低限必要なのである。
そうは言っても、解答を読み進んでいくと必ず疑問点にぶつかるはずだ。こういう疑問点は往々にして、問題のキーポイントとなっている。
東大レベルの問題には1題の中に様々なキーポイントが含まれており、解答を読む中できっちりとそのポイントを押さえておけば変化球にも対応できるのである。
化学はどう勉強するか。
まず、高校化学を3つに区分すると理論化学、無機化学、有機化学の分野に分けることが出来る。
1つ目の理論化学は3つの中で一番量が多く、大体全体の5割のウェイトを占める。内容的にも理解しにくいので、ここでつまずきやすい。しかし、この理論化学こそが科学の大切な基礎を成す分野であり、逆にここを乗り切れれば後はかなり楽にやって行けるということだ。乗り切るポイントは2つ。「想像力と反復練習」である。実は理論化学は原子や分子の振る舞いをテーマにした所が結構多く、これらの部分では想像力を逞しくして核の周りを飛び回る電子、結晶でぎゅうぎゅう詰めになっている原子、容器の中をびゅんびゅん飛び回り、内側に衝突する気体分子などの様子を頭の中で描ける様にしておくことが望ましい。これには図録が役に立つであろう。そしてイメージが湧くようになれば、一見難しい公式たちもその意味するところが理解できるようになるハズ。結局これらの公式というのは原子の挙動、または原子・分子の集まりに過ぎないマクロな物質の性質を記述する為のものでしかないのだから。そしてここまで理解が進めば、あとはそれらの公式を完全に使いこなせるようになるまで、ひたすら計算問題を解きまくるだけだ。“自分が今使っている公式が何を表現しているのか”ということを見失わないようにすれば、こなした問題の数だけ実力はアップしていくだろう。
次に無機化学であるが、ここは一番易しい分野である。量も化学全体の2割程度しかない、元素各論を除いた分野はほとんど理論化学分野の酸化還元反応と中和反応を中心とした復習に近い。ただ、理論化学と近い分、融合問題も出やすく、処理能力と計算力が問われる。そして元素各論については1人2人のプロフィールを覚えていく感じなので、ひたすらまとめノートを使ったりして楽しく覚えていけばよい。この分野は理論化学のしっかりした土台さえあれば1ヵ月集中的にやるだけでテストで9割狙えるようになります。
最後の有機化学は化学全体の中で3割程度を占めている。この分野、始めの頃はひたすらカタカナ語を覚えさせられる羽目になる。全ての物質名又は分類名なのだが、それほど大量にある訳でもないので大丈夫でしょう。量も大事なのは様々な官能基の性質とそれらが起こす反応を覚えることである。この分野は電気陰性度の考えを用いて電子の振る舞いに注意することで理解はぐっとし易くなります。ここでも理論化学の土台が効いているのです。先ほど官能基の性質を学ぶと言ったが、これはその官能基を持つ代表的な物質を用いて考えることになるので、官能基を一通り学び終えたときには、かなりの数の化学物質が頭に入っていることになる。そして最後の詰めとして、構造決定問題を大量にやること。しかも入試問題はこのパターンになることが大変多いので、しっかり数をこなすべきだ。なんだかやたらと問題数を多くやるべきだと主張してきたが、これは理解しただけでは点に直結しないからだ。処理のスピードと正確さが最終的にネックになるのだ。
・力学
微分方程式を知っていると、学習上少し有利になることを言っておきます。知らなくてもまったく問題はありませんが。
・熱力学
まあ、一番簡単な分野でしょう。少し公式を覚えた後、基本的には各状態においてすべての物理量を書けばすぐに答えが出ます。しかも間違いにくいです。
・電気
回路とかその辺の問題ですから、小学校の延長線上にあります。簡単でしょう。すぐに攻略できます。力学との融合問題になることが多々ありますが、落ち着いて力を出していけば簡単です。
・波動
抽象的で分かりにくく、頭から覚えることが多い分野ですが、三角関数の計算をきっちり身につけていればそんなに苦労することはないでしょう。波を考えるときは、いつも波長と速さと周期を考えるようにしましょう。
・電磁気
マジで難しい。たいていここで詰まります。しかも力学との融合問題が多く大変です。しかし、アンペールの貫流則を覚えておけばだいぶ楽になります。あとは力学の問題に変わりまる。自己誘導相互誘導は、一度基礎からしっかりと考えておくべきです。自分で公式の導出をしてみましょう。
・原子
がんばって覚えてください。ワンパターンな問題しか出ません。もっとも近年はほとんど出題がみられませんが。
化学の攻略法
・理論
公式を覚えるときにどうしてこの公式になるのかを考えるようにしましょう。あと、単純計算時のケアレスミスに注意しましょう。実際のところは目新しい題材を基にした割と簡単な応用問題が出ることが多いので、あきらめないで解読することがだいじです。
・無機
淡々と反応、沈殿を覚えましょう。覚えた知識は問題で確認しましょう。覚えて量がある程度超えると一気に答えられる問題が増えて、無機を勉強するのが楽しくなります。
・有機
覚えるべきことはそんなにありません。パズル的要素が強いので、そう思って楽しく勉強していきましょう。問題をぴったり解けたときは楽しいです。あと、高分子化合物は後回しにしてもいいでしょう。本当にただ覚えるだけですから。
京大は、現代文・擬古文・古文の大問3題から理系であれば好きなものを2題選択して解答するのだが、注目すべきはその解答用紙である。小問ごとに四角い枠があるだけで、数年前から行数指定のために枠内に破線が引かれるようになったが、基本的に全問題に字数指定はない。設問も大問3題とも「~について説明せよ」という曖昧なものがほとんどで非常に難解である。
それに対して東大は、現代文・古文・漢文の大問3題の出題で、京大と異なるのは漢字の書き取り問題が出るという点である。マニアックな漢字が出題されるわけではないので5点は確実に取れる。また、現代文では字数指定のついた要約が出題されるなど、設問自体に条件のついた問題が出ており取り組みやすい。更に古典では現代文以上に設問に条件がついている問題が多いし、基本的な文法知識があれば解ける問題で取り組みやすい。
このように、東大国語は基礎的な知識と少しばかり物を考えられる頭さえあれば合格点が取れる問題なのである。
にも関わらず、全国的に見た理系の受験生の国語能力は驚く程低い。いや、能力自体は低くはないのだろうが、国語の勉強をしている受験生が少ないのだ。
古文は現代日本語とは全く違う言語だし、漢文に至っては日本語ですらない。言ってみればこれらは英語に近い科目なのである。文法は一から覚えないといけないし、単語は全く新しいものが出てくるしと、設問として作文や並び替えが出題されないだけで新言語を学ぶ点では同じなのだ。受験生は英語で差がつなかいとでも思っているのだろうか?
理系だからとか、他の科目で点数取れるからとか高をくくらずに、せめてセンター国語で確実に8割取れる位の国語力はつけたい。先程も述べたとおり、東大の国語は易しいのだからそれ位の国語力でも十分である。
私に転機が訪れたのは受験半年前、出口汪先生の著者に出会ってからだ。出口先生の教えは、現代文を曖昧な科目ととらえず、正しい方法で勉強した者は必ず報われる科目である、と説く。その内容を全てここで紹介することはできないが、端的に言えば、書いてある内容を主観を入れずありのままに読む。筆者の主張をつかむ。筆者の主張は、具体例や比喩などを用いて、形を変えて繰り返される。だからそのたったひとつの主張をつかんだら、それを踏まえた上で、「重ねるように」読む。
さらに出口先生もやはり、読書と現代文の違いについて触れている。現代文の問題として出てくる文章は、何100ページもある本のごく一部が抜粋されているものなのだ。当たり前のことだが、それをよくよく意識しておかないとついつい本を読むときのように、主人公などに主観をいれまくって問題を読んでしまう。現代文という教科は解く人が解けば全員の答えが同じになる、非常に論理的な教科なのだ。主観を入れて、自分勝手に判断していたらこうはなるまい。文章中の表現だけが頼りなのだ。そこから客観的な判断をくだすから、一意的に答えが決まる。
記述式というのは、一見すると自由に自分の言葉で書いていいように思われがちだが(とくに要約など)、その実、長い文章からピンポイントで重要な部分を解答に盛り込まないと、部分点さえ中々もらえないようになっているのだ。実際、予備校の採点基準などを見ると、その文章のキーワードが書かれていなければ、たとえ答えとニュアンスがそっくりでも0点、もしくは大幅減点されていたりする。逆に自分でもよくわからないまま適当に解答を書いてしまっても、キーワードが入っているだけで案外点数が取れてしまったりする。
このように国語は、当たればでかいが当たらないとさっぱりという、ある種博打のような性質を持っているので、試験が終わっても自分でどれくらい点数を取れたか、見当をつけるのは難しいと言える。
その証拠に、数学や英語で全国上位を取る人たちは、毎回大体決まっている常連たちである。しかし国語はどうか。上位の名前がころころと変わるではないか。
実際、東大の文系ですら勝負は点差の開く80点満点の数学で決まってしまうことが多いと聞く。
文系ですらこうなのだからましてや、理系はもっと数学重視であろう。
現代文で要求されていることは、大きく分けて「これはどういうことか」と「なぜこのように言えるのか」の2パターンである。そのヒントや答えはすべて課題文の中に書いてある(そうでなかったら問題として成り立たない)“それらを探し出すことができれば、基本的には満点になる”ということだ。
これまで読書をほとんどしてこなかった人はどう対処すればよいのか。やはり、問題を解くことに尽きる。
せいぜい、大きく失点しない程度の内容だった。満点の取り方は知らないが、部分点を稼ぐ方法ならある程度知っているつもりだ。
その秘訣は、主語、理由を付け加え、本線の部分を明確にすることである。この方法は某予備校講師が言っていた方法で、これを習得してからは大幅な失点はしなくなった。
次に本番での時間配分について。国語は現代文、古文、漢文があり、古文、漢文のほうが短時間で解答することが可能だ。そのため、“古典を先に処理して、時間のかかる現代文を後回しにしたほうがいい”とされている。国語に限った話ではないが、簡単にできるものを先にやっておいたほうが精神的にもいいような印象を受ける。
②【感想など】
・東大理Ⅲ合格者の話は、頭の良さの次元が全く違うので参考にならないかと思ったりしていたが、非常に合理的で無駄がなく、通常の受験生にも適用できる有益な話が多かった。
・しかしながら、大学受験も東大レベルになってくると重視すべきことは違ってくる。
・理数系科目では、基本とは何か、本質とは何かをとことんまで追及することが必要である。真の理解に至るため、全ての定理、公式の歴的背景、意義を踏まえた上で、その証明や導出方法を身につけ、さらにそれを縦横無尽につかいこなす応用力が必要となってくる。
そして、問題の解答に当たっては、すぐに方針が立つものは少なく、あれこれ実験や試行錯誤の上、ひらめくことが多い。さらに、計算力などヘビー級の問題が多数を占め、試験時間の150分はまさにスポーツ的とも言えるとのことである。
・一方、国語も点がもらえたらもうけ的な発想で全く手をつけないという考え方ではなく、まずは、英語といった外国語学習のように取り組め比較的点数の取りやすい漢文、古文を攻略して、現代文の失点を防ぐやり方がよいとのことである。
・色々と批判もある大学受験制度ではあるが、ここは考え方を変えて、限られた時間内での効果的な成果が得られる処理法などを工夫することや、他方で、物事を深く追求するきっかけとなるよう取り組んでいくことは、将来仕事をしていく面でも十分、基盤力となると思われる。
③【今後、考えてみようと思うこと、実行してみようと思うこと】
・受験勉強をアスリート的に取り組んでみたらどうなるか。
・各科目において、得られた知見、成果(原理、定理、公式など)の歴史的背景や意義を調べ、その証明や導出に踏み込むこと。
・ミスをおかさず、重量級の計算力はどうやったら身につけることができるか。
【この本のAmazonへのリンク】


2005/07
①【私のここに注目】
東大が問いたいことは、基礎を完璧に理解しているか。うわべの知識にとどまらず、人に説明できるくらい、自分の中で知識が消化できているかなのだ。
たいていの勘違いの内容は、東大を受ける人は基礎より応用問題に重点をおいている、とか公式を山のように覚えている、などだと思う。
僕が参考書を選ぶときの基準は、「実況中継」(語学春秋社)など一から基礎をわかりやすく説明してくれる本を1冊、それに解答が詳しい問題集(解答が別冊になっているのがお勧め)を1冊。あとは赤本、この3冊だった。
ここではっきりいっておきたいことは、基礎となる最初の参考書を2冊も3冊も買わないことだ。信頼できる先生を1人見つけたら、最後までその先生についていくことだ。
特に東大の問題に関しては基礎は本当に大切で、出題者の意図は常にいつも基礎を問うている。ということは、点数配分や部分点も基礎的な内容がきちんと分かっているか、に割り当てているということだ。基礎力が7割を占め、あとの3割は問題集を使って実践形式で磨くというイメージでいい。こんなことをいうと当然次のような反論が出てくるだろう。教科書はちゃんとやっている。でも東大の問題は全然違うし、別次元だ、と。“ちゃんとやる”というのはきちんと理解するということだ。高校の小テストや中間や期末で満点近くとれる、というのはわけが違う。
たとえば理数系の公式の暗記より公式の導出方法を大切にし、歴史の知識の詰め込みより、その背景を大切にする。そんなことが要求される。断片的な知識は、それらを繋ぐ流れをおさえておかないと東大の試験では全く役に立たない。東大の出題者も正にそういったところを突いてくる。中間や期末試験のように横着な一夜漬けの丸暗記をしてきた生徒は大学側も欲しくないのだ。
数年前の数学の加法定理の証明などは正にその典型例だった。みんな結論は知っている。でも証明方法など、改めてあまり時間を割いて考えたことがない。さらに円周率3.14を何もない状態から導き出させたり、と型通りではない出題方法が目立つ。これらの問題に対処するには、普段から基礎をがっちりと、弟や妹や違う生徒に説明できるくらい、自分の中で消化していることが大切。
僕は満点を狙える能力よりも、常に8割を維持できる能力の方が重要であると思う。簡単な問題であろうと、である。
確かに満点を取るのは良い事である。その単元で学んだことを100%理解し、応用できている証拠だからだ。しかし、満点にこだわるせいで前に進めないのは甚だ問題である。一を身につけて二を身につけてから三を身につけようとする線形志向型の人はいつまでたっても一のままなのである。それよりも、一を8割がた身につけたらに二に進み、それも8割がた身につけたら三に進むというチェーンモデルな方法を採った方が結果的に全部を身につけるのが速いのだ。
皆さんの中には、そんな風に基礎がしっかり身についていない方法ではいずれ足元をすくわれるんじゃないか、と思われる方がいらっしゃるかもしれないが、そうなったらそうなった時にもう一度基礎に戻れば良いのである。これは一見すると行ったり戻ったりという非効率的なやり方だが、基礎となる事項がその先でどのように応用されているかを知っている分、基礎を身につけ直すのが速く効率が良い。また、先に進んで学んだ事を基礎的な事項にフィードバックさせる事もできる。
私も最後の30分は見直しに費やした。
私が言えることとしては、満点に近づくことができるような勉強をしてから、満点を狙うか捨てるかを選択すべきではないか、といったところである。
方針があっていてもポロポロと部分点を引かれて点数がなくなってしまう事も多々ある。
そもそも東大レベルの問題は3分で方針が立てられるはずがないからだ。現実には、手を動かして答案を書いている間に解法が見えてくる事の方が多い。数学の基本は「図を描き、目で見て、手を動かして、考える」である。
ではなぜ数学がスポーツなのか?東大の模試を受けたことがある人なら分かるだろうが、6問を150分で解くというのはかなりきつい。知らない人は、なぁんだ、1問に25分もかけられるのか、と思うかもしれないが、それは全く違う。たしかに、すぐ解法に気付く問題なら20分もいらないかもしれないが、大抵の問題はいわゆるハマってしまう問題である。40分、50分とかけても皆目見当もつかない。気付いたら時間がすごく経過していた、というのがありがちなパターンで一番やってはならないパターンである。大抵試験に失敗した人の話を聞くと、「ある問題に時間をかけすぎて、知らないうちにすごく時間が過ぎていた。しかも結局その問題は解けなかった」というのである。これを回避する鍵が正に、スポーツのように数学を解くことなのだ。試験中は手を休める時間を出来るだけ少なくする。常に何かを書いていること。手を動かすこと、手を動かすと脳が働き、すると最初ぼっーと問題とにらめっこしていても気付かなかった解法を思いついたりする。
始まるとばらばらと駆け足で全ページを一通り見て、どの問題から手をつけていくか大体決める。当然自分の得意分野から始める。幸先よく始めると、いい流れができるからだ。逆に得意分野のはずの最初の一問が解けないときも当然ある。そういうとき僕は開き直っていた。選んでしまった問題はたまたま難しく、自分が難しいと感じる問題は他人もまた難しいと感じているのだ、と。後で友達に聞いたりすると、みんなそういう問題には苦戦しているものだ。苦しいときはまわりも苦しんでいるのだ。
東大入試、特に数学において時間がネックであることは周知のとおりであり、従ってほとんどの人にとって下書きをしてから清書するといったことは不可能に近い。つまり、人によって程度の差はあれ、事実部分を一部削除したり、追加したりする必要性が出てくる。
2つ目として、かなりの分量が書けるようになってしまったために、答案が冗長になってしまいがちということがある。 東大数学のほとんどの問題は、それほど長い答案になってしまうことは少なく、長い答案になってしまうということはキーポイントを掴みきれていないということになる。
概して、少し飛躍気味の答案よりも冗長しすぎる答案のほうが読みづらく、採点者の印象が悪くなってしまうものであるのだ。
東大数学攻略三本柱を提示しておきましょう!
・計算力
単純な四則計算から様々な関数演算、さらには積分計算と三段階の計算能力を鍛えておく必要があります。数学を解く時には一番使う能力であり、これを鍛えていない受験生はきっと数学を攻略するのに苦労することでしょう。そもそも、計算能力は物理や化学の能力にもつながります。物理でも化学でも東大はややこしい式変形を何段もこなす必要があります。東大は、処理能力の高い柔軟な学生を求めているのですから。
・基本
実際のところ、すべての問題がわりと難しい問題ですが、最近の傾向としてきちんと基礎が出来ていて、なおかつ計算力があれば完答できる問題も一問はあるようです。さらに小問に分かれている問題があるときは、最初の小問は基礎的なことで解ける場合が多いようです。
とにかく物理はイメージが沸くかどうかなのだ。イメージがわけば、こむずかしい数式はいらない。微積分もいらない。数学に帰着させることもない。実際入試本番の問題というのは、微積分を使わなくても解けるような問題を出してくれている。使ったら回り道になりすぎて、時間以内に終わらないという悲惨なケースも多々ある。
「 問題は解けなくてもいいから僕の解答を読んで理解していって下さい。それで分からないところは僕の方が間違っているんじゃないかと批判的に見て下さい。そうやって考えて、それでも分からないところは何でも質問して下さい。それで、理解できたら今度解く時は解答を見ずに解く。それを繰り返して下さい。」
つまり、解答を読んで理解できることも1つの能力であるという事だ。考えてみれば、数学や物理ができない人の中には「解答を読んでもさっぱり分からない」と嘆く人が多い。解答を読んでも分からないのに自力で解く事ができるはずがない。東大レベルの難問を解くにあたっては、解答が読める能力が最低限必要なのである。
そうは言っても、解答を読み進んでいくと必ず疑問点にぶつかるはずだ。こういう疑問点は往々にして、問題のキーポイントとなっている。
東大レベルの問題には1題の中に様々なキーポイントが含まれており、解答を読む中できっちりとそのポイントを押さえておけば変化球にも対応できるのである。
化学はどう勉強するか。
まず、高校化学を3つに区分すると理論化学、無機化学、有機化学の分野に分けることが出来る。
1つ目の理論化学は3つの中で一番量が多く、大体全体の5割のウェイトを占める。内容的にも理解しにくいので、ここでつまずきやすい。しかし、この理論化学こそが科学の大切な基礎を成す分野であり、逆にここを乗り切れれば後はかなり楽にやって行けるということだ。乗り切るポイントは2つ。「想像力と反復練習」である。実は理論化学は原子や分子の振る舞いをテーマにした所が結構多く、これらの部分では想像力を逞しくして核の周りを飛び回る電子、結晶でぎゅうぎゅう詰めになっている原子、容器の中をびゅんびゅん飛び回り、内側に衝突する気体分子などの様子を頭の中で描ける様にしておくことが望ましい。これには図録が役に立つであろう。そしてイメージが湧くようになれば、一見難しい公式たちもその意味するところが理解できるようになるハズ。結局これらの公式というのは原子の挙動、または原子・分子の集まりに過ぎないマクロな物質の性質を記述する為のものでしかないのだから。そしてここまで理解が進めば、あとはそれらの公式を完全に使いこなせるようになるまで、ひたすら計算問題を解きまくるだけだ。“自分が今使っている公式が何を表現しているのか”ということを見失わないようにすれば、こなした問題の数だけ実力はアップしていくだろう。
次に無機化学であるが、ここは一番易しい分野である。量も化学全体の2割程度しかない、元素各論を除いた分野はほとんど理論化学分野の酸化還元反応と中和反応を中心とした復習に近い。ただ、理論化学と近い分、融合問題も出やすく、処理能力と計算力が問われる。そして元素各論については1人2人のプロフィールを覚えていく感じなので、ひたすらまとめノートを使ったりして楽しく覚えていけばよい。この分野は理論化学のしっかりした土台さえあれば1ヵ月集中的にやるだけでテストで9割狙えるようになります。
最後の有機化学は化学全体の中で3割程度を占めている。この分野、始めの頃はひたすらカタカナ語を覚えさせられる羽目になる。全ての物質名又は分類名なのだが、それほど大量にある訳でもないので大丈夫でしょう。量も大事なのは様々な官能基の性質とそれらが起こす反応を覚えることである。この分野は電気陰性度の考えを用いて電子の振る舞いに注意することで理解はぐっとし易くなります。ここでも理論化学の土台が効いているのです。先ほど官能基の性質を学ぶと言ったが、これはその官能基を持つ代表的な物質を用いて考えることになるので、官能基を一通り学び終えたときには、かなりの数の化学物質が頭に入っていることになる。そして最後の詰めとして、構造決定問題を大量にやること。しかも入試問題はこのパターンになることが大変多いので、しっかり数をこなすべきだ。なんだかやたらと問題数を多くやるべきだと主張してきたが、これは理解しただけでは点に直結しないからだ。処理のスピードと正確さが最終的にネックになるのだ。
・力学
微分方程式を知っていると、学習上少し有利になることを言っておきます。知らなくてもまったく問題はありませんが。
・熱力学
まあ、一番簡単な分野でしょう。少し公式を覚えた後、基本的には各状態においてすべての物理量を書けばすぐに答えが出ます。しかも間違いにくいです。
・電気
回路とかその辺の問題ですから、小学校の延長線上にあります。簡単でしょう。すぐに攻略できます。力学との融合問題になることが多々ありますが、落ち着いて力を出していけば簡単です。
・波動
抽象的で分かりにくく、頭から覚えることが多い分野ですが、三角関数の計算をきっちり身につけていればそんなに苦労することはないでしょう。波を考えるときは、いつも波長と速さと周期を考えるようにしましょう。
・電磁気
マジで難しい。たいていここで詰まります。しかも力学との融合問題が多く大変です。しかし、アンペールの貫流則を覚えておけばだいぶ楽になります。あとは力学の問題に変わりまる。自己誘導相互誘導は、一度基礎からしっかりと考えておくべきです。自分で公式の導出をしてみましょう。
・原子
がんばって覚えてください。ワンパターンな問題しか出ません。もっとも近年はほとんど出題がみられませんが。
化学の攻略法
・理論
公式を覚えるときにどうしてこの公式になるのかを考えるようにしましょう。あと、単純計算時のケアレスミスに注意しましょう。実際のところは目新しい題材を基にした割と簡単な応用問題が出ることが多いので、あきらめないで解読することがだいじです。
・無機
淡々と反応、沈殿を覚えましょう。覚えた知識は問題で確認しましょう。覚えて量がある程度超えると一気に答えられる問題が増えて、無機を勉強するのが楽しくなります。
・有機
覚えるべきことはそんなにありません。パズル的要素が強いので、そう思って楽しく勉強していきましょう。問題をぴったり解けたときは楽しいです。あと、高分子化合物は後回しにしてもいいでしょう。本当にただ覚えるだけですから。
京大は、現代文・擬古文・古文の大問3題から理系であれば好きなものを2題選択して解答するのだが、注目すべきはその解答用紙である。小問ごとに四角い枠があるだけで、数年前から行数指定のために枠内に破線が引かれるようになったが、基本的に全問題に字数指定はない。設問も大問3題とも「~について説明せよ」という曖昧なものがほとんどで非常に難解である。
それに対して東大は、現代文・古文・漢文の大問3題の出題で、京大と異なるのは漢字の書き取り問題が出るという点である。マニアックな漢字が出題されるわけではないので5点は確実に取れる。また、現代文では字数指定のついた要約が出題されるなど、設問自体に条件のついた問題が出ており取り組みやすい。更に古典では現代文以上に設問に条件がついている問題が多いし、基本的な文法知識があれば解ける問題で取り組みやすい。
このように、東大国語は基礎的な知識と少しばかり物を考えられる頭さえあれば合格点が取れる問題なのである。
にも関わらず、全国的に見た理系の受験生の国語能力は驚く程低い。いや、能力自体は低くはないのだろうが、国語の勉強をしている受験生が少ないのだ。
古文は現代日本語とは全く違う言語だし、漢文に至っては日本語ですらない。言ってみればこれらは英語に近い科目なのである。文法は一から覚えないといけないし、単語は全く新しいものが出てくるしと、設問として作文や並び替えが出題されないだけで新言語を学ぶ点では同じなのだ。受験生は英語で差がつなかいとでも思っているのだろうか?
理系だからとか、他の科目で点数取れるからとか高をくくらずに、せめてセンター国語で確実に8割取れる位の国語力はつけたい。先程も述べたとおり、東大の国語は易しいのだからそれ位の国語力でも十分である。
私に転機が訪れたのは受験半年前、出口汪先生の著者に出会ってからだ。出口先生の教えは、現代文を曖昧な科目ととらえず、正しい方法で勉強した者は必ず報われる科目である、と説く。その内容を全てここで紹介することはできないが、端的に言えば、書いてある内容を主観を入れずありのままに読む。筆者の主張をつかむ。筆者の主張は、具体例や比喩などを用いて、形を変えて繰り返される。だからそのたったひとつの主張をつかんだら、それを踏まえた上で、「重ねるように」読む。
さらに出口先生もやはり、読書と現代文の違いについて触れている。現代文の問題として出てくる文章は、何100ページもある本のごく一部が抜粋されているものなのだ。当たり前のことだが、それをよくよく意識しておかないとついつい本を読むときのように、主人公などに主観をいれまくって問題を読んでしまう。現代文という教科は解く人が解けば全員の答えが同じになる、非常に論理的な教科なのだ。主観を入れて、自分勝手に判断していたらこうはなるまい。文章中の表現だけが頼りなのだ。そこから客観的な判断をくだすから、一意的に答えが決まる。
記述式というのは、一見すると自由に自分の言葉で書いていいように思われがちだが(とくに要約など)、その実、長い文章からピンポイントで重要な部分を解答に盛り込まないと、部分点さえ中々もらえないようになっているのだ。実際、予備校の採点基準などを見ると、その文章のキーワードが書かれていなければ、たとえ答えとニュアンスがそっくりでも0点、もしくは大幅減点されていたりする。逆に自分でもよくわからないまま適当に解答を書いてしまっても、キーワードが入っているだけで案外点数が取れてしまったりする。
このように国語は、当たればでかいが当たらないとさっぱりという、ある種博打のような性質を持っているので、試験が終わっても自分でどれくらい点数を取れたか、見当をつけるのは難しいと言える。
その証拠に、数学や英語で全国上位を取る人たちは、毎回大体決まっている常連たちである。しかし国語はどうか。上位の名前がころころと変わるではないか。
実際、東大の文系ですら勝負は点差の開く80点満点の数学で決まってしまうことが多いと聞く。
文系ですらこうなのだからましてや、理系はもっと数学重視であろう。
現代文で要求されていることは、大きく分けて「これはどういうことか」と「なぜこのように言えるのか」の2パターンである。そのヒントや答えはすべて課題文の中に書いてある(そうでなかったら問題として成り立たない)“それらを探し出すことができれば、基本的には満点になる”ということだ。
これまで読書をほとんどしてこなかった人はどう対処すればよいのか。やはり、問題を解くことに尽きる。
せいぜい、大きく失点しない程度の内容だった。満点の取り方は知らないが、部分点を稼ぐ方法ならある程度知っているつもりだ。
その秘訣は、主語、理由を付け加え、本線の部分を明確にすることである。この方法は某予備校講師が言っていた方法で、これを習得してからは大幅な失点はしなくなった。
次に本番での時間配分について。国語は現代文、古文、漢文があり、古文、漢文のほうが短時間で解答することが可能だ。そのため、“古典を先に処理して、時間のかかる現代文を後回しにしたほうがいい”とされている。国語に限った話ではないが、簡単にできるものを先にやっておいたほうが精神的にもいいような印象を受ける。
②【感想など】
・東大理Ⅲ合格者の話は、頭の良さの次元が全く違うので参考にならないかと思ったりしていたが、非常に合理的で無駄がなく、通常の受験生にも適用できる有益な話が多かった。
・しかしながら、大学受験も東大レベルになってくると重視すべきことは違ってくる。
・理数系科目では、基本とは何か、本質とは何かをとことんまで追及することが必要である。真の理解に至るため、全ての定理、公式の歴的背景、意義を踏まえた上で、その証明や導出方法を身につけ、さらにそれを縦横無尽につかいこなす応用力が必要となってくる。
そして、問題の解答に当たっては、すぐに方針が立つものは少なく、あれこれ実験や試行錯誤の上、ひらめくことが多い。さらに、計算力などヘビー級の問題が多数を占め、試験時間の150分はまさにスポーツ的とも言えるとのことである。
・一方、国語も点がもらえたらもうけ的な発想で全く手をつけないという考え方ではなく、まずは、英語といった外国語学習のように取り組め比較的点数の取りやすい漢文、古文を攻略して、現代文の失点を防ぐやり方がよいとのことである。
・色々と批判もある大学受験制度ではあるが、ここは考え方を変えて、限られた時間内での効果的な成果が得られる処理法などを工夫することや、他方で、物事を深く追求するきっかけとなるよう取り組んでいくことは、将来仕事をしていく面でも十分、基盤力となると思われる。
③【今後、考えてみようと思うこと、実行してみようと思うこと】
・受験勉強をアスリート的に取り組んでみたらどうなるか。
・各科目において、得られた知見、成果(原理、定理、公式など)の歴史的背景や意義を調べ、その証明や導出に踏み込むこと。
・ミスをおかさず、重量級の計算力はどうやったら身につけることができるか。
【この本のAmazonへのリンク】











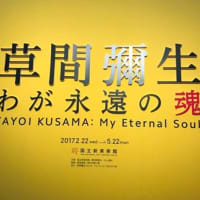






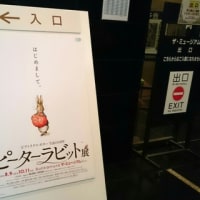

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます