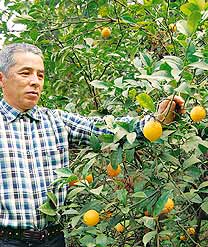だいぶ時間が経ってしまったのですが、僕も委員(パネリスト)のひとりとして参加させてもらった農水省主催の有機認証制度に関する会議についてご報告します。2010年2月9日(火)の14時から17時まで、農水省の第2特別会議室において「有機JAS規格に関する意見交換会」が開催されました。http://www.maff.go.jp/j/jas/kaigi/yuuki_iken_100209.html
だいぶ時間が経ってしまったのですが、僕も委員(パネリスト)のひとりとして参加させてもらった農水省主催の有機認証制度に関する会議についてご報告します。2010年2月9日(火)の14時から17時まで、農水省の第2特別会議室において「有機JAS規格に関する意見交換会」が開催されました。http://www.maff.go.jp/j/jas/kaigi/yuuki_iken_100209.html 日本には、有機食品の表示に関する有機認証制度(有機JAS制度:2000年~)があります。この法律により、国内で有機野菜・有機加工食品・有機畜産物等のオーガニック食品を生産、製造、販売する場合には商品に「有機JASマーク」を貼付しなければなりません。このマークを貼付するには、オーガニック食品の生産、製造、小分け(販売)、輸入に関わる事業者が有機認証団体(農水省の登録認定機関)による検査・認定を受ける必要があります。そして、有機食品を生産する方法に関する生産基準は「有機JAS規格」に規定されています(以下は登録認定機関「JONA」の有機JAS情報へのリンクです)。http://jona-japan.org/certified/#a01
日本には、有機食品の表示に関する有機認証制度(有機JAS制度:2000年~)があります。この法律により、国内で有機野菜・有機加工食品・有機畜産物等のオーガニック食品を生産、製造、販売する場合には商品に「有機JASマーク」を貼付しなければなりません。このマークを貼付するには、オーガニック食品の生産、製造、小分け(販売)、輸入に関わる事業者が有機認証団体(農水省の登録認定機関)による検査・認定を受ける必要があります。そして、有機食品を生産する方法に関する生産基準は「有機JAS規格」に規定されています(以下は登録認定機関「JONA」の有機JAS情報へのリンクです)。http://jona-japan.org/certified/#a01

 ■ヨーロッパ有機認証制度の歴史
■ヨーロッパ有機認証制度の歴史
日本では、2000年に有機JAS法と呼ばれる「有機農産物及びその加工食品に関するJAS規格」が施行されて、2001年にオーガニック食品の検査認証制度が実施されました。2005年には「有機畜産物及び有機飼料のJAS規格」が制定されました。これは、1999年の国際的な「オーガニック基準(有機食品の生産、加工、表示及び販売に係るコーデックスガイドライン)」の制定を受けてのことです。「コーデックス(国際食品規格)委員会(本部:イタリア・ローマ)」とは、FAO(国連食糧農業機関)とWHO(世界保健機関)が設置した、消費者の健康を保護し、食品の公正な貿易を確保するための政府間組織です(※以下はコーデックス有機ガイドラインの農水省による邦訳です)。
http://www.maff.go.jp/j/syouan/kijun/codex/standard_list/pdf/cac_gl32a.pdf

 ヨーロッパでは、1980年代からEU加盟各国の有機農業団体が自ら有機認証団体を作って、有機農業が環境に優しい農業であることや有機農産物やオーガニック食品の優位性に関して、自らの有機認証マークの宣伝活動を通じて消費者にアピールしてきました。代表的な有機認証団体は、イギリスのソイルアソシエーション(英国土壌協会)やドイツのビオランドやデメター、フランスのエコサートなどが挙げられます。これらの有機認証団体が有機農産物やオーガニック食品の安全面・健康面・環境面での貢献を消費者に対してPR活動やマーケティング活動、普及啓発活動を積極的に展開してきたことが原動力となってヨーロッパのオーガニック食品市場を盛り上げてきました。
ヨーロッパでは、1980年代からEU加盟各国の有機農業団体が自ら有機認証団体を作って、有機農業が環境に優しい農業であることや有機農産物やオーガニック食品の優位性に関して、自らの有機認証マークの宣伝活動を通じて消費者にアピールしてきました。代表的な有機認証団体は、イギリスのソイルアソシエーション(英国土壌協会)やドイツのビオランドやデメター、フランスのエコサートなどが挙げられます。これらの有機認証団体が有機農産物やオーガニック食品の安全面・健康面・環境面での貢献を消費者に対してPR活動やマーケティング活動、普及啓発活動を積極的に展開してきたことが原動力となってヨーロッパのオーガニック食品市場を盛り上げてきました。
![]() 上記のような有機農業団体の連盟として設立された「IFOAM(アイフォーム:国際有機農業運動連盟)」は、1980年に各構成団体のオーガニック基準と有機認証に関する現場で豊富に蓄積された経験をベースに「IFOAMオーガニック基礎基準」を策定しました。このオーガニック基礎基準(有機基準を作るための基準)は、世界各国の政府や有機認証団体による基準や検査システムを構築するための国際ガイドラインとして尊重されてきました。
上記のような有機農業団体の連盟として設立された「IFOAM(アイフォーム:国際有機農業運動連盟)」は、1980年に各構成団体のオーガニック基準と有機認証に関する現場で豊富に蓄積された経験をベースに「IFOAMオーガニック基礎基準」を策定しました。このオーガニック基礎基準(有機基準を作るための基準)は、世界各国の政府や有機認証団体による基準や検査システムを構築するための国際ガイドラインとして尊重されてきました。
http://blog.goo.ne.jp/masayakoriyama/d/20080907

![]() その後、オーガニック市場が発展するにつれて、有機表示のある商品が高く売れる状況になると、有機食品の偽装表示が横行するようになりました。そのような事態を受けて、消費者と生産者を守るために、EU加盟各国において法律で検査認証を義務付けるオーガニック食品の表示規制が導入されました。例えば、フランスでは1988年に有機認証制度がスタートしました。
その後、オーガニック市場が発展するにつれて、有機表示のある商品が高く売れる状況になると、有機食品の偽装表示が横行するようになりました。そのような事態を受けて、消費者と生産者を守るために、EU加盟各国において法律で検査認証を義務付けるオーガニック食品の表示規制が導入されました。例えば、フランスでは1988年に有機認証制度がスタートしました。 このことは、1990年代に入って、EUレベルでも実現しました。それがEUオーガニック基準に基づいて1992年に施行された「農産物の有機的生産ならびに農産物及び食品の表示規則[EEC/2092/91]」の導入です。この法律により、商品の生産過程がオーガニックであることを検査し、認証された生産物しか有機農産物と表示できないことを規則で決めた有機認証制度が導入されました。そして、この制度による生産工程の保証が消費者のオーガニック食品に対する信頼を獲得して、オーガニック市場の急成長の後ろ盾となったのです。そして、90年代には生協や大手のスーパーマーケットなどが有機食品を積極的に販売してオーガニック市場の拡大を牽引しました。特にイギリスでは、90年代後半から2大スーパーチェーンがそれぞれ独自のオーガニックブランドを立ち上げて数百アイテムの有機食品を販売しています。このように、EUでは民間のオーガニックセクターが有機認証制度の導入などを通じて有機食品の普及啓発と市場開拓をしてきたのです。
このことは、1990年代に入って、EUレベルでも実現しました。それがEUオーガニック基準に基づいて1992年に施行された「農産物の有機的生産ならびに農産物及び食品の表示規則[EEC/2092/91]」の導入です。この法律により、商品の生産過程がオーガニックであることを検査し、認証された生産物しか有機農産物と表示できないことを規則で決めた有機認証制度が導入されました。そして、この制度による生産工程の保証が消費者のオーガニック食品に対する信頼を獲得して、オーガニック市場の急成長の後ろ盾となったのです。そして、90年代には生協や大手のスーパーマーケットなどが有機食品を積極的に販売してオーガニック市場の拡大を牽引しました。特にイギリスでは、90年代後半から2大スーパーチェーンがそれぞれ独自のオーガニックブランドを立ち上げて数百アイテムの有機食品を販売しています。このように、EUでは民間のオーガニックセクターが有機認証制度の導入などを通じて有機食品の普及啓発と市場開拓をしてきたのです。
このEUのオーガニック食品表示規制の導入にはIFOAMが大きな役割を果たしました。そして、EUのオーガニック基準も上記の「コーデックス有機ガイドライン」もIFOAMのオーガニック基礎基準を参考として策定されました。IFOAMはコーデックス委員会の公式なオブザーバー資格を持ち、有機ガイドラインの策定過程からその後の定期的な改訂にも関与しています。http://blog.goo.ne.jp/masayakoriyama/d/20080907
 ■有機JAS規格に関する意見交換会
■有機JAS規格に関する意見交換会
前置きが大変長くなりましたが、意見交換会には、農水省から消費・安全局 表示・規格課長小川良介さん(当時)、同有機食品制度班課長補佐の島﨑眞人さん、有機農業推進法を担当する生産局の農業環境対策課から有機農業推進班 課長補佐の堀川昌昭さん(当時)と畜産部畜産規格課の野方博幸さんが参加されました。オブザーバーとしてオーガニックコスメやコットンを担当する経経済産業局繊維課の方なども参加されていました。また傍聴席には、有機農業に関わる生産者や加工メーカー、マスコミ関係者や研究者、有機認証団体の方などが列席されていました。
 この意見交換会に、有難いことに僕もIFOAMの国際理事として参加させてもらいました。そして、なんとお隣は東京の表参道で長らくオーガニックショップの「クレヨンハウス」を運営されている作家の落合恵子さんでした!クレヨンハウスでは30年前から、有機野菜やオーガニック食品、オーガニックコットンやコスメやシュタイナー教育のおもちゃなども販売しています。店内にはオーガニックレストランもありますし、子どもの本や女性の本、環境問題などオルタナティブなテーマの書籍が並ぶ書店も併設しています。実は個人的にクレヨンハウスのファンだったので、うれしくて思わず初対面の落合恵子さんにあれこれ話しかけてしまいました。http://www.crayonhouse.co.jp/home/index.html
この意見交換会に、有難いことに僕もIFOAMの国際理事として参加させてもらいました。そして、なんとお隣は東京の表参道で長らくオーガニックショップの「クレヨンハウス」を運営されている作家の落合恵子さんでした!クレヨンハウスでは30年前から、有機野菜やオーガニック食品、オーガニックコットンやコスメやシュタイナー教育のおもちゃなども販売しています。店内にはオーガニックレストランもありますし、子どもの本や女性の本、環境問題などオルタナティブなテーマの書籍が並ぶ書店も併設しています。実は個人的にクレヨンハウスのファンだったので、うれしくて思わず初対面の落合恵子さんにあれこれ話しかけてしまいました。http://www.crayonhouse.co.jp/home/index.html
今回、検討会への参加の打診をいただいた時には、通常の会議のように「委員」という名前でしたが、より多くの人に参加をしてもらい、会議を公開のものとするために、意見を聞かれる委員は「パネリスト」という名称(位置づけ)になったようでした。この手の会議には関係者が傍聴できるパターンが多いのですが、今回は関心の高いテーマだけにかなりの応募があったようで、知り合いの有機農家の方は、「事務所の5人で応募してやっとひとり参加できた」と話されていました。何倍の競争率だったかはわかりませんが、マスコミの取材を含めて100人弱の参加者があったと思います。検討会に参加されたパネリスト皆さんは以下の通りです。
【パネリスト】
(社)栄養改善普及会 理事 粟生美世氏
消費科学連合会 井岡智子氏
(財)自然農法国際研究開発センター 認定事務局長 今井悟氏
(独)農林水産消費安全技術センター(FAMIC) 規格検査部長 植木隆氏
クレヨンハウス 代表 落合恵子氏
IFOAM(国際有機農業運動連盟) 世界理事 郡山昌也氏
毎日新聞生活報道部 編集委員 小島正美氏
光食品株式会社 代表取締役社長 島田光雅氏
JA加美 よつば有機米生産部会長 沼太一氏
(特活)日本オーガニック&ナチュラルフーズ(JONA)協会 理事長 松本憲二氏
(特活)日本オーガニック検査員協会(JOIA) 理事長 丸山豊氏
主婦連合会 会長 山根香織氏
ワタミ株式会社 代表取締役会長 渡邉美樹氏
 今回の「有機JAS規格に関する意見交換会」のテーマは以下の4つでした。
今回の「有機JAS規格に関する意見交換会」のテーマは以下の4つでした。
【課題1】「世界の先進国に比べ、日本の有機生産が伸びない理由は?」
【課題2】「2005年に導入した有機畜産物がほぼ生産されない理由は?」
【課題3】「有機JAS規格の名称の表示の規制は充分か?」
【課題4】「同等性認定について、今後どのように実施するか?」
検討会では冒頭に消費・安全局 表示・規格課長の小川良介さんから会議の趣旨の説明がありました。小川課長は、ヨーロッパなど海外のオーガニック事情にも通じていて、この間はEUとの「同等性認定」に関して尽力されてきました。それに続いて有機食品制度班課長補佐の島﨑眞人さんから、配布資料を使って①「有機JAS制度を巡る現状について」②「有機JAS制度における課題」について報告がありました。主な内容は以下の通りです。詳しい報告内容については、配布資料を以下のページから見ることができます。http://www.maff.go.jp/j/jas/kaigi/yuuki_iken_100209.html
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
①有機JAS制度の現状については…
・日本の有機食品市場が非常に小さい(※以下、1ユーロ=160円で市場規模を計算:約150億円、ドイツ約8500億円、アメリカ約2兆1300億円、ヨーロッパ約2兆6000億円)。
・日本の有機圃場面積は非常に小さい(※全農地の0.18%:日本約9万ha、中国155万ha、ブラジル177万ha、アルゼンチン220万ha、EU776万ha)
・格付けは外国産の有機農産物が多い(※格付け量=輸入量ではない)
・格付けは外国産の有機農産物ではサトウキビの割合が高い(約7割)
・オーガニック加工食品は外国産と国産が同程度の量
・国内の有機畜産の現状(有機牛、豚、鶏)
・日本が有機農産物に関する有機農業認証制度を同等と認めている国
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/100623.html
②有機JAS制度における課題については…
○2008年度の有機農業総合支援対策による「消費者調査報告書」から。
・消費者の有機JASマーク認知度はまだ低い。
・有機農産物を購入している消費者は、「値段が高い」「品揃えが少ない」と考えている。
・有機農産物を購入していない消費者も、「価格が高い」「どこで買えるかわからない」と考えている。
○2007年度「有機農業や環境保全型農業に関する意識・意向調査」から。
・流通加工業者は、有機農産物を「安全な農産物」、「消費者が求めるもの」と考えている。
・5割の農業者が有機農業に取り組みたいと思っている。