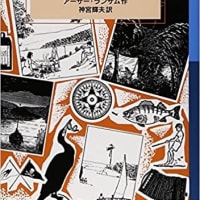ランサムは1918年の秋から1919年のはじめごろまでをMI6のために諜報活動を行っている。それまでも、ロシア特派員として情報提供に協力していたが、正式に諜報部員として雇われたのは、この期間ということらしい。
ランサムは1918年の秋から1919年のはじめごろまでをMI6のために諜報活動を行っている。それまでも、ロシア特派員として情報提供に協力していたが、正式に諜報部員として雇われたのは、この期間ということらしい。
 もろもろの事情もあって、ランサムはロシア行きを決行するのだが、ロシアに滞在していた時期に、第一次世界大戦が勃発し、ロシア革命が起こった。たまたまロシアにいたランサムは、「デイリー・ニューズ」という急進的新聞の特派員として活動を開始する。
もろもろの事情もあって、ランサムはロシア行きを決行するのだが、ロシアに滞在していた時期に、第一次世界大戦が勃発し、ロシア革命が起こった。たまたまロシアにいたランサムは、「デイリー・ニューズ」という急進的新聞の特派員として活動を開始する。
生来、誰とでも友だちになれる才能をもっているランサムは、トロツキー、ラデック、レーニンなど、ボルシェビキの要人たちとも親しく交わり、政治の世界にどっぷりつかっていく。トロツキーの個人秘書だったエヴゲーニヤ・ペトロヴナ・シェレピナとは恋愛関係となり、後に結婚することになる。
その中で、母国の需要に答えるべく、スパイ活動を行うのだが、ランサムがとった行動は、イギリスとロシアの友好の橋渡しをしたいという一念だったように思われる。
『アーサー・ランサム自伝』(神宮輝夫訳・白水社)は十三冊目のランサム・サーガといわれるほど、読み応えのある物語に仕上がっている。これを読めば、アーサー・ランサムがどのような思いで、政治の世界を泳いでいったかが、よくわかる。 こんなエピソードがある。
こんなエピソードがある。
ランサムはロシアでの諜報活動を切り上げ、1919年3月にロンドンのキングスクロス駅にたどり着いた。ホームで記者を降りるランサムを待っていたのはスコットランド・ヤード。彼はそのまま黒い服に山高帽をかぶった男に連行され、警視庁に赴いた。警視総監のバジル・トムソン卿の尋問を受けるためだった。
ランサムはロシアの革命推進派のボルシェビキに共感する立場を貫いていたので、ボルシェビキのスパイではないかという誹謗が他の諜報員からしきりに寄せられていたのだ。
「私はバジル・トムソン卿の部屋に通され、今までに数多くの犯罪者がすわったことで有名ないすにすわらされた。バジル卿は、きわめてむっつりとした顔で、私をじっと見据えた。ちょっと二人とも押し黙っていたが、すぐに彼は言った。
『さて、あなたの政見をちょっと知りたいのです』
『釣りですよ』
彼はびっくりして目を丸くした。
『それはいったいどういう意味ですかな?』
私はありのままに、自分がイギリスでは何の政治的意見もいだいたことはないこと、ロシアでは、この事実のおかげで革命についてはるかに明瞭な見解を持つことができたと思っていること。現在はたった一つ、干渉は破滅的なあやまちだというはっきりした意見をもっていること。そして、干渉が終わり、私が平常な仕事にもどれるようにのぞんでいることを述べた。
『釣り?』と、彼はいった。
『もうすぐシーズンですからね』」(自伝より) このあとランサムとトムソン卿はすっかり親しくなったそうだ。
このあとランサムとトムソン卿はすっかり親しくなったそうだ。
彼がいかに際どいところで活動し、さらに人と打ち解ける才能に優れていたかがよくわかるエピソードだ。 彼は人生の前半を、数々の危険をかいくぐって生きてきた。
彼は人生の前半を、数々の危険をかいくぐって生きてきた。
人生はハードだ。
だからこそ彼は、後になって、子どもの頃の休暇の輝くばかりの楽しさを、それだけを抽出して描いてみせたのだ。
大人になったら、もうそれどころじゃない、無心な、長い、光に包まれた日々。人生を豊かなものにしてくれる「休暇」という楽しい時間。
その時間に、読者はランサムの物語を読むことで、ひたりきることができる。『ツバメ号』のシリーズが、いまでも人びとに愛され続けている理由は、そこにある。
最近の「アーサー・ランサム」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
- ジブリノート(2)
- ハル文庫(98)
- 三津田さん(42)
- ロビンソン・クルーソー新聞(28)
- ミステリー(49)
- 物語の缶詰め(88)
- 鈴木ショウの物語眼鏡(21)
- 『赤毛のアン』のキーワードBOOK(10)
- 上橋菜穂子の世界(16)
- 森について(5)
- よかったら暇つぶしに(5)
- 星の王子さま&サン=テグジュペリ(8)
- 物語とは?──物語論(20)
- キャロル・オコンネル(8)
- MOSHIMO(5)
- 『秘密の花園』&バーネット(9)
- サラモード(189)
- メアリー・ポピンズの神話(12)
- ムーミン(8)
- クリスマス・ブック(13)
- 芝居は楽しい(27)
- 最近みた映画・ドラマ(27)
- 宝島(6)
- 猫の話(31)
- 赤毛のアンへの誘い(48)
- 年中行事 by井垣利英年中行事学(27)
- アーサー・ランサム(21)
- 小澤俊夫 昔話へのご招待(3)
- 若草物語☆オルコット(8)
バックナンバー
人気記事