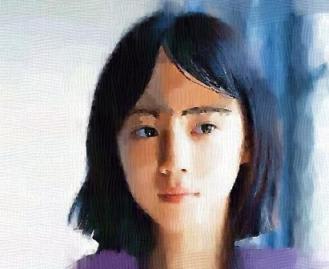紅白の草履

1
オヤ―?
修三さまは首をのばした。一ツ向方(むこう)の入り口から乗ったのはたしかにチビくん。やっぱり同じ様に小っちゃな子と二人連れで、丁度学校の退け時で、どっちを向いてもギュウギュウ詰めの省線の中、乗ったかと思ったら次の瞬間、人混みの中にもぐって見えなくなって了った。
「ごめんなさい」修三さまは人混みをわけてそっちの方へ突進して行った。
「ア」
やっぱりチビくんだった。目の前にヒュッと現れた修三さまの顔を、ビックリしたみたいに見て、あわててピョコンと頭を下げた。
「やっぱりチビくんだったんだナ。僕向方の入口から乗ったんだけど、たしかそうだと思って突進して来たんだヨ―すっかり立派な女学生になったね」
修三さまが感心した様に云うと、チビくんは恥しそうに目をほそくして首をまげた。
チビくんは女学生である。紺色のフェルトの帽子をかぶって、白いブラウスに紺じょジャンパー、人混みにおされて落しては大変と、シッカり小脇にかかえているのは真赤なビロウドの手提カバン。修三さまはチビくんを連れて女学校へ試験を受けに行った三月の時を思い出した。どこでもいいから女学校に入れてやりたいんですけれど―とチビくんのお母さんが相談しに来た時は、三月ももう半ばすぎで大ていの女学校は試験がすぎて了った後だった。それにチビくんは小学校を出てから一年遊んでいるので―。
「パパ、あすこどうです?あすこなら外の女学校みたいにうるさくなくて、それでいて中々いい学校だと思うけどなア―」修三さまがパパさまに声をかけた。
「ああ、小野さんのとこか、そうだねエ」
いいところに気がついた、と云わんばかりにパパさまはおうなずきになった。
小野さんとこと云うのは、パパさまの親友のやっている女学園であった。人数は少いけれど、生徒一人一人について、親切にゆきとどいた教育をしてくれると云うので有名な女学校だった。
修三さまはチビくんを連れて早速その小野女学園に行った。ここでは大勢集めて入学試験をするのではなくて、一人一人園長の小野先生と向いあって交差を受けるのだった。新しいメリンスの着物を着て、チョコンと小野先生の前に腰かけて、目を真円(まんまる)くしていたその時のチビくんの姿を考えると、修三さまはなんだかズッと遠い昔の事でも思い出す様なほほえましさを感じた―
「毎日楽しいかい、女学校生活は…?」
チビくんはコックリした。
「お母さん、元気かい?此の頃一寸も家へ遊びに来ないねエ。遊びにおいでよね、とても利恵子が淋しがってるよ。居たときはいじわるばっかりしてたくせにね…」
電車が駅へとまって一しきりドヤドヤと人が出たり入ったりした。そして又走り出した。
「どこへ行くの?」
「あのね、あの、神田へ買物に…」
「ヘエ。生(なま)ちゃんだナ、もう神田へ行くこと覚えたのかい?」
「これ、買いに行くんです」
チビくんは真赤になって何やらカバンの中からひっぱり出した。
紅と白の小さい草履だった。
「何だい、それ?」
「手芸でこさえるのよ」
チビくんのお隣に居たチビくんよりもっと小さいお友達が口を出した。
「お机の上のかざりにもなるし、そいからペン先ふきにも吸い取紙にもなるのよ、ホラ、ね、ここんとこがプカプカになってるでしョ、ここんとこへ吸い取紙をはっとくの」
そのお友達は紅白の草履の裏をひっくりかえして、紅と白をたたんだ所をプカプカさせて説明した。
「これの材料、神田でなきゃ売ってないんですって、ですから今日高木さんと買いに行くとこなんです」
一寸でもよごしては一大事と云う様に、チビくんは草履を又元の通りカバンにしまい込んだ。
「一つ出来てるじゃないか」
「もう一足こさえるんですって、そしてある人におくりものにするんですって」
高木さんが又側から知ったかぶりで説明した。
「ホオ、ある人に、おくりものにすんの、ウワー、凄え事云ってるなア」
修三さまは高木さんの云い方があんまりおませなので、おかしくなって思わず笑って了った。チビくんはだまって笑っていた。
「じゃ、失敬。本当に遊びに来たまえ、ね、待ってるからね」
電車は、修三さまの愉快な笑い顔を残して走り出した。
2
修三さまがお家の玄関に入って編上靴のヒモを解いていると、奥の方からお母さんの声がきこえた。
(アレ、お母さん、怒っているのかナ?)
大いそぎで靴をぬぐとお茶の間へ入って行った。しかしお茶の間には誰も居ない。
「そんなこと云ったって、仕様がないじゃありませんか?」
勉強部屋から又一きわ高いお母さんの声がきこえて来た。
(利イ坊め、又何か我まま云って怒られてるんだナ)
修三さまは悠然と勉強部屋へ入って行った。
「ウワー、何だい、こりゃア?」
お部屋の中は大さわぎである。本棚から雑誌と云わず本と云わず全部ぬき出して、そこいら中に放り出されている。本箱のガラス戸はあけっ放しで、絵草子箱も神人形のタトウもゴッチャになっている。ランドセルの上に紙につつんだビスケットが投げ出されている、その中で利イ坊さまはくの字形に坐って、お顔に八の字形に両手をあてて泣いている。お母さんは、と見ると衣桁(いこう)によりかかる様にして、怒った様な顔で立っていらっしゃる―
「どうしたんです、ええ、お母さん?」
「いいえ、又いつもの我ままなんですよ、―本当に此の人にも困っちまう。どうしてこうなんでしょうね。お母さん、もう情けなくなっちゃうわ―」
もうサジを投げた、と云う様子でお母さんは眉をくもらせて、ホーッと吐息。
「それにしても、このさわぎは一体全体何事じゃ、ウン、利恵子?ヒスか、あんまりヒステリイ起すんじゃないよ、子供のくせに」
面白可笑しい調子で修三さまは此の場の空気を中和しようと、利イ坊さまの泣きじゃくっている肩に手をかけた。
「いやんッ!」
利イ坊さまはじゃけんにふりはなした。
「修三、ほっておきなさい。いいえ、もう今度と云う今度は容赦しません。パパが帰っていらしたらよく御相談して、小岩の叔父様のとこへ預けますからね」
「ヤーン」一しきり利イ坊さまは声をはり上げた。小岩の叔父様と云うのは利イ坊さまの大の苦手である。御家は淋しい林の外れにポツンと建っていて、夜になるとフクロが啼くし、電車の駅まで行くには十五六町もある。それに叔父さまの恐いことったら、利イ坊さまなんかがお鼻をならしたってビクともするものではない。一昨年の夏、一週間程お泊りに行って居る中、二度も暗いお倉の中に放りこまれた恐しい経験があるのである。だから小岩の叔父さまときくと、利イ坊さまはブルブルッとふるえた。
「一体どうしたんですヨ、お母さんも利恵子も怒ったり泣いたりばかしして居ちゃ、僕たるもの仲裁が出来んじゃないですか…」
それでもお母さんは何にも云わず怒った顔で利イ坊さまをにらんでいらっしゃる―
「オヤ、いつの間にお帰りになりまして。どうか、何とかおっしゃってあげて下さいましよ、ね」
みねやが顔を出して、修三さまの顔を見ると助けの神よ、とばかりにすがりつく様に云った。
「だからさ、一体全体どしたんだ、ってきいてるんだけど、敵も味方もコーフンしきっていて駄目なんだよ」
「いえね、お嬢さんがね、又例の通りなんですけど…はじめね、学校から松平さんと帰ってらっしゃってね、ガラス紙だか何か差しあげるお約束だったらしいんですね、そしたらどこを探してもないんでございますって。みねやもご一緒になって探して差しあげればよかったんですけど、つい、お洗濯しかけだったもんですから―」一寸みねやはベンカイした。
「そいで…?」修三さまはせかした。
「その中に松平さんはお帰りになって了ったんですよ。その時『ウソつきね。ガラス紙三十枚も持ってらっしゃるなんて。あたくし、はじめっからウソだと思ったわ』っておっしゃったんですの。だもんですから余計やっきになって、これこの通りどこもかしこもひっかきまわして探してごらんになったらしいんですけど、どうしてもないんでございますって…。そこへ奥さまが御買物から帰ってらして、お八ツを紙につつんでもって入ってらしたら、この大さわぎなもんで、お怒りになったんですの、そしたら…」
「初子を呼んで来てくれ、と云うんですヨ。どうせどこかにあるんだからもっと気をおちつけてよーく探してごらんなさい、と云うんだけど、どうしても初子を呼んで来て探さしてくれなきゃいやだ、とこうなのよ。ねエ、兄さん、そんな我ままッてないでしょう」
お母さんはヤヤ興奮のしずまったらしい顔で、訴える様に修三さまの顔を見た。修三さまはフと、チビくんがいつも利イ坊さまのちらかした後をだまって、きれいに片づけていた頃の事を思い出した。
「チビくんが帰ってからもう一カ月以上もたってるじゃないか、その間にもう二度も三度も君出して見たんだろう?だから君がどこかへしまい忘れてるんだよ。今更チビくんを呼んで来たって仕様がないじゃないか―今迄自分で後片づけしなかったから、チビくんが居なくなったらその通りだ、バチがあたったんだよ」
お母さんは、足許に散らばっている本をまとめ出したが、フト気がついた様に、
「利恵子、これ、みんなお片づけなさい。自分が散らかしたものは自分で整とんする癖をつけなきゃ駄目です。いいですか、キチンと片づけるんですよ。もし云う事をきかないと、それこそ本当に小岩の叔父さんを呼びますからね―」
「さ、利イ坊さま、みねやが手伝ってあげますから、片づけましょう―」
みねやはさすが気の毒と思って、まわりの物を片づけ出した。
「みねや、放っておきなさい、よござんすったらッ―」
みねやは奥さまのきつい声に渋々手をやめて了った。
「もう五時ですヨ、御台所はいいんですか」
お母さんの後からみねやもつづいてお部屋を出て行って了った。―
「利イ坊、君、チビくんに逢いたいんだろオ?君のヒスのわけ、ちゃんとわかってるんだ。わかるともさア。こんなカンタンな精神分析が出来んようではあかんわ。ワシャ将来イ社になるんじゃから喃(のう)」キエンをあげ乍ら修三さまは、静かになった利イ坊さまの背中を軽く叩いた。
「今日、省線の中で逢ったよ、チビくんに。とても可愛い学生さんになっていたよ」
「アラ」と云う様な顔で、利イ坊さまは顔をあげた。眼が真赤、ついでに小っちゃいお鼻まで桜ん坊みたいに赤くなっている。
「ヤア、御機嫌が直って来たナ―あんまりすねるんじゃないヨ、いいかい?チビくんに逢いたければ、そうハッキリ云えばいいじゃないか。君は何でもすねるから物事がコンガラかっていかんよ。小っちゃいくせに君は非常にフクザツなる感情性格の持主じゃね。そう云うのはフロイドの精神分析法から診察すると、エエと―」
修三さまは或医科大学の予科に入ったので、此の頃は何でもこの調子で片づけようとする。
「チビくん、あそびに来る、って云ってた?」利イ坊さまは、雑誌の折れたのをソッと直しながら小さな声できいた。
「ああ、そ云っといた、是非是非近い中に来い、って。何だったら至急ハガキ出してあげようか、利恵子のガラス紙が行方不明につき至急御捜索をたのむ、って―」
「ハガキ、ある?」利イ坊さまは本気である。
「買って来なきゃないよ、生憎と」
上着のボタンを外しながら、修三さまは(そんなにチビくんに逢いたいかナ、あんなにイジワルばっかししてたくせに)と一寸その子供心がいじらしくなった。
「お母さまにお金いただいて、あたし買ってくるわ―」
利イ坊さまは、バタバタと廊下へとび出して行った。
「―なくて人の恋しかりける、か。昔の人は矢張り上手い事を云ったなア―」上着を衣桁(いこう)にかけると修三さまは、ヨイショとしゃがんで散らかった本や雑誌を片づけはじめた。
利恵子が、ガラス紙が行方不明になったので、探してもらいたいと云っています。是非家へ来て下さい。先(まず)は至急右御願いまで。
修三拝
追伸
ア、ガラス紙は机の抽斗しから出て来た相です。でもガラス紙はあっても是非来て下さい。お友達がなくて毎日毎日淋しがっています。たのむタノム。
3
修三さまからのハガキを枕の下へ敷いてから、もう一週間以上も経って了った。
早く行きたい、お土産の草履は出来たし、一体どうしたのかしら?と修三さまは不思議に思っていらっしゃるんだろうし…チビくんは床の中で、中々治らない風邪を焦れったく思っていた。風邪をひいてからもう十日位になる。風邪をひいたのは利イ坊さまにプレゼントする紅白の草履をこしらえるために夜更かしをしたからだった。手芸の時間、先生が白いネルのキレと真赤な絹の布(きれ)をノリで張り合わせ乍らおっしゃった。
「私はね、小さい時叔母さんの家に居たの。とても意地悪のいとこが居てね、私も強情っぱり、いとこも強情っぱりだったので毎日喧嘩ばかりしていたのよ。ところが十八のそのいとこはお嫁さんに行く事になったの。お嫁に行く前の晩、いとこが私のところへ来てそ云ったの、『長い間意地悪してごめんなさい。私もう行くわ』ッて。そしたら普段とても憎らしいと思っていたいとこが急になつかしくなって、私涙がこぼれて来たの。二人はしばらく手をとりあって泣いてたのよ。そしたらね、いとこがね小さな草履を出して記念にくれたの。今でもその草履もっているわ、そして見るたんびに小さかった時の事やいとこの事を想い出しているの。いいものね、一寸した贈り物でもいつまでもその人の事を記念する様になるんですもの。貴方たちもせいぜいキレイにこしらえて仲のいい方に贈るといいわ―」
その御話をきいた時、チビくんはすぐ利イ坊さまを思い出した。先生の御話に出て来る従妹と先生の様に、利イ坊さまと自分はよく喧嘩した事を思い出した。自分は喧嘩しているつもりではなかったけれど、もしも遠慮なく色んな事が云えるんだったらきっと自分も負けずに片意地や我ままをしたろう―しかし今となってはそれも考えるだけでもなつかしい思い出になっていた。仲のいい時は一緒に御床の中で御本を読んだ事もある。大好きなカステラを半分利イ坊さまがわけてくれた事もある―(そうだわ、利イ坊さまに小さいお草履をこさえて贈ろう。いつまでも一緒にいた時の事を記念するために!)チビくんはフイッとそう決心したのだった。一ツには大好きな手芸の先生の御話とソックリの事が出来るのが、たまらなくその決心をそそりたてたのでもあった。
早速神田へ材料を買いに行った。そして大いそぎで作りあげて利イ坊さまのところへ遊びに行くつもりだった。ところがあんまり無理をしてこんをつめたので咽喉をはらして了ったのだった―枕元の手芸箱をあけると、出来上がっている一足の小さな草履がチャンと並んでパラピン紙の中に包まれている。ネルと絹で三枚だたみになっている紅白の草履!鼻緒はこれも絹の紅糸で丹念に編んだものだった。
「ねエ、お母さん、もう明日位起きたっていいんじゃないの?私もうあきちゃった」
「駄目よ、そんなこと云って。又云う事をきかないとひどくなるよ」
「だってさ、早くこのお草履をあげたいんだもの…」
「お草履は何も逃げて行きはしないわよ」
お母さんは、思いつめたら矢もたてもたまらない子供心を微笑ましく思いながら、次の間から笑い声をたてた。
だって―何だか早くこのお草履を贈らないと、先生の御話をうかがった時の感激がうすれ相なので―。すぐにも利イ坊さまのところへあげなければ気のすまない様な、子供心に有り勝ちな一途な気持に追われて、チビくんはお床の中でドタドタと足を蹴ちらしたい様な、イライラした感じになった。
「おばさまア、初子さアーんー」
お庭の木戸があいてとび込んで来たのは高木さんだった。毎日学校のかえりに御見舞による事にしているので、その頃になるとチビくんは迚(とて)も楽しみに待っているのだった。
今日はその高木さんだけではなかった。後から元気のいい赭(あか)い顔と小さなおカッパ頭、修三さまと利イ坊さまだった。
「チビくん、病気だったんだってねえ、どうりでいつまで経っても家へ来ないと思ったア。ハガキついたろ?」
入って来るなり修三さまは快活な調子で話しかけた。
「マアマア、よく御出で下さいましたねエ、利イ坊さまも。ええええ、おハガキいただきましたヨ、丁度あの時風邪で熱が高い最中でね―もう大体いいんですけど。毎日毎日御宅へ伺わなくっちゃならないッてそればっかし云って私を責めるんですよ」
「駄目じゃないか、無理云っちゃア。よかったね、僕達の方から来て。だってね、利恵子の奴が毎日の様にチビくんに逢いたいあいたいってせくんだよ。居る時は勝手ばかり云ってたくせにねエ。やっぱり喧嘩友達ってものは馴染が深いんだろう、かえって。そしたら今朝このお友達に逢ったんだよ、電車の中で。きいたらズッと病気だってんだろう、早速御見舞がてら利イ坊を連れて来たのさ」
「これ、御土産よ」
利イ坊さまはソオッと西洋菓子の箱を出した。
「どうして風邪なんかひいちゃったの。あたし隋ぶん待ったのよオ」少し恨めし相な声である。
「あのね―」チビくんは起き上がって枕元の箱から草履を出した。
「これね、上げようと思ってね、一時迄夜更かししちゃって、クシャミがつづけ様に七ツも出たの、そして遂々(とうとう)寝ちゃったんです」
「あら、何、きれいね?マア、可愛いお草履!」

利イ坊さまは珍し相に小さな掌の上に草履をのせて眺めた。
「それを贈るとね、その人達はいつまでも仲よく永久に忘れないんですって、ねエ、手芸の先生の御話、ね」
高木さんが側から口を入れた。
「そうオ。ありがと。そんなら風邪ひいても許してあげるわ。―ごめんなさいね、風邪ひかしちゃって―」
利イ坊さまは嬉し相に頬ペタをみがいた林檎の様に真赤にかがやかして、掌の紅白の草履をソッと撫でている。その顔を見てチビくんは、ホッとした様に満足の息を吐いた。これで二人はいつまでもいつまでも忘れないで、仲よくして行けるんだわ―
「へエ、きいた。何あんだ、ある人に贈り物にする、なんて凄い事云ってたの、ある人って利イ坊か!なあんだ、一寸も物凄くなかったなアー」
修三さまは、省線の中で云った自分の言葉を思い出して頭をかきながら、高木さんと顔を見合して笑った。

1
オヤ―?
修三さまは首をのばした。一ツ向方(むこう)の入り口から乗ったのはたしかにチビくん。やっぱり同じ様に小っちゃな子と二人連れで、丁度学校の退け時で、どっちを向いてもギュウギュウ詰めの省線の中、乗ったかと思ったら次の瞬間、人混みの中にもぐって見えなくなって了った。
「ごめんなさい」修三さまは人混みをわけてそっちの方へ突進して行った。
「ア」
やっぱりチビくんだった。目の前にヒュッと現れた修三さまの顔を、ビックリしたみたいに見て、あわててピョコンと頭を下げた。
「やっぱりチビくんだったんだナ。僕向方の入口から乗ったんだけど、たしかそうだと思って突進して来たんだヨ―すっかり立派な女学生になったね」
修三さまが感心した様に云うと、チビくんは恥しそうに目をほそくして首をまげた。
チビくんは女学生である。紺色のフェルトの帽子をかぶって、白いブラウスに紺じょジャンパー、人混みにおされて落しては大変と、シッカり小脇にかかえているのは真赤なビロウドの手提カバン。修三さまはチビくんを連れて女学校へ試験を受けに行った三月の時を思い出した。どこでもいいから女学校に入れてやりたいんですけれど―とチビくんのお母さんが相談しに来た時は、三月ももう半ばすぎで大ていの女学校は試験がすぎて了った後だった。それにチビくんは小学校を出てから一年遊んでいるので―。
「パパ、あすこどうです?あすこなら外の女学校みたいにうるさくなくて、それでいて中々いい学校だと思うけどなア―」修三さまがパパさまに声をかけた。
「ああ、小野さんのとこか、そうだねエ」
いいところに気がついた、と云わんばかりにパパさまはおうなずきになった。
小野さんとこと云うのは、パパさまの親友のやっている女学園であった。人数は少いけれど、生徒一人一人について、親切にゆきとどいた教育をしてくれると云うので有名な女学校だった。
修三さまはチビくんを連れて早速その小野女学園に行った。ここでは大勢集めて入学試験をするのではなくて、一人一人園長の小野先生と向いあって交差を受けるのだった。新しいメリンスの着物を着て、チョコンと小野先生の前に腰かけて、目を真円(まんまる)くしていたその時のチビくんの姿を考えると、修三さまはなんだかズッと遠い昔の事でも思い出す様なほほえましさを感じた―
「毎日楽しいかい、女学校生活は…?」
チビくんはコックリした。
「お母さん、元気かい?此の頃一寸も家へ遊びに来ないねエ。遊びにおいでよね、とても利恵子が淋しがってるよ。居たときはいじわるばっかりしてたくせにね…」
電車が駅へとまって一しきりドヤドヤと人が出たり入ったりした。そして又走り出した。
「どこへ行くの?」
「あのね、あの、神田へ買物に…」
「ヘエ。生(なま)ちゃんだナ、もう神田へ行くこと覚えたのかい?」
「これ、買いに行くんです」
チビくんは真赤になって何やらカバンの中からひっぱり出した。
紅と白の小さい草履だった。
「何だい、それ?」
「手芸でこさえるのよ」
チビくんのお隣に居たチビくんよりもっと小さいお友達が口を出した。
「お机の上のかざりにもなるし、そいからペン先ふきにも吸い取紙にもなるのよ、ホラ、ね、ここんとこがプカプカになってるでしョ、ここんとこへ吸い取紙をはっとくの」
そのお友達は紅白の草履の裏をひっくりかえして、紅と白をたたんだ所をプカプカさせて説明した。
「これの材料、神田でなきゃ売ってないんですって、ですから今日高木さんと買いに行くとこなんです」
一寸でもよごしては一大事と云う様に、チビくんは草履を又元の通りカバンにしまい込んだ。
「一つ出来てるじゃないか」
「もう一足こさえるんですって、そしてある人におくりものにするんですって」
高木さんが又側から知ったかぶりで説明した。
「ホオ、ある人に、おくりものにすんの、ウワー、凄え事云ってるなア」
修三さまは高木さんの云い方があんまりおませなので、おかしくなって思わず笑って了った。チビくんはだまって笑っていた。
「じゃ、失敬。本当に遊びに来たまえ、ね、待ってるからね」
電車は、修三さまの愉快な笑い顔を残して走り出した。
2
修三さまがお家の玄関に入って編上靴のヒモを解いていると、奥の方からお母さんの声がきこえた。
(アレ、お母さん、怒っているのかナ?)
大いそぎで靴をぬぐとお茶の間へ入って行った。しかしお茶の間には誰も居ない。
「そんなこと云ったって、仕様がないじゃありませんか?」
勉強部屋から又一きわ高いお母さんの声がきこえて来た。
(利イ坊め、又何か我まま云って怒られてるんだナ)
修三さまは悠然と勉強部屋へ入って行った。
「ウワー、何だい、こりゃア?」
お部屋の中は大さわぎである。本棚から雑誌と云わず本と云わず全部ぬき出して、そこいら中に放り出されている。本箱のガラス戸はあけっ放しで、絵草子箱も神人形のタトウもゴッチャになっている。ランドセルの上に紙につつんだビスケットが投げ出されている、その中で利イ坊さまはくの字形に坐って、お顔に八の字形に両手をあてて泣いている。お母さんは、と見ると衣桁(いこう)によりかかる様にして、怒った様な顔で立っていらっしゃる―
「どうしたんです、ええ、お母さん?」
「いいえ、又いつもの我ままなんですよ、―本当に此の人にも困っちまう。どうしてこうなんでしょうね。お母さん、もう情けなくなっちゃうわ―」
もうサジを投げた、と云う様子でお母さんは眉をくもらせて、ホーッと吐息。
「それにしても、このさわぎは一体全体何事じゃ、ウン、利恵子?ヒスか、あんまりヒステリイ起すんじゃないよ、子供のくせに」
面白可笑しい調子で修三さまは此の場の空気を中和しようと、利イ坊さまの泣きじゃくっている肩に手をかけた。
「いやんッ!」
利イ坊さまはじゃけんにふりはなした。
「修三、ほっておきなさい。いいえ、もう今度と云う今度は容赦しません。パパが帰っていらしたらよく御相談して、小岩の叔父様のとこへ預けますからね」
「ヤーン」一しきり利イ坊さまは声をはり上げた。小岩の叔父様と云うのは利イ坊さまの大の苦手である。御家は淋しい林の外れにポツンと建っていて、夜になるとフクロが啼くし、電車の駅まで行くには十五六町もある。それに叔父さまの恐いことったら、利イ坊さまなんかがお鼻をならしたってビクともするものではない。一昨年の夏、一週間程お泊りに行って居る中、二度も暗いお倉の中に放りこまれた恐しい経験があるのである。だから小岩の叔父さまときくと、利イ坊さまはブルブルッとふるえた。
「一体どうしたんですヨ、お母さんも利恵子も怒ったり泣いたりばかしして居ちゃ、僕たるもの仲裁が出来んじゃないですか…」
それでもお母さんは何にも云わず怒った顔で利イ坊さまをにらんでいらっしゃる―
「オヤ、いつの間にお帰りになりまして。どうか、何とかおっしゃってあげて下さいましよ、ね」
みねやが顔を出して、修三さまの顔を見ると助けの神よ、とばかりにすがりつく様に云った。
「だからさ、一体全体どしたんだ、ってきいてるんだけど、敵も味方もコーフンしきっていて駄目なんだよ」
「いえね、お嬢さんがね、又例の通りなんですけど…はじめね、学校から松平さんと帰ってらっしゃってね、ガラス紙だか何か差しあげるお約束だったらしいんですね、そしたらどこを探してもないんでございますって。みねやもご一緒になって探して差しあげればよかったんですけど、つい、お洗濯しかけだったもんですから―」一寸みねやはベンカイした。
「そいで…?」修三さまはせかした。
「その中に松平さんはお帰りになって了ったんですよ。その時『ウソつきね。ガラス紙三十枚も持ってらっしゃるなんて。あたくし、はじめっからウソだと思ったわ』っておっしゃったんですの。だもんですから余計やっきになって、これこの通りどこもかしこもひっかきまわして探してごらんになったらしいんですけど、どうしてもないんでございますって…。そこへ奥さまが御買物から帰ってらして、お八ツを紙につつんでもって入ってらしたら、この大さわぎなもんで、お怒りになったんですの、そしたら…」
「初子を呼んで来てくれ、と云うんですヨ。どうせどこかにあるんだからもっと気をおちつけてよーく探してごらんなさい、と云うんだけど、どうしても初子を呼んで来て探さしてくれなきゃいやだ、とこうなのよ。ねエ、兄さん、そんな我ままッてないでしょう」
お母さんはヤヤ興奮のしずまったらしい顔で、訴える様に修三さまの顔を見た。修三さまはフと、チビくんがいつも利イ坊さまのちらかした後をだまって、きれいに片づけていた頃の事を思い出した。
「チビくんが帰ってからもう一カ月以上もたってるじゃないか、その間にもう二度も三度も君出して見たんだろう?だから君がどこかへしまい忘れてるんだよ。今更チビくんを呼んで来たって仕様がないじゃないか―今迄自分で後片づけしなかったから、チビくんが居なくなったらその通りだ、バチがあたったんだよ」
お母さんは、足許に散らばっている本をまとめ出したが、フト気がついた様に、
「利恵子、これ、みんなお片づけなさい。自分が散らかしたものは自分で整とんする癖をつけなきゃ駄目です。いいですか、キチンと片づけるんですよ。もし云う事をきかないと、それこそ本当に小岩の叔父さんを呼びますからね―」
「さ、利イ坊さま、みねやが手伝ってあげますから、片づけましょう―」
みねやはさすが気の毒と思って、まわりの物を片づけ出した。
「みねや、放っておきなさい、よござんすったらッ―」
みねやは奥さまのきつい声に渋々手をやめて了った。
「もう五時ですヨ、御台所はいいんですか」
お母さんの後からみねやもつづいてお部屋を出て行って了った。―
「利イ坊、君、チビくんに逢いたいんだろオ?君のヒスのわけ、ちゃんとわかってるんだ。わかるともさア。こんなカンタンな精神分析が出来んようではあかんわ。ワシャ将来イ社になるんじゃから喃(のう)」キエンをあげ乍ら修三さまは、静かになった利イ坊さまの背中を軽く叩いた。
「今日、省線の中で逢ったよ、チビくんに。とても可愛い学生さんになっていたよ」
「アラ」と云う様な顔で、利イ坊さまは顔をあげた。眼が真赤、ついでに小っちゃいお鼻まで桜ん坊みたいに赤くなっている。
「ヤア、御機嫌が直って来たナ―あんまりすねるんじゃないヨ、いいかい?チビくんに逢いたければ、そうハッキリ云えばいいじゃないか。君は何でもすねるから物事がコンガラかっていかんよ。小っちゃいくせに君は非常にフクザツなる感情性格の持主じゃね。そう云うのはフロイドの精神分析法から診察すると、エエと―」
修三さまは或医科大学の予科に入ったので、此の頃は何でもこの調子で片づけようとする。
「チビくん、あそびに来る、って云ってた?」利イ坊さまは、雑誌の折れたのをソッと直しながら小さな声できいた。
「ああ、そ云っといた、是非是非近い中に来い、って。何だったら至急ハガキ出してあげようか、利恵子のガラス紙が行方不明につき至急御捜索をたのむ、って―」
「ハガキ、ある?」利イ坊さまは本気である。
「買って来なきゃないよ、生憎と」
上着のボタンを外しながら、修三さまは(そんなにチビくんに逢いたいかナ、あんなにイジワルばっかししてたくせに)と一寸その子供心がいじらしくなった。
「お母さまにお金いただいて、あたし買ってくるわ―」
利イ坊さまは、バタバタと廊下へとび出して行った。
「―なくて人の恋しかりける、か。昔の人は矢張り上手い事を云ったなア―」上着を衣桁(いこう)にかけると修三さまは、ヨイショとしゃがんで散らかった本や雑誌を片づけはじめた。
利恵子が、ガラス紙が行方不明になったので、探してもらいたいと云っています。是非家へ来て下さい。先(まず)は至急右御願いまで。
修三拝
追伸
ア、ガラス紙は机の抽斗しから出て来た相です。でもガラス紙はあっても是非来て下さい。お友達がなくて毎日毎日淋しがっています。たのむタノム。
3
修三さまからのハガキを枕の下へ敷いてから、もう一週間以上も経って了った。
早く行きたい、お土産の草履は出来たし、一体どうしたのかしら?と修三さまは不思議に思っていらっしゃるんだろうし…チビくんは床の中で、中々治らない風邪を焦れったく思っていた。風邪をひいてからもう十日位になる。風邪をひいたのは利イ坊さまにプレゼントする紅白の草履をこしらえるために夜更かしをしたからだった。手芸の時間、先生が白いネルのキレと真赤な絹の布(きれ)をノリで張り合わせ乍らおっしゃった。
「私はね、小さい時叔母さんの家に居たの。とても意地悪のいとこが居てね、私も強情っぱり、いとこも強情っぱりだったので毎日喧嘩ばかりしていたのよ。ところが十八のそのいとこはお嫁さんに行く事になったの。お嫁に行く前の晩、いとこが私のところへ来てそ云ったの、『長い間意地悪してごめんなさい。私もう行くわ』ッて。そしたら普段とても憎らしいと思っていたいとこが急になつかしくなって、私涙がこぼれて来たの。二人はしばらく手をとりあって泣いてたのよ。そしたらね、いとこがね小さな草履を出して記念にくれたの。今でもその草履もっているわ、そして見るたんびに小さかった時の事やいとこの事を想い出しているの。いいものね、一寸した贈り物でもいつまでもその人の事を記念する様になるんですもの。貴方たちもせいぜいキレイにこしらえて仲のいい方に贈るといいわ―」
その御話をきいた時、チビくんはすぐ利イ坊さまを思い出した。先生の御話に出て来る従妹と先生の様に、利イ坊さまと自分はよく喧嘩した事を思い出した。自分は喧嘩しているつもりではなかったけれど、もしも遠慮なく色んな事が云えるんだったらきっと自分も負けずに片意地や我ままをしたろう―しかし今となってはそれも考えるだけでもなつかしい思い出になっていた。仲のいい時は一緒に御床の中で御本を読んだ事もある。大好きなカステラを半分利イ坊さまがわけてくれた事もある―(そうだわ、利イ坊さまに小さいお草履をこさえて贈ろう。いつまでも一緒にいた時の事を記念するために!)チビくんはフイッとそう決心したのだった。一ツには大好きな手芸の先生の御話とソックリの事が出来るのが、たまらなくその決心をそそりたてたのでもあった。
早速神田へ材料を買いに行った。そして大いそぎで作りあげて利イ坊さまのところへ遊びに行くつもりだった。ところがあんまり無理をしてこんをつめたので咽喉をはらして了ったのだった―枕元の手芸箱をあけると、出来上がっている一足の小さな草履がチャンと並んでパラピン紙の中に包まれている。ネルと絹で三枚だたみになっている紅白の草履!鼻緒はこれも絹の紅糸で丹念に編んだものだった。
「ねエ、お母さん、もう明日位起きたっていいんじゃないの?私もうあきちゃった」
「駄目よ、そんなこと云って。又云う事をきかないとひどくなるよ」
「だってさ、早くこのお草履をあげたいんだもの…」
「お草履は何も逃げて行きはしないわよ」
お母さんは、思いつめたら矢もたてもたまらない子供心を微笑ましく思いながら、次の間から笑い声をたてた。
だって―何だか早くこのお草履を贈らないと、先生の御話をうかがった時の感激がうすれ相なので―。すぐにも利イ坊さまのところへあげなければ気のすまない様な、子供心に有り勝ちな一途な気持に追われて、チビくんはお床の中でドタドタと足を蹴ちらしたい様な、イライラした感じになった。
「おばさまア、初子さアーんー」
お庭の木戸があいてとび込んで来たのは高木さんだった。毎日学校のかえりに御見舞による事にしているので、その頃になるとチビくんは迚(とて)も楽しみに待っているのだった。
今日はその高木さんだけではなかった。後から元気のいい赭(あか)い顔と小さなおカッパ頭、修三さまと利イ坊さまだった。
「チビくん、病気だったんだってねえ、どうりでいつまで経っても家へ来ないと思ったア。ハガキついたろ?」
入って来るなり修三さまは快活な調子で話しかけた。
「マアマア、よく御出で下さいましたねエ、利イ坊さまも。ええええ、おハガキいただきましたヨ、丁度あの時風邪で熱が高い最中でね―もう大体いいんですけど。毎日毎日御宅へ伺わなくっちゃならないッてそればっかし云って私を責めるんですよ」
「駄目じゃないか、無理云っちゃア。よかったね、僕達の方から来て。だってね、利恵子の奴が毎日の様にチビくんに逢いたいあいたいってせくんだよ。居る時は勝手ばかり云ってたくせにねエ。やっぱり喧嘩友達ってものは馴染が深いんだろう、かえって。そしたら今朝このお友達に逢ったんだよ、電車の中で。きいたらズッと病気だってんだろう、早速御見舞がてら利イ坊を連れて来たのさ」
「これ、御土産よ」
利イ坊さまはソオッと西洋菓子の箱を出した。
「どうして風邪なんかひいちゃったの。あたし隋ぶん待ったのよオ」少し恨めし相な声である。
「あのね―」チビくんは起き上がって枕元の箱から草履を出した。
「これね、上げようと思ってね、一時迄夜更かししちゃって、クシャミがつづけ様に七ツも出たの、そして遂々(とうとう)寝ちゃったんです」
「あら、何、きれいね?マア、可愛いお草履!」

利イ坊さまは珍し相に小さな掌の上に草履をのせて眺めた。
「それを贈るとね、その人達はいつまでも仲よく永久に忘れないんですって、ねエ、手芸の先生の御話、ね」
高木さんが側から口を入れた。
「そうオ。ありがと。そんなら風邪ひいても許してあげるわ。―ごめんなさいね、風邪ひかしちゃって―」
利イ坊さまは嬉し相に頬ペタをみがいた林檎の様に真赤にかがやかして、掌の紅白の草履をソッと撫でている。その顔を見てチビくんは、ホッとした様に満足の息を吐いた。これで二人はいつまでもいつまでも忘れないで、仲よくして行けるんだわ―
「へエ、きいた。何あんだ、ある人に贈り物にする、なんて凄い事云ってたの、ある人って利イ坊か!なあんだ、一寸も物凄くなかったなアー」
修三さまは、省線の中で云った自分の言葉を思い出して頭をかきながら、高木さんと顔を見合して笑った。