【外資系産業医に学ぶ、コロナ禍のメンタルヘルス】致知出版社のサイトより
メンタルが強い人の習慣
1.好きなことをする
好きなことをしている時、人は誰でもそれに集中する。それが気分転換になり、ほどよい疲れが出るため睡眠にも好影響が出る。趣味がない、もしくはコロナ禍を理由にそれを諦めている人は、一度自分の趣味を箇条書きにして、可視化してみると意外な発見があるだろう。大切なのは、楽しい時間を自らつくっていく姿勢だ。
2.構える
人は想定外の出来事に強いストレスを感じる。なので、日頃から「最悪のシナリオ」を描き、不測の事態に構えておくことが重要だ。あらゆる状況を想定する必要はない。
考えたくないかもしれないが、「もし自分が新型コロナウイルスに感染したら」「もし自分の会社が倒産したら」等いくつかの場合について、それが現実化した時をシミュレーションする。そうすればいざという時のショックが和らぎ、立ち上がりが早くなる。
また同時に、仕事でこうなったら最高に嬉しい、という「ベストシナリオ」もあるとよい。最悪と最高、理論上はこの二つの間にすべての出来事が含まれるから、多少問題が起きても頭が真っ白になる事態は避けられる。
3.区切る
ストレスを感情に置き換えれば、「緊張感」だと言える。緊張が続くほど心は擦り減る。在宅勤務で生活空間と仕事の区別がなくなってきた人も多い。その中で緊張をどう区切か。その「区切り方」を三つ。
時間を区切る
人間の集中力は無限には続かない。学生の頃、休み時間は当たり前にありましたが、社会人はそれを意識して取る必要がある。また米国では、一定程度の長い休みを控えた人は、その休みの八週間前から幸福度が高まるという研究結果も出ている。予め休みを決めている人のほうが充実している。時間を区切ることで、高いパフォーマンスが維持できる。
空間を区切る
在宅勤務の弊害の一つは、これまで別々だった職場と生活空間が一緒になり、仕事が終わったら勝手に気分が変わるということがなくなる点。感染対策に気を配った上で、週末に出掛けるのもよいが、単に散歩へ出掛けたり、身近にある高い所(ビル、展望台など)に上ってみるのもよい。日常から切り離される感覚を味わうだけで、気分は楽になる。
五感を区切る
人間の感情は五感に大きく影響を受けている。アロマを焚く、絵画を観る、音楽を聴く。方法は何でもよい。五感への刺激が気分を変え、リラックスするきっかけになる。
マラソン選手は疲れてから休むのではなく、無事に走り切れるよう、予め給水地点を決めている。ストレスも同じで、意識的に休み、区切りを入れることがよいパフォーマンスを維持する秘訣。
4.捨てる
不満をいくら解消しても、マイナスの感情が一時的にゼロに近づくだけで、幸せになれるわけではない。ストレスに上手に対処している人は、どうにもならない悩みを解決しようとせず、その時間をもっと幸せになれる何かに使うことを意識している。ネガティブな感情を減らそうと躍起になるより、ポジティブな感情を増やすほうが幸せになれると知っている。
捨てるとは「選ぶ」ことでもある。休日に仕事の悩みで悶々とし続けても状況は変わらない。家にいる時は家族との会話を最優先するなど、自分にとって何が大切かを考え、適宜気持ちを切り替える。
5.体を使う
心が緊張している時、筋肉は収縮し、体は硬くなる。対処の上手な人たちはその都度、体を使うことで緊張を緩和している。その例がジョギングやエアロビクスといった有酸素運動。一定のリズムを伴うこれらの運動をすると、幸せホルモンと呼ばれるセロトニンが多く分泌され、多幸感が得られると言われている。
時には100メートルダッシュや腕立て伏せなど強めの運動を取り入れる。運動の最中は悩みを忘れ、主に就寝中、筋肉修復のため分泌される成長ホルモンには抗ストレス効果があり、健康な体と心の維持に役立つ。
また、辛い時は顔を上に向けてみる。これだけでも俯いているより気分が楽になる。
6.書く・話す・読む
いつも漠とした不安に悩んでいるなら、その要因を箇条書きする。例えば会社をクビになるのが怖いなら、なぜそれが怖いのか。収入減の不安が原因なら、一体いくらあれば足りるのか、今後どのように貯めていったらよいのか……という要領で、心のわだかまりを明瞭にしていく。
自分で書いた内容を一か月後に見返してみる。不安の8~9割が、現実には起こらない。悩みを親しい人に話す、小説や自己啓発書を読むこともまた、心を鎮めることに繋がる。
7.新しい出会いを求める
ストレス耐性を高める上で、新しい知識や趣味、人間関係を持つ心があるかどうかは重要です。
会社勤めの人は自宅との往復が続き、それ以外の人間関係が希薄になりがち。その何が問題かと言えば、仕事で失敗し評価が下がった際、それが世間全体からの評価と勘違いする恐れがある。積極的に新たなコミュニティへ参加することで、メンタルの健康が保たれる可能性が高まる。
まあ、自分はメンタルが強いほうではないかと思う。
強いというより、何が起きても驚くより、またきたか、と麻痺している状態のような気がする。深呼吸して、さて、どうしようかね、と考えてすぐに自分がいいと思う方向へ行動しようと動く。
動くことで、悩み心配に陥って動けなくなることはないようにする。
1の好きなことをする、って、自分にとっていやされる動画を観て、Gyaoの映画を観て、ブログを書く。それで結構気分転換になる。
2の最悪のシナリオは、パートナーとの共同事業がなくなった場合だが、そのときはそのときで、日本でアパートを借りて転職をする。なんということもない。
3の区切るは、自分にとって旅は必要な楽しみなので、1年に一度、旅先と日程を決めて、その楽しみのために、残りの日々を仕事に集中できる。
4の捨てるだが、マイナスの感情は、日々捨てている。そんな感情にまみれているのはもったいないから、面白いことや自分が成長することに意識を向ける。
5の体を使うは、自分でも実感している。毎朝毎晩、ヨガとストレッチをして、体を整える。今は喘息でトレーニングを休んでいるが、春になって暖かくなって喘息が治まれば、ジョギングを始めたい気持ちでいっぱいだ。朝の爽やかなジョギング時間を羨望している。
6の不安を箇条書きにしてみる、って、不安要素を書くまでもない。ただお金をできるだけ貯めて、行動しやすいようにするだけだ。旅も何をするにも、経済的な基盤がいる。
7の新しい出会いは、どこでなにのコミュニティに参加するにしても、出会いには恵まれる。
職場、旅先、人が好きだからどこでも出会いがいい。
こういうチェックができて、いい。
すべてに感謝。
メンタルが強い人の習慣
1.好きなことをする
好きなことをしている時、人は誰でもそれに集中する。それが気分転換になり、ほどよい疲れが出るため睡眠にも好影響が出る。趣味がない、もしくはコロナ禍を理由にそれを諦めている人は、一度自分の趣味を箇条書きにして、可視化してみると意外な発見があるだろう。大切なのは、楽しい時間を自らつくっていく姿勢だ。
2.構える
人は想定外の出来事に強いストレスを感じる。なので、日頃から「最悪のシナリオ」を描き、不測の事態に構えておくことが重要だ。あらゆる状況を想定する必要はない。
考えたくないかもしれないが、「もし自分が新型コロナウイルスに感染したら」「もし自分の会社が倒産したら」等いくつかの場合について、それが現実化した時をシミュレーションする。そうすればいざという時のショックが和らぎ、立ち上がりが早くなる。
また同時に、仕事でこうなったら最高に嬉しい、という「ベストシナリオ」もあるとよい。最悪と最高、理論上はこの二つの間にすべての出来事が含まれるから、多少問題が起きても頭が真っ白になる事態は避けられる。
3.区切る
ストレスを感情に置き換えれば、「緊張感」だと言える。緊張が続くほど心は擦り減る。在宅勤務で生活空間と仕事の区別がなくなってきた人も多い。その中で緊張をどう区切か。その「区切り方」を三つ。
時間を区切る
人間の集中力は無限には続かない。学生の頃、休み時間は当たり前にありましたが、社会人はそれを意識して取る必要がある。また米国では、一定程度の長い休みを控えた人は、その休みの八週間前から幸福度が高まるという研究結果も出ている。予め休みを決めている人のほうが充実している。時間を区切ることで、高いパフォーマンスが維持できる。
空間を区切る
在宅勤務の弊害の一つは、これまで別々だった職場と生活空間が一緒になり、仕事が終わったら勝手に気分が変わるということがなくなる点。感染対策に気を配った上で、週末に出掛けるのもよいが、単に散歩へ出掛けたり、身近にある高い所(ビル、展望台など)に上ってみるのもよい。日常から切り離される感覚を味わうだけで、気分は楽になる。
五感を区切る
人間の感情は五感に大きく影響を受けている。アロマを焚く、絵画を観る、音楽を聴く。方法は何でもよい。五感への刺激が気分を変え、リラックスするきっかけになる。
マラソン選手は疲れてから休むのではなく、無事に走り切れるよう、予め給水地点を決めている。ストレスも同じで、意識的に休み、区切りを入れることがよいパフォーマンスを維持する秘訣。
4.捨てる
不満をいくら解消しても、マイナスの感情が一時的にゼロに近づくだけで、幸せになれるわけではない。ストレスに上手に対処している人は、どうにもならない悩みを解決しようとせず、その時間をもっと幸せになれる何かに使うことを意識している。ネガティブな感情を減らそうと躍起になるより、ポジティブな感情を増やすほうが幸せになれると知っている。
捨てるとは「選ぶ」ことでもある。休日に仕事の悩みで悶々とし続けても状況は変わらない。家にいる時は家族との会話を最優先するなど、自分にとって何が大切かを考え、適宜気持ちを切り替える。
5.体を使う
心が緊張している時、筋肉は収縮し、体は硬くなる。対処の上手な人たちはその都度、体を使うことで緊張を緩和している。その例がジョギングやエアロビクスといった有酸素運動。一定のリズムを伴うこれらの運動をすると、幸せホルモンと呼ばれるセロトニンが多く分泌され、多幸感が得られると言われている。
時には100メートルダッシュや腕立て伏せなど強めの運動を取り入れる。運動の最中は悩みを忘れ、主に就寝中、筋肉修復のため分泌される成長ホルモンには抗ストレス効果があり、健康な体と心の維持に役立つ。
また、辛い時は顔を上に向けてみる。これだけでも俯いているより気分が楽になる。
6.書く・話す・読む
いつも漠とした不安に悩んでいるなら、その要因を箇条書きする。例えば会社をクビになるのが怖いなら、なぜそれが怖いのか。収入減の不安が原因なら、一体いくらあれば足りるのか、今後どのように貯めていったらよいのか……という要領で、心のわだかまりを明瞭にしていく。
自分で書いた内容を一か月後に見返してみる。不安の8~9割が、現実には起こらない。悩みを親しい人に話す、小説や自己啓発書を読むこともまた、心を鎮めることに繋がる。
7.新しい出会いを求める
ストレス耐性を高める上で、新しい知識や趣味、人間関係を持つ心があるかどうかは重要です。
会社勤めの人は自宅との往復が続き、それ以外の人間関係が希薄になりがち。その何が問題かと言えば、仕事で失敗し評価が下がった際、それが世間全体からの評価と勘違いする恐れがある。積極的に新たなコミュニティへ参加することで、メンタルの健康が保たれる可能性が高まる。
まあ、自分はメンタルが強いほうではないかと思う。
強いというより、何が起きても驚くより、またきたか、と麻痺している状態のような気がする。深呼吸して、さて、どうしようかね、と考えてすぐに自分がいいと思う方向へ行動しようと動く。
動くことで、悩み心配に陥って動けなくなることはないようにする。
1の好きなことをする、って、自分にとっていやされる動画を観て、Gyaoの映画を観て、ブログを書く。それで結構気分転換になる。
2の最悪のシナリオは、パートナーとの共同事業がなくなった場合だが、そのときはそのときで、日本でアパートを借りて転職をする。なんということもない。
3の区切るは、自分にとって旅は必要な楽しみなので、1年に一度、旅先と日程を決めて、その楽しみのために、残りの日々を仕事に集中できる。
4の捨てるだが、マイナスの感情は、日々捨てている。そんな感情にまみれているのはもったいないから、面白いことや自分が成長することに意識を向ける。
5の体を使うは、自分でも実感している。毎朝毎晩、ヨガとストレッチをして、体を整える。今は喘息でトレーニングを休んでいるが、春になって暖かくなって喘息が治まれば、ジョギングを始めたい気持ちでいっぱいだ。朝の爽やかなジョギング時間を羨望している。
6の不安を箇条書きにしてみる、って、不安要素を書くまでもない。ただお金をできるだけ貯めて、行動しやすいようにするだけだ。旅も何をするにも、経済的な基盤がいる。
7の新しい出会いは、どこでなにのコミュニティに参加するにしても、出会いには恵まれる。
職場、旅先、人が好きだからどこでも出会いがいい。
こういうチェックができて、いい。
すべてに感謝。










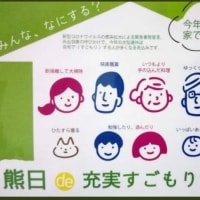









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます