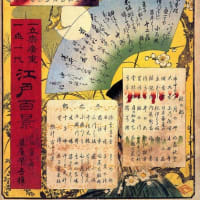はじめに
この小説『千歳』は、
平安時代の大嘗祭の様子を
題材に妄想した小説です。
フィクションですが、
その当時の風景を
感じていただければと思います。
・廻立殿
午後八時になると主上は内裏を出られた。
夜の空、月は雲に隠れ、
漆黒の闇に包まれている。
暗闇の路上、
側近の持つ紙燭の光だけが唯一の光だ。
それだけを頼りに主上たちは廻立殿へ向かう。
主上は、まだ若く、細身の体躯、
表情は幼げで頼りなさげな方である。
主上は、緊張してなのか、
もともとそういう性質なのか、
トボトボと歩き速度も遅い。
時間が差し迫る中、
急ぎもせず歩く主上に側近たちは、
急かすこともできず苛立ちを覚えた。
先帝が亡くなり、
これといった後ろ盾もないままの即位である。
頼る者がいないことは十分理解できる…
だが、これから大切な神事を控えているのだ。
大臣は苛立ちに笏をギュッと握り、
心のうちで呟いた。
政は我々がやればいいことだが…
これから行われる神事は、
主上だけが行えるのだ。
一時でもよいから…
しっかりとして欲しいものだ…
そして、
横目でチラリと主上を睨んだ。
当の主上は、
眉根を寄せ不機嫌極まりない表情を
浮かべていた。
不安を抱えながら、一行は廻立殿に到着した。
主上はそこで禊をなされる。
禊が終わると主上は、
最高の神事服である御祭服に着替えられた。
神聖・清浄を表現する白色の装束。
白色は神祭りに使われる尊い色、
そして無色の質素をも意味する。
主上は身支度を整えると廻立殿を出られ、
悠紀殿にお入りになられた。
天皇に従って
祭儀に奉仕する官人たちは
上衣に小忌衣を着用する。
白布に春草・小鳥などの模様を藍摺りにし、
肩に赤紐を垂らしたものだ。
通路にはあらかじめ布単と呼ばれる
白い布が敷かれている。
その上さらに葉薦が敷かれる。
これにより天皇おひとりだけが歩まれる、
聖別された特別な道がつくられる。
天皇の歩みにしたがい
係の者が葉薦をくりひろげては、
歩まれた後を巻きあげていく。
巻き取る係の者は、
主上の長い裾を踏まぬよう
注意しながら葉薦を巻き上げていく。
また、
主上の頭上には、
御菅蓋と呼ばれる大きな傘がさしかけられ、
それを持つものは細心の注意を払い
主上に付いて行った。
妄想は、続く
・主上
天皇を敬っていう語。
・紙燭(しそく・ししょく)
屋内で用いる松明(たいまつ)のことで、手火の一種。棒状の松の木を、あらかじめ先のほうに油を引いて乾かし、手元を紙で巻いて用いた。携帯用灯火。
・小忌衣(おみごろも)
古代から伝わる、神事などに使用される上衣。男女ともに装束の上に羽織り、右肩から赤紐を垂らす。模様としては、白絹及び白麻地に青摺と呼ばれる山藍の葉の汁で、花鳥風月等の素朴な文様を書くのが一般的。
・布単(ふたん)
遷宮、遷座、行幸などでその道筋に敷いた布帛。毯代(たんだい)。
・葉薦(はごも)
真菰(まこも)の葉を編んで作ったもの。または、簀薦(すごも)にまねて竹の簀子(すのこ)に錦などの縁をつけたもの。
・御菅蓋(おかんがい)
大嘗祭で、天皇が廻立殿から悠紀殿・主基殿へ行幸する時、天皇の頭上にさしかける大きいかさ。竹の骨に菅で編んである。