安倍総理大臣は、参議院予算委員会で、TPP(環太平洋経済連携協定)の交渉について「最終局面にあり、早期妥結へ全力を挙げている」と述べました。
TPPは「早期妥結」が課題でしたっけ?
<日経ビジネス 2011年10月25日>
「自由貿易」と併用して消費者利益と農業保護の両立を
山下 一仁の農業政策研究所
『農政は、778%という異常に高い税率の関税を米にかけるなどして、国内農産物市場を外国産農産物から守ってきた。にもかかわらず、農業が衰退してきたということは、その原因がアメリカやオーストラリアなどの海外にではなく国内にあることを意味している。TPPに参加する、しないにかかわらず、現在の政策では農業の衰退をとめることはできない。
高い関税で国内の農産物市場を守っても、市場は高齢化・人口減少で、どんどん縮小していく。日本農業を維持・振興していくためには、海外の市場に関税撤廃などを求め、環太平洋経済連携協定(TPP)などの貿易自由化交渉に積極的に参加していく必要がある。高齢化・人口減少時代において、米中心、それも供給制限による価格支持を中心としてきた今までの農政では、日本の農業に課せられた役割――食料安全保障、洪水防止や水資源の涵養などの農業の多面的機能の維持――を果たせない。
OECD(経済協力開発機構)が開発したPSE(生産者支持推定量)という農業保護の指標は、「納税者負担」と「消費者負担」の部分から成る。「納税者負担」は財政負担によって農家の所得を維持している部分。「消費者負担」は、消費者が安い国際価格ではなく、高い国内価格を受け入れることで農家に所得移転している部分だ。
【アメリカやEUの農業保護は納税者負担に移行】
各国のPSE(生産者支持推定量)の内訳を見ると、アメリカやEUにおいて消費者負担の割合は減少する傾向にある。ウルグアイ・ラウンド交渉で基準年とされた1986~88年の値はアメリカで37%、EUで86%。これに対して2009年の数値は、アメリカが15%、EUが24%となっている。日本は(消費者負担が)90%から84%になっただけで、20年間変化はない。』
4年前の記事ですが、現在も何も進展していないことがわかります。
「TPPなどの自由貿易に積極的参加・・」と言っていますが、人口減少という一面だけを捉えた問題提起です。日本の農業維持問題からいえば、逆にアメリカの資本に日本農業は逆につぶされる状況が今押し寄せています。
しかし、明確に「原因は国内である」こと、「農業には財政負担が必要である」ことを指摘しています。
下の数字は、現在、農業所得に占める財政負担の割合です。
日本 15.6%
アメリカ 26.4%
フランス 90.2%
イギリス 95.2%
スイス 94.5%
日本は先進国の中で突出して「農業予算が少ない国」で、ビックリです。
アメリカの26.4%の中身は、穀物類への財政負担は45%から60%代になっています。
なぜ、各国がここまで農家に予算を費やしているのか。
そうしなければ「国家の食料安全保障」が維持できないことが分かっているためで、食料自給率を引き上げるために、農家の「保護」に巨額の予算を費やしています。
日本の地域「農協」は、商社機能を果たすJA「全農」と農産物や肥料等を売買し、「農林中金」が提供する信用(銀行の役割)、「JA共済」が提供する保険を組合員に販売しています。
大元の農協の目的の一つである全農関連のビジネス(経済事業)では利益が出ず、農協の経営は信用、共済という二つの金融事業により支えられているというのが実態のようです。
全農の子会社の一つ、ロスアンゼルスに本社を置く全農グレイン株式会社という会社は、アメリカから穀物を輸入している会社です。
この会社は、現地で「仕分け」を実施し、日本に遺伝子組み換え作物等が流入しないように管理しています。
全農が株式会社化され、そこに「外国資本」が入ればどうなるのか。
我が国の食料流通が、外国に支配されることになってしまいます。
いま着々とその準備が進行し、数年後に、「気付いたらそうなっていた」ということでしょうか。TPP参加はそこへの入り口を意味します。
最近日本政府が、食料自給率の目標を50%から45%だかに下げたという情報もあります。
TPPを見越して、自給率も徐々に下がると見ているのでしょうか。
自給率減→農家減→農業補助金減→財政支出さらに引締め→政府の借金減→財政の健全化実現へまっしぐら
農業に限らず、復興予算はじめ補助金等はこの図式で削っていきたいと思っているのかもしれません。
政府の借金が減ることと、国民が豊かになることは必ずしもイコールではありません。
そのために農業を、国民を、中小企業を犠牲にしたら本末転倒です。
はっきりと言えることは、日本の農業政策は、「農家は自分のことは勝手に守れ、国は予算をもうこれ以上出しません」という考え方が行動に出ていると言うことです。
先に記した日経ビジネス記事のように、人口減少で日本農業は壊滅することを政府は予想している可能性があります。
潰れるゆく農業に、予算を裂くだけ無駄だと考えているのかも知れません。
食料が足りなければ、「アメリカ様から分けてもらえるよ」政策です。
安部総理は、農家は守らなくても、末端の日本人の、普代村民の胃袋も守ってくれるのでしょうか?
TPPは「早期妥結」が課題でしたっけ?
<日経ビジネス 2011年10月25日>
「自由貿易」と併用して消費者利益と農業保護の両立を
山下 一仁の農業政策研究所
『農政は、778%という異常に高い税率の関税を米にかけるなどして、国内農産物市場を外国産農産物から守ってきた。にもかかわらず、農業が衰退してきたということは、その原因がアメリカやオーストラリアなどの海外にではなく国内にあることを意味している。TPPに参加する、しないにかかわらず、現在の政策では農業の衰退をとめることはできない。
高い関税で国内の農産物市場を守っても、市場は高齢化・人口減少で、どんどん縮小していく。日本農業を維持・振興していくためには、海外の市場に関税撤廃などを求め、環太平洋経済連携協定(TPP)などの貿易自由化交渉に積極的に参加していく必要がある。高齢化・人口減少時代において、米中心、それも供給制限による価格支持を中心としてきた今までの農政では、日本の農業に課せられた役割――食料安全保障、洪水防止や水資源の涵養などの農業の多面的機能の維持――を果たせない。
OECD(経済協力開発機構)が開発したPSE(生産者支持推定量)という農業保護の指標は、「納税者負担」と「消費者負担」の部分から成る。「納税者負担」は財政負担によって農家の所得を維持している部分。「消費者負担」は、消費者が安い国際価格ではなく、高い国内価格を受け入れることで農家に所得移転している部分だ。
【アメリカやEUの農業保護は納税者負担に移行】
各国のPSE(生産者支持推定量)の内訳を見ると、アメリカやEUにおいて消費者負担の割合は減少する傾向にある。ウルグアイ・ラウンド交渉で基準年とされた1986~88年の値はアメリカで37%、EUで86%。これに対して2009年の数値は、アメリカが15%、EUが24%となっている。日本は(消費者負担が)90%から84%になっただけで、20年間変化はない。』
4年前の記事ですが、現在も何も進展していないことがわかります。
「TPPなどの自由貿易に積極的参加・・」と言っていますが、人口減少という一面だけを捉えた問題提起です。日本の農業維持問題からいえば、逆にアメリカの資本に日本農業は逆につぶされる状況が今押し寄せています。
しかし、明確に「原因は国内である」こと、「農業には財政負担が必要である」ことを指摘しています。
下の数字は、現在、農業所得に占める財政負担の割合です。
日本 15.6%
アメリカ 26.4%
フランス 90.2%
イギリス 95.2%
スイス 94.5%
日本は先進国の中で突出して「農業予算が少ない国」で、ビックリです。
アメリカの26.4%の中身は、穀物類への財政負担は45%から60%代になっています。
なぜ、各国がここまで農家に予算を費やしているのか。
そうしなければ「国家の食料安全保障」が維持できないことが分かっているためで、食料自給率を引き上げるために、農家の「保護」に巨額の予算を費やしています。
日本の地域「農協」は、商社機能を果たすJA「全農」と農産物や肥料等を売買し、「農林中金」が提供する信用(銀行の役割)、「JA共済」が提供する保険を組合員に販売しています。
大元の農協の目的の一つである全農関連のビジネス(経済事業)では利益が出ず、農協の経営は信用、共済という二つの金融事業により支えられているというのが実態のようです。
全農の子会社の一つ、ロスアンゼルスに本社を置く全農グレイン株式会社という会社は、アメリカから穀物を輸入している会社です。
この会社は、現地で「仕分け」を実施し、日本に遺伝子組み換え作物等が流入しないように管理しています。
全農が株式会社化され、そこに「外国資本」が入ればどうなるのか。
我が国の食料流通が、外国に支配されることになってしまいます。
いま着々とその準備が進行し、数年後に、「気付いたらそうなっていた」ということでしょうか。TPP参加はそこへの入り口を意味します。
最近日本政府が、食料自給率の目標を50%から45%だかに下げたという情報もあります。
TPPを見越して、自給率も徐々に下がると見ているのでしょうか。
自給率減→農家減→農業補助金減→財政支出さらに引締め→政府の借金減→財政の健全化実現へまっしぐら
農業に限らず、復興予算はじめ補助金等はこの図式で削っていきたいと思っているのかもしれません。
政府の借金が減ることと、国民が豊かになることは必ずしもイコールではありません。
そのために農業を、国民を、中小企業を犠牲にしたら本末転倒です。
はっきりと言えることは、日本の農業政策は、「農家は自分のことは勝手に守れ、国は予算をもうこれ以上出しません」という考え方が行動に出ていると言うことです。
先に記した日経ビジネス記事のように、人口減少で日本農業は壊滅することを政府は予想している可能性があります。
潰れるゆく農業に、予算を裂くだけ無駄だと考えているのかも知れません。
食料が足りなければ、「アメリカ様から分けてもらえるよ」政策です。
安部総理は、農家は守らなくても、末端の日本人の、普代村民の胃袋も守ってくれるのでしょうか?















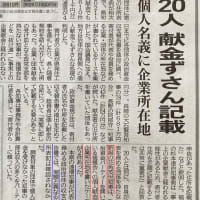
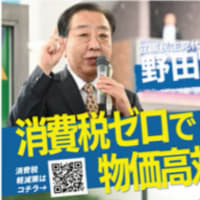


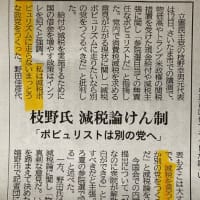
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます