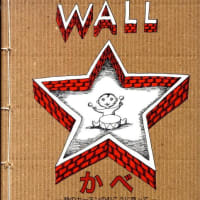「あなたは冷ややかな素振りの内側に、純粋な思いを秘めている。それは尊い。しかしさらにその奥底には、ひとごろしの私もおののくほどの冷たい心がある」
犯人は主人公のフリージャーナリストの太刀洗万智にこう語る。
「ベルーフ」のシリーズの太刀洗万智が初登場した『さよなら妖精』は、もともと『氷菓』に始まる「〈古典部〉シリーズ」の第三作にして完結編にあたる作品だったという(ベルーフはドイツ語で職業、仕事)。
しかし架空の国の内戦を背景にしたハードなテーマが、角川スニーカー文庫の読者層との乖離により本作を出せない状況に陥った。この際、笠井潔の推薦もあって、東京創元社が動き、全面改稿の末に出版されることとなったということだ。
笠井潔は『バイバイ・エンジェル』の矢吹駆シリーズの作者だけれど、太刀洗万智には、女性版・矢吹駆といった趣がある。
『さよなら妖精』は一般読者向けに、架空の国をユーゴスラビアに舞台に変えた。作者の米澤氏の大学時代の専攻がユーゴスラビアだったらしい。『氷菓』では、折木奉太郎の姉・供恵は世界放浪中で、最後はサラエヴォへの手紙で終わっている。
全面改稿に当たって新たに登場したのが、太刀洗万智である。改稿にあたり新たに加わったキャラクターというが(伊原摩耶花とチェンジしたようだ)、冷徹に見えるところが、「女帝」入須冬美とオーバーラップしてしまう。
「古典部」シリーズの入須冬美は、一学年下の折木奉太郎の視点で完璧無欠のように描かれるけれど、同級生の視点の『さよなら妖精』の太刀洗万智は、どこか抜けたところもあり、人間味溢れている。授業中に堂々と舟を漕いで(居眠りをして)、「センドー」(船頭)とあだ名をつけられ、「私はいたいけな園児の頃から流れるような黒髪に憧れていたの」といまどき流行らない「ワンレングス」(若い人、知ってる?)をやめなかったりする。友人たちは冷徹に見える万智が、「いつも一言足りない」だけの不器用な人間であることも理解している。事実上の彼氏の守屋くんを、ボッと出のユーゴスラビア人留学生マーヤに奪われてしまう不憫キャラでもある。
大学卒業後、新聞社に就職した彼女は同僚の事自殺をきっかけに退職し(自殺したのは、『真実の一〇メートル手前』の彼だろうか?)、フリージャーナリストとなる。
『王とサーカス』は、フリー初仕事の雑誌の海外旅行特集で赴いたネパールで、国王を初めとする王族殺害事件(現在も迷宮入りの実話)に遭遇する。早速取材を開始する万智。その彼女の目の前に、この事件に関係がありそうな人物の死体が転がる。
創元推理文庫版の末國善己氏の解説が良かった。そうそう、何の権限もないはずなのに、他人のプライバシーに土足でズカズカ入り込めるのは、フィクションの素人探偵も、現実のジャーナリストも同じなのだ。
〈古典部〉シリーズの折木奉太郎は、持ち前の推理能力で、あるいじめの計画を見抜いて頓挫させたかわりに、自分が悪役を引き受けた苦い思い出がある。〈小市民〉シリーズの小鳩常悟朗にも、似たような思い出があるらしい。
本書のタイトルは、太刀洗万智に、「お前の書くものはサーカスの演し物(だしもの)だ。我々の王の死は、とっておきのメインイベントというわけだ」と、ジャーナリストを批判する軍人の言葉に由来する。特権的な探偵のあり方を問い直す米澤穂信氏の試みは、太刀洗万智を主人公に据え、ジャーナリズムの本質に迫る〈ベルーフ〉シリーズで更に深化されている。
ボオの『モルグ街の街の殺人事件』には「異様な叫び声」「理解できない音声」が登場するが、本書では、異様ではあるが理解できなくはない、あるサインが登場する。笠井潔の名前を挙げたけれど、『王とサーカス』は、同氏の『探偵小説論序説』の「象徴論」への華麗なるアンサーになっているようにも感じた。
(しかし前の記事にも書いたけれど、太刀洗さんももうアラフィフなんだね)