見水の俳句紀行
さげもんがゆれる川面を雛の舟


春になると、水郷・柳川を訪れたくなる。
まちの隅々まで掘割がはりめぐらされた柳川では、2月中旬から4月の初めまで、雛祭りの「さげもんめぐり」が開催される。
昨春は大牟田で義父の七回忌があり、翌日、柳川に立ち寄った。
水上パレードの掘割の通りは、人々で埋め尽くされ、歩けないほど賑わっていた。

堀割に浮かぶれんぎょうゆきやなぎ 見水
「柳川に行ってみんとですか」
義父に誘われ、幼い姪や義兄と初めて柳川を訪ねたのは、30年以上前だった。家を出て、西鉄で30分。柳川駅前から川下り舟に乗り、水辺の花々や赤煉瓦の醤油蔵を眺め、水門をくぐって、家の裏手の水汲み場を見ながら船着場に到着。元藩主立花氏の別邸「御花」で鰻のせいろ蒸しを食べ、北原白秋の生家や詩碑を見てまわった。掘割の美しさに魅了された。

もともと九州に縁はなかった。若い頃に長崎や阿蘇に旅はしたが、異郷の地だった。九州弁も外国語のようでなじめなかった。妻の両親が退職後に帰郷し、九州の大牟田が妻の実家になり、夏休みや正月休みに親族で集まるのが恒例になって、九州は身近な土地になった。
近くのスーパーをのぞくと、醤油は九州独特の甘口醤油、鮮魚売場には有明海の魚介や「ワケ」の名前でイソギンチャクも並び、夏には熊本・植木町の超巨大西瓜が安く売られていた。
持てあます西瓜ひとつやひとり者 荷風
最近も、墓参りや法事で訪れ、柳川に泊まることも多い。



柳川の風景
掘割は家々の裏手にある。表通りを車で走れば、柳川は何の変哲もない地方都市である。
柳川三年肥後三月、肥前、筑前朝飯前
戦国時代、蒲池氏が築き、蒲池氏滅亡後、立花宗茂が入城した柳川城は、堀に守られた難攻不落の城だった。関ケ原の後、田中吉政が封じられ五層の天守閣を築いたが、田中氏の除封で立花宗茂が返り咲き、以後250年間立花氏の居城となり、「舞鶴城」の雄姿を誇った。
維新後1872年に城は焼失。石垣も海岸の堤防に転用され、城下町の面影はほとんどない。
町を外れ、沖端川の河口に来ると、漁船をもやう長い竿が川沿いに林立している。有明海は干満差が6mあり、潮が引くと広大な干潟が広がり、潮が満ちると川の堤防まで海になる。この景観を見ると、柳川に来た実感がわいてくる。
北九州は大陸に近い。古代の磐井の乱、遠の朝廷・大宰府、元寇、キリシタンの席捲と禁教、長崎の平戸・出島、西南戦争、産業の近代化と炭鉱の盛衰…。北九州には、中央の政治の動きとは違った激動の歴史が色濃く残っている。
遠きにありて
詩人・北原白秋は、1885年、この地に生まれた。1904年、19歳で上京、早稲田大学英文科予科に入学する。若山牧水、与謝野鉄幹、与謝野晶子をはじめ、石川啄木、吉井勇、上田敏、蒲原有明、薄田泣菫、森鴎外、斎藤茂吉、折口信夫、谷崎潤一郎、高村光太郎、萩原朔太郎、室生犀星、鈴木三重吉、芥川龍之介、山田耕筰らそうそうたる才人たちと出会い、熱く生き、明治末期から大正、昭和初期、めぐまれた詩才を存分に開花させた。
子規は嫌いで、俳句はあまり作らなかったという。
芥川龍之介は、「食物として」というややふざけた短いエッセイに、室生犀星は干物、谷崎潤一郎は西洋酒で煮て食えばうまい、北原白秋はビフテキだと書いている。白秋は九州人らしくエネルギッシュだった。
さしむかひ二人暮れゆく夏の日のかはたれの空に桐の匂へる 白秋
20代で詩集「邪宗門」、「思ひ出」、歌集「桐の花」を発表し、三木露風とともに「白露時代」ともてはやされる。二度の結婚生活に破綻するが、やがて幸せな家庭を得て、詩集・歌集を次々と世に出すとともに、鈴木三重吉が発刊した児童雑誌「赤い鳥」などに多くの童謡を発表、また寄せられる投稿作品の選者となり、白秋の名声は不動となる。
「砂山」、「からたちの花」、「この道」、「ペチカ」、「待ちぼうけ」。かつては誰もが親しみ、森繁久弥らも愛唱した童謡は、最近あまり聞かれない。詩聖・白秋の名も遠くなりつつある。
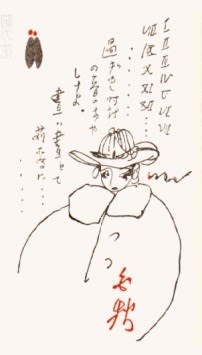


北原家は、江戸時代は海産物問屋として栄え、父の代には一町三反の敷地に10棟ほどの酒倉が建ち並ぶ造り酒屋と魚問屋、精米業を営んでいたが、白秋16歳のときに大火に遭い、26歳のとき一家は破産する。
「思ひ出」は、明治の近代化に取り残されていく故郷柳川への懐旧と決別の詩集である。
時は逝く、何時しらず柔らかに影してぞゆく、
時は逝く、赤き蒸汽の船腹の過ぎゆくごとく。
時は過ぎた。さうして温かい苅麥のほめきに、赤い首の螢に、或は青いとんぼの眼に、黒猫の美くしい毛色に、謂れなき不可思議の愛着を寄せた私の幼年時代も何時の間にか慕はしい「思ひ出」の哀歡となつてゆく。
白秋は、詩集を「わが生ひたち」の文章で始めている。柳川と近郊の暮らしを詩情豊かに描き、読む人を不安で懐かしい少年の心に戻らせる。
白壁や芭蕉玉巻く南京寺 龍之介
1907年、34歳の与謝野鉄幹は、まだ学生の白秋、吉井勇、木下杢太郎、平野万里を伴って、九州を旅する。長崎・天草・島原・阿蘇を巡り、この地に色濃く残る南蛮文化を再発見し、文壇に切支丹ブームを巻き起こす。白秋は処女詩集「邪宗門」に結実させ、後に芥川龍之介は切支丹物を書いた。一行は白秋の実家に2度立ち寄り、北原家は彼らを大いに歓待している。
その後実家の破産により故郷を失った白秋は、柳川を「水に浮いた灰色の棺」「廃市」と言い切り、一家が東京に移ってからは、柳川に帰ろうとしなかった。
帰りなんいざ
20年後の1928年、新聞社の企画で、白秋は故郷柳川の上空を6人乗り小型旅客機で飛ぶ。
白秋は故郷で大歓迎を受け、母校の矢留小学校の子供たちは、雨の中3時間も歓迎の列に並び、飛行の日には校庭に「ヤ」の人文字を書いて白秋を感激させる。破産した生家の跡は缶詰工場になっていたが、中に入ってしばし昔日を懐かしんだという。
晩年、白秋は目が不自由になる。死の前年1941年の帰郷で「帰去来」の詩を作る。
山門は我が産土、/雲騰る南風のまほら、/飛ばまし今一度、
筑紫よかく呼ばへば、/恋ほしよ潮の落差、/火照り沁む夕日の潟
盲ふるに、早やもこの眼、/見ざらむ、また葦かび、/籠飼や水かげろふ。
帰らなむ、いざ、鵲、/かの空や櫨のたむろ、/待つらむぞ今一度。
故郷やそのかの子ら、/皆老いて遠きに、/何ぞ寄る童ごころ。
白秋が亡くなって、戦後の1948年に九州の文化人らが、矢留小学校の横に「帰去来」の碑を建てる。後に「まぼろしの邪馬台国」(1967年)を書く宮崎康平も建立に尽力している。
筑後では邪馬台国の蝉がなく 見水
詩碑はからたちの花に囲まれ、11月2日の命日には毎年、この碑の前で白秋祭が行われ、掘割を「白秋祭水上パレード」が巡航する。
もうし、もうし、柳河じや、/柳河じや。
銅(かね)の鳥居を見やしやんせ。/欄干橋をみやしやんせ。


掘割の物語
二十数年前、テレビで「柳川掘割物語」を見た。この映画は、1987年公開のドキュメンタリーで、脚本・監督は高畑勲、制作(プロデュース)は宮崎駿の個人事務所「二馬力」である。
柳川の風景が出ているので、5歳ぐらいだった息子といっしょに見始めたのだが、川下りの記憶がよみがえり、美しい映像に引き込まれた。黒縁メガネの朴訥とした市職員・広松伝(つたえ)氏が登場したときは、息子と一緒に思わず大笑いしたが、最後まで釘づけになって見た。
息子の通った中学校は神戸一のマンモス校だったが、修学旅行先が北九州で、福岡、長崎を回って3日目の最終日、学年400人全員で柳川の川下りの舟に乗り、「御花」で鰻のせいろ蒸しを食べたという。
水遊び習った歌を鼻唄に 見水
宮崎・高畑のジブリ映画は、「風の谷のナウシカ」「天空の城ラピュタ」「となりのトトロ」「火垂るの墓」がテレビで放映される1990年頃から、子供と親の心をつかみ、「魔女の宅急便」「おもひでぽろぽろ」「紅の豚」「平成狸合戦ぽんぽこ」「耳をすませば」などで客層を広げ、「もののけ姫」や「千と千尋の神隠し」が公開されると誰もが劇場に出かけた。
夏服のメイとサツキが走り去る 見水
「風の谷のナウシカ」の成功に気をよくした宮崎は、プロデュースをしてくれた東映動画の5歳先輩の高畑に、映画制作を勧める。高畑はアニメ映画のロケハンに水郷・柳川を訪れるが、市職員・広松に出会い、掘割そのもののドラマに魅せられて実写映画に変更する。宮崎が資金提供したが、「柳川堀割物語」の制作は1年の予定が3年になり、製作費が嵩んだ。その借金返済のためにスタジオジブリが誕生し、宮崎は急いで「天空の城ラピュタ」を作ったという。
子を空へヒコーキをする夏畳 見水
映画は、美しい掘割の風景から始まり、掘割が果たしてきた役割や巧みな仕組み、かつて厳しく守られながら、荒廃していった掘割の水の変遷を紹介し、柳川に水を引き込んだ先人達の涙ぐましい努力に触れ、市の一職員の市長への直訴を機に、市民が掘割を再生させる姿を描く。
ナレーションはNHKの加賀美幸子・国井雅比古。映画は真摯で説得力のある完璧な教育映画に仕上がった。高畑はこの映画に興行的な成功を求めず、上映は自主上映方式で行われた。東大仏文科で大江健三郎と同期、翻訳家でもある高畑のこだわりだった。
宮崎は20年ほど前から、地元で川掃除のボランティアを続けているという。2001年公開の「千と千尋の神隠し」は神々を癒す湯屋の話で、川に捨てられたごみやヘドロと同化したオクサレ様や、ハクという少年が登場する。どちらも人間に見捨てられた川の神である。
映画「千と千尋の神隠し」は空前の大ヒットとなったが、宮崎は高畑がかつて「柳川堀割物語」で描いたメッセージをこの作品に込めている。
でんさん
市職員・広松は、1937年柳川市生まれで、映画制作当時50歳。市長への直訴から始まった水路再生の取り組みから10年経っていたが、高畑によると広松は、当時、役所内で孤立し、浮いた印象だったらしい。
柳川市は、いま人口7万人だが、2005 年に周辺の2町と合併する前は人口4万人だった。
隣の家具の町・大川市の助役を経て、1959年から1979年まで5期20年にわたって柳川市長を務めた古賀杉夫氏は、白秋生家の復元や川下りの観光に力を入れ、柳川出身の作家・檀一雄や、大川市出身の作曲家・古賀政雄とも親交のある元・文学青年だった。

-1990年頃の矢部川(柳川上流の船小屋付近)-
かつて飲み水や水運に利用されていた柳川の掘割の水源は、小さな矢部川である。
その後、大河・筑後川から水道が引かれ、下水道幹線が整備され、クルマ社会が進む中で、掘割は役割をなくし、水草が繁茂し、ゴミが不法投棄され、悪臭を放ち、訪れた観光客を失望させた。作家の檀一雄は、古賀市長にシュブタ(淡水魚のタナゴの一種)の句を送って嘆いた。
我が故郷はシブタも住まず蚊蚊ばかり 一雄
市は公費を注ぎ込んで業者による掘割の浚渫を行ったが、汚れは進む一方。市民の苦情の声に後押しされ、市と市議会は、5ヵ年計画で国から12億円の補助金を受け入れ総額20億円で主要な掘割以外の掘割を暗渠にして埋め立てることにした。
1977年、水道の技術職で40歳の広松に、都市下水路係長への異動が発令される。
都市下水路係長の職責は、掘割の埋立事業を進めていくことだった。

宮崎康平は「まぼろしの邪馬台国」に、「帰去来」碑建立当時のことを書いている。
柳川の土地は、もともと有明海に堆積した柔らかい泥の層で、重い石碑を設置するには、沈下や傾きに細心の注意を払って基礎造りをすることが、地元では常識になっていた。
水道の技術畑一筋の広松は、柳川の掘割を埋めることの危険性を痛いほどわかっていた。建物や道路が傾き、水害が頻発し、住めない町になる。
すでに設計会社が動きだし、一係長が埋立に反対しても、周囲は取り合わない。広松は意を決して、課長、部長を飛び越え、古賀市長への直談判の挙に出る。
小さな市の組織とはいえ一係長の突然の直訴に市長も驚いただろう。
「いまはもうこの方法しかない。君の仕事は、埋立事業を進めることだ」、と言えば終わっていた。しかし、広松の切々たる訴えは、古賀市長の心の琴線に触れた。
「半年間の猶予を与える。万人が納得のいく実現可能な再生案を出せば埋立計画を中止しよう」、と提案する。

広松は、堀割の歴史的背景、機能と役割、住民の関わり、荒廃の原因、再生の必要性などを少しずつまとめ、「郷土の川に清流を取り戻そう」の文書にして、関係者に配り、住民参加による河川浄化を模索し、現地の実態調査を繰り返す。
先進都市の事例も参考にと、広松は全国で初めて「人間環境都市宣言」をした神戸市を視察する。神戸市ではその頃、兵庫運河をよみがえらせており、神戸市の職員からアドバイスをいただいたと、後に書き残している。
約束通り半年で広松は「河川浄化計画」案をまとめ、古賀市長に提出する。心血を注いだ計画案を、古賀市長はしっかりと受け止める。
早速、市長は議会に埋立計画の撤回と掘割再生計画を上程し、議会の承認を得て、市を挙げて再生事業を進めることになる。
広松は、住民と膝を交えた懇談会を100回以上開き、柳川の堀割の役割を歴史的・科学的に解き、清流の思い出を語り合い、住民主体の掘割浄化を訴えた。そして自ら率先してヘドロの堀に入って水草を取り、浚渫の先頭に立った。
当初は「観光客誘致のためだろう」と不信感や反対があったが、ひたむきな広松(でんさん)への信頼の輪が広がってゆき、わずらわしくても自分たちが汚したものは自分たちの手できれいにする住民参加の取組みがスタートする。
1978年から着手した掘割の浚渫事業は、広松の予測を上回るスピードで達成し、町並みや水辺の整備も進んで、柳川の掘割はよみがえる。

十月の末には、先づ秋祭の準備として柳河のあらゆる溝渠はあらゆる市民の手に依て、一旦水門の扉を閉され、水は干され、魚は掬くはれ、腥くさい水草は取り除かれ、溝どろは奇麗に浚ひ盡くされる。この「水落ち」の樂しさは町の子供の何にも代へ難い季節の華である。
と、白秋が「思ひ出」に書いた「水落ち」で獲れた鯉を料理して酒宴をする様子や、新しい機械を導入し省力化して掘割を浚渫する姿を、映画「柳川掘割物語」はていねいに描く。
人に皆没年のあり夏の河 見水
掘割浄化に着手した翌年の1979年に古賀市長は退任する。掘割への生活廃水の流入や下水道整備の不足などの問題は抱えつつ、広松の直訴と古賀市長の英断で議会の承認を得た「河川浄化計画」の取組みは後戻りすることなく続き、古賀氏は1996年に87歳で亡くなった。
映画・柳川掘割物語で、一躍「公務員の星」となった広松のもとに、全国から自治体関係者らが訪れ、講演を求めた。広松は気軽に応じて出向き、一方で地道に環境保護活動を続けた。1999年に広松は「第1回日本水大賞【市民活動賞】」を受賞する。柳川市立水の資料館嘱託、水の会会長、全国水環境交流会代表幹事を務めたが、2002年に64歳で亡くなっている。
白南風に掘割の水ゆらめいて 見水

白秋生家
2015年の夏、白秋生家と、小さな掘割を挟んで隣接する柳川市立歴史民俗資料館を訪ねた。
資料館には白秋の業績を中心に、柳川周辺の歴史資料が展示されている。





白秋生家は古い酒蔵の母屋と穀倉が保存され、展示写真から、「思ひ出」に描かれた白秋の少年時代の暮らしや、後の柳川への帰郷の様子などがうかがえる。白秋の遺品展示も多い。
展示品の中に、関西学院大学の校歌「空の翼」の楽譜を見つけた。
1933年の大学昇格時に、関西学院出身の山田耕筰は校歌を依頼される。山田は無報酬で引き受け、白秋を伴って、神戸市灘区の原田の森から西宮市上ヶ原へ移転したばかりの真新しいキャンパスを訪ね、二人で作詞・作曲をした。白秋は学内を流れる小川の清流に感心し、ポプラの樹もまだ細かったが、大樹をイメージして詩を作ったという。
風に思う空の翼/輝く自由 Mastery for Service
清明ここに道あり我が丘/関西 関西 関西 関西学院
ポプラは羽ばたくいざ響け我等/風 光 力 若きは力ぞ
いざ いざ いざ 上が原ふるえ/いざいざいざ いざ 上が原ふるえ
自らの鬱々とした柳川での少年時代と上京で得た自由をふり返り、学生たちへの熱い応援歌になっている。
この道
晩年の白秋や山田耕筰が軍部に協力したこともあってか、「この道はいつか来た道」は、戦前の忌まわしい時代への逆行を警戒するフレーズとしてよく使われた。
敗戦後、GHQは政治家や職業軍人を公職追放し、文化人も菊池寛らが公職追放された。
菊池寛は「自分こそ真の自由主義者」と不本意のまま1948年に亡くなった。
公職追放はされなかったものの、藤田嗣治は従軍画家として戦争画を描いたことを非難されてフランスに帰化し、戦争詩を書いた高村光太郎は岩手の山中にこもり、山田耕筰は「戦犯」と罵られ半身不随になるが世界的作曲家として1965年まで生きた。
母に手を曳かれて遠しせみの声 白秋
白秋は敗戦を見ることなく1942年に57歳で亡くなった。
「思ひ出」には、熊本県北端の南関(なんかん)の母の里のことも書いている。南関は柳川の南東5里の山中にあり、白秋少年は夏休みをこの山里で過ごした。
南関への道の郷愁も感じられる「この道」は、すがすがしい情感あふれる歌である。
九州では、自然災害が相次いだ。2016年に阿蘇・熊本で震災、2017年は北九州で豪雨だった。熊本城天守は無残な姿になり、阿蘇大橋は崩落、有明海は一時期流木で埋まった。荒々しい大地の嘆きが聞こえるようだった。
振り向けば二万世紀を抜けた夏 見水
はるばるとやってきて、大牟田で素朴な「草木饅頭」を買う。柳川の宿に落ち着いて、饅頭をつまみながら、柳川の市民が守ってきた美しい掘割を眺める。
縁故の人は少なくなったが、筑後地方は、もう、わが故郷なのかも知れない。







(2018.2・見水)

























一気に読みました。見水さんと広松さんがダブりました。そして、奇しくも、今日のニュースで高畑勲氏の訃報が流れています。
私は、福岡で学会があったとき、柳川まで脚をのばしました。御花の鰻せいろ蒸しも頂きましたよ。
あらためて見水さん、紀行文、上手いなあと思いました。