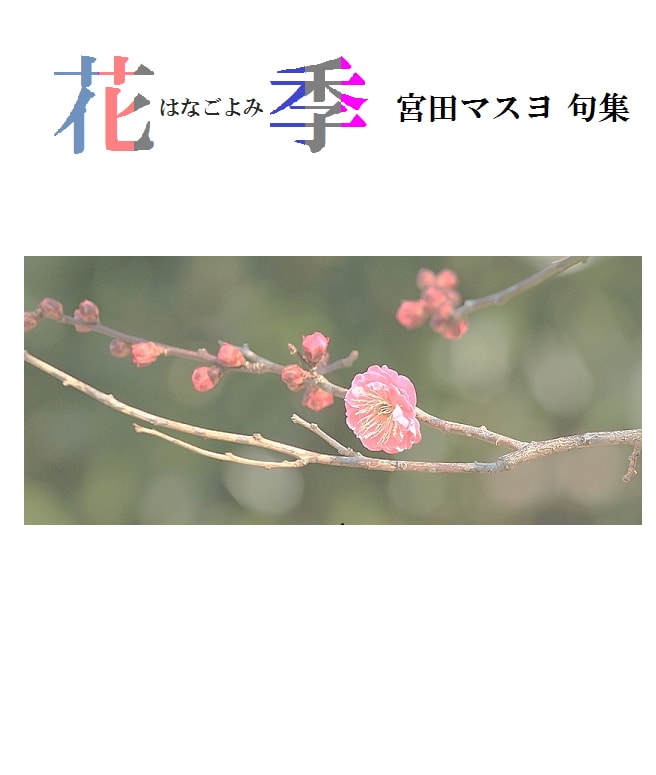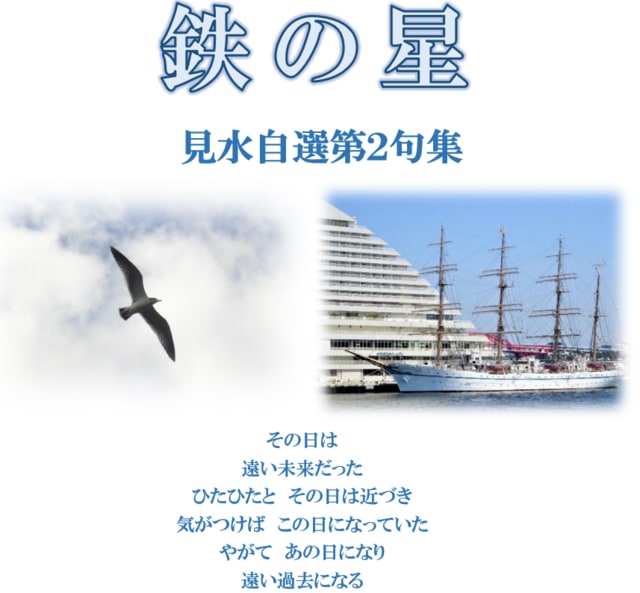

牧場へと続く山道風涼し 21・森林植物園・弓削牧場句会
ヤルゴイは草原の花夏の牛 21・森林植物園・弓削牧場句会
緑蔭の句会にひらり蝶の来る 21・森林植物園・弓削牧場句会
アオサギの巨体のっそり原生林 徳島
ホーホケキョ同行二人の笠の上 徳島
俘虜の地は夏の緑に囲まれて 徳島
くねくねと黒塀の道新酒の香 22・魚崎郷ほろよい句会
この沖に新酒番船集結す 22・魚崎郷ほろよい句会

島渡る船を待つ人春を待つ 日生港
海うらら自転車道は岬へと 小豆島
春山を背に黒々と醤油蔵 小豆島
これがまあ放哉庵か咳ひとつ 小豆島
現れた砂州また消えて春の波 小豆島
海鼠ゲタメバルぶちまけ並べられ 小豆島
かわらけが突き抜け空も海も春 小豆島・寒霞渓
葡萄づる勢いを増す夏の空 23・夏の神戸ワイナリー句会
ひばり鳴き山桃実るワイン城 23・夏の神戸ワイナリー句会
仰ぎ見る主塔すっくと天高し 24・海峡スケッチ句会
玉葱は完売しました道の駅 24・海峡スケッチ句会
三ケ日の潮風やさし甘蜜柑 浜名湖

さげもんがゆれる川面を雛の舟 柳川
庭眩しつつじ赤白咲き始む 25・北野工房寄り道句会
薫る風館の鎧戸開け放つ 25・北野工房寄り道句会
燕飛ぶハイカラ神戸坂のまち 25・北野工房寄り道句会
ろうそくに春の楽しさ塗りこめる 25・北野工房寄り道句会
遊覧のデッキに群れる冬鴎 26・神戸開港150年句会
冬鴎突然高く舞い上がる 26・神戸開港150年句会
小春風飛鳥出港十七時 26・神戸開港150年句会
元町に波止場の名残冬温し 26・神戸開港150年句会
本堂は紅葉伊吹山は雪 東近江

孫 文
レーニンや毛沢東やチェ・ゲバラが英雄だった頃
孫文もまた偉大な英雄だった
文革が失敗し、ソ連が崩壊し
毛沢東もレーニンも、忌まわしい独裁者になった
「革命いまだならず」
それでよかったのだ
孫文はいい時に死んだ
夏来る夢見ぬ男のゆめの跡 27・初夏の舞子海岸句会
吊り橋の消えゆく先に青岬 27・初夏の舞子海岸句会
藤村の詩を朗誦す夏座敷 馬籠
一万騎過ぐ涸れ川の湊川 28・湊川まちぶら句会
枯尾花イギリス積みの煉瓦壁 28・湊川まちぶら句会
冬空にここぞと立てり赤鳥居 鎌倉
冬ざれの参道長し鶴岡宮 鎌倉
舞殿は今日は凩舞ふばかり 鎌倉
江ノ電に家々迫る冬隣 江ノ電
冬波の寄せくる七里電車ゆく 江ノ電
冬鳩を追って大路の豊島屋へ 鎌倉
大輪の山茶花の赤ちらほらと

容赦なき機銃掃射の塀薄暑 29・城下町尼崎句会
夏草を食む赤き牛霧深し 阿蘇
花蜜柑段々畑の丘の道 宇土半島
胸おどる藍より青き夏の海 天草
絵にしたい四郎ヶ浜の夏の雲 天草
ちょこちょこと瓜坊六甲お出迎え
蚯蚓鳴く悲話語り継ぐおとめ塚 30・御影ハイカラ建築句会
寒稽古飄然と立つ治五郎翁 30・御影ハイカラ建築句会

鉄の星
宇宙から降る素粒子は
隙間だらけの地球を
難なくすり抜け
宇宙の彼方へ飛んでゆく
地球は卵のような星
薄い殻の大地
白身のマグマが煮えたぐり
黄身は鉄とニッケル
地球の三分の一は
鉄とニッケルの塊で
その磁力のために
天空をオーロラが泳ぐ
虚しくはないのだろうか
この星の科学者たちは
春めくや小さな駅の待ち合わせ 三木下見
日脚伸ぶわが青春の城下町 三木下見
五月には萌える新緑寒雀 三木下見
冬ぬくし地産地消のバイキング 三木下見
春隣昭和の町をそぞろ行く 三木下見
上の丸二の丸黒し冬銀河 三木下見
巣篭りの庭にちいさな菫草
春眠は出口の見えぬ夢ばかり
鯉幟くねる里山千の風
所在なく季節過ぎゆく夏木立 31・夏のおうちde句会
日溜りに三人三様秋惜しむ 32・秋のおうちde句会
ふりそそぐ小春の光ちぬの海

花堤抜けて顔出す昼列車 33・春のおうちde句会・三木句会
紋黄蝶保育園児のように逃げ 33・春のおうちde句会・三木句会
巨大なる夏雲一瞬顔となる 34・夏・俳句日記句会
長嶋の一歩は待てる夏五輪 34・夏・俳句日記句会
はちきれんばかりの獅子唐苦み良し 34・夏・俳句日記句会
北神ねぎ入口に盛る道の駅 35・淡河本陣マスク句会
納屋カフェの太き煙突薪暖炉 35・淡河本陣マスク句会
冬日射す三百年の石灯篭 35・淡河本陣マスク句会
凍空に温し淡河の十割蕎麦 35・淡河本陣マスク句会
久々に集ひし句座の暖かし 35・淡河本陣マスク句会
古希祝小春の街の中華飯
六甲の峰ベランダに蒲団干す

1972年
生まれ変わる札幌の街で冬のオリンピック
恥ずかしながら横井さんがグァム島から帰還
山岳での陰惨な連合赤軍事件の総括
米軍基地を抱えて沖縄が復帰
独りテレビに向かって佐藤栄作が退陣
逗子のマンションで川端康成が自死
日本列島改造論を手に田中角栄が首相
ニクソンに続いて中国に行き国交を回復
この年、二十歳だった
若い助教授の刑法ゼミで「自由」を議論し
裁判の傍聴や刑務所の見学に出かけた
翌年ベトナム戦争がようやく終わり
オイルショックで何もかも値上げ
あれから半世紀が経った
「自由とは」半世紀前のゼミの春
赤豌豆そよ風の庭咲き揃ふ
風ぐるま地球クルクル棲み難し
鯉のぼり泳げ平和の空泳げ 36・祝20周年みたび、有馬句会
ねね橋にみたび参りて若楓 36・祝20周年みたび、有馬句会
緑さす炭酸泉源のぼりきて 36・祝20周年みたび、有馬句会
梅雨明けて印南野からの千の風 播町さん弔句
マドンナ逝く雨の六甲ねむの花 だっくすさん弔句
未来図に寂しさもあり秋うらら 37・回想の三宮句会
市庁舎に冬の日差しが降り注ぐ 37・回想の三宮句会
メタセコイヤの巨人たちみな紅葉 37・回想の三宮句会
小春日の海風やさし花時計 37・回想の三宮句会

永き日に欠伸を一つ本を閉ず 38・花の大中遺跡句会
悠久の大中遺跡青き踏む 38・花の大中遺跡句会
洗い場に下りていきたい夏の川 若狭熊川宿
次から次赤蜻蛉来る琵琶湖畔 彦根
夕焼雲鯖街道の鯖を焼く 彦根
舞い上がりやがて着水夏の湖 彦根
ソーラーがしれっと並ぶ炎天下 近江路
酋長の座す草屋根の夏館 近江八幡
紅葉散る平氏栄えし湊山 39・みなとやま水族館句会
六甲颪神戸の街を吹きわたる 39・みなとやま水族館句会

船溜まり雨に打たるる残り鴨 40・新長田・駒ヶ林ひねもすのたり句会
春雨に打たれ鉄人飛び立つか 40・新長田・駒ヶ林ひねもすのたり句会
其の日此の日やがてはあの日春惜しむ
野も山も若葉の萌ゆる鉄の星

4月3日、新長田・駒ヶ林で第40回神戸RANDOM句会を開催。その後、桜を長く楽しんだ。
2014年に播町さんがネット句集を提案され、翌年、ブログに句集「二万世紀」の99句をアップした。あれから9年が経っている。
遅き日のつもりて遠きむかし哉 蕪村
日が永くなったので、「二万世紀」以降の、第21~40回の句会(未投句の句を含む)や旅先、見水庵(6畳の自室)で詠んだ350句から100句を選び、第2句集を編んだ。後半のコロナ禍や播町さんとだっくすさんの旅立ちで心の重い日々に詠んだ句も、愛おしいあの日の記憶。絵や写真や詩を混ぜた‟見水ワールド”で再び遊んだ。
コロナ禍の巣籠もりで、わが地球のことを調べていたら、地球の1/3は鉄の塊であることを知り、詩にした。詩のタイトルの「鉄の星」を、句集のタイトルにした。
5月になった。いま、空も海も山野も命の満ちあふれる列島である。
見 水
見水・プロフィール…1951年に生まれ、神戸で暮らし続けている。
********************
見水自選第2句集
鉄の星
著者:見水
2024年5月1日
発行 KOBE@RANDOM