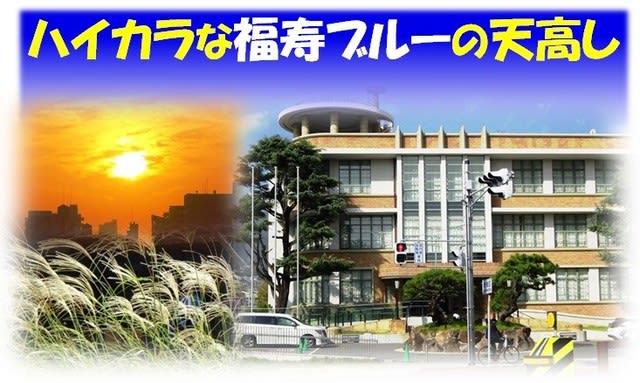
秋が深まると、六甲の裏に広がる酒造会社の幟の立つ兵庫の稲田は黄金色に輝き、酒米が刈り取られていきます。
10月は、消費税10%への増税に始まり、吉野彰さんのノーベル賞受賞、日本でのラグビーW杯開催で沸き、各地の秋祭りで盛り上がる中、台風15・19・21号の東日本豪雨が広範囲に河川を決壊させ甚大な被害。天皇即位祝賀パレードも11月に延期され、自然災害と隣り合わせの列島を実感しました。
第30回神戸ランダム句会は、過去の水害・戦災・震災に耐えて2年前に蘇ったハイカラ建築・御影公会堂をめざし、新酒の仕込みの始まった灘の酒蔵にも足を延ばします。4年前の第22回の句会では御影郷の東端から魚崎郷、住吉川を歩きましたが、今回は御影郷の西地区と石屋川を歩きます。
御影塚町・石町を歩く―――――――

令和元年10月30日(水)、午前10時15分、阪神電車・新在家駅前が集合場所。
秋佳日るんるんるんや句会便 ひろひろ
暑い秋やっと過ぎると夜寒かな 英
六甲の黄砂の空に鰯雲 英① (丸数字は句会での得点)
楽しきは句会と仲間秋日和 蛸地蔵①
昨日の雨が上がり朝の霧も晴れて気持ちのいい秋晴です。ただし天気予報では季節外れの黄砂が飛んでくるとのこと。
句会の参加者は、さくらさん、だっくすさん、つきひさん、どんぐりさん、へるめんさんと女性5名。男性は一風さん、蛸地蔵さん、英さん、播町さん、ひろひろさん、見水さんの6名で総勢11名。
用意してきた本日の吟行のコースとスケジュール表を全員に配ります。
吟行のスタートです。少し東へ歩くと浜田公園。近くの保育園児らが保母さんと元気一杯遊んでいます。横を通り抜けながら蛸地蔵さんはわがお孫さんを思い浮かべ、会心の一句、
赤白の兵隊帽の児秋遊び 蛸地蔵
を詠みましたが、なぜか選句に入らず。この公園を過ぎると東灘区。昭和初期のハイカラ建築「甲南漬資料館」が見えてきます。
甲南漬資料館


南側は国道43号線と阪神高速、北側は阪神電車石屋川車庫に挟まれていますが、この一画は都会のオアシスのよう。他の観光客も訪れています。
建物は1930年築で、設計者は、今日の午後に向かう御影公会堂を設計した清水栄二。蒲鉾型の屋根や階段室の窓、玄関の庇のデザインが独特です。
清水栄二(1895~1964)は地元六甲村出身の建築家で、東京大学で学び、古い伝統に挑戦し当時世界的に流行した表現主義などを取り入れた建築を、神戸中心に数多く手がけました。
高嶋平介商店の2代目当主は、甲南漬(奈良漬)の製造で成功し、清水の設計でこの邸宅を建てました。現在は国登録有形文化財に指定され、甲南漬資料館として保存し公開しています。内部も海外の調度品を集めた重厚な造りです。


玄関を入ると天井の高い1階の廊下沿いに、奈良漬の歴史や酒粕と灘五郷の関わり、髙嶋酒類食品150年の歴史、味醂作りの道具などを展示。阪神・淡路大震災で倒壊する前の魚崎郷・御影郷の模型もあります。格式高い洋室は喫茶コーナー、日本庭園に面した和室は食事処。
建物を出ると、日本庭園が残され、片隅に鬼瓦も置かれています。
鬼瓦屋根を下され暮の秋 どんぐり⑤◎ (◎は特選句で2点)
外にかまどがあり、店の人が5升炊きの大釜で御飯を炊いていました。
冬支度羽釜飯炊く薪を積む どんぐり④◎
薪を焼(く)べ大釜で炊く今年米 だっくす⑤◎
炊き立ての新米にぜひ甲南漬 見水①
日本庭園を抜けた「武庫の郷」では、甲南漬や関連商品を販売。句会の賞品の甲南漬を調達。





「武庫の郷」を出て東へ歩きます。「高羽川」の表示のある用水路のような川をふと覗くと、海抜が低いため海水が逆流しています。潮に乗って小さな稚魚。
「ボラの子やな」
思わぬプレゼントでした。
処女塚


さらに東へ歩くと、こんもりした森が見えてきます。処女塚古墳です。
処女塚古墳は、全長70mの前方後方墳で4世紀前半頃に築造。国の史跡に指定されています。車の交通量が多く、古墳には石段もあるので、見て通り過ぎる予定でしたが、
「いままで来たことがなかった。せっかくなので寄ってみたい」
の声があがり、天気もいいので自由に見学し、神戸酒心館で11時30分に合流することに。
金柑や石段登り処女塚 だっくす
秋風や処女塚から家並見る 一風
処女塚桜色づき初めんとす へるめん
万葉集や大和物語には、この地の伝説として、菟原処女(うないおとめ)が菟原壮士(うないおとこ)と茅渟壮士(ちぬおとこ)の激しい妻争いに耐えられず命を絶ち、男達も後を追って、遺族が3つの墓を造った話を残しています。西に2km離れた場所に西求女塚古墳、東に1.5km離れた場所に東求女塚古墳があります。
身に入むや身焦がす恋の処女塚 さくら
蚯蚓鳴く悲話語り継ぐおとめ塚 見水⑤◎◎
天気がいいので、蝶や小鳥も来ています。
カップルで処女塚舞ふ秋の蝶 さくら④◎
処女塚近き公園小鳥来る どんぐり
古墳の傍らには古い石碑が2つ建っています。1336年の湊川の戦いに敗れた総大将・新田義貞を京に逃すためここで討死した小山田高家の石碑と、処女塚に立ち寄って詠んだ万葉歌人・田辺福麻呂の歌碑です。



処女塚古墳の東隣には、東明の地名の由来となった神功皇后ゆかりの東明八幡神社があります。1700年前に武内宿禰が植えたという幹まわり5mの「武内松」の巨木が摂津の名所として明治時代まであり、近在からも大勢訪れたそうです。
神戸酒心館

国道43号線を渡って、御影郷の酒蔵へ。
行く秋の昭和を醸す酒どころ 播町④
御影郷新酒の香り訪ひ歩く さくら①
神戸酒心館に到着。堂々とした門を入ると、萩やすすき、柿などが植えられた庭が目に飛び込んできます。
萩に柿酒屋の庭の門構え 蛸地蔵②
酒蔵に萩・すすき・友せいぞろい 英③
ここは御影郷の清酒「福寿」の蔵元の酒造会社。
福壽酒造は1751年にこの地で清酒の醸造を始めましたが、1995年1月の阪神・淡路大震災で木造蔵が全壊し、2年後に豊澤酒造とともに神戸酒心館を設立。蔵元のほかに、酒の量り売り販売も行う東明蔵や、「旬の酒と肴」をテーマにした料亭「さかばやし」があります。


門の脇に2つの大きな桶が置かれ、中に板があって休憩できるようになっています。
立札には、「お酒の仕込みに用いました。約6キロリットル入ります。毎日180mlずつ飲むと87年かかります。昔は酒造りが終わると桶を洗い、これを蔵の外で干すため子供の恰好の遊び場になっていました。」の説明が英文でも書かれています。
中に入って座ると開放的で風も心地よく、大樽に住んでいた古代ギリシアの哲学者の気分。
処女塚をゆっくり見学したメンバーも、「さかばやし」の予定開始時刻の11時30分に到着。早速、昼宴を始めます。
1階の奥の個室に案内され着席。手作りの新豆腐や湯葉を使った季節料理が並んでいます。席に着いて、会費の徴収。続いて、11時40分に乾杯。
今回は、ノーベル賞受賞後の晩餐会で提供される福寿の青瓶を注文し、全員の杯に注ぎ、係りの人に乾杯の写真のシャッターをお願いしました。



ノーベル賞福寿の新酒出番待つ 一風②
ノーベル賞誉は灘の新酒とて さくら①
ノーベル賞流石神戸は粋な街 ひろひろ
ロウソクの科学に乾杯新酒注ぐ 見水
今年は12月10日に名城大教授で旭化成名誉フェローの吉野彰さんがリチウムイオン電池の開発でノーベル化学賞を受賞します。2008年に4人の日本人がノーベル賞を授与した時期から、日本人がノーベル賞を受賞した晩餐会では「福寿純米吟醸(青瓶モデル)」が出されています。
吹田市出身で、小学校4年の担任教諭にファラデーの「ロウソクの科学」を読むよう薦められて科学への目を開かせたという、カラオケと日本酒が好きな吉野先生、晩餐会の「福寿」の乾杯で大いに盛り上がることでしょう。
「リチウムイオン電池も、初めはなかなか使い途が無かったらしいな」
一風さん、かつてラジオ講座で3ヵ月間、吉野彰さんの講義を熱心に聞いたとか。
おっとっともちょっと飲ませ今年酒 一風①
古酒新酒世間ばなしを山盛りに つきひ①
少しお酒が入ったところで、句会幹事長の一風さん、
「幹事にこの句会への意見があればお聞きします」
「ないない、いつも、ありがとう」
「ありがトウならミミズはハタチ。イモムシ十九で嫁に行く」
「何それ?」
と、しばし、世間話で盛り上がります。
冷し酒神戸憂える一語あり 播町
新酒酌む男老いても凛として 播町⑤◎


福寿の酒瓶の濃いブルーの色に、しみじみと見惚れます。
「きれいな青色やな」
「福寿ブルーや」
「ノーベル賞のお酒・福寿ブルー、いいわね。句に詠みたい」
秋灯下福寿ブルーの吟醸酒 つきひ②◎
先生は福寿ブルーの今年酒 播町①
「最近は『阪急ブルー』もできたんや」
神戸・三宮では、10月にそごう神戸店が85年の歴史を閉じ、神戸阪急に交代。
神戸阪急はイメージカラー「神戸ウインドブルー」を万年筆インクの「Kobe INK物語」を手がけるナガサワ文具センターと共同開発し、この色を使った帽子や小物などのオリジナル商品を販売。ほんのり緑がかった鮮やかな青色で、港からの潮風と自然豊かな六甲山からの風を、新店舗の新風として吹かせます。
桐一葉青春はそごうに花時計 へるめん
12時30分、御飯とデザートのシャーベットをいただき、ほろ酔いで「さかばやし」を出ます。
今年酒飲める幸続けよと 蛸地蔵①
深秋やほどよく酔ひて老い楽し へるめん②
美酒からだ廻り御影の秋惜しむ へるめん
秋うらら昼酒に酔ひ御影郷 だっくす①
あとは、御影公会堂での句会です。5句を作らなくては。
新酒呑むランダム句会ほろ酔いや ひろひろ
灘五郷五臓六腑の熟柿句を ひろひろ④◎◎
御影郷古酒を楽しむ吟行と 英
新酒(あらざけ)に気分洋々いざ句会 蛸地蔵①






神戸酒心館の庭はよく手入れされ、すすき、萩、ザクロ、柿など季節感たっぷり。さらに目敏く、水引草、錦木、池の鯉、みのむし(鬼の捨て子)、1~2輪の冬桜などを見つけて句づくりに活かしたメンバーもいれば、目が節穴のその他大勢のメンバーも。
小流れに白水引のひそやかに さくら①
一献の昼餉錦木紅葉かな どんぐり②
水澄みて日本画めきし鯉現るる つきひ
宙ぶらりん鬼の捨て子と酒林 つきひ
酒蔵の壁にまぎれて冬桜 どんぐり③
ほろ酔ひの至福に仰ぐ冬桜 つきひ①
一風さんは、大樽の中でちょっと一息。
昼食べて樽の中からすすき見る 一風
忙しく句づくり励み秋惜しむ 一風
句会のスケジュールが押していますが、ここ東明蔵の販売所での句会の賞品調達もあり、御影公会堂での句会の開始時間を少し遅らせます。
母在れば土産にしたし新酒糟 だっくす④
酒蔵の町に短き秋惜しむ だっくす④◎
予定では、全員揃って神戸酒心館を出て、句会場の御影公会堂までの約1kmの酒蔵の道と石屋川を吟行することにしていましたが、皆さんいよいよ「老人力」がつき、行動緩慢、時間無視、ばらばらの動き。午後1時半頃までに各自で句会場に着くことにして、移動を開始。
酒蔵の道・石屋川を歩く




神戸酒心館の東側の泉酒造も今年の酒造りを始めています。「酒蔵の道」には御影郷の酒蔵のイラストや案内図も掲示。江戸時代には海に面して酒蔵がひしめくように建っていたようです。
酒蔵の道から石屋川に沿って北へ43号線と阪神電鉄を抜けます。遊歩道や公園のある川の左岸(東側)を歩きます。昔から残された松の緑も多く、少し色づき始めた六甲山や秋の雲を眺めながら歩くと、2019年の神戸の街中にいることを忘れさせます。
石屋川秋の水流れ茅渟の海 英
表現は自由ぞおおい秋の雲 へるめん


公園を抜け、国道2号線を渡って、御影公会堂に到着。
御影公会堂



御影公会堂は、国の登録有形文化財に登録され、集会施設に利用されるほか、地階の老舗洋食店のオムライスが有名です。
建設当時、東灘区はまだ神戸市に編入されておらず、公会堂は御影町の施設として建てられました。建設費用のほとんどは、白鶴酒造の7代当主・嘉納治兵衛(1862-1951)の寄付で賄われ、1933年に竣工。公会堂の玄関ホールに嘉納治兵衛の胸像が掲げられています。
建築家・清水栄二にとっては、今日最初に見学した甲南漬資料館(高嶋邸)から2年後の設計です。丸窓、アーチ窓、アールをつけたコーナー、重厚感のあるタイルの外装、水平を強調する庇、太い円柱が並ぶ館内の通路等、斬新な建築スタイルが満載。
築百年秋気に澄みてモダンなる 播町①
公会堂ハイカラ建築秋御影 ひろひろ
公会堂の米寿を祝ひ山粧ふ 見水②



1945年、3度にわたる神戸大空襲により御影町は焦土と化し、公会堂も被災しました。
1950年に御影町と神戸市が合併した後、市が修繕・改修し、1953年から使用を再開。1957年から結婚式場を設置し、最盛期には年間1100組が挙式しましたが、その後各地に結婚式場ができ1983年に閉鎖。施設の利用も次第に減少しました。
1995年の年初、神戸市は公会堂を大改修して柔道の殿堂「嘉納記念館」とする構想を立案。が、半月後に阪神・淡路大震災が発生。約1年避難所として活用し、構想は立ち消えになりました。
震災から21年後の2016年、神戸市は耐震化、老朽化修繕及びバリアフリー工事を行い、2017年4月に再オープン。地階に御影郷土資料室と嘉納治五郎記念コーナーが設けられました。


嘉納治五郎(1860-1938)は、御影で生まれ、東京大学で学業を修め、高等師範学校の校長などを務めた教育者。学業のかたわら柔術を習得・研究し、21歳で講道館柔道を創始。国民への体育の普及とスポーツを通した社会貢献に力を注ぎました。柔道の精神として唱えた「精力善用」「自他共栄」は、設立に関わった現・灘中学校・高等学校の校是にもなっています。世界的な視野を持つ国際人で、ユーモアがあって人望があり、小泉八雲や魯迅、クーベルタンらとも心を通わせ、柔道は世界的なスポーツになりました。
今年のNHK大河ドラマ「いだてん」では、50代以降の治五郎の、日本のオリンピック初参加や東京開催招致の成功などの尽力を、役所広司が熱く演じ、治五郎の知られざる魅力を引き出しました。
寒稽古飄然と立つ治五郎翁 見水
ご本人は、記念コーナーの柔道着姿の銅像ほどの小柄な飄々とした方だったようです。
御影句会――――――――――――
午後1時30分過ぎ、句会場の御影公会堂303集会室にようやく全員集合。この部屋は最上階の南西の部屋で、天井が高く、コーナーはこの建物の特徴のアールがつけられています。11人が座るには十分ですが、部屋の真ん中の円柱が少しじゃま。改修してまだ2年半なので隅々まできれいです。
各自、自由に席に着き、渡された5枚の短冊に句を書いて提出。出句の締切は午後2時です。


午後2時、集まった短冊をばらして選句表に清書し、清書した選句表を受付事務所のコピーサービスで人数分コピー。清書からコピーができるまで、つきひさん差し入れの和菓子・ほうらく饅頭をいただきながら、コーヒー&ティータイム。

午後2時40分全員に選句表を配付し、各自、自作以外の気に入った6句を選びます。特選1句2点、その他5句は1点で、各人の持ち点は計7点。参加者11名の総点数77点の争奪戦です。
午後3時、つきひさんの進行で、特選句から順番に選んだ理由も挙げながら発表。55句全部に点数が付けられて作者が明かされました。
高得点句
本日は5点獲得句が4句と、4点句が6句ありました。
鬼瓦屋根を下され暮の秋 どんぐり⑤◎
二度と使われることのない鬼瓦が哀れです。
薪を焼(く)べ大釜で炊く今年米 だっくす⑤◎
甲南漬食事処の5升炊の釜。煙にむせる竈。
蚯蚓鳴く悲話語り継ぐおとめ塚 見水⑤◎◎
この塚を蚯蚓も土の中でずっと守ってきた。
新酒酌む男老いても凛として 播町⑤◎
男はいつまでも凛々しくあらねばならない。
冬支度羽釜飯炊く薪を積む どんぐり④◎
人は何千年もそうして暮らした。
母在れば土産にしたし新酒糟 だっくす④
粕汁か甘酒作ってみましょうか。
カップルで処女塚舞ふ秋の蝶 さくら④◎
悲恋の地の蝶たちはお幸せに。
行く秋の昭和を醸す酒どころ 播町④
あの頃は地酒ブームに沸いた。
灘五郷五臓六腑の熟柿句を ひろひろ④◎◎
五臓六腑沁みわたる酩句です。
酒蔵の町に短き秋惜しむ だっくす④◎
酒造りの文化を満喫した一日。
みんなで添削
午後4時、今回の獲得点数が決まったところで、30分間の時間をいただいて新しい試みです。点数が取れなかった句をどう添削すればいい句にできるか、テレビ番組のプレバトのようにみんなで意見を出し合ってみることにしました。
例として、4年前の句会の0点句の
(添削前) 酒造り唄利酒でまわる酔い
を、つきひさんとだっくすさんが添削した結果、
(添削後) 利酒に酔い酒造り唄に酔い
と直せば、言いたいことが相手によく伝わるのではないか、との結論。


では、今回点数が取れなかった句を1つ取り上げます。私ならこう直す、と意見を言ってください。
(添削前) 公会堂ハイカラ建築秋御影
「公会堂は建物なので、建築、は要らないのでは」
(添削1) ハイカラや秋の御影に公会堂
「それなら、御影公会堂の秋、がいい」
(添削2) ハイカラや御影公会堂の秋
「これで良くなりましたか。どうでしょう」
「自分はやっぱり元のままがいいと思う」
「そうかしら。今回はこれくらいで、またやりましょう」
いい勉強になりました。次回もぜひ続けてください。
表彰式
午後4時30分、獲得点数により表彰式。14点獲得者はお二人いるので、ジャンケンします。
優勝はどんぐりさん(14点)、続いてだっくすさん(14点)、播町さん(11点)。
他のメンバーは、見水さん(8点)、さくらさん(7点)、蛸地蔵さん(5点)、つきひさん(4点)、ひろひろさん(4点)、英さん(4点)、一風さん(3点)、へるめんさん(2点)。
今回の賞品は、幹事のさくらさんとへるめんさんが武庫の郷・甲南漬と神戸酒心館・東明蔵の売店で選んだ御影の特産品です。

受賞者 賞品
優勝 新酒賞 どんぐりさん 清酒・福寿 純米吟醸
2位 新走賞 だっくすさん 清酒・福寿 寒造り
3位 今年酒賞 播町さん 清酒・福寿 ひやおろし
4位 当日敢闘新米賞 見水さん 清酒・福寿 御影郷
5位 桔梗賞 さくらさん 甲南漬とおつまみ
6位 秋桜賞 蛸地蔵さん 甲南漬とおつまみ
7位 野路菊賞 つきひさん 甲南漬とおつまみ
7位 木犀賞 ひろひろさん 甲南漬とおつまみ
7位 白萩賞 英さん 甲南漬とおつまみ
10位 ブービー木槿賞 一風さん 梅酒
11位 芙蓉賞 へるめんさん 甲南漬とおつまみ
今回の「御影ハイカラ建築句会」は、当初は、嘉納治五郎記念コーナーのある御影公会堂と甲南漬資料館の見学をメインに処女塚、神戸酒心館、石屋川を吟行し、御影の町の様々な句が詠まれる予想でしたが、吉野彰さんのノーベル化学賞受賞のニュースもあって、福寿・神戸酒心館での句がメインになったようです。女性軍対男性軍では、つきひさんやへるめんさんの句になぜか点が入らず、女性軍がややリード、で句会は終了しました。
句会場を出て、御影公会堂をバックに全員の記念写真を撮ろうと、公会堂の方にお願いしてシャッターを押していただきました。

天気に恵まれた秋の一日を満喫。全員で阪神石屋川駅まで歩き、その後、有志で三宮の居酒屋で二次会を楽しみ、散会しました。
今回の事前準備と幹事の一風さん、さくらさん、へるめんさんお疲れさまでした。
さて次回は、また神戸を離れましょうか。ご希望があれば一風幹事長まで。
2019.11 写真/bantyo,mimizu・文/mimizu


























添削前も添削後も、季語の選択が安易ですね。
築数十年の公会堂をリスペクトして句にするには、
澄み渡った高い空に向かって立っているイメージがいいのでは。
そこで、
(添削3)ハイカラな公会堂や天高し
シンプルすぎるかもしれませんが……。
ブログ、楽しく拝見しました
さすがです
お世話下さった皆さま、大変ありがとうございました。