過日,取手駅の近くの長禅寺さんまで散歩しました。
そこで長禅寺さんの由来を見つけました。
再掲になりますが,その由来を記します。
-----
長禅寺の由来
創建は平将門と伝えられており,境内には市指定文化財の三世堂をはじめ数々の堂宇や,小林一茶句碑,小川芋銭景幕の碑,開闡郷士碑などがある。
また,新四国相馬霊場八十八ヶ所の総本山で,一番,五番,八十八番の札所でもある。
-----
写真は,これです。クリックすると拡大します。

この中の「小川芋銭景幕の碑」の「景幕」がわからないと,コメントをいただきました。
どうも「景幕」の字は,「景慕」の誤植のようです。
そこで以前,旧取手宿本陣について,メールをいただいた市役所の方に確認することにしました。
ついでに,どうしてもわからなかった「トンパチ」についても,確認しました。
トンパチは,以前酒仙堂さんに教えてもらった言葉なのですが,ネットでも確認できずにいたものです。
----
■トンパチについて
坂口安吾さんの作品に,日本文化私観というのがあります。
この中の「四 美に就て」という個所に,以下の文章がでてきます。
三年前に取手という町に住んでいた。
利根川に沿うた小さな町で,トンカツ屋とソバ屋の外に食堂がなく,僕は毎日トンカツを食い,半年目には遂に全くうんざりしたが,僕は大概一ヶ月に二回ずつ東京へでて,酔っ払って帰る習慣であった。
尤も,町にも酒屋はある。
然し,オデン屋というようなものはなく,普通の酒屋で,框(かまち)へ腰かけてコップ酒をのむのである。
これを「トンパチ」と言い,「当八」の意だそうである。
即ち一升がコップ八杯にしか当らぬ。
つまり,一合以上なみなみとあり,盛りがいいという意味なのである。
村の百姓達は「トンパチやんべいか」と言う。
勿論僕は愛用したが,一杯十五銭だったり,十七銭だったり,日によってその時の仕入れ値段で区々(まちまち)だったが,東京から来る友達は顔をしかめて飲んでいる。
----
で,市役所の方からメールをいただきました。
「景幕」は「景慕」の誤植だったようです。
また,「トンパチ」については,坂口安吾の作品にでてくるのは知っていたそうですが,聞いたことはないそうです。
そこで,少し調べていただきました。
以下,そのメールの概略です。
----
先日メールをいただきました坂口安吾の随筆中にある「とんぱち」についてですが,
取手やその周辺生まれの70代の男性に聞いたところ,「とんぱち」という言葉自体聞いたことがない
ということでした。
取手では,「だっぺ」のようにポピュラーな方言ではないかもしれません。
また文献で「とんぱち」について調べたところ、
小学館発行「日本国語大辞典」には方言として掲載されており,
①鉢(鳥取、出雲地方)「どんばち」などで赤穂や奈良県、広島県で使われている
②酒を一気に飲むこと。茶碗酒(茨城県稲敷郡,千葉県東葛飾郡)
と掲載されておりました。
(稲敷郡も千葉県の東葛飾郡も取手が所在する北相馬郡に接しているような位置関係です)
また,東京堂出版から発行されている「茨城方言民俗語辞典」には
「トンパジ・・・茶碗酒」として掲載されております。
使用する地方として,那珂郡那珂町(県北),稲敷郡,北相馬郡となっておりました。
----
これを読むと,取手で使われていてもおかしくありませんね。
ただし,70代の男性が知らなかったということは,もっと古い言葉か限られた地域の言葉だったのでしょうか。
坂口安吾が取手にいたのは,1938年から1940年です。
70代の男性が生まれて間もない頃となります。
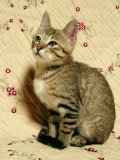
いつでも里親募集中
そこで長禅寺さんの由来を見つけました。
再掲になりますが,その由来を記します。
-----
長禅寺の由来
創建は平将門と伝えられており,境内には市指定文化財の三世堂をはじめ数々の堂宇や,小林一茶句碑,小川芋銭景幕の碑,開闡郷士碑などがある。
また,新四国相馬霊場八十八ヶ所の総本山で,一番,五番,八十八番の札所でもある。
-----
写真は,これです。クリックすると拡大します。

この中の「小川芋銭景幕の碑」の「景幕」がわからないと,コメントをいただきました。
どうも「景幕」の字は,「景慕」の誤植のようです。
そこで以前,旧取手宿本陣について,メールをいただいた市役所の方に確認することにしました。
ついでに,どうしてもわからなかった「トンパチ」についても,確認しました。
トンパチは,以前酒仙堂さんに教えてもらった言葉なのですが,ネットでも確認できずにいたものです。
----
■トンパチについて
坂口安吾さんの作品に,日本文化私観というのがあります。
この中の「四 美に就て」という個所に,以下の文章がでてきます。
三年前に取手という町に住んでいた。
利根川に沿うた小さな町で,トンカツ屋とソバ屋の外に食堂がなく,僕は毎日トンカツを食い,半年目には遂に全くうんざりしたが,僕は大概一ヶ月に二回ずつ東京へでて,酔っ払って帰る習慣であった。
尤も,町にも酒屋はある。
然し,オデン屋というようなものはなく,普通の酒屋で,框(かまち)へ腰かけてコップ酒をのむのである。
これを「トンパチ」と言い,「当八」の意だそうである。
即ち一升がコップ八杯にしか当らぬ。
つまり,一合以上なみなみとあり,盛りがいいという意味なのである。
村の百姓達は「トンパチやんべいか」と言う。
勿論僕は愛用したが,一杯十五銭だったり,十七銭だったり,日によってその時の仕入れ値段で区々(まちまち)だったが,東京から来る友達は顔をしかめて飲んでいる。
----
で,市役所の方からメールをいただきました。
「景幕」は「景慕」の誤植だったようです。
また,「トンパチ」については,坂口安吾の作品にでてくるのは知っていたそうですが,聞いたことはないそうです。
そこで,少し調べていただきました。
以下,そのメールの概略です。
----
先日メールをいただきました坂口安吾の随筆中にある「とんぱち」についてですが,
取手やその周辺生まれの70代の男性に聞いたところ,「とんぱち」という言葉自体聞いたことがない
ということでした。
取手では,「だっぺ」のようにポピュラーな方言ではないかもしれません。
また文献で「とんぱち」について調べたところ、
小学館発行「日本国語大辞典」には方言として掲載されており,
①鉢(鳥取、出雲地方)「どんばち」などで赤穂や奈良県、広島県で使われている
②酒を一気に飲むこと。茶碗酒(茨城県稲敷郡,千葉県東葛飾郡)
と掲載されておりました。
(稲敷郡も千葉県の東葛飾郡も取手が所在する北相馬郡に接しているような位置関係です)
また,東京堂出版から発行されている「茨城方言民俗語辞典」には
「トンパジ・・・茶碗酒」として掲載されております。
使用する地方として,那珂郡那珂町(県北),稲敷郡,北相馬郡となっておりました。
----
これを読むと,取手で使われていてもおかしくありませんね。
ただし,70代の男性が知らなかったということは,もっと古い言葉か限られた地域の言葉だったのでしょうか。
坂口安吾が取手にいたのは,1938年から1940年です。
70代の男性が生まれて間もない頃となります。
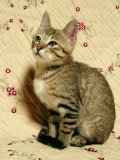
いつでも里親募集中










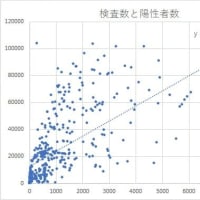
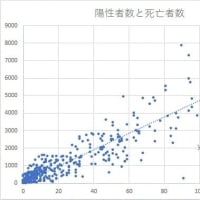
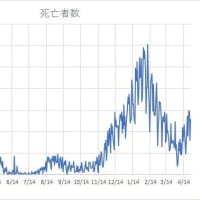


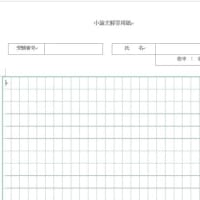


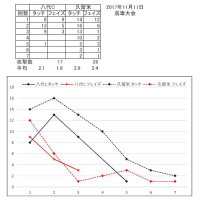









1950年頃まで、店先でコップ酒を売っていたようです。
お盆に親と帰省した時など、醤油や味噌を量り売りしていたのを覚えていますが、コップ酒を飲むオジサン達の姿は見た覚えがありません。良い子は早く寝たからでしょうか(あら?)
というか、私の物心がつく頃には止めていたのでしょう。(飲食店ではないので、保健所とのからみかも?)
店先でのコップ酒を、「トンパチ」というとは全然知りませんでした。
自分の田舎は,人口が2000人ぐらいの小さな村でした(過去形)。
それでも,地域によって使う言葉が少し違ってました。
そんなんで,どこでもトンパチと言ってた訳ではないと思いますよ。
そりゃあ,すんごいものです。
最近は,指示代名詞だけで会話することもあります(笑)。