☆☆☆
神社本庁のトップを代々皇族出身女性が務めている経緯
2016.10.20 16:00 NEWSポストセブン
http://www.news-postseven.com/archives/20161020_455203.html
【GHQを意識し女性祭主に】
戦後に設立された神社本庁は、当初から現在に至るまで皇室と切っても切れない密接な関係を築いてきた。現在、神社本庁の「総裁」を務める池田厚子さん(85歳)は昭和天皇の第四皇女で、旧名は厚子内親王。1952年に結婚に伴い皇籍を離脱し、1996年
戦後に設立された神社本庁は、当初から現在に至るまで皇室と切っても切れない密接な関係を築いてきた。現在、神社本庁の「総裁」を務める池田厚子さん(85歳)は昭和天皇の第四皇女で、旧名は厚子内親王。1952年に結婚に伴い皇籍を離脱し、1996年に総裁に推戴された。神社本庁憲章に〈総裁は、神社本庁の名誉を象徴し、表彰を行ふ〉とあるように、神社本庁は名誉職として「総裁」を推戴してきた。
戦後誕生した神社本庁の歴代総裁は、初代の北白川房子さん(明治天皇の第七皇女)に始まり、鷹司和子さん(昭和天皇の第三皇女)と続き、池田厚子さんで三代目。これまで皇族出身の女性たちが推戴されてきた。
神社本庁の総裁は、伊勢神宮の「祭主」も務めてきた。祭主とは伊勢神宮のみに置かれた最高の役職であり、神宮の祭祀に奉仕し、天皇のお心を伝えるとともに、伊勢神宮の神職をまとめる立場である。最近では今上天皇の長女で、清子内親王だった黒田清子さんが「臨時神宮祭主」に就任した。
この臨時神宮祭主は、2013年に行われた式年遷宮に際し、伯母である池田さんが高齢のため神社本庁が「万全を期すため」池田さんの補佐として黒田さんに就任してもらったものだ。
一方で神社本庁を実質的に代表する「統理」の役職には現在、北白川房子さんの孫にあたる元伊勢神宮の大宮司・北白川道久氏が就任している。ほかにも、高円宮憲仁親王の次女・典子さんが一昨年、代々出雲大社の宮司を務める千家家に嫁いだことも話題となった。
なぜ皇室と神社本庁はつながりが深いのか。それを知るには天皇と神道との歴史的経緯を遡る必要がある。神道が国家の信仰として歴史上初めて法的に位置づけられたのは大宝元年(701年)の大宝律令とみなされる。
律令では立法・司法・行政をつかさどる太政官と並ぶ形で、神祇官が置かれた。皇室の祖神とされる天照大神が祀られている伊勢神宮に神祇官から勅使が遣わされ、皇室と伊勢神宮の関係は不離一体のものとして制度化されることになったのだ。『日本書紀』『古事記』が編纂されたのもこの時期であり、神話の神と皇統が結びつけられた。
その関係は朝廷の力が衰えた武家政治の時代にも細々と続いたが、それを強力に復活させたのは明治維新期の王政復古であり、明治期以降日本は再び神道を国家の基礎に据えたのである。
敗戦後間もない1945年12月、政教分離を徹底しようとするGHQは「神道指令」を出す。神祇院は廃止され、公的に国家と神社との結びつきが絶たれた逆風の中で、神社関係者や関連団体によって設立されたのが宗教法人・神社本庁だった。
政教分離を求められたところで、皇室と伊勢神宮は切っても切れない関係にある。
GHQとしても「信教の自由」を掲げる以上、配慮しないわけにはいかず、「国家神道は廃絶すべきだが、宗教法人化された伊勢神宮にはあまりうるさく容喙しない」という方針をとった。
それでも日本の神社関係者は、国家神道の復活を危険視するGHQを意識せざるを得なかった。伊勢神宮の祭主には明治以来、男性皇族が就く伝統があった。しかしそれでは戦前のイメージが残っていると見られると危惧し、改める必要があった。
そこで女性皇族が祭主に就くことになったのだ。その女性初の祭主になったのが前述の通り北白川房子さんだった。戦後の祭主を皇族出身の女性が務めているのはこのようないきさつがあったからである。 ※SAPIO2016年11月号
☆☆☆
神社本庁の集金システム 全国約8万の神社から10億円の収入
2016.10.20 07:00 週刊文春
http://www.news-postseven.com/archives/20161020_455202.html
【「神宮大麻」の初穂料の半額は伊勢神宮へ】
いま、「神社本庁」の存在感が急激に増している。安倍政権と密接な「日本会議」より先鋭的な思想を持つとされ、その関連団体「神道政治連盟国会議員懇談会」には300人以上の国会議員が加盟している。
八幡神社の初詣でお札を買ったら、「天照皇大神宮」の文字。違う氏神を祀っている神社なのになぜなのか。そこには全国の97%の神社を包括する神社本庁を中心とした組織構造がある。
神社本庁は全国約7万9000社の神社を包括し、それらは「被包括神社」と呼ばれる。戦前の神社界には「社格」制度があり明確な序列があった。その名残から、中でも旧社格制度で格の高かった神社や規模の大きい約350社が「別表神社」として規定されている。
また別表神社の中には、祭礼の際に天皇から勅使が遣わされる神社として「勅祭社」がある。16ある勅祭社だが、靖国神社だけはその性質から神社本庁に包括されない「単立神社」となっている。
神社本庁は各都道府県にひとつずつ、各神社との間の事務を代行する神社庁、市町村にその支部を設置している。各神社が日常の仕事以外に本庁と結びつくのは「神宮大麻」とその“代金”のやり取りが挙げられる。
各神社には毎年、「天照皇大神宮」と書かれた神札が頒布される。これを神宮大麻という。「神宮」とは神社本庁が本宗と仰ぐ伊勢神宮を指す。神宮大麻は伊勢神宮の神札であり、伊勢神宮しか発行できない。これを各神社が代行して“委託販売”している格好だ(初穂料は神社によって異なることがあるが800円のケースが多い)。
各神社は神宮大麻を“販売”し、その“売り上げ”総額をまずは伊勢神宮に納める。伊勢神宮はその金額の半分を収入とし、残りの半分を神社本庁に交付(本宗交付金)する。神社本庁はこの金額に多少増額させた額を各神社に配分している(本宗神徳宣揚費)。
つまり神宮大麻一体あたり800円なら、400円強が回り回って各神社の取り分となる。ただし、これは全国一律ではなく3割程度しか入ってこない神社もあるようだ。
各神社は神宮大麻の“売り上げ”の他に、それぞれの神社庁を窓口にして神社本庁に納付金名目で会費のようなものを支払っている。その額は基本的に氏子の数で決められる。この場合の氏子数はその神社の地域人口をもとに算出される。
神社本庁は国勢調査の人口をもとに各神社庁からヒアリングを行い、各都道府県の納付金額を決める。割り振られた金額から神社庁は、管轄の各神社の規模や事情を加味して負担する額を決定する。
正月に1万3000人の参拝がある東北地方の某神社では、年間36万円を神社庁に支払っているという。年間の納付金が数千円の神社もあれば、数百万円の神社も存在する。それは社務所もない無人の神社もあれば、初詣に100万人規模が訪れる有名神社もあるからだ。
勅祭社である東京の明治神宮は、神社としては浅い100年ほどの歴史で氏子数は知名度に比べて多くないが、初詣には300万人が訪れ、神宮外苑に結婚式場や競技施設などを持っている大神社である。こうした事情も納付金額に反映される要素である。神社本庁は本年度の納付金額は一般会計予算で約10億円としている。そのほか各神社の厚意による寄附収入もある。
この“上納”システムを各神社はどう捉えているのか。北日本にある別の神社の宮司が語る。
「行事などで突飛なイベントをやっても『いかがなものか』と言われるくらいで、神社本庁から厳格に管理・指導・強制されることはない。むしろ神職として研鑽を積むための研修を催してくれたり、神社神道が危機に陥ったときには神社本庁が盾になって守ってくれたりするといったメリットがあるのです」
神社本庁に属する被包括神社は、さながら神社本庁の下で運営するフランチャイズ企業を彷彿とさせる。このようにして日本一の宗教法人は成り立っている。 ※SAPIO2016年11月号
☆☆☆













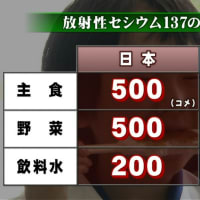

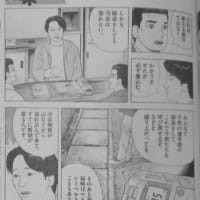
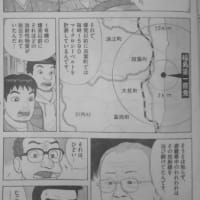
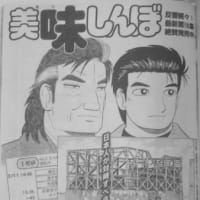
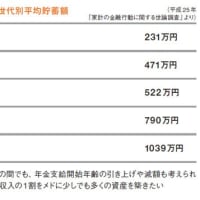
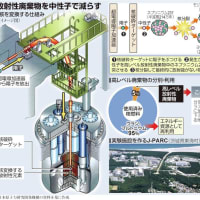

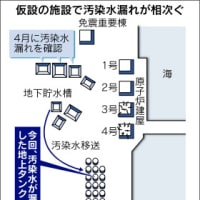
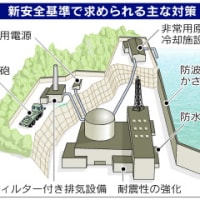
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます