
◇1日の講座内で演習問題を、○×式と5択式で3回実施して、習得知識の進捗確認を行っています。
◇傾向的には、徐々に不正解の比率が低下していきますので、数字的には好ましい傾向にあります。
◇その中で、習得状況が不十分な項目を整理していきますと・・・
◇朝一番の演習では、敷地内に複数の建築物間の各棟間における延焼線の有無を問う問題が弱い。
◇午前終了時の演習では、階数の緩和条項に「居室」が絡むと、誤った判断を誘発するようです。
◇午後の演習では、面積計算等の図形問題に弱点があるようです。
◇という事で、この3点を整理していきます。
◇法2条六号 延焼のおそれのある部分の条文を参照すると、
・1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分をいう
・そしてかっこ書き内で「延べ面積の合計が500㎡以内の建築物は、一の建築物とみなす」としている。
◇令2条1項八号 階数の定義の条文を参照すると、
・建築面積の1/8以下の塔屋は、原則、階数に算入されない。
・その一部に休憩室(法2条四号に規定する居室である)を設けたものへの記述は無い。
・すなわち、居室を含む場合には、階数に算入する必要がある。
◇面積計算は、令2条各号の条文の記述されている文言参照に慣れることではないでしょうか?
・特に今回は、階数の定義の緩和条項の理解に弱点が見うけられる。
・これは演習の繰り返しが最良の策だと推察しています。
2025年4月22 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者











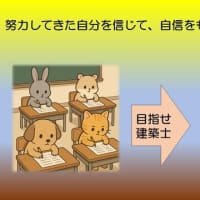
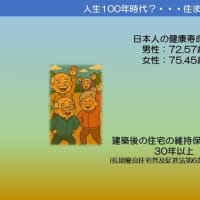
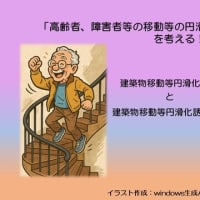
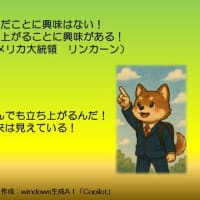

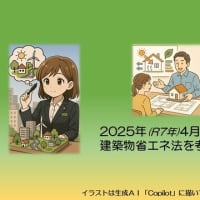


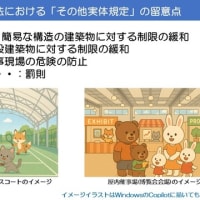




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます