
◇先週の講座の振り返り事項について、具体事項を整理していきます。
◇容積率の算定で、特定道路が絡んだ場合の計算方法ですが、まずは、緩和幅員を算定します。
◇特定道路の影響による前面道路の幅員の緩和措置は「法52条9項⇒令135条の18」を参照します。
◇令135条の18:「(12-前面道路幅員)×(70-特定道路までの延長)÷70」で、算出します。
◇ここで、全面道路の緩和幅が算出できますので、後は、この緩和幅を加算して、容積率算定をします。
◇敷地に高低差がある場合の措置ですが、令135条の2第1項に緩和措置の算定方法が記述されています。
◇建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合、1mを減じたものの1/2だけ高い位置とする。
◇ここまでは理解しているのですが、その後に、受講生を悩ます事項があるのです。
◇道路斜線制限は、道路の中心線からの高さを計算していますが、求める高さは地盤面からの高さです。
◇えっ!なんで?・・・令2条1項六号に、建築物の高さは「地盤面からの高さによる」としています。
◇そうっ!宅盤差を差し引いて回答値を算出する必要があるのです・・・ここが、受講生の悩みなのです。
◇この直ぐ後に、北側斜線の高低差緩和による規制値を算定する時に、また頭を悩ませるようです。
◇今度は、同じ地盤面からの高さを算定していますので、「宅盤差」というのは存在しません。
◇単純に緩和措置の算定値を加算するだけなのですが・・・今度は「+」するのが納得いかないようです。
◇「何で、道路斜線の時は緩和数値を引いたのに、今度は足し算をするの?」・・・断面図で説明しました。
◇断面図を見て、ようやく納得したようですが・・・今週、演習問題で、習得状況を確認する予定です。
2025年6月11日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者













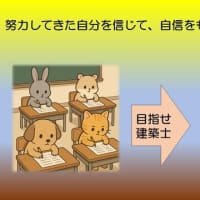
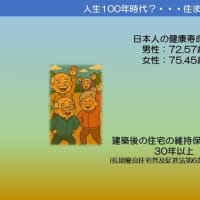
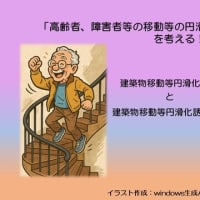
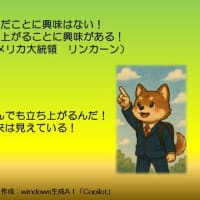

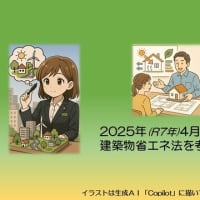





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます