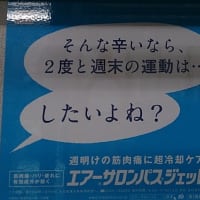「あをによし寧楽(なら)の京師(みやこ)は咲く花の薫(にほ)ふがごとく今盛りなり 」
とも出ていた。”青丹よし”は、奈良から青丹が出たことに由来し、青丹は孔雀石のことで奈良の枕詞とある。
この青によしはあおあおとした 様で、青青/蒼蒼/碧碧とも書かれて、新緑(?)のさまを表している。つまり、山々の緑である。信号機の青がそうであるように、緑色した信号機が青信号という風に(今はLEDで青色)、青も緑も似たような色が万葉の時代だったのだろう。要するに、日本人は色さえもきちんと区別を避けてきたように、何事も厳密にする必要はないのである。 どうも最近デジタル化で区別したがる風潮があるので敢えて書かなければと想った次第。