


#ккк
#極東国際軍事裁判(#東京裁判) - Wikipedia
http://p216.pctrans.mobile.yahoo-net.jp/fweb/0901H3TqOpG9cfJt/0?_jig_=http%3A%2F%2Fja.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25E6%25A5%25B5%25E6%259D%25B1%25E5%259B%25BD%25E9%259A%259B%25E8%25BB%258D%25E4%25BA%258B%25E8%25A3%2581%25E5%2588%25A4&_jig_keyword_=%93%8C%8B%9E%8D%D9%94%BB&_jig_done_=http%3A%2F%2Fsearch.mobile.yahoo.co.jp%2Fp%2Fsearch%2Fonesearch%3Fp%3D%2593%258C%258B%259E%258D%25D9%2594%25BB%26fr%3Dm_top_y&_jig_source_=srch&guid=on
#ррр #XXX #DEW #条約 #指向性エネルギー兵器 #テロリスト #工作員 #慰安婦 #兵器 #WW123
極東国際軍事裁判
極東国際軍事裁判(きょくとうこくさいぐんじさいばん、The International Military Tribunal for the Far East)は、第二次世界大戦で日本が降伏した後の1946年(昭和21年)5月3日から1948年(昭和23年)11月12日にかけて行われた、連合国が「戦争犯罪人」として指定した日本の指導者などを裁いた一審制の裁判のことである。
東京裁判(とうきょうさいばん)とも称される。
概要[編集]
この裁判は連合国によって東京に設置された極東国際軍事法廷により、東條英機元首相を始めとする、日本の指導者28名を、「平和愛好諸国民の利益並びに日本国民自身の利益を毀損」した[1]「侵略戦争」を起こす「共同謀議」を「1928年(昭和3年)1月1日から1945年(昭和20年)9月2日」にかけて[1]行ったとして、平和に対する罪(A級犯罪)、人道に対する罪(C級犯罪)および通常の戦争犯罪(B級犯罪)の容疑で裁いたものである。
「平和に対する罪」で有罪になった被告は23名、通常の戦争犯罪行為で有罪になった被告は7名、人道に対する罪で起訴された被告はいない。
裁判中に病死した2名と病気によって免訴された1名を除く25名が有罪判決を受け、うち7名が死刑となった。
日本政府及び国会は1952年(昭和27年)に発効した日本国との平和条約第11条によりこのthe judgments[2]を受諾し、異議を申し立てる立場にないという見解を示している[3]。
戦犯裁判までの経緯[編集]
「ニュルンベルク裁判#前史」および「国際軍事裁判所憲章」も参照
アメリカの対日政策[編集]
裁判方式[編集]
1944年8月から終戦以降の政策方針と敗戦国の戦争犯罪人の取り扱いについて議論された。
ヘンリー・モーゲンソー財務長官はナチス指導者の即決処刑を主張し、他方、ヘンリー・スティムソン陸軍長官は「文明的な裁判」による懲罰を主張した[4]。
アメリカの新聞はモーゲンソーの即決処刑論を猛攻撃し、ルーズベルト大統領も裁判方式を支持することとなった[4]。
スティムソンは裁判は「報復」の対極にあるとみなしていた[5]。
国務・陸軍・海軍三省調整委員会極東小委員会[編集]
アメリカの対日政策を検討する機関として1944年12月に国務・陸軍・海軍三省調整委員会(SWNCC)が設立された[6]。
さらにその下位組織極東小委員会(Subcommittee for the Far East,SFE)が1945年1月に設立され、日本と朝鮮の占領政策案が作成された[6][7]。
戦犯裁判方式にするか、指導者の処刑方式かの検討もなされ、1945年8月9日報告書(SFE106)では対独政策を踏襲し、「共同謀議」の起訴を満州事変までさかのぼること、日本にはドイツのような組織的迫害の行為はなかったので人道に対する罪を問責しても無駄であると報告された[7]。
8月13日の会議では日本に対しても平和に対する罪、人道に対する罪の責任者を含めることが合意され、8月24日のSWNCC57/1で占領軍が直接逮捕をし、容疑者が自殺で殉教者になることを防ぐ、連合国間の対等性を保障し各国が首席判事を出すこと、判決の権限はマッカーサーにあるとされた[8]。
連合国戦争犯罪委員会による対日勧告[編集]
また、1943年10月20日に17カ国が共同で設立した連合国戦争犯罪委員会(UNWCC)は戦争犯罪の証拠調査を担当する機関であったが、終戦期には政策提言などを行うようになっており、オーストラリア代表ライト卿が対日政策勧告を提言し、1945年8月8日には極東太平洋特別委員会を設置し、委員長には中華民国の駐英大使顧維鈞が就任し、8月29日に対日勧告が採択された[9]。
SWNCC57/3指令[編集]
アメリカ統合参謀本部がJCS1512、またアメリカ合衆国内の日本占領問題を討議する国務・陸軍・海軍調整委員会が1945年10月2日にSWNCC57/3指令をマッカーサーに対して発し、日本における戦犯裁判所の設置準備が開始された[10]。
しかし、ダグラス・マッカーサーはこうした「国際裁判」には否定的で、「57/3指令を公表すれば、日本政府がダメージを受けて直接軍政をせざるをえない、東条英機を裁く権限を自分に与えるよう1945年10月7日の陸軍宛電報でのべ、アメリカ単独法廷を主張し、ハーグ条約で対米戦争を裁くことによって「戦争の犯罪化」に反対した[11]。
GHQ参謀第二部部長ウィロビーによれば、マッカーサーが東京裁判に反対したのは南北戦争で南部に怨恨が根深く残ったことを知っていたからとのべている[11]。
スティムソン、マクロイ陸軍次官補らはマッカーサーの提言を採用せず、57/3指令の国際裁判方針を固守した[12]。
イギリス[編集]
イギリス外務省はアメリカの対日基本政策に対して消極的で、日本人指導者の国際裁判にも賛同していなかった。
もともとイギリスは、1944年9月以来、ドイツ指導者の即決処刑を米ソに訴えていた。
イギリスは、裁判方式は長期化するし、またドイツに宣伝の機会を与えるし、伝統的な戦犯裁判は各国で行えばよいという考えだった[13]。
結局英国は、1945年5月に、ドイツ指導者の国際裁判に同意した。
ただし、この時点でもまだ日本指導者の国際裁判には同意していなかった。
のち、イギリス連邦政府自治省およびイギリス連邦自治領のオーストラリアやニュージーランドによる裁判の積極的関与をうけたが、イギリスは1945年12月12日、アメリカに技術的問題の決定権を委任した[14]。
国際検察局の設置[編集]
1945年(昭和20年)12月6日、アメリカ代表検事ジョセフ・キーナンが来日する[15]。
翌7日、マッカーサーは事後法批判の回避、早期開廷、東条内閣閣僚の起訴をキーナンに命じた[15]。
翌1945年(昭和20年)12月8日、GHQの一局として国際検察局(IPS)が設置された[15]。
国際軍事裁判所憲章と特別宣言[編集]
「国際軍事裁判所憲章」を参照 1946年(昭和21年)1月19日、ニュルンベルク裁判の根拠となった国際軍事裁判所憲章を参照して極東国際軍事裁判所条例(極東国際軍事裁判所憲章)が定められた[16](1946年4月26日一部改正)。
同1946年(昭和21年)1月19日、連合国軍最高司令官マッカーサー元帥が極東国際軍事裁判所設立に関する特別宣言を発した[16]。
この宣言は、ポツダム宣言および降伏文書、1945年12月26日のモスクワ会議(英語版)によってマッカーサーに対してアメリカ・イギリス・ソ連、そして中華民国から付与された、日本政府が降伏条件を実施するために連合国軍最高司令官が一切の命令を行うという権限に基づく[17]。
フランス[編集]
アメリカ国務省は1945年末にフランス政府に対し判事と検察官を指名するよう要請したが、フランスが悠長であったため翌1946年1月22日に催促した[18]。
フランスははじめインドシナ高等弁務官のダルジャンリューの意見もあり、パリ大学のジャン・エスカラを選んだ[18]。
エスカラは1920年代に蒋介石中華民国の法律顧問をつとめたこともあったが、要請を断り、他の学者を紹介するにとどめた[18]。
一方、第二機甲師団陸軍准将ポール・ジロー・ド・ラングラードらが政府に対して派遣する法律家は植民地での経験があるものがよいと提言し、マダガスカルや西アフリカの控訴院判事を歴任したアンリ・アンビュルジュが指名された[18]。
しかしアンビュルジュも出発直前になって固辞し、アンリ・ベルナールが指名された[19]。
日本の裁判対策[編集]
終戦後、日本では自主裁判も構想されたが、美山要蔵の日記にもあるように残虐行為の実行者のみが裁判の対象となってしまい、戦犯裁判は戦勝国による「勝者の裁き」であるとの覚悟があったとされる[20]。
1945年10月3日、東久爾内閣は「戦争責任に関する応答要領(案)」を作成し[21]、その後11月5日終戦連絡幹事会は「戦争責任に関する応答要領」を作成し、天皇を追求から守ること、国家弁護と個人弁護を同時に追求すると書かれた[22]。
外務省外局終戦連絡中央事務局主任の中村豊一は1945年11月20日、戦犯裁判対策を提言し、弁護団、資料提供、臨時戦争犯罪人関係調査委員会の設置、戦争犯罪人審理対策委員会を提言したが、外務省は政府指導になるという理由で却下した[20]。
その後、吉田茂が12月に法務審議室を設置した[23]。
1946年2月には内外法政研究会が発足し、高柳賢三、田岡良一、石橋湛山らが戦争犯罪人の法的根拠や開戦責任などについての研究報告をおこなった[24]。
裁判[編集]
国際検察局から執行委員会へ[編集]
1946年(昭和21年)2月2日、イギリス代表検事が来日する[25]。
2月13日にジョセフ・キーナンアメリカ合衆国代表検事がアメリカ以外の検事は参与であるとの通達を出すと、イギリス、英連邦検事はこれに反発し、3月2日に各国検事をメンバーとした執行委員会が設立される[26]。
執行委員会一覧
ジョセフ・キーナン(アメリカ合衆国派遣) - 首席検察官
アーサー・S・コミンズ・カー(グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国派遣) - 次席検察官
S・A・ゴルンスキー(ソビエト社会主義共和国連邦派遣)
アラン・ジェームス・マンスフィールド(オーストラリア連邦派遣)
ロナルド・ヘンリー・クイリアム(ニュージーランド派遣)- 裁判の進め方や未訴追戦犯の拘留が長い事に抗議し、1947年末に帰国している[27]。
ヘンリー・グラタン・ノーラン(カナダ派遣)
向哲濬(中華民国派遣)
ロベル・L・オネト(フランス共和国派遣)
W・G・F・ボルゲルホフ・マルデル(オランダ王国派遣)
ゴビンダ・メノン(インド派遣)
ペドロ・ロペス(アメリカ領フィリピン派遣)
被告の選定[編集]
1946年1月、被告の選定にあたってイギリスはニュルンベルク裁判と同様に知名度を基準に10人を指名した[28]。
執行委員会の4月4日会議では29名が選ばれるが、4月8日には石原莞爾、真崎甚三郎、田村浩が除外された[29]。
4月13日にはソ連検事が来日したが、ソ連側は天皇訴追を求めなかった[30]。
そのかわり4月17日、ソ連は鮎川義助、重光葵、梅津美治郎、富永恭次、藤原銀次郎の起訴を提案し、そのうち重光と梅津が追加され、被告28名が確定した[31]。
被告人一覧
詳細は「A級戦犯#極東国際軍事裁判に起訴された被告人」を参照
荒木貞夫
板垣征四郎
梅津美治郎
大川周明
大島浩
岡敬純
賀屋興宣
木戸幸一
木村兵太郎
小磯國昭
佐藤賢了
重光葵
嶋田繁太郎
白鳥敏夫
鈴木貞一
東郷茂徳
東條英機
土肥原賢二
永野修身
橋本欣五郎
畑俊六
平沼騏一郎
広田弘毅
星野直樹
松井石根
松岡洋右
南次郎
武藤章
起訴状の作成過程[編集]
1946年4月5日の執行委員会でイギリスのアーサー・S・コミンズ・カー検事は起訴状案を発表、そのなかで「平和に対する罪」の共同謀議を、1931年~1945年の「全般的共同謀議」と4つの時期におよぶ個別的共同謀議(満州事変、日中戦争、三国同盟、全連合国に対する戦争)の5つに分割した[32]。
また平和に対する罪では死刑を求刑できないので、通例の戦争犯罪である公戦法違反で裁くべきであると主張した[33]。
訴因「殺人」と「人道に対する罪」[編集]
極東国際軍事裁判独自の訴因に「殺人」がある。
ニュルンベルク・極東憲章には記載がないが、これはマッカーサーが「殺人に等しい」真珠湾攻撃を追求するための独立訴因として検察に要望し、追加されたものである[34]。
これによって「人道に対する罪」は同裁判における訴因としては単独の意味がなくなったともいわれる[34]。
しかも、1946年4月26日の憲章改正においては「一般住民に対する」という文言が削除された。
最終的に「人道に対する罪」が起訴方針に残された理由は、連合国側がニュルンベルク裁判と東京裁判との間に統一性を求めたためであり、また法的根拠のない訴因「殺人」の補強根拠として使うためだったといわれる[34]。
このような起訴方針についてオランダ、中華民国、フィリピンは「アングロサクソン色が強すぎる」として批判し、中国側検事の向哲濬(浚)は、南京事件の殺人訴因だけでなく、広東・漢口での日本軍による行為を追加させた[34]。
ニュルンベルク裁判の基本法である国際軍事裁判所憲章で初めて規定された「人道に対する罪」が南京事件について適用されたと誤解されていることもあるが、南京事件について連合国は交戦法違反として問責したのであって、「人道に関する罪」が適用されたわけではなかった[35]。
南京事件は訴因のうち第二類「殺人」(訴因45-50)で扱われた[36]。 詳細は「人道に対する罪」を参照
昭和天皇の訴追問題[編集]
オーストラリアなど連合国の中には昭和天皇の訴追に対して積極的な国もあった[37]。
白豪主義を国是としていたオーストラリアは、人種差別感情に基づく対日恐怖および対日嫌悪の感情が強い上に、差別していた対象の日本軍から繰り返し本土への攻撃を受けたこともあり、日本への懲罰に最も熱心だった[38]。
また太平洋への覇権・利権獲得のためには、日本を徹底的に無力化することで自国の安全を確保しようとしていた[39]。
エヴァット外相は1945年9月10日、「天皇を含めて日本人戦犯全員を撲滅することがオーストラリアの責務」と述べている。
1945年8月14日に連合国戦争犯罪委員会(UNWCC)で昭和天皇を戦犯に加えるかどうかが協議されたが、アメリカ政府は戦犯に加えるべきではないという意見を伝達した[40]。
1946年1月、オーストラリア代表は昭和天皇を含めた46人の戦犯リストを提出したが、アメリカ、イギリス、フランス、中華民国、ニュージーランドはこのリストを決定するための証拠は委員会の所在地ロンドンに無いとして反対し、このリストは対日理事会と国際検察局に参考として送られるにとどまった[41]。
8月17日には、イギリスから占領コストの削減の観点から、天皇起訴は政治的誤りとする意見がオーストラリアに届いていたが、オーストラリアは日本の旧体制を完全に破壊するためには天皇を有罪にしなければならないとの立場を貫き[42]、10月にはUNWCCへの採択を迫ったが、米英に阻止された[43]。
アメリカ陸軍省でも天皇起訴論と不起訴論の対立があったが、マッカーサーによる天皇との会見を経て、天皇の不可欠性が重視され、さらに1946年1月25日、マッカーサーはアイゼンハワー参謀総長宛電報において、天皇起訴の場合は、占領軍の大幅増強が必要と主張した。
このようなアメリカの立場からすると、オーストラリアの積極的起訴論は邪魔なものでしかなかった[44]。
なお、オーストラリア同様イギリス連邦の構成国であるニュージーランドは捜査の結果次第では天皇を起訴すべしとしていたが、GHQによる天皇利用については冷静な対応をとるべきとカール・ベレンセン駐米大使はピーター・フレイザー首相に進言、首相は同意した[44]。
またソ連は天皇問題を提起しないことをソ連共産党中央委員会が決定した[30][45]。
1946年4月3日、最高意思決定機関である極東委員会(FEC)はFEC007/3政策決定により、「了解事項」として天皇不起訴が合意され、「戦争犯罪人としての起訴から日本国天皇を免除する」ことが合意された[46]。
4月8日、オーストラリア代表の検事マンスフィールドは天皇訴追を正式に提議したが却下され、以降天皇の訴追は行われなかった[41]。
海軍から改組した第二復員省では、裁判開廷の半年前から昭和天皇の訴追回避と量刑減刑を目的に旧軍令部のスタッフを中心に、秘密裏の裁判対策が行われ、総長だった永野修身以下の幹部たちと想定問答を制作している。
また、BC級戦犯に関係する捕虜処刑等では軍中央への責任が天皇訴追につながりかねない為、現場司令官で責任をとどめる弁護方針の策定などが成された。
さらに、陸軍が戦争の首謀者である事にする方針に掲げられていた。
1946年3月6日にはGHQとの事前折衝にあたっていた米内光政に、マッカーサーの意向として天皇訴追回避と、東條以下陸軍の責任を重く問う旨が伝えられたという。
また、敗戦時の首相である鈴木貫太郎を弁護側証人として出廷させる動きもあったが、天皇への訴追を恐れた周囲の反対で、立ち消えとなっている[47]。
なお昭和天皇は「私が退位し全責任を取ることで収めてもらえないものだろうか」と言ったとされる[48])。
起訴状の提出[編集]
起訴状の提出は1946年4月29日(4月29日は昭和天皇の誕生日)に行われた[49]。
極東国際軍事裁判において訴因は55項目であったが、大きくは第一類「平和に対する罪」(訴因1-36)、第二類「殺人」(訴因37-52)、第三類「通例の戦争犯罪及び人道に対する罪」(53-55)の三種類にわかれた[36]。
判決では最終的に10項目の訴因にまとめられた[50]。
裁判官・判事[編集]
ウィリアム・ウェブ(オーストラリア連邦派遣) - 裁判長。連邦最高裁判所判事[51]。
マイロン・C・クレマー少将(アメリカ合衆国派遣)- 陸軍省法務総監。ジョン・P・ヒギンズから交代。
ウィリアム・パトリック(グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国派遣)- スコットランド刑事上級裁判所判事
イワン・M・ザリヤノフ少将(ソビエト社会主義共和国連邦派遣)- 最高裁判所判事。陸大法学部長- 法廷の公用語である英語を使用できなかった[52]。
アンリー・ベルナール(フランス共和国派遣)- 軍事法廷主席検事 - 法廷公用語である英語を十分使用できなかった[53]。
梅汝 (中華民国派遣) - 立法院委員長代理。イェール大学ロー・スクール学位取得者だが、法曹経験はなかった。
ベルト・レーリンク(オランダ王国派遣) - ユトレヒト司法裁判所判事
E・スチュワート・マックドウガル(カナダ派遣)- ケベック州裁判所判事。
エリマ・ハーベー・ノースクロフト(ニュージーランド派遣)- 最高裁判所判事。
ラダ・ビノード・パール(インド派遣) - カルカッタ高等裁判所判事。判事の中では唯一の国際法の専門家であった。東京裁判では平和に対する罪と人道に対する罪とが事後法にあたるとして全員無罪を主張。
デルフィン・ハラニーリャ(フィリピン派遣) - 司法長官。最高裁判所判事。日本の戦争責任追及の急先鋒で、被告全員の死刑を主張[54]。
弁護団の結成[編集]
GHQは1945年11月には戦犯容疑者が非公式で弁護人を探すことを許可していた[55]。
日本人弁護団
日本人弁護団は、団長を鵜澤總明弁護士とし、副団長清瀬一郎、林逸郎、穂積重威、瀧川政次郎、高柳賢三、三宅正太郎(早期辞任)、小野清一郎らが参加した「極東国際軍事裁判日本弁護団」が結成された[16]。
しかし、日本人弁護団内部では、自衛戦争論で国家弁護をはかる鵜澤派(清瀬、林ら)と個人弁護を図る派(高柳、穂積、三宅)らがおり、さらに国家弁護派内部でも鵜澤派と清瀬派の対立などがあった[56]。
日本人弁護団の正式結成は開廷翌日の1946年5月4日であった[57]。
アメリカ人弁護団
ニュルンベルク裁判では弁護人はドイツ人しか許されなかったが[58]、東京裁判ではアメリカ人弁護人も任命された。
日暮吉延によればこれは「勝者による報復」批判を免れるためだった[59]。
1946年(昭和21年)4月1日に結成されたアメリカ人弁護団団長は海軍大佐ビヴァリー・コールマン(横浜裁判の裁判長)。
弁護人としては海軍大佐ジョン・ガイダーほか六名であった。
しかしコールマンが主席弁護人を置くようマッカーサーに求めたところ、受理されず、コールマンらは辞職する。
変わって陸軍少佐フランクリン・ウォレン、陸軍少佐ベン・ブルース・ブレイクニーらが派遣され、新橋の第一ホテルを宿舎とした[60]。
陸軍少佐フランクリン・ウォレン(土肥原、岡、平沼担当)
陸軍少佐ベン・ブルース・ブレイクニー(日本語を解した。東郷・梅津担当)
ジョージ山岡(日本語を解した。東郷担当)
ウィリアム・ローガン(木戸担当)
オーウェン・カニンガム(大島浩担当)
陸軍中尉アリスティディス・ラザラス(畑担当)
デイヴィッド・スミス(広田担当)
ローレンス・マクマナス(荒木担当)
E・ハリス(橋本担当)
ジョージ・ウィリアムズ(星野担当)
フロイド・マタイス(板垣、松井担当)
マイケル・レヴィン(賀屋興宣、鈴木担当)
ジョゼフ・ハワード(木村担当)
アルフレッド・ブルックス(小磯、南、大川担当)
ロジャー・コール(武藤担当)
ジェイムズ・フリーマン(佐藤担当)
陸軍大尉ジョージ・A・ファーネス(重光担当)
エドワード・マクダーモット(嶋田担当)
チャールズ・コードル(白鳥担当)
ジョージ・ブルウェット(東條担当)
開廷[編集]
1946年5月3日午前11時20分、市ヶ谷の旧陸軍士官学校の講堂において裁判が開廷した。
27億円の裁判費用は当時連合国軍の占領下にあった日本政府が支出した。
ウィリアム・F・ウエップ裁判長
判事席
連合国のうち、イギリス、アメリカ、中華民国、フランス、オランダ、ソ連の7か国と、イギリス連邦内の自治領であったオーストラリア[61]、ニュージーランド、カナダ[62]、そして当時独立のためのプロセスが進行中だったインド[63]とフィリピン[64]が判事を派遣した。
同日午後、大川周明被告が前に座っている東条英機の頭をたたき、翌日に病院に移送された[65]。
罪状認否[編集]
1946年5月6日、大川をのぞく被告全員が無罪を主張した[65]。
この罪状認否手続きで無罪を主張するのは普通のことだが、毎日新聞記者はラジオで「傲然たる態度」と罵倒し、読売新聞記者も同様の罵倒をした[65]。
弁護側の管轄権忌避動議[編集]
1946年5月13日、清瀬一郎弁護人は管轄権の忌避動議で、ポツダム宣言時点で知られていた戦争犯罪は交戦法違反のみで、それ以後に作成された平和に対する罪、人道に対する罪、殺人罪の管轄権がこの裁判所にはないと論じた[66]。
この管轄権問題は、判事団を悩ませ、1946年5月17日の公判でウェブ裁判長は「理由は将来に宣告します」と述べて理由を説明することになしにこの裁判所に管轄権はあると宣言した[67]。
しかしその後1946年6月から夏にかけてウェブ裁判長は平和に対する罪に対し判事団は慎重に対処すべきで、「戦間期の戦争違法化をもって戦争を国際法上の犯罪とするのは不可能だから、極東裁判所は降伏文書調印の時点で存在した戦争犯罪だけを管轄すべきだ。
もし条約の根拠なしに被告を有罪にすれば、裁判所は司法殺人者として世界の非難を浴びてしまう。
憲章が国際法に変更を加えているとすれば、その新しい部分を無視するのが判事の義務だ」と問題提起をしたという[68]。
日暮吉延はこのウェブ裁判長の発言は裁判所の威厳保持のためであったとしたうえで、パル判決によく似ていたと指摘している[68]。
補足動議[編集]
1946年5月14日午前、ジョージ・A・ファーネス弁護人が裁判の公平を期すためには中立国の判事の起用が必要であるとのべた[69]。
またベン・ブルース・ブレイクニー弁護人は、戦争は犯罪ではない、戦争には国際法があり合法である、戦争は国家の行為であって個人の行為ではないため個人の責任を裁くのは間違っている、戦争が合法である以上戦争での殺人は合法であり、戦争法規違反を裁けるのは軍事裁判所だけであるが、東京法廷は軍事裁判所ではないとのべ、さらに戦争が合法的殺人の例としてアメリカの原爆投下を例に、原爆投下を立案した参謀総長も殺人罪を意識していなかったではないか、とも述べた[69]。
翌日の5月15日の朝日新聞は「原子爆弾による広島の殺傷は殺人罪にならないのかー東京裁判の起訴状には平和に対する罪と、人道に対する罪があげられている。
真珠湾攻撃によって、キツド提督はじめ米軍を殺したことが殺人罪ならば原子爆弾の殺人は如何ー東京裁判第五日、米人ブレークニイ弁護人は弁護団動議の説明の中でこのことを説明した」と報道した[69]。
また全米法律家協会もブレイクニー発言を機関紙に全文掲載した[69]。
検察側立証[編集]
立証段階[編集]
以下、立証段階の日程と項目である[70]。
1946年6月4日、検察側立証開始:冒頭陳述。
1946年6月13日、一般段階:国家組織、世論指導など。
1946年7月1日、満州事変段階。
1946年8月6日、日中戦争段階。
1946年9月19日、日独伊三国同盟段階。
1946年9月30日、仏印段階。
1946年10月8日、ソ連段階。
1946年10月21日、一般的戦争準備段階。
1946年11月4日、太平洋戦争段階。
1946年11月27日、残虐行為段階。
1947年1月17日、個人別追加立証。
1947年1月24日、検察側立証終了。
キーナン冒頭陳述[編集]
1946年6月4日、首席検察官を務めたジョセフ・キーナンは冒頭陳述において、この裁判を「これは普通一般の裁判ではありません」「全世界を破滅から救うために文明の断乎たる闘争の一部を開始している」、被告(日本軍部)は「文明に対し宣戦を布告しました」と述べた[71][72]。
キーナンは日本の不義なる体質を日露戦争にまでさかのぼって、侵略戦争をするのは国家でなく個人であると主張した[70]。
キーナンは陳述を終えるとすぐに帰国し、不在の間決定権は誰にあるのかわからない状態であった[73]。
英連邦検察陣はキーナンの尊大で自分が目立つことばかり考えていると語っていた[73]。
裁判の進行は遅く、ニュージーランドの判事や検事は検察のおよび裁判長の運営方法が問題であるとして辞意を示している[74]。
証人喚問[編集]
証人にはドナルド・ニュージェント、大内兵衛、瀧川幸辰、前田多門、伊藤述史、鈴木東民、幣原喜重郎、清水行之助、徳川義親、若槻礼次郎、田中隆吉らがなった[75]。
また前満州国皇帝愛新覚羅溥儀も出廷した[76]。
ハバロフスクに抑留中の溥儀は中国からは漢奸裁判にかけられるかもしれないという脅威もあり、すべて日本の責任で自分に責任はないと証言した[76]。
8月21日にブレイクニ弁護人が溥儀の書簡を出して反対尋問を行うと「全く偽造であります」といい、重光葵は歌舞伎の芝居のようであったと回想している[77]。
溥儀も後の自伝で、自身を守るために偽証を行い、満州国の執政就任などの自発的に行った日本軍への協力を日本側によると主張し、関東軍吉岡安直などに罪をなすりつけたことを認めている。
また自らの偽証が日本の行為の徹底的な解明を妨げたとして、「私の心は今、彼(キーナン検事)に対するおわびの気持ちでいっぱいだ」と回想している[78]。
アンリ・ベルナール判事は溥儀の証言について「溥儀は、満州国は最初から全て日本の支配下にあったと述べているが、彼自身がすでに、1932年3月10日に本庄に対して同意を提案する書簡を書いているではないか。
この書簡の署名が強制のもとになされたものであるという事実は証明されなかったのだから、溥儀が法廷で行った興味深い供述から生じたような結果などよりも、本官はその書簡によって示されたものを信じる」と述べている[79]。











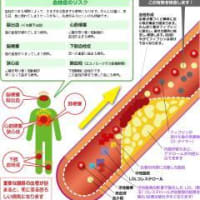




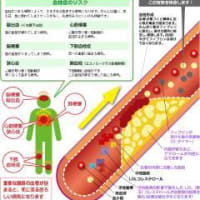



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます