





#ккк #感染症 #伝染病
チフス[編集]
詳細は「発疹チフス」、「リケッチア」、「シャルル・ジュール・アンリ・ニコル」、「腸チフス」、および「サルモネラ」を参照
チフスはもともと、発疹チフスのときに見られる高熱による昏睡状態のことを、古代ギリシアのヒポクラテスが「ぼんやりした」「煙がかかった」を意味するギリシア語 typhusと表記したことに由来するといわれるが、長い間、発疹チフスと腸チフス、パラチフスの区別がなかった。
発疹チフス[編集]
かつらをかぶったニュートン(1689年)
発疹チフスとはコロモジラミが媒介するリケッチアによる感染症で、高熱、せき、発疹が特徴である。
人口密集地域、不衛生な地域にみられ、冬期、または寒冷地での流行が顕著である。
1490年、スペイン兵がキプロス島から発疹チフスをもちこみ、ヨーロッパで流行し、1545年にはメキシコで流行した。
17世紀以降、ヨーロッパの王侯貴族や裕福な中・上級市民の間で頭髪を丸刈りにしてかつらをかぶる習俗が大流行した背景にはシラミ予防の意味もあったという。
1812年のナポレオンのロシア遠征の際にはフランス軍で大流行し、大勢の死者を出した。
19世紀の発疹チフスの流行は、コレラとともに労働運動活発化の一因となり、各国は都市の改造や公衆衛生を徹底させるなどの都市政策をおこなった。
第一次世界大戦下のロシアでは3,000万人が罹患し、その1割にあたる人びとが死亡している。
また、ナチス・ドイツによるユダヤ人虐殺のための強制収容所内でも大流行した。
フランスの細菌学者シャルル・ジュール・アンリ・ニコルはフランス植民地のチュニス(チュニジア)において風土となっていた発疹チフスを研究し、病院に入院すると感染しない傾向がみられるから院内と院外の条件を比較して、患者の衣服に着目した。
ニコルは1928年に発疹チフスの研究でノーベル生理学・医学賞を受賞している。
腸チフス・パラチフス[編集]
腸チフスやパラチフスは、16世紀のイタリアの数学者でもあり医者でもあったジェロラモ・カルダーノが発見者といわれているが、これはともにサルモネラの一種であるチフス菌によるもので発疹チフスとは全く異なる条件下、異なる病原体が原因で起こるものであるが、症状が似ているため区別が遅れた。
1836年にようやく両者の識別がなされて、別の疾患として扱われるようになった。
結核[編集]
詳細は「結核」、「結核菌」、「カリエス」、および「産業革命」を参照
古代エジプトで結核で死亡したと思われる人のミイラ(大英博物館)
結核は、結核菌によって引き起こされ、全身の倦怠感、食欲不振、体重減少、37℃前後の微熱が長期間にわたって続く、就寝中に大量の汗をかくなどの症状をともない、咳嗽(痰をともなうこともともなわないこともある)が疾患の進行にしたがって発症してくる。
かつては「不治の病」「死の病」「難病」とされ、「白いペスト」と呼ばれることもあった。
結核は太古より存在する病気として知られ、発掘調査で出土した紀元前5000年ころの人骨に結核の痕跡が認められるものがあり、2008年には紀元前7000年ころの結核痕跡をともなう2体の人骨がイスラエル沖で発見された。
また、紀元前1000年ころのエジプト第21王朝のミイラには、骨の結核である脊椎カリエスの認められる遺体がある。
2009年末、エルサレムで発見された1世紀前半の男性の骨から結核菌とらい菌のDNAが見つかり、イエス・キリストの時代のエルサレムの上流階級では結核がかなり流行していたことが確認された。
1972年に発見された中国長沙市郊外の馬王堆遺跡の1号墳に埋葬された紀元前2世紀の女性のミイラからは結核病変を確認しており、中国後漢末の武将で三国志の英雄曹操も死因は結核だといわれる。
また、2006年に韓国南部の勒島(ヌクト)の遺跡から出土した若い女性の人骨の脊椎3か所にカリエスを発見した。
ポーランドの音楽家で「ピアノの詩人」といわれたフレデリック・ショパンや『嵐が丘』で知られるエミリー・ブロンテも結核で亡くなっている。
日本における最古の結核症例は、鳥取県鳥取市に所在する弥生時代の考古遺跡青谷上寺地遺跡の発掘調査で検出した5,000体中の2点の脊椎カリエスの進行した人骨である。
縄文時代の遺跡出土の人骨からは、結核痕跡が確認されていないので、現在のところ、日本列島における結核はアジア大陸から渡来した人びとによってもたらされたものと考えられる。
平安時代、清少納言は『枕草子』のなかで「胸の病」について書き記しており、紫式部の『源氏物語』でも紫の上が胸の病を患い、光源氏が悲しむさまが描かれている。
神奈川県鎌倉市の由比ヶ浜南遺跡からは、1333年の新田義貞の鎌倉攻め(元弘の乱)の戦没者とみられる人骨が多数確認されているが、このなかの1体よりカリエスにより変形した肋骨と結核菌DNAとを検出した。
50歳前後の男性と推定されている。
産業革命期イギリスの炭坑で働く少年労働者(18世紀)
結核は、産業革命後に「世界の工場」と呼ばれて繁栄したイギリスで大流行した。
最も繁栄を謳歌していたはずの1830年ころのロンドンでは5人に1人が結核で亡くなったといわれている。
当時の労働者は賃金が低く抑えられていたうえに1日15時間もの長時間労働が一般的であった。
また、急激な都市への人口集中によってスラムが形成され、人びとは生活排水をテムズ川などの河川に投棄し、その川の水を濾過して飲料水とするなど、生活環境も劣悪であった。
過労と栄養不足が重なり、抵抗力が弱まったことから結核菌が増殖し、非衛生的な都市環境がそれに拍車をかけたものと考えられる。
これは、一面では産業革命が各国へ拡大し、普及したことにともなってイギリス発で結核が広がることともなった。
明治初年、日本からイギリスへの留学生がそこで結核にかかり、学業半ばで帰国したり、亡くなったりするケースも多かったのである。
日本では、明治初期まで肺結核を称して労咳(癆 、ろうがい)と呼んだ。新選組の沖田総司、幕末の志士高杉晋作はともに肺結核のために病死した。
正岡子規も結核を病み、喀血後、血を吐くまで鳴きつづけるというホトトギスに自らをなぞらえて子規の号を用いた。
陸奥宗光、石川啄木、樋口一葉、立原道造、堀辰雄、高山樗牛、国木田独歩、竹久夢二、長塚節、中原中也、新美南吉、梶井基次郎、滝廉太郎、佐伯祐三、新島襄なども結核で亡くなっている。
昭和天皇の弟でスポーツ振興に尽くした秩父宮雍仁親王の1953年(昭和28年)の死去も、死因は結核といわれている。
近代において、特に犠牲のひどかったのは、紡績工場ではたらく女工であった。
細井和喜蔵の『女工哀史』にみられるように、ここでも長時間労働や深夜業による過労と栄養不足、集団生活が大きな原因となっているが、工場内では糸を保護するため湿度が高かったことも結核菌の増殖をおおいに助けることとなった。
日本で結核による死亡者が最も多かったのは1918年であった。
このとき、人口10万人あたり257人が亡くなっており、1991年には人口10万人あたり2.7人にまで低下したが長い間、日本人の「国民病」であった。
また、第二次世界大戦前は、徴兵され、狭い兵舎で集団生活を送る若い男性に結核が蔓延した。
1935年から1950年までの15年間、日本の死亡原因の首位は結核であり、「亡国病」とも称された。
日本では1889年に兵庫県須磨浦(神戸市須磨区)に最初の結核療養所が民間の手によって創設されたが、国立結核療養所官制の公布はようやく1937年になってからのことで、それによって茨城県那珂郡に最初の国立結核療養所として村松晴嵐荘(現在の国立病院機構茨城東病院)が営まれた。
セルマン・ワクスマン
結核については、徳富蘆花の『不如帰』、堀辰雄の『風立ちぬ』『菜穂子』、久米正雄の『月よりの使者』、トーマス・マンの『魔の山』など結核患者やそれをめぐる人間関係、サナトリウムでの生活などを題材、舞台にした小説も多い。
結核菌は1882年、細菌学者ロベルト・コッホにより発見され、1943年にはセルマン・ワクスマンとワクスマン研究室の学生であったアルバート・シャッツによるストレプトマイシンなどの抗生物質があらわれて[注釈 3]、結核は完治する病気となって、患者はいったん激減した。
しかし、近年、学校や老人関係施設、医療機関等での集団感染が増加しており、結核治療中の患者は日本だけで約27万人にのぼり、新たな結核患者が年間3万人も増加している。
世界保健機関(WHO)の推計では世界人口60億人の3分の1にあたる20億人が結核菌に感染していると発表している。
これは、抗生物質の効かない耐性結核菌の発生によっており、「菌の逆襲」とよばれることがある。
また、後天性免疫不全症候群(AIDS)との結びつきが指摘され、「今や結核対策はAIDS対策でもある」と考えられるにいたっている。
インフルエンザ[編集]
詳細は「インフルエンザ」、「インフルエンザウイルス」、「スペインかぜ」、および「第一次世界大戦」を参照
紀元前412年、「医学の父」と呼ばれたヒポクラテスは、すでにインフルエンザと思われる病気の大発生について記録している。
インフルエンザは、1889年に大流行したとき、ドイツの元軍医でコッホの衛生研究所にいたリヒャルト・プファイファーが患者よりグラム陰性の細菌を分離することに成功し、1892年に「インフルエンザ菌」と名づけ、これこそがインフルエンザの病原体であると発表した。
こののち、インフルエンザの病原体をめぐっては論争が繰り広げられたが、1933年に決着した。
スペイン風邪[編集]
詳細は「スペインかぜ」を参照
スペイン風邪の患者でごった返すアメリカ軍の野戦病院(アメリカ合衆国・カンザス州)
鳥インフルエンザの一種と考えられるスペイン風邪は、1918年、アメリカ合衆国の兵士の間で流行しはじめ、人類が遭遇した最初のインフルエンザの大流行(パンデミック)となり、感染者は6億人、死者は最終的には4,000万人から5,000万人におよんだ。
当時の世界人口は12億人程度と推定されるため、全人類の半数もの人びとがスペイン風邪に感染したことになる。
この値は、感染症のみならず戦争や災害などすべてのヒトの死因の中でも、もっとも多くのヒトを短期間で死に至らしめた記録的なものである。
死者数は、第一次世界大戦の死者をはるかにうわまわり、日本では当時の人口5,500万人に対し39万人が死亡、アメリカでは50万人が死亡した。
詩人ギヨーム・アポリネール、社会学者マックス・ヴェーバー、画家エゴン・シーレ、劇作家エドモン・ロスタン、作曲家チャールズ・ヒューバート・パリー、革命家ヤーコフ・スヴェルドロフ、音楽家チャールズ・トムリンソン・グリフスが亡くなっており、日本でも、元内務大臣の末松謙澄、東京駅の設計を担当した辰野金吾、劇作家の島村抱月、大山巌夫人の山川捨松、皇族の竹田宮恒久王、軍人の西郷寅太郎などの著名人がスペイン風邪で亡くなっている。
「黒死病」以来の歴史的疫病で、インフルエンザに対する免疫が弱い南方の島々では島民がほぼ全滅するケースもあった。
1918年のシアトル警察(アメリカ合衆国・ワシントン州)
全員、マスクをしている。
流行の第1波は、1918年3月に米国シカゴ付近で最初の流行があり、アメリカ軍の第一次世界大戦参戦とともに大西洋をわたって、5月から6月にかけてヨーロッパで流行したものである。
第2波は1918年秋にほぼ世界中で同時に起こり、病原性がさらに強まって重症な合併症を起こし死者が急増した。
第3波は1919年春から秋にかけてで、やはり世界的に流行した。
日本ではこの第3波が一番被害が大きかった。
インフルエンザウイルスの病原性については、1931年にアメリカのリチャード・ショープが、ブタにおこるインフルエンザが、プファイファーの発見したインフルエンザ菌とウイルスとの混合感染によっておこることを確認し、1933年に、イギリスのウィルソン・スミスとクリストファー・アンドリュースたちが患者からインフルエンザウイルスを分離し、フェレットを用いた実験によって証明して、病原体論争はおさまった。
さらに、スペイン風邪の病原体の正体は、アラスカの凍土から1997年8月に発掘された4遺体から採取された肺組織検体からやがてウイルスゲノムが分離されたことによって、ようやく明らかとなった。
これにより、H1N1亜型であったことと、鳥インフルエンザウイルスに由来するものであった可能性が高いことが証明された。
つまり、スペイン風邪は、それまでヒトに感染しなかった鳥インフルエンザウイルスが突然変異し、受容体がヒトに感染する形に変化するようになったことが原因と考えられる。
したがって、当時の人びとにとっては全く新しい感染症(新興感染症)であり、スペイン風邪に対する免疫を持った人がきわめて稀であったことが、この大流行の原因だと考えられるようになったのである。
スペイン風邪におけるおもな死因は二次性の細菌性肺炎であったといわれる。
なお、アメリカ発であるにもかかわらず「スペイン風邪」と呼ばれたのは、当時は第一次世界大戦中であり、世界各国・各地域で諸情報が検閲を受けていたのに対し、スペインは中立国であったため、主要な情報源がスペイン発となったためである。
一説には、スペイン風邪の大流行により第一次世界大戦終結が早まったともいわれている。
アジア風邪と香港風邪[編集]
詳細は「アジアかぜ」、「香港かぜ」、および「ソ連かぜ」を参照
20世紀の100年間でインフルエンザのパンデミックは3度あった。
上述のスペイン風邪、H2N2亜型ウイルスによる1957年のアジア風邪、H3N2亜型による1968年の香港風邪である。
アジア風邪では、世界で200万人もの人びとが死亡した。
1957年の冬、中国の貴州に発生し、中国全土に広がった。
中国の科学者は病原体の分離に成功したが、当時、中国がWHOのインフルエンザ関係機関に加わっていなかったため、その情報が他の諸国に伝えられたのは、流行から2か月も経過してからであった。
このあいだアフリカや中南米に拡大し、欧米では夏にはあまり広がらなかったが秋に入り、世界的に流行した。
日本での感染者は届出のあったものだけで98万3,105人、死者は7,735人にのぼる。
香港風邪では、世界で100万人が死亡し、日本の死者は2,200人以上である。
H3N2亜型に属する新型ウイルスであった。
同時にH2N2亜型のものは姿を消した。
現在の季節性インフルエンザの原因の1つである。
その後、1977年にはソ連風邪がエンデミック(局地的流行)となった。
これまでパンデミックを起こしたインフルエンザウイルスは、いずれも鳥類に由来するものであり、しかも弱毒性のものであった。
今後、発生が心配されているのはH5N1亜型の強毒性のものである。世界保健機関(WHO)の李鍾郁(イ・ジョンウク)元事務局長は「もはや新型インフルエンザが起こる可能性を議論する時期ではなく、時間の問題である」と述べており、2005年、アメリカのジョージ・W・ブッシュ大統領は、新型インフルエンザ対策を優先度の高い国家戦略とすると表明し、国際的な協力体制の構築を各国によびかけた。
2009年新型インフルエンザ[編集]
詳細は「2009年新型インフルエンザの世界的流行」および「新型インフルエンザ」を参照
21世紀にはいり、2009年には新型インフルエンザの世界的流行があった。
当初はメキシコおよびアメリカ合衆国での局地的流行であったが、2009年春頃から2010年3月にかけ、A型、H1N1亜型のインフルエンザウイルスによる豚インフルエンザとして世界的に流行した[注釈 4]。
WHOは2009年4月27日にフェーズ4を、2日後の4月29日にはフェーズ5を、6月11日にはフェーズ6を宣言した。
これは、21世紀に入って人類が経験するインフルエンザ・パンデミックの最初の事例となった。
日本では感染症予防法第6条第7項第1号において「新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザ」と規定され「新型インフルエンザ」と命名されている。











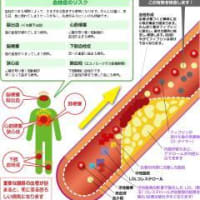

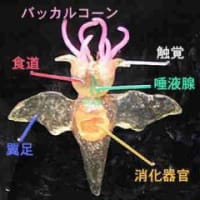

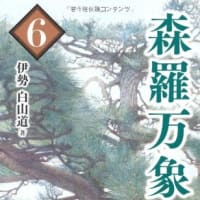
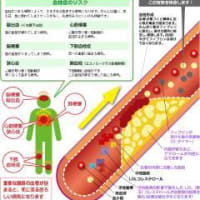

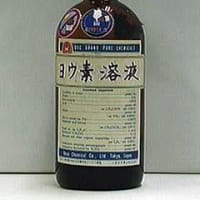
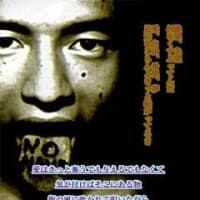
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます