9月10日は旧暦八月四日で二百二十日
うっかりしていましたが、今日9月10日は旧暦の八月四日で二百二十日です。(立春から数えて220日目です)
八月の和風月名は「葉月(はづき)」です。
「葉月」の由来ついては木の葉が黄葉して落ちる月、「葉落ち月」が「葉月」に訛ったものであると言う説、また、稲穂の「発月(はりづき)」の意からきたと言う説もあります、また、南方より吹く「ぐ風」(台風のこと)の多い月と言うことから、「南風月(はえずき)」の転化ではと言う説もあります、日本書紀にはこの言葉を記した一例があると言うことです。
旧暦では、七月・八月・九月が秋です、八月は真ん中なので「仲秋」です、だから、旧暦の八月十五日(新暦9月21日)は「仲秋の名月」です、また、別名「芋名月」とも言われます。
また、旧暦の八月一日を「八朔」と呼びます。
「八朔(はっさく)」とは旧暦八月朔日(ついたち)の呼び名で(朔は“ついたち”の意味)古くは、稲の取り入れに因んで、この日に身分の上下なく、それぞれ贈り物をする風習があったようです。
江戸時代には、徳川家康の江戸入城が天正十八年八月朔日(勿論、旧暦です)だったことから、幕府の重要な式日となり、諸大名や直参旗本が正装して、将軍家へ祝いの詞を申し述べる行事が行われたそうです。
また、「八朔」は旧暦八月一日頃に吹く強い風の事も言い、農家にとって、二百十日・二百二十日と共に、三大厄日として、収穫前の稲の大敵として、恐れられたと云います。
それにしても、今台風が二つも同時に発生しています、14号が来週東に進路を変えなければ良いのですが。
近年台風の進路が九州・四国より、東や北の方にずれているように感じますし、雨の降り方も激しさを増しているようです、(今世紀は400年周期の大雨の世紀だそうですが)やはり、地球を取り巻く色々なものが(太陽からの放射線や銀河からの放射線等)、少し変化しているのですかね。
近年は特に災害が多いのは、日本各地の神様が、なぜか非常にお怒りになっておられるのでは、ないのでしょうか、はやく、お怒りを収めて頂ければ良いのですが。
しかし、人間が、己の欲の為に、森や林を伐採し原野を潰して、重金属を含むパネルを敷き並べたり、尾根に風車を並べて、森に入る風を弱めて二酸化炭素が森の隅々まで行き渡るのを阻害したり、再生エネルギーの利用を大義名分に、日本の各地で大規模に自然を破壊しているのを見ると、神様もきっとお怒りになるだろうなあと思います。
まあ、今世紀は400年周期の大雨の世紀に当たるそうですし、色々ある世紀だと覚悟して、神様を怒らせ無い様に、真っ当に働いて暮らしましょう。
「働く」とは傍(はた)を楽にすることだそうで、ようは、自分が動く(働く)ことにより周りの誰かが楽になるのが、「働く」と言うことです、けっして「労働」ではありません。(これはどこかの先生の受け売りですが)
また「五輪書」に曰く「神仏を敬い、神仏を頼りとせずと」 神社にお参りする時には、未来をお願いするのでは無く、過去の息災への御礼を。










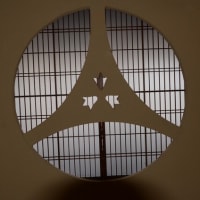








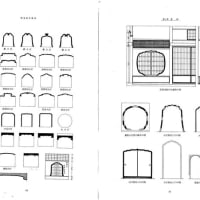

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます