

埼玉六宿の一つ、日光街道杉戸宿は、2016年に江戸幕府が日光街道に設置した宿場として開宿400年を迎えました。本陣、脇本陣、又庶民の宿泊する旅籠も設けられ、街は枡型と呼ばれる出入り口がクランク状態に曲がっていて江戸防衛が意識された宿場町になってます。
街道沿いには古い民家や、蔵が多く残され高札場と共に街道の歴史を伝えています。早春の街道と、宿場を散策に行きましょう

【開催日】 平成30年3月17日(土)
【集合場所】 東武スカイツリーライン 東武動物公園駅改札口
【集合時間】 午前10時
【解散場所、時間】東武動物公園駅近く古川橋あたり 午後3時ごろ
【参加費】 正・家族会員 3,000円
準会員・一般 3,500円
【コース】
東武動物公園駅~関口酒造~杉戸町役場~来迎院~延命院~
香取神社 昼食(芝甲)~高札場~近津神社~神明神社~
問屋場跡~本陣跡~宝性院~浅間神社~愛宕神社~流灯工房
~古川橋

【昼 飯】 蕎麦の膳 芝甲 www.shibakou.org
メニュー
1.天丼セット(天丼に、温かい蕎麦かうどん付き)
※うどんの方は連絡下さい
2.エビ床柱のかき揚げ天せいろ
3.活〆穴子天せいろ
※.メニューの写真は添付の「訪問先メモ―杉戸宿」の最後尾をご覧下さい。
【ガイド】 杉戸宿案内人の会
【募集人員】 30人

< お申し込みの方 >
1.正会員は必ず会員番号をご記入ください。
(ご記入のない方は、準会員・一般価格となります。)
2.緊急連絡先(携帯番号)を必ずご記入ください
3.ご希望のメニューをご記入下さい
では、皆様のお申込みをお待ちしています。
<訪問先メモ>
【関口酒造】
春は新緑に包まれ、夏は太陽の光を燦々と頂き、又紅葉の秋は黄金の稲穂に囲まれ、冬は日光連山からの風雪を仰ぐ「万葉集にも歌われた紫峰・筑波山」。四季折々の恵みを授かり、広がる裾野は良質の小麦や大豆の産地として知られ、古くから醤油の醸造が行われてきました。
関口酒造は、その四季に恵まれた筑波山の裾野に根を下ろし、大正十二年より醤油を製造しております。又、米菓部門では「お醤油屋さんのつけやき」等を世に送り出し、今日まで数多くの方々からの御愛顧を頂いております。
【来迎院】

来迎院は、正式には花光山来迎院と言います。本尊は不動明王で、約800年ほど前に作られたものだそうです。
眼病を治す不動明王として知られているそうです。境内入ってすぐ右手には十三仏像という石像があり、それぞれの表情と説明書きに見入ってしまいました。その横にある鐘楼も雰囲気がありました。
一転、正面にある拝殿はコンクリート造りの現代的な建物ですが、数色の布が壁に掛けられていて、無機質感はありませんでした。拝殿内には運慶作の不動明王がまつられています。
【延命院】

延命院は、正式には倉松山延命院と言います。本尊は延命地蔵菩薩です。開山は長亨元年(1487)に領主一色丹波守直基の帰向によるものとされています。
日光街道の七福神の弁財天です。弁財天とは唯一の女神で、知恵財宝、愛嬌縁結びの徳があるといわれます。 インドの水の神、音楽の神、知恵の神。 本来の姿は、八臂で金剛杵・弓矢・刀などを持ち、水の恵みを与え、河の怒りをもって水を供給してくれる五穀豊穣の神様でもある。 中世以降では、琵琶を抱える姿が多くなり、音楽や芸能、弁舌の神様となったそうです
【香取神社】

創建年代は明らかではないが、本殿に安置されている石造の十一面観音像に延宝三年(1675)の銘がある。また、当地は元和・寛永年間(1615~43)の開発と伝えられているので、およそその時期と思われる。
当社は上新田の鎮守であったが、明治五年(1872)の社格制定に際し村社となった。昭和五十九年(1984)区画整理にともない現在地に移転した。
境内には、宝暦二年(1752)銘の稲荷大明神と疱瘡を免れることを祈って祀られた疱瘡神がある
【昼食(芝甲)】

芝甲の蕎麦は、蟻巣石(ありす)と安山岩の二台の石臼で製粉しています。
蟻巣石の石臼は、特徴として
石の構造が蟻の巣状になっており、その為、熱を持ちにくく、蕎麦の風味を壊さずに甘皮までしっかりと挽ききることが可能になります。
【高札場】

杉戸宿の上町エリアに入った。
特になんの表示もないが、この民家の場所が高札場跡であるらしい。
ここに、掟とかお達しなど掲げられていました。
【近津神社】

近津神社は、清地村の鎮守であるという。 天和4年に本社建立という記録があるようで、創建は江戸初期より前になるだろうか。 境内に残る石祠や石碑が当時の記憶を止めるものとなっている。
小さなお社ですが、大銀杏の木が守る神社で、狛犬がかなりユニークでした。
近津神社も狛犬は、見返り美人ならぬ見返り狛犬で、神社を守る狛犬は後ろを睨みつけるようにして振り返っていました。
杉戸宿散歩をするならば、日本でも珍しい見返り狛犬は必見。関東大震災をはじめ、最近では不審火により、何度か拝殿は焼失しているそうです。教会の隣から始まる長い参道を行くと、多数の石碑や富士山を模した岩山などが残っています。
【神明神社】

住宅街の中にぽっりと空地があり、そこに白い鳥居と小さな拝殿が建っている、何となく不思議な異空間です。古くからある地元の鎮守様で、夏祭りの時はとても賑わうそうです。
なんでも、寄進者の名前に、斎藤作兵衛など名字があり、庶民の苗字帯刀が禁止されていたはずの江戸期にも名字を名乗った町民がいたことが分かるのだという。 また、別当寺院の神明院があったが、明治に廃寺になったとある。
【問屋場跡】

「本陣跡地前」という交差点を渡ると 三井住友信託銀行の店先に「明治天皇御小休止阯」の碑が建っている。
当時、県の第六区区務所が置かれていて、東北巡幸に際して休憩を取ったのだとか。
江戸期においては、杉戸宿の問屋場が置かれ旅人の荷物の輸送と宿泊の調整が行われていたという。
【本陣跡】

本陣とは、江戸時代、大名や幕府の役人が街道を通行する際に使用した専門の宿泊施設です。杉戸宿では長瀬家がその任にあたり、建坪およそ166坪半であったと『宿村大概帳』にはあります。同家には、往時を偲ばせる門がまえが現在も残っています。
門のある民家が杉戸宿本陣跡(長瀬清兵衛邸)であるという。
両側には脇本陣(酒屋伝右衛門邸、蔦屋吉兵衛邸)があったというが正確な場所の特定には至っていないらしい。
【宝性院】

杉戸宿 横町にある真言宗 宝性院は、日光道中の安全を守るお寺で法要など他に、戸籍管理、寺子屋、旅籠といった公共施設としての役割も担っていたという。
境内には毘沙門天像や六地蔵尊、庚申塚などみどころがたくさんありました。庭の手入れも行き届いていて、とても心の休まるお寺でした。
【浅間神社】

麓から大日如来、仙元大菩薩、小御岳石尊大権現、御室浅間太神とあり、塚頂に富士大権現が鎮座している。また、大日如来の脇に芭蕉句碑が埋め込まれている。
【愛宕神社】

こじんまりとした、いかにも町の鎮守様といった風情の神社。拝殿の彫刻は見事でした。また、拝殿横にそびえる大イチョウの木は、火災に遭い上部がありませんが、太い幹からは新木が生まれ、力強い生命力を感じました
【流灯工房】
杉戸町は日光街道の宿場町として栄え、再来年の平成28年に400年を迎えます。
そこで、町の伝統文化である「古利根川流灯まつり」継承のため整備された「杉戸町流灯工房」において、文化芸術イベント「杉戸宿開宿400周年記念すぎと今昔物語」を開催しました。
【古川橋】

杉戸町観光協会は、杉戸宿開宿400年に併せ、町の活性化、町のにぎわい創出の一環「杉戸宿開宿 400 年プロジェクト」として、杉戸町民生委員、子ども会育成連絡協議会、アグリパークゆめすぎと、ボーイスカウト杉戸第1団・第2団の協力の下、杉戸町の西部に流れる大落古利根川に、4月 29 日㈮~5 月 8 日㈰までこいのぼりを掲揚した。
<昼食メニュー>
1.天丼セット

天丼に温かいそば又はうどんにもなります
2. 海老と小柱のかき揚げ天せいろ

3. 活〆穴子天せいろ

当店にてさばいた穴子は、鮮度と旨みが違います













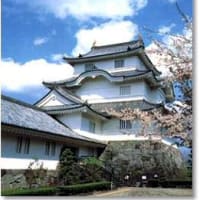






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます