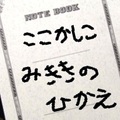…ということで染料植物園から続く遊歩道 を歩き、たどり着いたのは
高崎一の観光スポットでもあろう白衣大観音でありました。
・・・と、この後は高崎白衣大観音の話なのですけれど、続きはこちらをご覧願えれば幸いです。
歴史ものだなと「豪姫」という映画を見てみたのですね。
前田利家の娘で幼くして秀吉の養女となり、やがて宇喜田秀家に嫁ぐも
関ヶ原 の敗戦で夫も子供も八丈島に配流されることに。
豪姫自身は前田家にお預けとなりますが、八丈島で命脈をつないだ宇喜田家の末裔に
前田家では後々までも物資を送るなどの配慮を欠かすことがなかった…。
てなところが豪姫周りの歴史ということになりましょうけれど、
勅使河原宏監督によるこの映画、ストーリー自体、かなり自由に作っていると思いますし、
また淡々とした映像はいかにもながら、戦国の世を映し出すという動的な側面からは敢えて離れているような。
・・・という書き出しながら、この後は陶芸の話になっていくのですけれど、続きはこちらをご覧願えれば幸いです。
南西ドイツ紀行 というわりにはフランスへのサイドトリップ の話が何回かに及んでおりますが、
今しばらくはフランス、コルマールのお話ということで。
で、ちと後だしになりましたけれど、ウンターリンデン美術館 随一の目玉作品といえば
マティアス・グリューネヴァルトの「イーゼンハイム祭壇画」ということになりますですね。
・・・と、この後はイーゼンハイム祭壇画をじっくり見たという話なのですけれど、続きはこちらをご覧願えれば幸いです。
染料植物園はその名のとおりに染料となる各種の植物を植えてあるわけですね。
「草木染め」という言葉がありますけれど、古来の染物はかなり草木に頼っていたでしょうから、わざわざ「草木染め」とことわるまでもなかったのではと思ってしまいます。
園内をざあっとひと回りする中で、一見したところでは単なる野山の散歩道かと思うところながら、
ほとんどの植物には種類の名前と、その植物からどんな色合いを作り出せるかの説明が。
・・・と、この後は染料植物園と遊歩道の話なのですけれど、続きはこちらをご覧願えれば幸いです
日本にタバコが伝わったのは16~17世紀とされて、明確な渡来時期は不明なんだそうですね。
確かな記述としてはスペイン・フランシスコ会の修道士ヘロニモ・デ・ヘススが
家康にタバコの種を献上したのが慶長六年(1601年)であったということ。
これは「珍しいもの」として時の権力者に献上したとも受け取れなくはありませんから、
当時は未だタバコが一般的に流通していたとは言えないような気がしたものです。
(Wikipediaでは「全国に普及したのは江戸時代初期」とありました)
と、高崎市染料植物園染色工芸館 での「江戸の男子のファッション事情」なる展示に絡んで、
ファッションの一環たる煙管などの展示を見たときに、ふと「?!」と思いましたのが
TV東京で放送中のドラマ「石川五右衛門」なのでありますよ。
・・・と、この後は石川五右衛門の話なのですけれど、続きはこちらをご覧願えれば幸いです。
ヌフ=ブリザック を後にしたバスはしばし田園風景を走り過ぎ、だんだんと町らしい中へと入り込んで行きましたけれど、とある街角に停まるやドライバーが乗客の方を向いて何やらひと声告げたのですな。
すると乗客が我も我もと降りていく…となれば終点でもあらんかと慌てて降車。バスは走り去り、周囲はバスから降りた人ばかりでなく観光客がたくさんいるものの、「はて、ここはどこ?」と。
と言いますのも、バスはコルマールの駅行きであって、駅から旧市街はちと歩かねばなあと思っていたわけですが、降りたところはどう考えても駅ではない。まあ、結果から言えば乗ったバスは終点のコルマール駅に向かう途中に旧市街に停車することから、みんなわらわら降車したという次第でありました。
後から思えばドライバーは「テアトル!」と叫んだようで、要するに劇場前。となると、コルマールで第一の目的地たるウンターリンデン美術館は回りこんですぐ裏にあるはず。駅から歩くものとばかり考えていたことからすれば、なんとらくちんにたどり着いてしまったことか。
・・・と、この後はウンターリンデン美術館を見て回るのですけれど、続きはこちらをご覧願えれば幸いです。