2020年7月5日
パッドユニットはAmazonで1100円。
ピックローラユニットは5000円(使えるだけ使うか)。


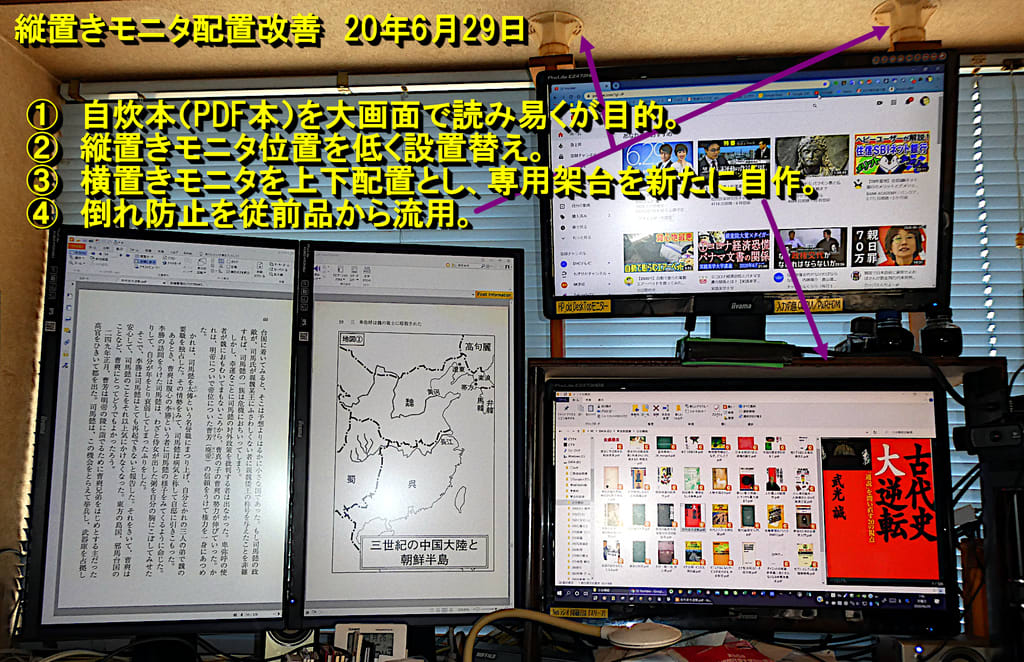


これを改善する外国製のフリーソフトが紹介されています。が、素人がパソコンの基本機能であるpdf閲覧に手を加えたくない。何かあっても元に戻せない。躊躇せざるを得ないです。
①使っているpdfリーダを単体で立ち上げ「開く」でpdfファイルホルダを参照します。すると、各pdfファイルのサムネイルが作成されます。キャンセルを押してpdfリーダを閉じます。(説明の例はAdobe Reader X 、いつも使っているのはFoxitReaderですのでpdfのマークが異なっています)。
②エクスプローラでpdfのフォルダを開きます。
サムネイルが表示されています。書店の平積みから本を選ぶような快適さが生まれます。
本はパソコンで読む。自炊本、電子本。紙本廃棄で空間すっきり。だが、紙で残しておきたい本が、数十冊に1冊はあります。厚さ45mm、800ページの本を自炊裁断後、再製本しました。成功です。実践記録を展示します。
①私の自炊、電子化本の目的はパソコンで読む、紙書籍を捨てるです。従って、再製本は数十冊に1冊月に1度か2度でしょう。今回は、ブログ表示改善の為に中古本で購入したHTMLの教本です。なんと、800ページ厚さ45mmです。本の性格上、他ページ参照が頻繁に出てきます。パソコンで行きつ、戻りつは面倒です。紙の本をそばに置いてパソコンで読みます。②世の中には個人用の製本道具が売られています。電子化して且つ紙本も残すのであればこれらも便利でしょう。しかし、45mmの厚さには対応できない、滅多に使わないのであれば「自力更生」の他に手はありません。
とじ太くん 卓上製本機とじ太くん 3000型 3000
価格:¥ 8,400(税込)
発売日:
①本にはいろいろな綴じ方があります。本文の背を接着剤で固める無線綴じ、並製本で目的を達成できます。②道具も、やり方も簡単です。最大のコツは揃えた本文を確実に固定すること。ただそれだけです。このため、自作プレス機を作りました。単なる丈夫な紙ばさみです。丈夫な板2枚と8mmのボルト、調ナットです。いずれもホームセンターで入手できます。
①本文を揃え固定します。背にのりをつけ接着しますが、背の反対側のページをめくる表側が平面になる様に揃えます。②本文が厚すぎて自作プレス機で固定できません。残念、想定外の厚みです。③あきらめきれず、あり合わせのクランプで固定しました。確実に固定する。これだけがコツです。クランプとは日曜大工で時々必要になる締め付け固定器具です。ホームセンターでも売っています。色々な種類を持っています。下のタイプが比較的使いやすい、安定感、安心感があります。<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&bc1=000000&IS2=1&bg1=FFFFFF&fc1=000000&lc1=0000FF&t=somethingha00-22&o=9&p=8&l=as4&m=amazon&f=ifr&ref=ss_til&asins=B001D7DCGS" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="width: 120px; height: 240px;"> </iframe>
接着面の面積を増やして接着の強さをあげる必要があります。接着面背の部分、を金のこで溝を切ります。5mm感覚で深さ1~2mmが目安です。今回は本が厚すぎたことと、金のこの刃が消耗していて旨く切れませんでした。何とか0.2から0.5mmの溝をつけました。接着面(背の部分)を紙ヤスリですって傷をつけておけば気休めになります。(効果はあると思います)。加工後は掃除機で吸わせます。<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&bc1=000000&IS2=1&bg1=FFFFFF&fc1=000000&lc1=0000FF&t=somethingha00-22&o=9&p=8&l=as4&m=amazon&f=ifr&ref=ss_til&asins=B0026FBG32" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="width: 120px; height: 240px;"> </iframe>
接着面に接着剤を厚めに塗り、へらやブラシ(歯ブラシの古いもの)で軽くすり込みます。今回は皮、布用のボンドを使いました。接着後の柔軟性を期待したためです。しかし、粘度が高く刷り込みにくい。使う量が多いため高くつく。明快な効果は不明。次は一般的な木工用の速乾ボンドを使います。
木工用速乾ボンド 180g
価格:(税込)
発売日:
接着剤が30分から1時間でほぼ乾いたら、ねちねち感が残っていても手に付かなければOKとします。何時間も待てませんので。接着面全面にホットメルトガンでホットメルト材を溶かしながら付着させます。1~2mmの厚みまで付着させます。見返しの背部分にも表紙との接着用に一筋塗っておきます。すぐに温度が下がり固まります。付着面はでこぼこでムラがありますが、かまいません。表紙をつける時にアイロンを押しつけ溶かして接着しますので。ホットメルトガンは一家に一台の必需品と思います。<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&bc1=000000&IS2=1&bg1=FFFFFF&fc1=000000&lc1=0000FF&t=somethingha00-22&o=9&p=8&l=as4&m=amazon&f=ifr&ref=ss_til&asins=B003EILCG6" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="width: 120px; height: 240px;"> </iframe> <iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&bc1=000000&IS2=1&bg1=FFFFFF&fc1=000000&lc1=0000FF&t=somethingha00-22&o=9&p=8&l=as4&m=amazon&f=ifr&ref=ss_til&asins=B003EIG4Z0" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="width: 120px; height: 240px;"> </iframe>
接着された本文をプレス機から取り出します。表紙を丁寧に位置をあわせと、本文に取り付けます。背の部分にアイロンを高温にセットして押し当てます。ホットメルトが溶けて本文と表紙とが背の部分で接着されます。背の周囲にもアイロンを押し当て、見返しののど部での接着を確実にします。
アイロンの押し当てで表紙が変色することもあります。白紙を1枚おいてアイロンを押し当てます。
これで完成です。カバーをつければ、元の通りです。念のため、接着剤が完全に乾くまでページは強く開かない様にしましょう。
ホットメルトが多いので、表紙をぴったり本文に合わすは難しいです。もう一度アイロンを当てると、容易に表紙をはがすことが出来ます。位置を修正してまたアイロンを当てます。これを数度繰り返せば、何とか満足のいく結果が得られるでしょう。
紙質と印刷インクにもよりますが、アイロンを当てたところの変色はある程度覚悟しましょう。機能上は問題ありませんので。
退職で専門書、雑誌は即座に捨てました。買い手はありません。古紙回収又は燃えるゴミ行きです。いつかは読むかも知れない、役に立つかも知れない。捨てがたい一般書が、人生のうみのように残っております。残り少ない人生だ。全て捨てようと決断した時に、自炊本の流行をネットで知りました。早速、機材をそろえ実践しました。以来1ヶ月、約9,000枚、18,000頁を電子化・整理しました。みるみる本棚の一段が空き、カメラ置き場に変身。う~ん、久々の充実感。簡単です。分かりやすく、しつこく説明します。
①空間の創出
退職で専門書、雑誌は捨てた。
それでも捨てがたい本がいっぱい残った。これを捨てれば夢の空間が生まれる。
②拡大して読める。
紙の本は字が小さい。老年では読めない。重い。疲れる。パソコンで読む。タブレットで読む。スマホで読む。加えて、重量ゼロ。マーク、しおり自由自在。頭に入る。
③分類整理が容易。必要な時に取り出せる。
山積みの本は、取り出せない。必要な時には見つからない。電子ファイルの整理で全てが解決。
④切り貼り自在。文字の検索可能。
紙では望めない電子機能。これだけでも、電子化の値打ちあり。
①私は 富士通 ScanSnap S1300i FI-S1300A を購入しました。
富士通 ScanSnap S1300i FI-S1300A
価格:(税込)
発売日:2012-05-25整理ソフトがついたものもあるようです。
FUJITSU ScanSnap S1300i Deluxe FI-S1300A-D
価格:(税込)
発売日:2012-11-16
②ネットではこのScanSnapシリーズが好評です。
上位機種の ScanSnap iX500 FI-IX500がベストのようですが約2万円高いです。急いで数百冊を処理する必要があれば上位機種が良いでしょう。時間はある、ぼちぼち整理するであれば、結果的に、この1300で充分です。
③小さくて机のすきまに設置できます。
手の届くところに置けば、紙のセットも修正も、排除も苦になりません。効率が上がります。
④ちなみに、私は長年フラットベッド方式のスキャナーを愛用しています。
数種類を購入、廃棄の後、EPSONのGT-7600Uが2台が生き残っています。1台は友人にもらったものです。故障時のバックアップとして持っています。契約書類、パンフレット、手紙類は電子化して保管しています。オートシートフィーダ、フィルム読み取りセットも専用のものを持っていますがこれらは使っていません。結構手間がかかる為です。家庭で使うスキャナーはこれしかないと10年以上も信じていました。それでも本1冊をスキャンするなど言うことはその手間を考えれば夢にも考えませんでした。
⑤ScanSnapは撮像素子でシートを動かす自動給紙方式、同時両面読み取りのスキャナーです。
200ページ、300ページの読み取りも10数分で苦になりません。但し、本はバラバラにし、各ページを切りそろえ、各ページを紙の束にする必要があります。裁断する必要があります。
⑥数十冊に数冊は紙の本で置いておきたい場合があります。
裁断した本を、再び製本することが出来ます。後日、方法と実践結果を展示します。裁断が出来ない本もあります。例えば、仏壇の「御文章」の様なものです。これは各ページをカメラで撮影して電子本にします。後日、方法と実践結果を展示します。また、図書館で借りた本は傷をつけてはいけません。必要部分をフラットベッド方式のスキャナーでコピー電子化するか、カメラで撮影します。これも、後日、実践結果を展示します。
①私は カール事務器 ディスクカッター DC-210N を購入しました。②ネット上で色々な裁断機が売られています。
このタイプが最も小さく、軽く、安価です。小さいと云っても、常時、机の上に置けるサイズでありません。キャスターワゴンの上にはめ込み台を自作し、設置しました。移動式裁断機です。快適です。<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&bc1=000000&IS2=1&bg1=FFFFFF&fc1=000000&lc1=0000FF&t=somethingha00-22&o=9&p=8&l=as4&m=amazon&f=ifr&ref=ss_til&asins=B002HVI8UE" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="width: 120px; height: 240px;"> </iframe>