目次
1はじめに
2.日本語の外来語の起源
3.外来語増加の要因
4.外来語増加の悪い影響
5.終わりに
6.参考文献リスト
1.初めにはじめに
言語は生きているもので、経済や政治の発展に伴い、変化を受け取って、社会の特徴を表わす。現在日本語の特色の一つは外来語の増加である。 外来語の増加に関して、色々な意見があるので、外来語の影響について調べて、外来語の増加が問題になっていると言う意見についても考えたいと思う。
2.日本語の外来語の起源
外来語は外国から借りられて、自国語と同様に使用するようになった単語である。日本語にはおもに西洋諸言語からの借用が多く、洋語とも呼ばれる。西洋からの外来語は本格的に幕末期~明治時代以降に増加したが、それ以前にも、16世紀にポルトガル語から入ってきたタバコ、パン、江戸時代にオランダ語から入ってきたガラスなどが日本語としてよく定着している。明治維新以降もドイツ、イギリス、アメリカの3国を中心に、フランスからも色々な分野の言葉が多く借りられた。鉄道用語はイギリス英語、医学用語はドイツ語、芸術用語はフランス語起源のものが多く使われている。戦後の日本語には英語から置き換えられた言葉が多くなった。
3.外来語増加の要因
外来語は現在文化の実在を表して、社会状況をよく反映する。田島・金(2011)には日本人の外来語の使用の利点について、次の点が認められると述べている。
①日本語による社会的なコミュニケーションが一層適切に行われるようにしていくこと
②日本語を一層魅力的で価値あるものにしていくこと
③日本語に関する働き掛けを通して人類の有する文化の多様性が世界の中で生かされるようにしていくことが大切であるという認識
④日本語は昔から外国語を取り入れてきたということ
⑤日本語や日本文化が豊かになるということ
4.外来語増加の悪い影響
情報の交流の増大や、諸分野における国際化の進展に伴い、日本語の中での外来語の使用が増大して、問題になっていると言われている。借用語は増加して、一般の人々にとって覚え切れないほどに新しい語が次々に出現している。専門領域で使われていた語がそのまま一般社会に出て、コミュニケーションを阻害する。それは、社会的な情報の共有を妨げるおそれがある。外国語ができないため、情報を受け取れない人もいる。しかし、一方で、原語の発音と外来語の発音の違いが大きくて、外国語がよくわかる人も分からないことばが多い。つまり、外来語は日本語の一形態になっていて、日本語の特別な部分なので、あえて習わないと、困ることもあるらしい。
文化庁の平成24年度「国語に関する世論調査」の結果によると、外来語が分からなくて、日常生活で困ることがある人が少くない。「日頃,読んだり聞いたりする言葉の中に出てくる外来語や外国語などのカタカナ語の意味が分からずに困ることが,よくあるか,たまにあるか,それとも,ないか」と尋ねたところ、「よくある」と「たまにはある」と回答した人を合わせた「ある(計)」の割合は8割弱,「困ることはない」は2割であった。さらに、外来語をよく使用するのは若い世代で、高齢者にとっては分らない外来語が多い。調査によると「(困ることが)よくある」と回答した人の割合は,16歳から30代までは1割に満たないが,40代で1割強,50代で2割強,60歳以上で3割強となって,年代が高いほど,割合が高くなる傾向があるのが見える。この結果を考えてみたら、世代にはコミュニケーションギャップがあることが推測できる。
更に、同じような言葉が日本語にあるにもかかわらず、外来語を使うのは日本語の伝統を崩して、日本語の価値を損なう危険性もあると言われている。言語学の記事を読んでいて、面白い引用を見つけたので、このレポートに加えたいと思う。言語学者の田中克彦は「外国語要素の充満は独立性の喪失のみならず、自らの言語の無能力、力不足を露呈したことにもある。外の言語の力をかりたということになるからである」と述べている。
原語の意味から外れた誤った外来語使用や和製英語の濫用は日本人の外国語学習にとっても障害となる。一方、外国人にとっても片仮名語は分かりにくくて、日本語理解の障害となることもある。学習者として、能力試験の勉強をしていた時、試験の問題に出る片仮名語は語彙の教科書と違って、別の教科書になっていると分かった。自分の経験から言うと、わかりやすい外来語もあいまいな意味がある外来語もあって、英語が上手な人が分からない、英語から借りられた外来語もある。
5.終わりに
要するに、現在の日本語には外来語は付き物だと言える。経済ヤ政治の発展のため、外来語は今より増えるという気がする。しかし、外来語の普及は止められなくても、日本語の独自性や美しさを無くさないように気を付けなければならないと思う。
参考文献リスト
1.外来語 Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E6%9D%A5%E8%AA%9E
2016年11月 日参照
2.平成24年度「国語に関する世論調査」の結果の概要
http://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/kokugo_yoronchosa/pdf/h24_chosa_kekka.pdf 2016年11月 日参照
3.文部科学省国語審議会「国際社会に対応する日本語の在り方「三.国際化に伴うその他の日本語の問題」」
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/old_bunka/kokugo_index/toushin/attach/1325316.htm 2016年11月 日参照
4.田島毓堂・金華(2011)「日本語の外来語の増加と中国の日本語教育」愛知学院大学人間文化研究所紀要26号
http://kiyou.lib.agu.ac.jp/pdf/kiyou_02F/02__26F/02__26_138.pdf
2016年11月 日参照
5.中村典子(2011)「外来語と外国語学習について」甲南大学・国際言語文化センター報 Vol.18 No.3
http://www.konan-u.ac.jp/kilc/modules/kiyou/zpy/zp201103.pdf
2016年11月 日参照
1はじめに
2.日本語の外来語の起源
3.外来語増加の要因
4.外来語増加の悪い影響
5.終わりに
6.参考文献リスト
1.初めにはじめに
言語は生きているもので、経済や政治の発展に伴い、変化を受け取って、社会の特徴を表わす。現在日本語の特色の一つは外来語の増加である。 外来語の増加に関して、色々な意見があるので、外来語の影響について調べて、外来語の増加が問題になっていると言う意見についても考えたいと思う。
2.日本語の外来語の起源
外来語は外国から借りられて、自国語と同様に使用するようになった単語である。日本語にはおもに西洋諸言語からの借用が多く、洋語とも呼ばれる。西洋からの外来語は本格的に幕末期~明治時代以降に増加したが、それ以前にも、16世紀にポルトガル語から入ってきたタバコ、パン、江戸時代にオランダ語から入ってきたガラスなどが日本語としてよく定着している。明治維新以降もドイツ、イギリス、アメリカの3国を中心に、フランスからも色々な分野の言葉が多く借りられた。鉄道用語はイギリス英語、医学用語はドイツ語、芸術用語はフランス語起源のものが多く使われている。戦後の日本語には英語から置き換えられた言葉が多くなった。
3.外来語増加の要因
外来語は現在文化の実在を表して、社会状況をよく反映する。田島・金(2011)には日本人の外来語の使用の利点について、次の点が認められると述べている。
①日本語による社会的なコミュニケーションが一層適切に行われるようにしていくこと
②日本語を一層魅力的で価値あるものにしていくこと
③日本語に関する働き掛けを通して人類の有する文化の多様性が世界の中で生かされるようにしていくことが大切であるという認識
④日本語は昔から外国語を取り入れてきたということ
⑤日本語や日本文化が豊かになるということ
4.外来語増加の悪い影響
情報の交流の増大や、諸分野における国際化の進展に伴い、日本語の中での外来語の使用が増大して、問題になっていると言われている。借用語は増加して、一般の人々にとって覚え切れないほどに新しい語が次々に出現している。専門領域で使われていた語がそのまま一般社会に出て、コミュニケーションを阻害する。それは、社会的な情報の共有を妨げるおそれがある。外国語ができないため、情報を受け取れない人もいる。しかし、一方で、原語の発音と外来語の発音の違いが大きくて、外国語がよくわかる人も分からないことばが多い。つまり、外来語は日本語の一形態になっていて、日本語の特別な部分なので、あえて習わないと、困ることもあるらしい。
文化庁の平成24年度「国語に関する世論調査」の結果によると、外来語が分からなくて、日常生活で困ることがある人が少くない。「日頃,読んだり聞いたりする言葉の中に出てくる外来語や外国語などのカタカナ語の意味が分からずに困ることが,よくあるか,たまにあるか,それとも,ないか」と尋ねたところ、「よくある」と「たまにはある」と回答した人を合わせた「ある(計)」の割合は8割弱,「困ることはない」は2割であった。さらに、外来語をよく使用するのは若い世代で、高齢者にとっては分らない外来語が多い。調査によると「(困ることが)よくある」と回答した人の割合は,16歳から30代までは1割に満たないが,40代で1割強,50代で2割強,60歳以上で3割強となって,年代が高いほど,割合が高くなる傾向があるのが見える。この結果を考えてみたら、世代にはコミュニケーションギャップがあることが推測できる。
更に、同じような言葉が日本語にあるにもかかわらず、外来語を使うのは日本語の伝統を崩して、日本語の価値を損なう危険性もあると言われている。言語学の記事を読んでいて、面白い引用を見つけたので、このレポートに加えたいと思う。言語学者の田中克彦は「外国語要素の充満は独立性の喪失のみならず、自らの言語の無能力、力不足を露呈したことにもある。外の言語の力をかりたということになるからである」と述べている。
原語の意味から外れた誤った外来語使用や和製英語の濫用は日本人の外国語学習にとっても障害となる。一方、外国人にとっても片仮名語は分かりにくくて、日本語理解の障害となることもある。学習者として、能力試験の勉強をしていた時、試験の問題に出る片仮名語は語彙の教科書と違って、別の教科書になっていると分かった。自分の経験から言うと、わかりやすい外来語もあいまいな意味がある外来語もあって、英語が上手な人が分からない、英語から借りられた外来語もある。
5.終わりに
要するに、現在の日本語には外来語は付き物だと言える。経済ヤ政治の発展のため、外来語は今より増えるという気がする。しかし、外来語の普及は止められなくても、日本語の独自性や美しさを無くさないように気を付けなければならないと思う。
参考文献リスト
1.外来語 Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E6%9D%A5%E8%AA%9E
2016年11月 日参照
2.平成24年度「国語に関する世論調査」の結果の概要
http://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/kokugo_yoronchosa/pdf/h24_chosa_kekka.pdf 2016年11月 日参照
3.文部科学省国語審議会「国際社会に対応する日本語の在り方「三.国際化に伴うその他の日本語の問題」」
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/old_bunka/kokugo_index/toushin/attach/1325316.htm 2016年11月 日参照
4.田島毓堂・金華(2011)「日本語の外来語の増加と中国の日本語教育」愛知学院大学人間文化研究所紀要26号
http://kiyou.lib.agu.ac.jp/pdf/kiyou_02F/02__26F/02__26_138.pdf
2016年11月 日参照
5.中村典子(2011)「外来語と外国語学習について」甲南大学・国際言語文化センター報 Vol.18 No.3
http://www.konan-u.ac.jp/kilc/modules/kiyou/zpy/zp201103.pdf
2016年11月 日参照










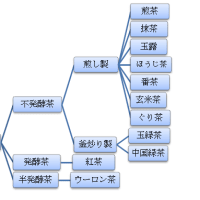
とても興味深い話題なんですね。
学習者として考えると、日本語の表現につまずいたり、困った時に助けてくれる外来語でもありますし、日本語の本来の「美しさ」を乱してしまう外来語でもありますよね。
〈外来語を使いがちな〉教師としては、外来語を使うとき、学習者の抵抗を感じることが多いですが、「ちゃんと日本語で言えるのに」と思うこともあれば、「外来語も日本語なんじゃない?」と全く違和感を感じられないことも少なくありません。
正に、使いすぎないように気を付けなければなりませんね。