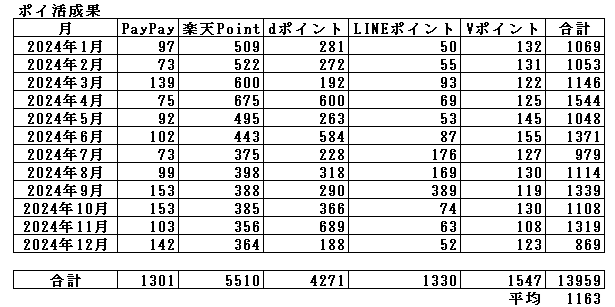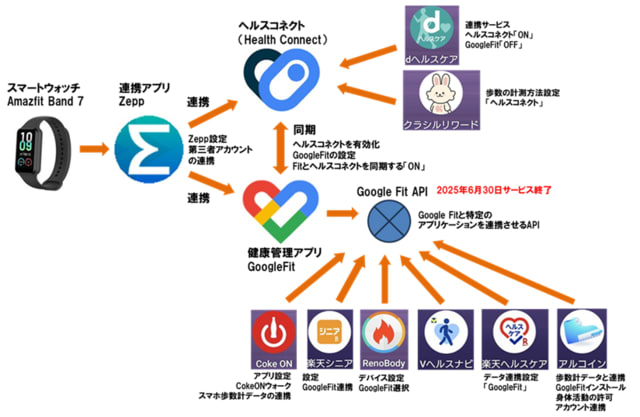2024年12月2日(晴れ)
2年ほど前に眼鏡の買い替えの検眼中に左目だけが方眼紙の縦横線が少し歪んで見えることを自覚する。
眼科での精密検査を勧められる。
眼科で精密検査で左目の網膜部が画像では赤く映っていて厚みがあるとのこと。今後の進み方により手術もとの診断で定期的な検査を勧められた。
その後、2年間放置していたが最近視界の焦点を合わせるのに微妙にズレがおきてるかと感じてきたので過去に通院したことのある眼科で初診を受ける。
黄斑前膜と少し白内障も見受けられるとのことで、早いうちの方が修復度が上がりますが手術をどうしますかとの問いに5秒で「はい」と返事をしていました。
タブレットで手術の説明の動画を見て、手術の説明書を使って対面で説明を受ける。
手術日を1か月後を設定し手術前検査を受け入院のパンフレットの説明と入院時に提出する「手術同意書」「緊急連絡先」「寝具借用書」「入院時食事確認表」と手術前点眼薬(手術3日前から1日4回と手術当日の朝の点眼)を受取り帰宅する。
ここまで、1つの病院で入院以外で7時間(8時~15時まで)を過ごすのは初めてと多数の検査を受けて少し疲れました。
入院までの4週間でいろいろと準備をして迎えた手術日
12時に入院後の大まかな流れ

①ナースセンターで入院の手続き
②手術の案内(予定時間 15時~16時)
③体重測定
④点眼(手術前に4回)
⑤医師から硝子体可視化染色薬の使用についての説明を受ける
(従来使用の染色薬が供給停止による代替薬詩使用に対する同意書)
⑥手術担当医の診察
⑦部屋で手術着に着替え待機
⑧予定時間に手術待合室に移動し待機
⑨手術準備室での前処置
・椅子型のベッドに座る(背もたれが倒れベッドになる)
・点眼(抗菌・散瞳・麻酔など)
・心電図のシール・ 血圧計など装着
・点滴をする
・枕の高さ調整して順番まで待ち
⑩手術室に移動
・術眼の洗眼(消毒液がしばらくしみる)
・顔に消毒をした紙をかぶせる
・まぶたにテープを張って眼を大きく開ける
・ベッドのまま顕微鏡の位置に移動
⑪手術開始
・手術はまぶたを開ける機械を付ける(まばたきできない)
・顕微鏡のまぶしい光を見る
・上や下を見てとの指示に目だけ動かす
・眼の動きは少しだけにする
2つの手術を同時に施術
・術式:硝子体茎顕微鏡下離断(網膜付着組織を含むもの)
・術式:水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合・その他のもの)
⑫手術後部屋に戻る(ガーゼと保護帯を装着)
⑬手術日だけ夕食は部屋に運ばれる
2日目以降は朝の検温や数回の点眼や診察、検査に定期的に呼ばれる。
手術翌日にガーゼが外れたので保護帯の穴から手術眼の視界が出来て無事に見えていることが分かってホッとする。両目が使えるので遠近感が有効になり生活に不自由しないで良い。
で、術後順調に経過しているので退院日は術後3日目か4日目との説明を受け病院での養生を少しでもと4日目に退院としました。
最初の通院日を退院日に予約して帰宅する。
退院後の点眼薬 3種
・クラビット(1日4回 朝昼夕就寝前)
細菌のDNA複製を阻害
・サンデゾーン(1日4回 朝昼夕就寝前)
抗炎症作用や抗アレルギー作用により、目の炎症を抑えます
・ブロナック(1日2回 朝就寝前)
炎症の原因物質であるプロスタグランジンの生成抑制作用などにより炎症を抑えます
日常生活
・入浴、シャワーは退院日から出来る(首から下のみ)
・保護帯は1週間装着
・洗髪、洗顔は1週間過ぎてから目の周りを避けて顔を拭く(それまで髪は美容院等で)
・手術後の充血は自然吸収されるまで2〜3週間程かかる
1週間後に保護帯も取れて、手術側の眼には注意をしながらですがいつもの生活が出来ている。
特に手術の眼は手術前と見え方はそれほど変わりなく視力低下を感じない。
少し歪みが少なくなったようにも感じる、今後歪みがどの程度、改善していくかは期待しています。
今のところ、既存の眼鏡をかけて問題なく生活できるのはありがたいです。
...........