2014年05月 哲学の会 Vol.6 からの続き
彼が変えようとしている美術界もその社会の恩恵をたくさん受けている。
美術界を盛り上げたり、存続していくことは
理不尽に扱われる人たちを作っているということも私は知ってほしい。
いくら絵で生活するために貧窮を極めても
遊んで暮らしていることにはわかりない。
鎌倉時代まで農民一人が
侍、役人、坊さんを養っていたという事実から言っている遊びで
無駄金を浪費する遊びを言ってるわけではない。
室町になると農業生産が爆発的に向上し、
養ってもらえる人たちが増えて、俺は能をやる、俺は絵を描く、
じゃ俺は建築家になるという具合に職業の選択が広がった。
絵でも能でもやっている本人はわからないが、
養っている人たちがいないと絶対に成立しないのである。
(養っている人たちもわかっていないけども)
文化は養っている人たちの基盤がしっかりしていないと育たないものである。
だから、徒党を組んで偉そうにしている絵描きの絵や
こころを込めて描いても評価もされずゴミのように消えていく絵、
そういうものも含めて絵の具は安くなっている。
後世に残る絵が素晴らしく、ゴミになった絵が素晴らしくないのではない。
後世に残る絵もゴミの絵も等しく尊く、ゴミの絵があるからこそ
それとは違う絵が光り輝くわけである。
だから、美術界の悪しき慣習を切って捨てることは
美術界自体を失くすことにも繋がるのである。
絵もゴミの絵と評価された絵とを二者択一する考えではなく、
どちらの絵も支えている人たちがいて、
参加することすら出来ない経済状況の人たちがいるという事実がある。
二社択一よりも三角形の三者を考えてみてはいかがだろうか。

こんなことを書くのも
まあ、ただの負け犬の遠吠えなのだろう。
2014年05月 哲学の会 Vol.8 へ続く
彼が変えようとしている美術界もその社会の恩恵をたくさん受けている。
美術界を盛り上げたり、存続していくことは
理不尽に扱われる人たちを作っているということも私は知ってほしい。
いくら絵で生活するために貧窮を極めても
遊んで暮らしていることにはわかりない。
鎌倉時代まで農民一人が
侍、役人、坊さんを養っていたという事実から言っている遊びで
無駄金を浪費する遊びを言ってるわけではない。
室町になると農業生産が爆発的に向上し、
養ってもらえる人たちが増えて、俺は能をやる、俺は絵を描く、
じゃ俺は建築家になるという具合に職業の選択が広がった。
絵でも能でもやっている本人はわからないが、
養っている人たちがいないと絶対に成立しないのである。
(養っている人たちもわかっていないけども)
文化は養っている人たちの基盤がしっかりしていないと育たないものである。
だから、徒党を組んで偉そうにしている絵描きの絵や
こころを込めて描いても評価もされずゴミのように消えていく絵、
そういうものも含めて絵の具は安くなっている。
後世に残る絵が素晴らしく、ゴミになった絵が素晴らしくないのではない。
後世に残る絵もゴミの絵も等しく尊く、ゴミの絵があるからこそ
それとは違う絵が光り輝くわけである。
だから、美術界の悪しき慣習を切って捨てることは
美術界自体を失くすことにも繋がるのである。
絵もゴミの絵と評価された絵とを二者択一する考えではなく、
どちらの絵も支えている人たちがいて、
参加することすら出来ない経済状況の人たちがいるという事実がある。
二社択一よりも三角形の三者を考えてみてはいかがだろうか。

こんなことを書くのも
まあ、ただの負け犬の遠吠えなのだろう。
2014年05月 哲学の会 Vol.8 へ続く



















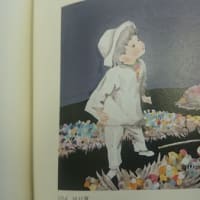
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます