「集志貫徹」
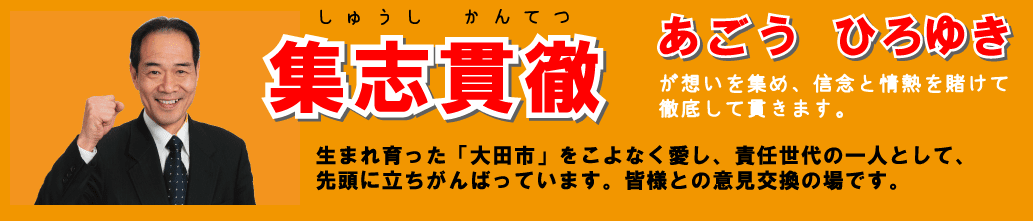
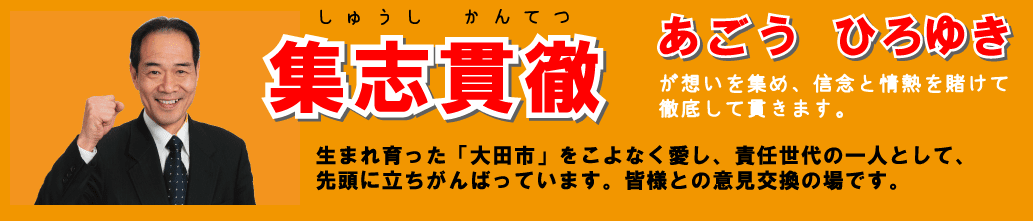

今回約14,000人の方が投票を棄権した理由は何なのか。
投票に行けなかった人の行動を引き続き分析したいと思います。
投票所が25ヶ所も減少した見直し方針は国からの選挙区の基準により
「投票所間3Km以内又は1ヵ所約300人未満を統合対象とし、1投票区3,000人
を限度とする。」とされました。
この影響で約6,800人(H22見直し案当時のデータ)が統合された別の投票所で
投票することを余儀なくされました。
当時と比べて有権者総数が約6.7%減少しているので、今回は6,300人ほどが
何らかの影響があった可能性があります。
全ての方が選挙に行けなかったとは思えませんし、結びつけるには少し危険かもしれませんが
影響が及ぶ人が棄権者数の約半分の数字であります。
見直し方針に「地形、交通の利便性、地域の特性(旧行政区、小学校区等)を考慮して」と謳っていますが
これにより新たに設置された投票所は五十猛のみであとは全て統合になっています。
これらのことを考えたとき、統合された計画は国の方針に基づいた数値的な数合わせもあったのではないかと
私自身も深く反省しているところです。
県議選の前回(H19)と今回の選挙等で見直し前後の統合で影響を受けた方々の選挙行動を詳しく分析し
投票に行けなかった人の民意をどう選挙に反映させていくのかを考える時に来ていると強く思う次第です。
引き続き、投票率低下の要因を考えてみたいと思います。
選挙にいけなっかた方の大きな要因となっているのが、投票所の減少であることを
考えるのが自然の流れではないでしょうか。
全国区のニュースでも取り上げられ、話題になったから言うのではありませんが
行政もきちんと投票所統合前後のデータを詳しく解析して影響力を測る必要があると思います。
2013(H25)年の参議院選からこれまで56ヶ所あった投票所は31ヶ所に整理・統合されました。
実に25ヶ所もの減少です。
その理由は、有権者数の減少、期日前投票の定着、職員数減少による事務従事者確保が困難、
経費削減等を勘案した結果で、統合の目的を
①全市を同一の基準により見直し、市全体の均衡を図る。
②選挙経費の削減を図る。
③投票所事務の合理化を図る。
というものでした。
行政の財源が縮小する中で行財政改革が推進され、確かに選挙費用が縮減されています。
知事県議会議員選挙の執行経費の予算状況を見ますと
この経費は全額県支出金(委託金)で賄われており、前回(H22年度及びH23年度予算)の3,851万7千円から
今回(H26年度及びH27年度予算)は3,404万8千円と446万9千円の削減が図られています。
予算的には結構厳しくなりつつある現状が見て取れます。
同時にポスター掲示場所も288ヶ所から207ヶ所に縮減されました。
立候補者の制作等は選挙公報で知り得ることが出来るので、ポスターの掲示は立候補者の確認にすぎないと
私は感じているのでこれは理にかなっていると思います。
選挙事務に従事する職員も行政職員全体が減少しているので厳しい中ではありますが
それよりも投票所に詰める立会人の確保が難しい問題に直面していると感じています。
では、一番重要な投票所の減少がどう影響しているのかは次回に譲りたいと思います。
知事選・県議選が終了して気になったのはやはり投票率の低さです。
より身近な選挙であった県議会議員選挙の大田選挙区のデータを少し分析しながら
投票率低下の要因を考えてみたいと思います。
今回の選挙の有権者数は30,795人。
投票者数は16,773票(うち無効416票)ですから、投票率は54.47%でした。
前回(H23)は無投票でしたから、前々回(H19)の63.20%と比較すると
8.73ポイント投票率が低下したことになります。
人数にして約2,600人が前回と比べて投票に行かなかった計算になります。
ここで問題になるのが、投票に行かなかったのか?、行けなかったのか?ということです。
投票に意識的に行かなかったということになれば、政治に関しての無関心・無意識、諦め等の表れであろうし
行けなかったということになれば、投票の時間的な問題や投票所の開設場所等の問題であろうと考えられます。
仕事などで日程や時間的な制約があり投票が困難であろう方のために
期日前投票や不在者投票の制度があるのは皆様ご存知のことでしょう。
特に期日前投票は告示の翌日から8:30~20:00までの間、土・日も投票ができ
印鑑等も不要で、以前よりも随分気軽に投票できるようになりました。
今回の県議選(大田選挙区)でこれを利用したのは3,753人で全体の12.02%。
とりわけ午後5時以降に投票した人は817人で期日前全体の21.77%を占めています。
年々投票率は増加傾向にあります。
選挙にいけないという方の時間的・日にち的な問題は、大方解決されているのではないかと分析しています。
では、なぜ投票率は下がる傾向にあるのか、別の要因を次回に分析したいと思います。
統一地方選挙の前半戦、島根県知事選挙及び島根県議会議員一般選挙が終了し、結果が出揃いました。
知事選、県議選(大田選挙区)とも応援していた溝口・生越両候補が当選を果たしました。
ご支持・ご支援を賜り、応援いただいた皆様には深く感謝と御礼を申し上げます。
県議選では土壇場で選挙と言うことになり、正直言うと最初は気が重く感じておりました。
しかし、結果的には選挙を経て当選したことが非常に良かったと思っています。
前回は無投票でしたので、本人も自分の政策をもっと伝えたかったと思いますし、
本当に信任されたのかどうか不安な気持ちでもあったと思います。
今回の選挙戦では、体調不良があり、事前の運動量も非常に少なかった中で
投票数の過半数近くの支持を頂き、本人も自信に繋がったのではないかと想像します。
生越県議は持ち前のバイタリティーと強いリーダーシップ、そして人と付き合う・人を育てる
ことには卓越した才能をお持ちで、県議1回生ながら県連の中でも一目置かれる存在感を示して
こられました。
2期目のこれからはますますこの魅力を活かし、県と大田市の大きな架け橋になって頂くことを
期待します。きっと「素早く」かつ「大胆に」仕事を成し遂げて頂けることでしょう。
産業振興を柱とした定住対策を基本に地方創生に向かってご活躍を祈念しております。
前回に引き続き、「国民健康保険料」についてです。
保険料が引き下がる(一部を除き)ことは前回お示しした通りですが、
これはあくまで25年度と比較した場合です。
24年度と26年度を比較してみると
所得割基準額が100万円の場合
4人家族世帯は、12,700円、2人世帯は、9,500円。
所得割基準額が200万円の場合
4人家族世帯は、18,700円、2人世帯は、15,500円。
所得割基準額が300万円の場合
4人家族世帯は、24,700円、2人世帯は、21,500円。
所得割基準額が400万円の場合
4人家族世帯は、38,800円、2人世帯は、39,200円。
それぞれ増額となっています。
保険料は年々高くなっていると言っても良いでしょう。
保険料が高くなる要因の主なものは
①医療費の高騰
②加入世帯及び加入者の減少
が考えられます。
保険料の高騰を抑えるために、26年度は
6月補正で一般会計から36,300千円、基金会計から155,345千円の繰り入れを行い、
補正後、両者合わせて517,481千円もの巨額な繰り入れを実施しています。(予算時)
これは国民健康保険事業予算の約11%にあたります。
予算規模では25年度に補正後502,744千円、24年度は360,965千円の繰り入れで
保険料の高騰を抑え、事業を維持しています。
とは言っても県内8市では、江津市、浜田市についで3番目に保険料が高い水準です。
また、年収に対する保険料の負担割合ですが
所得割基準額が100万円の場合は約15.5%。
私の手元計算だと、年収が上がるにつれて、負担率が下がる計算になります。
これはいかがなものでしょうか。
所得割基準額が100万円の場合は、年収換算で約234万円くらいでしょうから、
2割軽減基準額(今年度から基準改正で対象が拡大)
の213万円にもギリギリ引っかかりません。
年収約234万円で保険料を年額362,700円支払い、市・県民税も支払い、2人の子育てをしなければならないことになります。
子供に対する医療費は随分負担軽減になりましたが、
転ばぬ先の杖といえ、病院にかかっていない世帯の負担感は大きいものがあるのではないでしょうか。