杉 風(さんぷう) 岩田九郎 氏著
芭蕉が江戸に下った當初から、大阪に最後の息を引きとるまで、或は師弟として或は生活の支持者とし風ほど師翁に深いゆかりをもった人は、多くの蕉門中にも稀であった。またその師翁歿後における思慕追念の情けの深かったことも、この人にまさるものは少かったといってよかろう。それだから「杉風句集」の編者採荼(さいだ)庵梅人が杉風を評して「はいかいに遊ぶこと几六十年、蕉門の高弟なり。實學ならぶ人なし。奥旨深意、翁より傳偉へずといふことなし。」
といつたのは、一應もっともとうなずける。もしそうだとするならば、杉風はいつたい何程の師風をうけついでいるのであろうか。いゝかえれば芭蕉の俳風が杉風にいかに投影しているであろうか。そういう點について、この小稿では種々なる角度から親察してみようと思う。それはやがて杉風の俳諧の長短を論ずることにもなるであろう。
芭蕉は自ら「たよりなき風雲に身をせめ、花鳥に情けを労じて」といつているように、風月の趣味に生涯を終始して、「いざ行む雪見にころぶ所まで」などの句をのこしているが、杉風の師風をうけた最も著しいところは、やはりその風狂の姿であった。「覚悟して風引に行雪見かな」は師翁の句に比して平板いうに足りない出来であるが、兎に角その心構えは相似たものがあるといえよう。
そういう態度からは、
「川ぞひの畠をありく月見かな」
「客とめむ時雨の雲の通る内」
などが生れてきたので、これらは安らかな調べの中に、風雅人の清らかな心境が窺われる。ことに後の句
は、芭蕉の
「人々をしぐれよ宿は寒くとも」
などの心にも通っていると思われる。
「花に気のとろけて戻る夕日哉」
「月の頃は宸に行夏の川優哉」
「水晋やほたるたのみに宿とりぬ」
これらもまたみな師翁の花鳥風月の趣味をうけ入れた作で、やゝもすると低調になり易い句風を、ともかくもこの高さに引上げて、一つの風格を形づくっているところは、たしかに師翁の感化といわねばならぬ。
芭蕉の詩境に閑寂の味の深かったことは今更いうまでもないが、杉風もまたその詩味を理解しないではなかった。それが師翁ほどに深奥所に撤していたとは言えないかもしれぬが、ともかく杉風の句境の中に、
その趣のあることは、何として屯師翁の影響といわなければならぬ。
「鎧の音物にまぎれぬ秋の暮」
「かれがれてもの寂わたる冬の園」
などには、杉風が曾て屬していた談林調のかすかなにおいさえもなく、まったく蕉風になりきっていることを示すものであろう。
「空も地も一つになりぬ五月雨」
「降かくす小家は雪のすがたかな」
いずれも静かに寂びた姿があって、蕉門の句たるに異論はない。
芭蕉の句には
「初しぐれ猿も小蓑をほしげ也」
に見るような、和歌や漢詩などでもまだ詠み得なかった物のあわれを捉えているものがあるが、杉風もまたその師風をうけて、弱いもの淋しいものに同情の目をそそぎ、温かい人情を詠み出たものが少くない。
「子や待ん餘りひばりの高上り」
は、憶良の歌に縁はもっているものゝ、その情趣は仝く俳諧の世界になりきっている。「猿も小蓑」の句は、芭蕉の作品中でも人の心をひくものであるが、杉風の「雲雀」も彼の傑作として、その最もよい方面を代表する句といってよかろう。そのほか
「木枯に何やら一羽塞げなり」
「唖蝉の啼ぬ梢もあはれなり」
「あられにも怪我せぬ雀かしこさよ」
などみなこの類に屬するもので、よく師のこころをうけついだものといえよう。
芭蕉には
「観音のいらか見やりつ花の雲」
「冬ごもり又よりそはむ此はしら」
に見るような寂びしく静かでゆったり落ちついた句境をもったものが多い。前に云った閑寂昧は、対象となる自然に見出した味であるが、ここにいうのはむしろゆったりした心の姿である。この詩境もまた杉風のみずから學び得たところで、
「とぼ/\と日は入切てむめの花」
の句をみると、夕日の沈む頃に、ひとり静かにたそがれゆく梅の花を見入っている詩人の姿が、さびしく想像される。また
「遅うくるゝ日もけふ切のわかれ哉」
には、春のすぎてゆくのを惜しみつゝ、ひと日を安らかに過ごした心境が、おだやかに語られている。句格も高くて俗なところがない。そのほかに
「そのの梅老木に花のしづか也」
「冬ごもりこの水仙や老が友」
など同じ句境とみることができよう。
「辛崎の松は花より朧にて」
を芭蕉は「たー眼前なるは」と自ら説いているが、そのように眼前の景色をとらえ、刹那の感激を句に打出したものが芭蕉には少なくないが、杉風もまた眼前の即景を句にしたものが多い。
「ふりあぐる鍬の光りや春の野ら」
は春風胎蕩たる春の野に出て、ふと目にとまつた光景を、巧まず平明に表現したもので、暢建の気味まで師翁の風に似通つている。
「五月雨に蛙のおよぐ戸口哉」
「飛胡蝶まぎれて失し白ぼたん」
などみんこうした情趣の句としてあげることができよう。
芭蕉には、自然の中の美しさを凝親して、造化の妙なる力に深く心をとめた句がある。
「よく見れば薺花さく垣ねかな」
「山路末て何やらゆかしすみれ草」
などがそれで、そこに芭蕉の深い自然愛を見ることができる。杉風もまたこうした師の風に心を寄せて、これに似たものを詠んでいる。
「名は知らず草毎に花哀なり」
「朝顔やその日その日の花の出末」
など、到底師翁のごとく幽遠な自然の奥に心をひそめる所には達していないが、ともあれ詩作の態度とし
て、そういう黙に心をよせていることはみとめられる。
芭蕉は五十一歳で世を去ったので、まだ老境とまではいかないが、元來じみな心の持主であった為に、四十頃からもう翁といってすましていたくらいだから、晩年には老人らしい感懐をのべたものがある。杉
凪は八十六で亡くなったから、これは文字通りの老境で芭蕉と比較するのは無理であるが、杉風は師風を模して、そうした句境のものが多い。芭蕉の
「おとろへや歯に喰あてし海苔の砂」
には杉風
「がっくりとぬけそむる歯や秋の風」
が想い合わされるし、芭蕉の
「この秋は何で年よる雲に鳥」
には、杉風の
「月雪もふるき枕にとし暮ぬ」
などが思い出される。
「いざよひも更て人なし老が友」
「七十の暮行としぞつれなさよ」
のように老齢のわびしさを詠んだものが多い。
芭蕉は晩年に「軽み」をとなえて、
「木のもとに汁も膾回もかな」
「煤はきは己が棚つる大工かな」
の句を詠んでいるが、この種のものは一見平明のように見えて、良く模倣すると月並風の平俗に堕してしまうおそれがある。杉風はしかしこの種の句においても、さすがに師翁の感化をうけて、月並調にまでは落ちたかった。
「大年礼雀の遊ぶ垣ほかな」
「山雀もこもりの小箱冬ごもり」
などがそれである。
最後に、杉風は師に模して辞世の句を詠んだが、
「旅に病で夢は枯野をかけ廻る」
に比して
「痩顔に扇扇をかざし絶し息」
は、その余りに開きの大きいのにがっかりさせられる。師翁の句には烈々たる詩魂が漲って人をして慄然たらしめるものがあるが、杉風のは全く無気力で、ただ安らかに朽木が倒れる如き感を與えるのみで、そこに何ものも人の心をうつものがない。
これを要するに、杉風は師翁の風姿を學び、その力に庶じて相応の作品をのこしているが、かの師翁の枯淡な禅昧や、徴かな余情の通う「匂ひ」の世界や、自然の風姿にある雄大な趣や、漢詩に背景を持つ深味のある句境や、中世以来の傳統的な芸道の香りなどは、終に多くを學びとることができなかった。
しかしそうはいうものゝ、温雅平明な詩境と、安らかにして穏やかな作風とは、よく師翁の藝風に洗われて、平俗に堕落せず、一個心風格を持しているところは、蕉門高弟名に恥じないものといってよかろう。
(學習院教授)











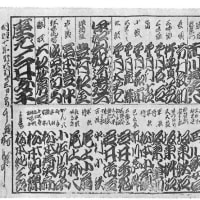



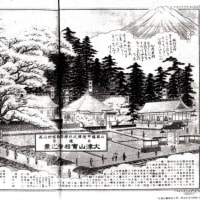
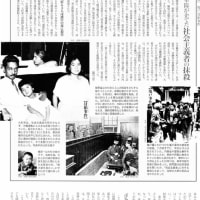
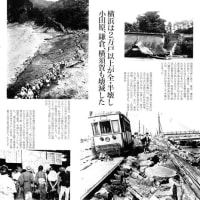


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます