閉田耕筆


(前文略)
源氏に見ゆるも櫻の木陰なり.新古今集にも雅経卿の言葉書きに、
最勝寺のさくらは鞠のかゝりにて久しくなりにしを、
その木歳ふりて風にたふれたる由開き侍りしかば、
をのこどもに仰せてこと木を其あとにうつし植ゑさせし時、
まかりて見侍りければ、
あまたの年々暮れにし春まで立馴れけることなど、
思ひ出でてよみ侍りける。
馴れ\/て見しは名残の春ぞとも などしら川の花の下かげ
と有り。また柳も鞠に詠合せたることめづらしからす。又雑木を植うる證も有りとやらん、
北辺の人は委しく知るべし。
○蹴鞠の佳の立合に、
人には蹴よきようにしてわたし、蹴にくき所をとりであつこふなど、萬の心ばへかゝらましかばと思わるゝを、その技にのみとどまり、他の交りにうつすべきこととも知らぬは念なし。
されどもさすがに勝負を争い、われよく人悪しかれと思ふ様には似ず。ただし此の技日毎に半日を費し、はりありの屏に暮を待つは惜むべし。
○茶、
茶、香は風流の態にて、近世盛に行はる。香はもてあつかふ調度など、金銀蒔檜のものにかなひて、貴人の翫びと見ゆ。茶具はものさびて、其室も松の木柱、竹のなげし、ゆかしく、やがてさし入りしに、飛石の上にわらふだを設けたるは、雪のあとをいとふならんと、いよ\/興に入りて待合に休らひたれば、あるじ長き棹を携へて、ものかけに枝もたわゝになりたる柚の賓をうち落すが見ゆ。とりあへぬ饗のまうけならんと思ひつゝ居るに、後はたして膳のさきに柏味噌を調じて付けたり。
さればこそとをかしきに、又鮮けき魚をあつものにして出したりしかば、是にことさめて、彼柚はわざと風流をかまへたるなりしと覚えぬとぞ。荼のみにあらず、萬の事にもわたるべし。自然に出づると作りものとは、魚目(ぎょもく)と真珠の違なり。
○茶の態(わざ)の盆は、
いとふつゝかにあら\/しき人も、是を翫べば起居おとなしく、物を取扱ふも見ざまよくなりぬ。また主客の禮節、たとへば夜分にあるじ手燭を携へ出でて客を迎へ、燭を石上などに置きて禮して退く、客其燭を取りで庭の木立など見るふりして、わざとなく主の帰る道を照すなどやうの心づかひ、禮の真に適ひて、此意をめぐらさば陰徳なるべし。
さるに俗流の弊風、得がたきをもとめ含賤を費し、あるはまた其産業ならぬ人も、黠智(かつち)あれば是をもて利を射るにも及び、心ざまよからず成り行くもまゝ見ゆ。
富豪の家に茶を翫ぶことを禁ずがあるも、子孫過奢(かき)に及ばんことを懼るゝとなり。
利休のことばとかや、
釜ひとつ持てば茶湯はなるものをよろづの道具好むはかなさ
鎌なくば鍋湯なりともすき給へそれこそ茶湯日本一なれ
かくいへば有る道具をも押隠しなきれ似をする人もはかなき
○茶禮に心得がたき事あり。
招るゝ俗體の客は、麻上下の禮服をつけ、迎ふる主僧は法衣を脱ぎてあらぬ服をつけ、茶をたつるに辨利なるやうを計らふ。禮の相當らぬをいかん。
また必ず禮服をつくべきならば、官位ある人は烏帽子装束なるべきを、さて狭き入口の名におふにじりあがり叶ふべからねば、首服を脱ぎ上(かみ)をとり、指貫(さしぬき)ばかりにておはさんか。凡そかゝれば果して禮による歟(か)よらざるか、書院のあつかひは別なるべけれど、これは常ざまの茶室のうへにて思へるなり。
一人荼を翫びて、苔むしたる石の陶水盤を愛し、今參の男に水かへさせけるが、彼苔を残りなく洗ひ捨つるにおどろきて、斯くはするものかとむづかりしに、答へて、
「さきに見侍れば、蚯蚓(みみず)、蛞蝓(なめくじ)、蝸牛(でゝむし)やうの蟲、苔をよすがに宿りしかば、口をも漱ぎ給ふものをと思ひで能く清め侍りし」といふ。
主こゝにして思惟(しゆい)すらく、彼がいふは理にして、吾古びを好むは僻(ひが)めりと、これより古器の潔からぬを悟りて遂に茶事を廃せり。
又俳諧の連歌をたしめりしが、或會に卑俗(ひあく)なる句を付合せ仁るに、披講(ひこう)の時、其句にあたりて吾名を読みあげられしに恥を生じて、おぼえす背に汗す。是より武技をも止めて。學文に精を入れ、歌をもよめりしと。其知己の人語りぬ。事にあたりて道理を考へ恥を知らぱ君子なる哉、吾濟(わなみ)及ぶべからす。











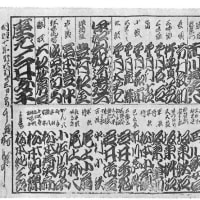



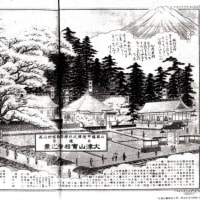
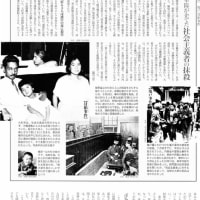
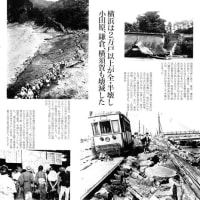


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます